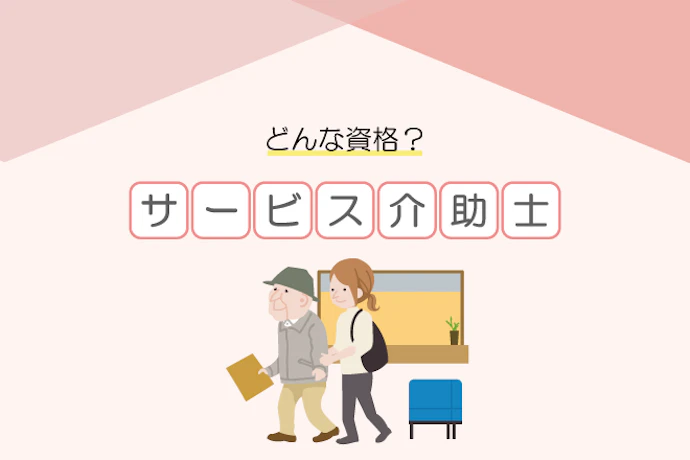介護コラム
公開日:2023.10.12
更新日:2023.11.13
サービス介助士(ケアフィッター)資格をかんたん解説!
#介護
目次
「サービス介助士(ケアフィッター)」という資格があります。「介護福祉士」「ケアマネージャー」のような介護職の実務に活かせる専門資格とは異なり、日常生活において誰もが役立てられる民間資格です。
このサービス介助士(ケアフィッター)資格について、「
今回は日常のあらゆる場面で活かせる資格「サービス介助士」について、
■資格内容
■取得方法
■費用
■取得までにかかる期間
■難易度
などについてわかりやすく解説いたします!
このサービス介助士(ケアフィッター)資格について、「
具体的にどんな場面で活かせるのか
」「資格取得は難しいのか
」詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか?今回は日常のあらゆる場面で活かせる資格「サービス介助士」について、
■資格内容
■取得方法
■費用
■取得までにかかる期間
■難易度
などについてわかりやすく解説いたします!
サービス介助士(ケアフィッター)ってどんな資格?
サービス介助士(ケアフィッター)は「
「高齢者、体の不自由な方が安心して過ごせる環境」を整えるために、誰もが受講でき、社会の中で役立てられる内容のこの資格。
小売や観光などのサービス業を中心にさまざまな企業で導入されており、個人受講とあわせて累計20万人以上が取得しています。(2022年時点)
一般的に介護職の方が知識や技術を習得する場合には「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」資格を取得しますが、そこからさらに
おもてなしの心
」「安全な介助技術
」を学べる資格です。公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が主催する民間資格で2000年に創設されました。「高齢者、体の不自由な方が安心して過ごせる環境」を整えるために、誰もが受講でき、社会の中で役立てられる内容のこの資格。
小売や観光などのサービス業を中心にさまざまな企業で導入されており、個人受講とあわせて累計20万人以上が取得しています。(2022年時点)
一般的に介護職の方が知識や技術を習得する場合には「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」資格を取得しますが、そこからさらに
接遇やおもてなしの心を身につけたいと考える介護職の方
には、この「サービス介助士(ケアフィッター)」の資格もおすすめです。「サービス介助士(ケアフィッター)」資格を取得するメリット
介護職の方がサービス介助士資格を取得するメリットは、
サービス介助士の役割はただ安全な介助をおこなうだけではありません。
資格所有者の使命として、”ホスピタリティを持って人と向き合い「手伝ってよかった」「手伝ってもらってよかった」と相互に思い合える関係を作っていくこと”が掲げられています。
これは接遇において大切な姿勢のひとつであり、介護業界においても欠かせないスキルといえます。
たとえ高い介護技術を持っていたとしても、利用者の方へ思いやりを持って接する事ができていなければ、スキルの高い介護職員とはいえません。
また利用者の方だけでなく、そのご家族や職場のスタッフなどあらゆる人との良好なコミュニケーションをとれて初めて、質の高い介護サービスを提供しているといえるのではないでしょうか。
接遇、ホスピタリティ・マインドを学べる
ところにあるでしょう。サービス介助士の役割はただ安全な介助をおこなうだけではありません。
資格所有者の使命として、”ホスピタリティを持って人と向き合い「手伝ってよかった」「手伝ってもらってよかった」と相互に思い合える関係を作っていくこと”が掲げられています。
これは接遇において大切な姿勢のひとつであり、介護業界においても欠かせないスキルといえます。
たとえ高い介護技術を持っていたとしても、利用者の方へ思いやりを持って接する事ができていなければ、スキルの高い介護職員とはいえません。
また利用者の方だけでなく、そのご家族や職場のスタッフなどあらゆる人との良好なコミュニケーションをとれて初めて、質の高い介護サービスを提供しているといえるのではないでしょうか。
サービス介助士の資格を通して「おもてなしの心」を学ぶことで、一人ひとりの利用者の方に寄り添った介護サービスを提供できる介護職員になれる
でしょう。サービス介助士(ケアフィッター)資格の取得方法
では、サービス介助士(ケアフィッター)資格の取得方法についてご説明します。まずはサービス介助士の3つの資格とその違いについてご説明します。
サービス介助士(ケアフィッター)資格の種類・違い
サービス介助士資格には3種類あります。
■サービス介助士:在宅学習+二日間の実技講習を受講
■准サービス介助士:在宅学習
■サービス介助基礎研修:2時間1回のパッケージ型セミナー
それぞれの資格によって、学習内容や費用、取得にかかる期間が異なります。
各講座の概要については下記のとおりです。
各講座の概要については下記のとおりです。
サービス介助士 | サービス介助 基礎研修 | 准サービス介助士 | |
料金 | 41,800円 | 5,500円 | 22,000円 |
受講形態 | 自宅学習 +実技2日間 | 2時間1回 (座学と実技) | 自宅学習 |
教材 | テキスト 提出課題 | レジュメ (当日配布) | テキスト 提出課題 DVD |
提出課題 | あり | なし | あり |
検定試験 | あり | なし | あり |
平均取得期間 | 1.5〜2ヶ月 | 1回 | 1〜1.5ヶ月 |
受講期間 | 最大12 ヶ月 | 1回 | 最大6 ヶ月 |
実技教習 | あり | あり | なし |
資格更新制度 | 有 | 無し | 無 |
※サービス介助士 公式ホームページ「比較表」より抜粋
受講するコースの選び方ですが、
公式ホームページによると8割以上の方が「サービス介助士」を受講されているようです。
自宅学習では、テキストの内容を繰り返し学ぶことでサービス介助の考え方や接遇の知識をつけられます。
そして2日間の実習では、介助の実技演習や他の受講者とのディスカッションにより、新たな気づきを得て自身の見解を深めることができるでしょう。
「サービス介助基礎研修」は2時間1回のセミナーのみ、「准サービス介助士」は自宅学習のみで実習なしの講座となり、もちろんそれぞれに利点はありますが、介護のプロとして資格を取得するのであればやはりサービス介助士資格がおすすめといえるでしょう。
受講するコースの選び方ですが、
介護職の方が取得をされる場合にも、サービス介助士資格をおすすめ
します。ホスピタリティ・マインドや接遇について自宅学習(テキスト)と実習の両方で学べる機会があるのはサービス介助士だけだからです。公式ホームページによると8割以上の方が「サービス介助士」を受講されているようです。
自宅学習では、テキストの内容を繰り返し学ぶことでサービス介助の考え方や接遇の知識をつけられます。
そして2日間の実習では、介助の実技演習や他の受講者とのディスカッションにより、新たな気づきを得て自身の見解を深めることができるでしょう。
「サービス介助基礎研修」は2時間1回のセミナーのみ、「准サービス介助士」は自宅学習のみで実習なしの講座となり、もちろんそれぞれに利点はありますが、介護のプロとして資格を取得するのであればやはりサービス介助士資格がおすすめといえるでしょう。
資格取得にかかる費用
費用は受講するコースによって異なりますのでご注意ください。
■サービス介助士:41,800円
■サービス介助基礎研修(パッケージ型セミナー):5,500円
■准サービス介助士料金 :22,000円
※全て税込み表記(2022年時点)
資格取得までの流れ
サービス介助士の資格取得の流れについてご説明します。
まず申し込み後に送られてくるテキストを使って自宅学習を進めます。学習を終えたらテキストの内容に基いた提出課題に取り組みます。しっかりとテキストの内容を理解しながら学習を進めてください。
提出課題が合格点であれば実技教習(2日間)に進めます。その実技教習の最後に実施されるのが検定試験。この試験に合格すればサービス介助士に認定となります。
まず申し込み後に送られてくるテキストを使って自宅学習を進めます。学習を終えたらテキストの内容に基いた提出課題に取り組みます。しっかりとテキストの内容を理解しながら学習を進めてください。
提出課題が合格点であれば実技教習(2日間)に進めます。その実技教習の最後に実施されるのが検定試験。この試験に合格すればサービス介助士に認定となります。
提出課題の難易度と検定試験の合格率
■提出課題
前述のとおり、自宅でのテキスト学習を終えたあとに課題を提出する必要があります。
提出課題はマークシート式(3択)の100問の問題です。
100点満点で60点が合格点。点数が満たなければ再提出となります。
自宅でテキストを参考にしながら解答できますので難易度は高くない
でしょう。■検定試験
検定試験は講座の締めくくりとして、2日間の実技教習の最後に実施されます。
試験内容はマークシート形式の3択問題。1問2点で50問の出題です。
100点満点で70点以上が合格ラインとなっており、制限時間は50分。
試験の合格率は80%と発表されています
。テキスト学習と2日間の講習を真面目に取り組めば合格できるでしょう。サービス介助士(ケアフィッター)資格の更新
検定試験に合格すれば、晴れてあなたもサービス介助士に認定です!
しかし、
有効期限の1か月前を目途に、更新申請表などの必要書類の提出と更新料(2,200円)の入金が必要となります。(※必要書類は、申し込み時に登録している住所に送られます。)
万が一、更新を忘れて有効期限が切れてしまった場合でも、期限切れから1ヶ月以内であれば手続きは可能です。
更新をした場合には介助技術を維持するためのフォローアップセミナーを受講できます。
しかし、
サービス介助士は3年に1回の更新が必要な資格
。永久的な資格ではありません。有効期限の1か月前を目途に、更新申請表などの必要書類の提出と更新料(2,200円)の入金が必要となります。(※必要書類は、申し込み時に登録している住所に送られます。)
万が一、更新を忘れて有効期限が切れてしまった場合でも、期限切れから1ヶ月以内であれば手続きは可能です。
更新をした場合には介助技術を維持するためのフォローアップセミナーを受講できます。
まとめ
サービス介助士の資格について解説しました。
この「サービス介助士」は、介助技術以上に「おもてなしの心」「接遇」に重きをおいた資格。質の高い介護サービスを提供するためのホスピタリティ・マインドを学ぶことができるでしょう。
利用者や利用者のご家族に選ばれる介護職員、事業所となるために、「接遇サービスのレベルアップをしたい!」とお考えの介護職員の方におすすめな資格です。
資格に興味が出てきたというあなたは、公式ホームページで詳細をご確認ください。
サービス介助士公式ホームページ
この「サービス介助士」は、介助技術以上に「おもてなしの心」「接遇」に重きをおいた資格。質の高い介護サービスを提供するためのホスピタリティ・マインドを学ぶことができるでしょう。
利用者や利用者のご家族に選ばれる介護職員、事業所となるために、「接遇サービスのレベルアップをしたい!」とお考えの介護職員の方におすすめな資格です。
資格に興味が出てきたというあなたは、公式ホームページで詳細をご確認ください。
サービス介助士公式ホームページ
質の高い介護ができる職場へ転職したいあなたは介護ワーカーにご相談を!
今よりももっと一人ひとりの方に手厚い介護がしたい。
質の高い介護サービスを提供できる介護職員になりたい。
理想の介護と現場のギャップから転職を考えて始めているあなたは、ぜひ介護ワーカーにご相談ください。
業界最大手の介護ワーカーだからこそご紹介できる人気の非公開求人も多数。
まずは現状のお悩みやご希望をお聞かせください!
経験豊富な転職アドバイザーがあなたにぴったりの転職先をご提案いたします!!
アドバイザーに相談する
まずは求人を見てみる
質の高い介護サービスを提供できる介護職員になりたい。
理想の介護と現場のギャップから転職を考えて始めているあなたは、ぜひ介護ワーカーにご相談ください。
業界最大手の介護ワーカーだからこそご紹介できる人気の非公開求人も多数。
まずは現状のお悩みやご希望をお聞かせください!
経験豊富な転職アドバイザーがあなたにぴったりの転職先をご提案いたします!!
アドバイザーに相談する
まずは求人を見てみる
※掲載情報は公開日あるいは2021年04月07日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.