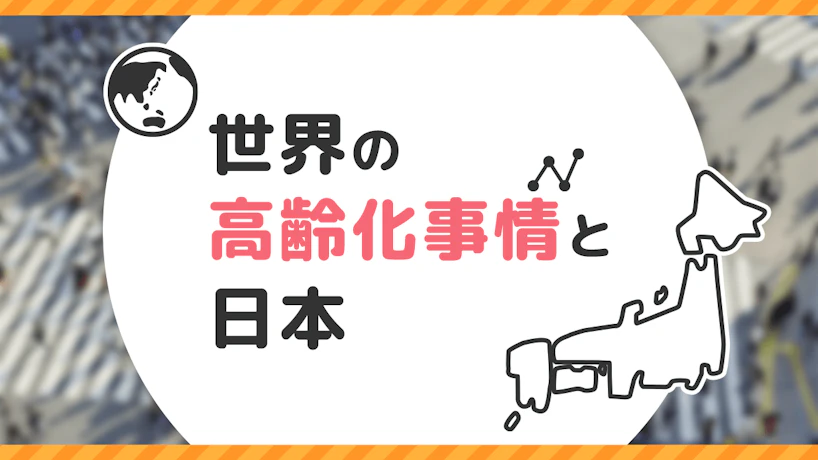介護コラム
公開日:2023.10.12
更新日:2023.11.09
世界の高齢化事情と日本
#介護
高齢化社会とは
総人口に対して65歳以上の高齢者が占める割合を高齢化率といい、WHOの定義によると、高齢化率が7%を超えた社会は”高齢化社会“と呼びます。
さらに14%を超えると”高齢社会“、21%を超えると”超高齢社会“と呼びます。
日本においては、2007年にこの高齢化率が21%を超え、超高齢社会に突入しています。
さらに14%を超えると”高齢社会“、21%を超えると”超高齢社会“と呼びます。
日本においては、2007年にこの高齢化率が21%を超え、超高齢社会に突入しています。
海外の高齢化事情
すでに、日本が超高齢社会に突入していることには言及しましたが、この高齢化率上昇の問題は日本に限ったことではなく、多くの先進諸国が抱えている共通の課題と言えるでしょう。
そこで、2015年時点における各国の高齢化率を確認してみましょう。
1位:日本 25.78%
2位:イタリア 21.45%
3位:ドイツ 21.25%
4位:ギリシャ 19.95%
5位:フィンランド 19.74%
という結果となり、日本、イタリア、ドイツの3国において世界に先立って超高齢社会を迎えていることがわかります。
しかし、2位以下の国においては、高齢化社会から高齢社会に至る過程で50年、80年という長い年月を経ているのに対して、日本は24年で到達したことから世界でもまれにみる速さで高齢化に突入したことで今度の対策と動向に世界から注目を浴びています。
そこで、2015年時点における各国の高齢化率を確認してみましょう。
1位:日本 25.78%
2位:イタリア 21.45%
3位:ドイツ 21.25%
4位:ギリシャ 19.95%
5位:フィンランド 19.74%
という結果となり、日本、イタリア、ドイツの3国において世界に先立って超高齢社会を迎えていることがわかります。
しかし、2位以下の国においては、高齢化社会から高齢社会に至る過程で50年、80年という長い年月を経ているのに対して、日本は24年で到達したことから世界でもまれにみる速さで高齢化に突入したことで今度の対策と動向に世界から注目を浴びています。
高齢化社会を招く原因
高齢化率の上昇を語る点において、少子化というキーワードは外せないポイントです。高齢化率を算定する時にお気づきかと思いますが、高齢者が増加してもその他の世代人口が一定数キープされている分には高齢化率の上昇を防ぐことができます。
しかし、深刻な高齢化問題を抱えている上記のような国においては、少子化問題も顕著。よって、65歳以下の人口が減少していることに加え、医療の発達が進み平均寿命が延びたことからより急速に高齢化が進んだと考えることができます。
また、少子化の原因は、未婚、晩婚、晩産化が進んだためと言われています。日本を含め、多くの先進諸国では女性の社会進出がすすみ、結婚、出産以外にも女性にとっての幸せの形が多様に広がりました。女性も仕事に就くことで、晩婚、晩産の傾向が強まり、女性が生涯で出産する子どもの人数も少なくなったことが、ひいては高齢化を加速させてきたのです。
そこで、ヨーロッパ諸国においては、この少子化問題を解決すべく社会保障政策が確立され、高齢化率の急激な上昇を阻止し、高齢化、少子化共に緩やかな上昇に留めることができています。
日本においては景気の不安定さから、若年層において非正規雇用やフリーターが増加。ワーキングプアという言葉が生まれたように、正規雇用であっても薄給であるという経済的な不安定さから結婚に踏み切ることができない男女が増加したことや、核家族化が進んだことで親世代に育児のサポートを期待できない家庭が増えたこと等の社会不安も少子化に拍車をかけていると言えるでしょう。
しかし、深刻な高齢化問題を抱えている上記のような国においては、少子化問題も顕著。よって、65歳以下の人口が減少していることに加え、医療の発達が進み平均寿命が延びたことからより急速に高齢化が進んだと考えることができます。
また、少子化の原因は、未婚、晩婚、晩産化が進んだためと言われています。日本を含め、多くの先進諸国では女性の社会進出がすすみ、結婚、出産以外にも女性にとっての幸せの形が多様に広がりました。女性も仕事に就くことで、晩婚、晩産の傾向が強まり、女性が生涯で出産する子どもの人数も少なくなったことが、ひいては高齢化を加速させてきたのです。
そこで、ヨーロッパ諸国においては、この少子化問題を解決すべく社会保障政策が確立され、高齢化率の急激な上昇を阻止し、高齢化、少子化共に緩やかな上昇に留めることができています。
日本においては景気の不安定さから、若年層において非正規雇用やフリーターが増加。ワーキングプアという言葉が生まれたように、正規雇用であっても薄給であるという経済的な不安定さから結婚に踏み切ることができない男女が増加したことや、核家族化が進んだことで親世代に育児のサポートを期待できない家庭が増えたこと等の社会不安も少子化に拍車をかけていると言えるでしょう。
高齢化の問題点
高齢化が進むとどのような点で困ることが出てくるのでしょうか?
・増税
・社会保障、医療保障などの削減
・経済の弱体化
・高齢者の貧困化
高齢化が進むと、1人の高齢者を今よりも少ない生産年齢(≒15歳~64歳の働くことができる年齢)で支えることになります。これは、すなわち増税を意味することになるでしょう。
例えば、高齢化率世界3位のドイツでは、2025年時点の総人口における生産年齢は63%、高齢者は23%であることから、10年後にはおよそ2.8人で1人の高齢者を支えていかなければならない時代に突入します。そして高齢化率世界第1位の日本の10年後はと言うと、1.87人で1人の高齢者を支える時代と予想されています。
このように高齢化が進んだ各国では、結婚適齢期である若年層においても給与から徴収される税金は増え、生産年齢の減少により国の財政が圧迫されることから各種社会保障費は削減され、何をするにも今よりも出費がかさむ、よってますます結婚も出産も遠ざかる・・・そんな悪循環、不遇の時代を生きなければいけない可能性があるのです。
また、十分な社会保障を受けることができなくなること、年金額の引き下げ等によって、運用できる資産が少ない一部の高齢者は厳しい生活を強いられる可能性も出てきます。
・増税
・社会保障、医療保障などの削減
・経済の弱体化
・高齢者の貧困化
高齢化が進むと、1人の高齢者を今よりも少ない生産年齢(≒15歳~64歳の働くことができる年齢)で支えることになります。これは、すなわち増税を意味することになるでしょう。
例えば、高齢化率世界3位のドイツでは、2025年時点の総人口における生産年齢は63%、高齢者は23%であることから、10年後にはおよそ2.8人で1人の高齢者を支えていかなければならない時代に突入します。そして高齢化率世界第1位の日本の10年後はと言うと、1.87人で1人の高齢者を支える時代と予想されています。
このように高齢化が進んだ各国では、結婚適齢期である若年層においても給与から徴収される税金は増え、生産年齢の減少により国の財政が圧迫されることから各種社会保障費は削減され、何をするにも今よりも出費がかさむ、よってますます結婚も出産も遠ざかる・・・そんな悪循環、不遇の時代を生きなければいけない可能性があるのです。
また、十分な社会保障を受けることができなくなること、年金額の引き下げ等によって、運用できる資産が少ない一部の高齢者は厳しい生活を強いられる可能性も出てきます。
対策が必要
高齢化対策は少子化対策と言っても過言ではないでしょう。
総人口における生産年齢人口を確保することで高齢化率を緩和させることができるので、歴史的に移民の受け入れを行ってきたアメリカ、ドイツ等ではこれらを推進することで労働人口を確保する努力をしています。
しかし、そういった歴史の乏しい日本では海外から労働者を受け入れると言っても政府がよほど大胆な政策を打ち出さない限り大きな効果は期待できないのではないでしょうか。
やはり、生産年齢人口を増大するためには若年層にも安心して結婚、出産を選択してもらえるような社会環境を整えることが急務であると言えるでしょう。
総人口における生産年齢人口を確保することで高齢化率を緩和させることができるので、歴史的に移民の受け入れを行ってきたアメリカ、ドイツ等ではこれらを推進することで労働人口を確保する努力をしています。
しかし、そういった歴史の乏しい日本では海外から労働者を受け入れると言っても政府がよほど大胆な政策を打ち出さない限り大きな効果は期待できないのではないでしょうか。
やはり、生産年齢人口を増大するためには若年層にも安心して結婚、出産を選択してもらえるような社会環境を整えることが急務であると言えるでしょう。
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.