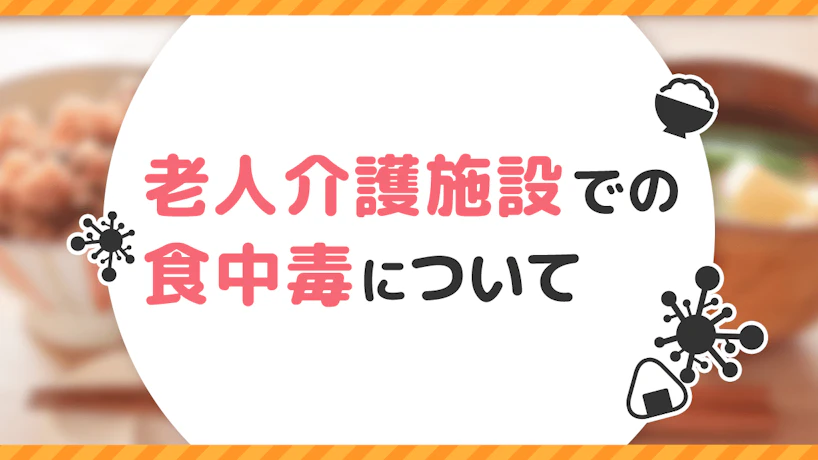介護コラム
公開日:2023.10.12
更新日:2023.11.09
老人介護施設での食中毒について
#介護
老人介護施設での食中毒について
夏場は気温や湿度が高くなるため、1年の中でも食中毒が発生しやすい時期であることが知られています。
夏はただでさえ暑さで体力を奪われやすい環境にある上、高齢者ともなると免疫力も低下していることから重篤な状態に陥るリスクが高いので十分に注意を払う必要がありますし、高齢者の特徴として、健康な人の場合だと発症まで至らない微量の細菌感染でも食中毒を発症してしまうことが挙げられます。
事実、近年でも老人介護施設においてO-157やサルモネラ属菌、ノロウィルス等に集団感染した事例もあり夏場はもちろんのこと年間通じて感染を予防する意識を高く持つ必要があると言えるでしょう。
在宅生活を送る高齢者に対しては家族やヘルパーなど福祉サービスを提供するスタッフが衛生的に食事を提供することが求められますが、上記で述べたように老人介護施設における食事の提供はひとつ間違えると食中毒の集団感染を引き起こす可能性がありますのでより一層徹底した対策が必要になります。
夏はただでさえ暑さで体力を奪われやすい環境にある上、高齢者ともなると免疫力も低下していることから重篤な状態に陥るリスクが高いので十分に注意を払う必要がありますし、高齢者の特徴として、健康な人の場合だと発症まで至らない微量の細菌感染でも食中毒を発症してしまうことが挙げられます。
事実、近年でも老人介護施設においてO-157やサルモネラ属菌、ノロウィルス等に集団感染した事例もあり夏場はもちろんのこと年間通じて感染を予防する意識を高く持つ必要があると言えるでしょう。
在宅生活を送る高齢者に対しては家族やヘルパーなど福祉サービスを提供するスタッフが衛生的に食事を提供することが求められますが、上記で述べたように老人介護施設における食事の提供はひとつ間違えると食中毒の集団感染を引き起こす可能性がありますのでより一層徹底した対策が必要になります。
食中毒を予防するための大原則を知ろう
①しっかり手洗いを行う
②調理する食品をよく洗う
③全ての食材を十分に加熱する
つまり、“菌をつけない・増やさない・殺菌する”ことが重要だとわかります。
まずは、この3原則を念頭に置き徹底して守るようにしましょう。
②調理する食品をよく洗う
③全ての食材を十分に加熱する
つまり、“菌をつけない・増やさない・殺菌する”ことが重要だとわかります。
まずは、この3原則を念頭に置き徹底して守るようにしましょう。
調理現場に立つスタッフの心得
調理員は手についた細菌が食品に付着することを防止するために、調理前はもちろん動作の合間でこまめに手洗いを行うと同時に、使用する調理器具の洗浄消毒をしっかり行うことが大切です。生肉や魚などを調理した後の包丁やまな板には菌が付着している可能性が高いので使用するたびに洗浄消毒を徹底して行いましょう。
調理後は食事を提供する時間まで、異物混入のないよう密封した状態で新鮮且つ適切な温度で保管しましょう。
調理後は食事を提供する時間まで、異物混入のないよう密封した状態で新鮮且つ適切な温度で保管しましょう。
介護スタッフの心得
食事介助を行う現場の介護スタッフは、介助前にしっかりと手洗いを行いましょう。
また、高齢者ご本人にも食事前にはきちんと手洗いをしていただけるよう習慣化して声を掛け介助を行います。
嚥下や咀嚼に問題がある高齢者に対する刻み食やミキサー食への対応は施設内に厨房と専門の調理員が在中している場合そちらで対応することが殆どですが、中には現場の介護スタッフが提供された食事の刻み対応をする必要が生じることもあるかもしれません。その際は、使用する調理ハサミ等の調理器具がきちんと洗浄殺菌されたものであるか確認してから使用するようにしましょう。
また、高齢者の思想としてよくある“食べものを残したら勿体ない”という考え方。この考え自体は素晴らしいのですが、“勿体ないから後で食べよう”と食事中に食べ切れなかったものを残しておいて数時間後に食べたことによって食中毒を招いてしまう可能性があります。よって、
・規定の提供時間を過ぎた食事は絶対に提供しない
・食事中食べ切れなかったものを自室に持ち帰らせない
・食事が終わればすぐに下膳し食べ残しは速やかに処分する
以上の3点が、“勿体ないが故に食中毒を発生させないためのポイント”です。
また、家族や知人などが食品を入所者へのお見舞い品として持参することがあるかと思います。食事に関する制限がなく認められている場合でも、そういった差し入れが賞味期限を過ぎていないか、生ものではないか等に介護職員は巡回時にさりげなく気を配るようにしたいものです。
また、高齢者ご本人にも食事前にはきちんと手洗いをしていただけるよう習慣化して声を掛け介助を行います。
嚥下や咀嚼に問題がある高齢者に対する刻み食やミキサー食への対応は施設内に厨房と専門の調理員が在中している場合そちらで対応することが殆どですが、中には現場の介護スタッフが提供された食事の刻み対応をする必要が生じることもあるかもしれません。その際は、使用する調理ハサミ等の調理器具がきちんと洗浄殺菌されたものであるか確認してから使用するようにしましょう。
また、高齢者の思想としてよくある“食べものを残したら勿体ない”という考え方。この考え自体は素晴らしいのですが、“勿体ないから後で食べよう”と食事中に食べ切れなかったものを残しておいて数時間後に食べたことによって食中毒を招いてしまう可能性があります。よって、
・規定の提供時間を過ぎた食事は絶対に提供しない
・食事中食べ切れなかったものを自室に持ち帰らせない
・食事が終わればすぐに下膳し食べ残しは速やかに処分する
以上の3点が、“勿体ないが故に食中毒を発生させないためのポイント”です。
また、家族や知人などが食品を入所者へのお見舞い品として持参することがあるかと思います。食事に関する制限がなく認められている場合でも、そういった差し入れが賞味期限を過ぎていないか、生ものではないか等に介護職員は巡回時にさりげなく気を配るようにしたいものです。
食中毒の可能性を感じたら・・・
高齢者から吐き気の訴えや下痢・嘔吐など食中毒の可能性を感じたら速やかに医師の診察を受けるよう手配しましょう。
他者への二次感染を防ぐために空間を分けたり吐物を適切なマニュアルに則って処理することも重要です。緊急時慌てず適切な対応がとれるようにするためにも、食中毒防止マニュアルと併せて食中毒発生時のマニュアルも確認しておくと良いでしょう。
他者への二次感染を防ぐために空間を分けたり吐物を適切なマニュアルに則って処理することも重要です。緊急時慌てず適切な対応がとれるようにするためにも、食中毒防止マニュアルと併せて食中毒発生時のマニュアルも確認しておくと良いでしょう。
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.