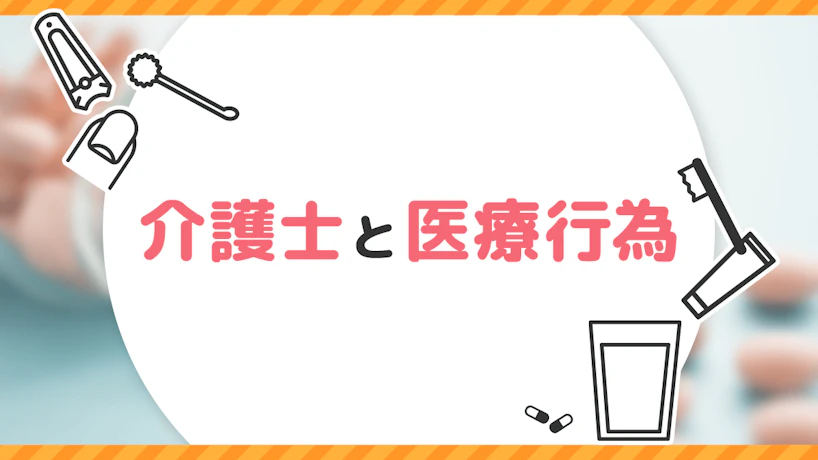介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.09
介護士と医療行為
#介護
介護士と医療行為
介護士は、医療従事者ではありません。しかし、介護の現場では医療行為に準じる働きをしなければならない場面が多々あり、2012年に「介護士による医療行為」が解禁になりました。今までグレーだった介護現場での医療行為の基準が明確になったのです。では、具体的に介護士はどのような医療行為が行えるのでしょうか。
医療的ケア
介護福祉士だけでなく、介護職員が行える医療行為があります。
服薬介助/軟膏塗布(床ずれの処置は除く)/湿布を貼る/目薬を差す/座薬を挿入する/体温計で体温測定/自動血圧測定器での血圧測定/酸素濃度測定器の装着/軽い擦り傷や切り傷の処置
これらの処置は現在医療行為と見なされなくなったので、介護職員でも問題なく行えます。
その他に、現在でも医療行為とされているが、介護職員でも行えるものがあります。
耳垢を取り除く/爪切り爪やすり/歯ブラシ綿棒による口腔ケア/ストーマのパウチに溜まった排泄物除去/自己導尿補助/カテーテルの準備/体位保持/市販の浣腸器による浣腸
これらの医療行為は、要介護者に異常が見られない場合のみ許されています。
例えば、耳垢が固まって耳を塞いでいる場合などは、耳垢塞栓になっている可能性が高く、医師の治療を必要とします。このような場合には、介護士は耳かきを行ってはいけません。
また、これらの医療ケアの中には、本人や家族の同意が必要なものや、医師・看護師の指示が必要なものが含まれているので注意が必要です。
服薬介助/軟膏塗布(床ずれの処置は除く)/湿布を貼る/目薬を差す/座薬を挿入する/体温計で体温測定/自動血圧測定器での血圧測定/酸素濃度測定器の装着/軽い擦り傷や切り傷の処置
これらの処置は現在医療行為と見なされなくなったので、介護職員でも問題なく行えます。
その他に、現在でも医療行為とされているが、介護職員でも行えるものがあります。
耳垢を取り除く/爪切り爪やすり/歯ブラシ綿棒による口腔ケア/ストーマのパウチに溜まった排泄物除去/自己導尿補助/カテーテルの準備/体位保持/市販の浣腸器による浣腸
これらの医療行為は、要介護者に異常が見られない場合のみ許されています。
例えば、耳垢が固まって耳を塞いでいる場合などは、耳垢塞栓になっている可能性が高く、医師の治療を必要とします。このような場合には、介護士は耳かきを行ってはいけません。
また、これらの医療ケアの中には、本人や家族の同意が必要なものや、医師・看護師の指示が必要なものが含まれているので注意が必要です。
介護福祉士が条件付きで行える医療行為
・喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く)
・経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する)
上記2点に関しては、実地研修(2種類)を終了し、認められた介護福祉士のみが行えます。
その他にも規定があります。勤めている事業所や施設が、医療と介護の連携を整えており、都道府県知事に登録している。本人、または家族の同意を得ている。医療関係者との連携のもと提供体制を構築しているなどです。以上のすべての条件を満たして、介護士が初めて行える医療行為です。
・経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する)
上記2点に関しては、実地研修(2種類)を終了し、認められた介護福祉士のみが行えます。
その他にも規定があります。勤めている事業所や施設が、医療と介護の連携を整えており、都道府県知事に登録している。本人、または家族の同意を得ている。医療関係者との連携のもと提供体制を構築しているなどです。以上のすべての条件を満たして、介護士が初めて行える医療行為です。
介護士が行えない医療行為
介護士に医療行為が一部認められているとはいえ、医療従事者ではないので、ほとんどの医療行為が禁止されています。
摘便/床ずれの処置/インスリン注射/血糖測定/点滴の管理
これらの医療行為は、介護の現場で実際に求められることのある行為です。しかし、介護士は行うことができない医療行為なので、看護師を呼んで、代わりに行ってもらう必要があります。介護士が行えば、医療行為違反になります。
摘便/床ずれの処置/インスリン注射/血糖測定/点滴の管理
これらの医療行為は、介護の現場で実際に求められることのある行為です。しかし、介護士は行うことができない医療行為なので、看護師を呼んで、代わりに行ってもらう必要があります。介護士が行えば、医療行為違反になります。
介護現場でのニーズの高まり
2012年の法改正は、介護現場での医療行為のニーズが高まってきたためです。
現在、要介護者の増加と深刻な看護師不足により、今後ますます、介護士による医療行為の必要性が出てきます。そこで介護士に認められる医療行為の範囲がさらに広がっていくと予想されます。
現在、要介護者の増加と深刻な看護師不足により、今後ますます、介護士による医療行為の必要性が出てきます。そこで介護士に認められる医療行為の範囲がさらに広がっていくと予想されます。
介護士はしっかりと医療行為の認識を
インスリン注射などを、医療行為ではないと認識している利用者や家族が多くいます。介護士も「これくらいだったら」といって、医療行為の一部を行っている現状があります。しかし、医療行為であることには変わらず、一歩間違えば重大な医療ミスにつながり、最悪死に至る可能性があります。
「知らなかった」では済まされず、医療行為違反で書類送検される事件も実際に起こっています。
医療行為が行えるということは、それだけ責任も増えます。
介護士は正しい知識を身に着け、自分に何ができて、何ができないかをしっかりと認識する必要があります。
できないことは看護師に依頼し、自分は介護に専念するというしっかりとした線引きが、良質で安心安全な介護につながるのです。
「知らなかった」では済まされず、医療行為違反で書類送検される事件も実際に起こっています。
医療行為が行えるということは、それだけ責任も増えます。
介護士は正しい知識を身に着け、自分に何ができて、何ができないかをしっかりと認識する必要があります。
できないことは看護師に依頼し、自分は介護に専念するというしっかりとした線引きが、良質で安心安全な介護につながるのです。
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.