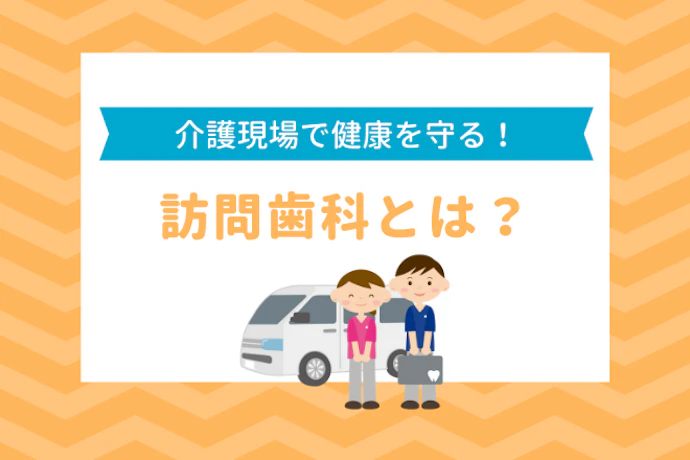介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
介護現場で健康を守る!訪問歯科とは?
#介護
目次
介護現場で大変重宝されている「訪問歯科」というサービス。
具体的にどんなことをするサービスなのか分からない方も多いはずです。
そこでこのコラムでは訪問歯科の
■特徴
■業務内容
■必要資格
■メリット
について詳しくご紹介していきます。
これから目指す方や介護の仕事に少しでも役立てたいと思う方はぜひ参考にしてみてはいかがですか?
はじめに、訪問診療とはなにかというところから説明していきます。
具体的にどんなことをするサービスなのか分からない方も多いはずです。
そこでこのコラムでは訪問歯科の
■特徴
■業務内容
■必要資格
■メリット
について詳しくご紹介していきます。
これから目指す方や介護の仕事に少しでも役立てたいと思う方はぜひ参考にしてみてはいかがですか?
はじめに、訪問診療とはなにかというところから説明していきます。
訪問歯科の特徴とは?
本来は歯科医院などの医療機関で患者をみるところ、歯科医師や歯科衛生士が患者の自宅または施設に直接訪問し、歯科治療や口腔ケアなどの歯科診療を提供するサービスです。
訪問歯科には2種類あり、突発的な疾患が起こり病院などへ行けない事情がある場合に患者の元へ訪問し応急的な診療・処置をすることを「往診」。
患者の求めに応じて定期的に訪問して診察や処置をすることを「在宅診療」または「訪問診療」といいます。
往診も在宅診療も「訪問歯科」という一つのくくりで呼ばれています。
【訪問歯科を受けられる対象者】
誰でも訪問歯科診療を受けられるというわけではありません。
訪問歯科診療の対象者は「通院困難な方」と決められています。
具体的には
上記のように自力通院が難しい方が訪問歯科診療の対象となります。
次に訪問歯科がおこなう業務の内容について見ていきましょう。
訪問歯科には2種類あり、突発的な疾患が起こり病院などへ行けない事情がある場合に患者の元へ訪問し応急的な診療・処置をすることを「往診」。
患者の求めに応じて定期的に訪問して診察や処置をすることを「在宅診療」または「訪問診療」といいます。
往診も在宅診療も「訪問歯科」という一つのくくりで呼ばれています。
【訪問歯科を受けられる対象者】
誰でも訪問歯科診療を受けられるというわけではありません。
訪問歯科診療の対象者は「通院困難な方」と決められています。
具体的には
・介護認定を受けている高齢者
・介護老人保健施設や介護老人福祉施設に入所している高齢者
・障がいがあり身体が不自由な方、病気を持っている方
・歯科、口腔外科がない病院に入院している方
上記のように自力通院が難しい方が訪問歯科診療の対象となります。
次に訪問歯科がおこなう業務の内容について見ていきましょう。
訪問歯科の業務内容とは?
訪問歯科の業務内容は一般的な歯科医院などの医療機関で行われる内容とほぼ変わりはありません。
例えば、虫歯治療や歯石除去、口腔清掃といった虫歯予防のケアなどです。
しかし、特殊な機材など持ち運びができないものもあるため、対応できる範囲内での診療となります。
訪問歯科の患者で一番多い年齢層は高齢者。
高齢者で特に多いのが「食べる事が難しくなっている」という訴えです。
なかでも「入れ歯を壊してしまった」 「入れ歯が合わなくて痛い」といった悩みが非常に多く、この訴えを汲み取りながら歯周病の治療や入れ歯の作製・修理、口腔ケアをおこなっていきます。
また口腔内が汚れていると誤嚥性肺炎を引き起こすリスクもあるためその予防を。
そして口腔内の不具合は食事の意識低下につながるので、食べる意欲を回復させるための口腔機能のリハビリテーションも業務の一部となっています。
口腔機能の維持管理は食べるということばかりではなく、生きる力やQOL(生活の質)の向上にもつながるのです。
診療内容によりますが、なかには歯科医院などで受診することが必要なときもあります。
続いて、実際に訪問歯科をするためにはどんな資格が必要なのかを見ていきましょう。
例えば、虫歯治療や歯石除去、口腔清掃といった虫歯予防のケアなどです。
しかし、特殊な機材など持ち運びができないものもあるため、対応できる範囲内での診療となります。
訪問歯科の患者で一番多い年齢層は高齢者。
高齢者で特に多いのが「食べる事が難しくなっている」という訴えです。
なかでも「入れ歯を壊してしまった」 「入れ歯が合わなくて痛い」といった悩みが非常に多く、この訴えを汲み取りながら歯周病の治療や入れ歯の作製・修理、口腔ケアをおこなっていきます。
また口腔内が汚れていると誤嚥性肺炎を引き起こすリスクもあるためその予防を。
そして口腔内の不具合は食事の意識低下につながるので、食べる意欲を回復させるための口腔機能のリハビリテーションも業務の一部となっています。
口腔機能の維持管理は食べるということばかりではなく、生きる力やQOL(生活の質)の向上にもつながるのです。
診療内容によりますが、なかには歯科医院などで受診することが必要なときもあります。
続いて、実際に訪問歯科をするためにはどんな資格が必要なのかを見ていきましょう。
訪問歯科をするには?
訪問歯科をおこなうためには、
ここからは訪問歯科の主体となる
「歯科医師」
か「認定訪問歯科衛生士」
の資格取得が必要になります。ここからは訪問歯科の主体となる
「認定訪問歯科衛生士」
になるための過程をご紹介します。【認定訪問歯科衛生士】を取得するには
歯科衛生士の免許を取得していることが前提。
歯科衛生士は高等学校を卒業後、歯科衛生士の養成校に進学します。
養成校で必要なカリキュラムを修めることにより受験資格を得ることができます。
その後、国家資格に合格し、厚生労働省の認可を得ることで歯科衛生士になれます。
受験資格
・歯科衛生士として日本訪問歯科協会に2年以上継続して在籍していること
・訪問歯科学会に参加している会員クリニックに2年以上在籍していること
・日本訪問歯科協会の認定する講習会・セミナーに出席すること
また、ブロック研修会や研究会、ワークショップなどに出席しておくと更に良いでしょう。
上記をすべて満たして試験に合格すると訪問歯科認定衛生士として登録が可能になり、日本訪問歯科協会にも登録されます。
歯科医院だと歯科衛生士が常にいるイメージですが、訪問歯科は歯科医師だけでも始めることができます。
しかし、患者の継続的なフォローが必要な場合は歯科衛生士がいる方がいいとされています。
次に、訪問歯科として働くメリットと患者にとってのメリットを見ていきましょう。
歯科衛生士は高等学校を卒業後、歯科衛生士の養成校に進学します。
養成校で必要なカリキュラムを修めることにより受験資格を得ることができます。
その後、国家資格に合格し、厚生労働省の認可を得ることで歯科衛生士になれます。
受験資格
・歯科衛生士として日本訪問歯科協会に2年以上継続して在籍していること
・訪問歯科学会に参加している会員クリニックに2年以上在籍していること
・日本訪問歯科協会の認定する講習会・セミナーに出席すること
また、ブロック研修会や研究会、ワークショップなどに出席しておくと更に良いでしょう。
上記をすべて満たして試験に合格すると訪問歯科認定衛生士として登録が可能になり、日本訪問歯科協会にも登録されます。
歯科医院だと歯科衛生士が常にいるイメージですが、訪問歯科は歯科医師だけでも始めることができます。
しかし、患者の継続的なフォローが必要な場合は歯科衛生士がいる方がいいとされています。
次に、訪問歯科として働くメリットと患者にとってのメリットを見ていきましょう。
訪問歯科のメリットは?
・歯科衛生士が主体となって活躍できる
訪問歯科では、歯科衛生士が単独で患者を訪問し口腔ケアを行うことが出来ます。
治療の関係で歯科医師も訪問する場合がありますがその時はスキルを磨けるチャンスであり働くうえで常に学ぶことができるでしょう。
・患者やそのご家族と親密な関係性を築く事ができる
患者のなかにはコミュニケーションを取ることが困難な場合もあるので治療は大変です。
しかしその分、患者と向き合う時間が長いので、患者やそのご家族との信頼関係を築く事ができ、それが大きなやりがいへと繋がります。
・扱う機材が少なく、ブランクを気にせず働く事ができる
歯科医院などの医療機関での業務と比べ、訪問歯科で使用できる機材は限られています。
「ブランク期間が長く、一から覚え直さないといけない」といったことで悩む場面は少ないでしょう。
患者に関してのメリットも通院しなくてもいいということだけではありません。
歯科医や歯科衛生士が直接患者の食事場面を見ることにより入れ歯の調節や噛み合わせを確認して調節することができるからです。
実際に見てもらうことで患者さんも安心して食事をすることができますね。
ここまで訪問歯科に特化した内容でしたが、実は介護職員にもできることはあります。
訪問歯科では、歯科衛生士が単独で患者を訪問し口腔ケアを行うことが出来ます。
治療の関係で歯科医師も訪問する場合がありますがその時はスキルを磨けるチャンスであり働くうえで常に学ぶことができるでしょう。
・患者やそのご家族と親密な関係性を築く事ができる
患者のなかにはコミュニケーションを取ることが困難な場合もあるので治療は大変です。
しかしその分、患者と向き合う時間が長いので、患者やそのご家族との信頼関係を築く事ができ、それが大きなやりがいへと繋がります。
・扱う機材が少なく、ブランクを気にせず働く事ができる
歯科医院などの医療機関での業務と比べ、訪問歯科で使用できる機材は限られています。
「ブランク期間が長く、一から覚え直さないといけない」といったことで悩む場面は少ないでしょう。
患者に関してのメリットも通院しなくてもいいということだけではありません。
歯科医や歯科衛生士が直接患者の食事場面を見ることにより入れ歯の調節や噛み合わせを確認して調節することができるからです。
実際に見てもらうことで患者さんも安心して食事をすることができますね。
ここまで訪問歯科に特化した内容でしたが、実は介護職員にもできることはあります。
介護職員にもできること
もちろんのことですが、介護職員は医師や歯科衛生士のように治療というものはできません。
しかし、介護職員でもできることはあります。それは日頃の「口腔ケア」です。
「口腔ケア」は口の中を清潔に保つだけではなく、唾液を出しやすくしたり味覚の向上にもつながります。
しかし、介護職員でもできることはあります。それは日頃の「口腔ケア」です。
「口腔ケア」は口の中を清潔に保つだけではなく、唾液を出しやすくしたり味覚の向上にもつながります。
口腔ケアの流れ
1.口の中の状態を確認します。このとき出血、腫れ、口臭などをチェックします。
2.うがいをしてもらいますが、左右の頬を膨らまして動かしてもらうと口の体操にもなります。
3.歯ブラシをするときはできるだけ自力でおこなってもらいましょう。
このとき手が不自由な方であれ電動歯ブラシを使用したり、磨き残しがある場合は介助します。
介助する場合は、歯ブラシとは反対の手指で唇や頬を広げて口の中を磨いていきます。
歯ブラシでは誤嚥の可能性がある方には、介助者は使い捨て手袋を装着し、ガーゼを指に巻いて水で濡らして絞り汚れを取っていきます。細かい部分は歯間ブラシや綿棒などを使うといいでしょう。
4.口腔ケア用のスポンジブラシやウェットティッシュなどを使い、歯茎や上あごなどのデリケートな部分の汚れをとります。
舌の汚れは口臭につながるので舌用ブラシやスポンジブラシで優しくこすりとっていきます。
5.うがいをしてもらいます。
以上のことが介護職員が利用者におこなえる介助になります。
日常で口腔ケアをしっかりおこなっておけば虫歯や病気のリスクも減り、食事もおいしくいただけますので職員は利用者の口腔内をしっかり把握しておくことが大切です。
2.うがいをしてもらいますが、左右の頬を膨らまして動かしてもらうと口の体操にもなります。
3.歯ブラシをするときはできるだけ自力でおこなってもらいましょう。
このとき手が不自由な方であれ電動歯ブラシを使用したり、磨き残しがある場合は介助します。
介助する場合は、歯ブラシとは反対の手指で唇や頬を広げて口の中を磨いていきます。
歯ブラシでは誤嚥の可能性がある方には、介助者は使い捨て手袋を装着し、ガーゼを指に巻いて水で濡らして絞り汚れを取っていきます。細かい部分は歯間ブラシや綿棒などを使うといいでしょう。
4.口腔ケア用のスポンジブラシやウェットティッシュなどを使い、歯茎や上あごなどのデリケートな部分の汚れをとります。
舌の汚れは口臭につながるので舌用ブラシやスポンジブラシで優しくこすりとっていきます。
5.うがいをしてもらいます。
以上のことが介護職員が利用者におこなえる介助になります。
日常で口腔ケアをしっかりおこなっておけば虫歯や病気のリスクも減り、食事もおいしくいただけますので職員は利用者の口腔内をしっかり把握しておくことが大切です。
まとめ
訪問歯科は患者の家や施設に直接出向き、治療をしていく外出が難しい方には非常に便利なサービスであることがお分かりいただけたと思います。
診療所の数%しか訪問歯科をおこなっていません。そしてそのほとんどが大都市圏に集中しているため地方で訪問歯科というサービスが行きわたるのはまだまだこれからというのが現状です。
しかし、高齢化社会がすすんでいるなかで、訪問歯科の必要性はとても高く、将来性があります。
介護現場での口腔ケアもとても大切なことですが、やりきれない部分は訪問歯科に相談したりすることも1つの手です。
ぜひこのコラムを参考にしてみてはいかがでしょうか。
診療所の数%しか訪問歯科をおこなっていません。そしてそのほとんどが大都市圏に集中しているため地方で訪問歯科というサービスが行きわたるのはまだまだこれからというのが現状です。
しかし、高齢化社会がすすんでいるなかで、訪問歯科の必要性はとても高く、将来性があります。
介護現場での口腔ケアもとても大切なことですが、やりきれない部分は訪問歯科に相談したりすることも1つの手です。
ぜひこのコラムを参考にしてみてはいかがでしょうか。
介護のお仕事探しは介護ワーカーにお任せ!
「介護職に転職したい!」「自分に合う職場を見つけたい!」などお考えの方はぜひ
介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください。
<<介護ワーカーを見る>>
介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください。
<<介護ワーカーを見る>>
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.