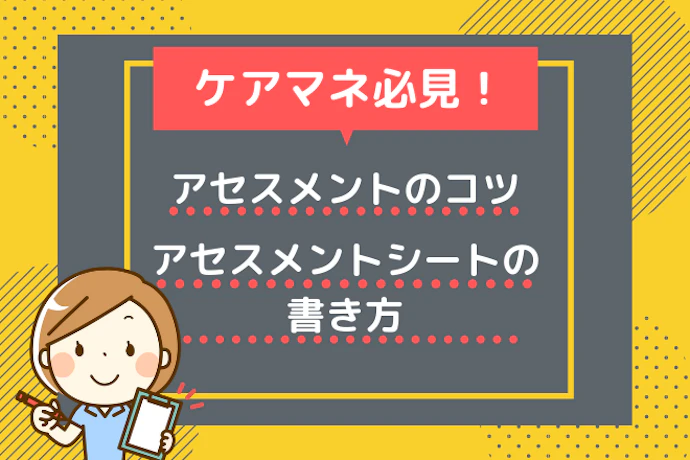介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
ケアマネ必見!アセスメントのコツ&アセスメントシートの書き方まとめ
#介護
目次
ケアマネージャーの大切な業務の1つアセスメント。利用者1人1人にあったケアプランを作成するために欠かせません。
このコラムではそのアセスメントについて内容から書き方まで詳しくまとめていますのでケアマネージャー業務にぜひお役立てください。
はじめに、アセスメントの重要性から解説していきます。
このコラムではそのアセスメントについて内容から書き方まで詳しくまとめていますのでケアマネージャー業務にぜひお役立てください。
はじめに、アセスメントの重要性から解説していきます。
ケアマネの仕事の中核となる「アセスメント」の重要性
そもそもアセスメントとは「評価・評定・査定」などの意味を持っています。
「人材アセスメント」「製品アセスメント」など、多分野で使われている言葉ですが、いずれも「事前に予測・評価する、課題分析」を意味します。
介護分野においては、利用者の心身状態や生活状態、利用者と家族の希望などの情報を聞き出して「どのような介護サービス・ケアが必要なのか」を判断するためにアセスメントをおこないます。
例えば、利用者を介護度別で分け、その全員に同じサービスを提供するだけでは、一人ひとりの「できること」ができなくなり残っている体の機能が低下してしまいます。
また、利用者が希望するケアから大きく外れてしまうとやる気を奪ってしまうことも考えられます。
そこで、利用者一人ひとりに合ったケアプランを作るために、アセスメントが大変重要になるのです。
「人材アセスメント」「製品アセスメント」など、多分野で使われている言葉ですが、いずれも「事前に予測・評価する、課題分析」を意味します。
介護分野においては、利用者の心身状態や生活状態、利用者と家族の希望などの情報を聞き出して「どのような介護サービス・ケアが必要なのか」を判断するためにアセスメントをおこないます。
例えば、利用者を介護度別で分け、その全員に同じサービスを提供するだけでは、一人ひとりの「できること」ができなくなり残っている体の機能が低下してしまいます。
また、利用者が希望するケアから大きく外れてしまうとやる気を奪ってしまうことも考えられます。
そこで、利用者一人ひとりに合ったケアプランを作るために、アセスメントが大変重要になるのです。
アセスメントの質を上げる6つのポイント
介護におけるアセスメントはケアマネージャーの担当で、病院や自宅、施設に訪問し、利用者の生活全般についてその状態を十分把握しなければなりません。
具体的には利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するものです。
そのアセスメントに関して、質を向上させるための次の6つのポイントをご紹介します。
具体的には利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するものです。
そのアセスメントに関して、質を向上させるための次の6つのポイントをご紹介します。
1.訪問は原則1時間以内に済ませる
アセスメントのための初回訪問では介護保険制度の説明やサービスの流れも説明しなければならないのでとても時間がかかります。
長時間にわたってしまうと利用者が疲れてしまったり、なんらかの負担になりかねません。
そのため情報収集は基本的な事だけに絞り、1時間~1時間半ほどで切り上げましょう。
また、開始前にどのくらい時間がかかるか、トイレに行きたかったり疲れたときは言うように伝えておくと、見通しがつき要介護者さんは安心してくれます。
長時間にわたってしまうと利用者が疲れてしまったり、なんらかの負担になりかねません。
そのため情報収集は基本的な事だけに絞り、1時間~1時間半ほどで切り上げましょう。
また、開始前にどのくらい時間がかかるか、トイレに行きたかったり疲れたときは言うように伝えておくと、見通しがつき要介護者さんは安心してくれます。
2.事前に他職種・他機関から情報収集しておく
病院や施設から紹介された利用者については、これまでの病歴や家族構成、生活歴、入院(入居)中のADLなどの情報収集をおこなっておきます。また、初回訪問前に介護相談員や医療ソーシャルワーカーなどからら情報を事前に集めることで、的外れな質問を避け時間短縮にもなります。さまざまな角度からの情報を集めることによって、より正確に利用者の心身の状態を把握することが出来るでしょう。
3.利用者の立場に立って一緒に考える
ケアマネジャーの質問の仕方によっては、利用者や家族が言いたいことを言えなくなってしまうケースも。
正しい情報を得るために利用者が安心してくれるような姿勢で考えましょう。
粘り強く情報を掘り下げていく姿勢は「自分のことを考えてくれている」という評価に繋がり、相手との信頼関係にも繋がっていきます。
正しい情報を得るために利用者が安心してくれるような姿勢で考えましょう。
粘り強く情報を掘り下げていく姿勢は「自分のことを考えてくれている」という評価に繋がり、相手との信頼関係にも繋がっていきます。
4.課題やニーズを具体的に把握する
現在の生活にどのような支障があるのかその状況を具体的に把握し、関連情報を集めていきます。
さらに動作を細かく分割するなど、どこまで出来るか、どこから支障があるのかを明らかに
していくのです。
例えば【転んだ:いつ?、どのような場面で?、何をしていた時?】などです。
上記のように利用者に起こりうる危険性を予測することなどにより、潜在化
している課題を発見し、課題の見落としを防ぎましょう。
さらに動作を細かく分割するなど、どこまで出来るか、どこから支障があるのかを明らかに
していくのです。
例えば【転んだ:いつ?、どのような場面で?、何をしていた時?】などです。
上記のように利用者に起こりうる危険性を予測することなどにより、潜在化
している課題を発見し、課題の見落としを防ぎましょう。
5.インフォームドコンセントを行う
専門的な助言をする時は、利用者の希望や意思を尊重しながら、説明と了解を得ること(インフォームドコンセント)を実践します。
いいことも悪いことも伝える時は、利用者の自尊心を傷つけないように併せて介護計画の芯がぶれないように注意しましょう。
いいことも悪いことも伝える時は、利用者の自尊心を傷つけないように併せて介護計画の芯がぶれないように注意しましょう。
6.情報の必要性を精査して記録する
情報の必要性を精査し記録しておくことで、多種多様な介護サービスのうち、最も適切な支援が受けられる介護サービス、介護事業所を見つけ出すことができるのです。<あわせて読みたい>
■「ケアマネージャーってどんな資格?」
■「ケアマネージャーってどんな資格?」
アセスメントシートの作成のポイント
アセスメントでは、アセスメントシートにのっとって情報を聞き取り、記録していきます。
「課題分析標準項目」の23項目を聞き取り
国が定めた『課題分析標準項目』の23の情報項目が最低限の聞き取り事項となります。
1. 基本情報
氏名、性別、住所、電話番号など利用者の基礎となる情報を記入します。
2.生活状況
現在の生活状況や生活歴などを記入します。
3.利用者の介護保険などの被保険者情報
介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無などを記入します。
4.現在利用している介護サービス等の状況
介護保険かどうかは問わず、利用者が現在受けているサービスの状況を記入します。
5.障害高齢者の日常生活自立度―ランクJ〜Cの日常生活自立度
寝たきり度などの日常生活レベルを把握し記入します。
6.認知症高齢者日常生活自立度―自立ランクⅠ〜Mの認知症の方の日常生活自立度
移動が自立しているか、車いす・歩行器などの補助が必要かといった移動に関する情報は、支援方針を決定する上で重要です。
基本的な枠組みはチェックリストにまとめて、詳細は特記事項に記載するとよいでしょう。
7.主訴(利用者やご家族の主な希望、要望)
本人の意思はすべてにおいて最も尊重されます。
アセスメントシートにおける要望・希望が、抽象的になってしまうと、支援の方針が意にそぐわないことになりかねません。
本人の主張に真摯に耳を傾け情報を正確に記載しましょう。
8.認定情報
利用者の要介護度区分など認定結果の情報を記入します。
9.課題分析(アセスメント)理由
初回、定期、退院退所時等を記入します。
10.健康状態
利用者の健康状態について記入します。
11.ADL(日常生活動作)に関する項目
寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等の日常生活動作について記入します。
12.IADL(手段的日常生活動作)に関する項目
調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等の手段的日常生活動作について記入します。
評価は「自立可」「見守りなどの程度であれば可」「一部介助有」「全介助」の4種類。
13.認知
日常の意思決定がどのくらいできるかなどの認知能力のレベルに関する項目です。
14.コミュニケーション能力
意思の伝達、視力、聴力等の意思疎通に関する基本的な能力を評価します。
15.社会との関わり―社会との関わりに関する項目
社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等の社会との関わりの状況を記入します。
16.排尿・排便
排泄の頻度、ポータブルトイレ、おむつなどの使用状況の項目です。
失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法なども聞き取ります。
17.褥瘡・皮膚の問題
褥瘡(じょくそう)、皮膚の清潔状況などを記入します。
18.口腔衛生
歯や口腔内の状態、衛生に関する状況を記入します。
19.食事摂取
栄養、食事回数、水分量などに関する状況を記入します。
20.問題行動
暴言暴行の有無、徘徊(はいかい)、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動などの状況を記入します。
21.介護力
介護者の有無や介護者に関する情報などの介護力に関する状況を記入します。
22.居住環境
利用者の居住環境、住宅改修の必要性についての状況を記入式や図面式で記入します。
介護度合いが高い方は、バリアフリーがどの程度整備されているのかが重要になります。
バリアフリー未整備であったりバリアフリーだが自宅での転倒が多いなど、機能が不完全な住環境の場合もあります。
その場合は、利用者の特性にマッチした住環境というものを、支援の取り組みとして提案することもあります。
23.特別な状況
介護者による虐待や終末期ケア(ターミナルケア)に関する状況を記入。
基本情報に関する項目
1. 基本情報
氏名、性別、住所、電話番号など利用者の基礎となる情報を記入します。
2.生活状況
現在の生活状況や生活歴などを記入します。
3.利用者の介護保険などの被保険者情報
介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無などを記入します。
4.現在利用している介護サービス等の状況
介護保険かどうかは問わず、利用者が現在受けているサービスの状況を記入します。
5.障害高齢者の日常生活自立度―ランクJ〜Cの日常生活自立度
寝たきり度などの日常生活レベルを把握し記入します。
6.認知症高齢者日常生活自立度―自立ランクⅠ〜Mの認知症の方の日常生活自立度
移動が自立しているか、車いす・歩行器などの補助が必要かといった移動に関する情報は、支援方針を決定する上で重要です。
基本的な枠組みはチェックリストにまとめて、詳細は特記事項に記載するとよいでしょう。
7.主訴(利用者やご家族の主な希望、要望)
本人の意思はすべてにおいて最も尊重されます。
アセスメントシートにおける要望・希望が、抽象的になってしまうと、支援の方針が意にそぐわないことになりかねません。
本人の主張に真摯に耳を傾け情報を正確に記載しましょう。
8.認定情報
利用者の要介護度区分など認定結果の情報を記入します。
課題分析(アセスメント)に関する項目
9.課題分析(アセスメント)理由
初回、定期、退院退所時等を記入します。
10.健康状態
利用者の健康状態について記入します。
11.ADL(日常生活動作)に関する項目
寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等の日常生活動作について記入します。
12.IADL(手段的日常生活動作)に関する項目
調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等の手段的日常生活動作について記入します。
評価は「自立可」「見守りなどの程度であれば可」「一部介助有」「全介助」の4種類。
13.認知
日常の意思決定がどのくらいできるかなどの認知能力のレベルに関する項目です。
14.コミュニケーション能力
意思の伝達、視力、聴力等の意思疎通に関する基本的な能力を評価します。
15.社会との関わり―社会との関わりに関する項目
社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等の社会との関わりの状況を記入します。
16.排尿・排便
排泄の頻度、ポータブルトイレ、おむつなどの使用状況の項目です。
失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法なども聞き取ります。
17.褥瘡・皮膚の問題
褥瘡(じょくそう)、皮膚の清潔状況などを記入します。
18.口腔衛生
歯や口腔内の状態、衛生に関する状況を記入します。
19.食事摂取
栄養、食事回数、水分量などに関する状況を記入します。
20.問題行動
暴言暴行の有無、徘徊(はいかい)、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動などの状況を記入します。
21.介護力
介護者の有無や介護者に関する情報などの介護力に関する状況を記入します。
22.居住環境
利用者の居住環境、住宅改修の必要性についての状況を記入式や図面式で記入します。
介護度合いが高い方は、バリアフリーがどの程度整備されているのかが重要になります。
バリアフリー未整備であったりバリアフリーだが自宅での転倒が多いなど、機能が不完全な住環境の場合もあります。
その場合は、利用者の特性にマッチした住環境というものを、支援の取り組みとして提案することもあります。
23.特別な状況
介護者による虐待や終末期ケア(ターミナルケア)に関する状況を記入。
分かりやすいアセスメントシートの書き方とは
アセスメントシートはケアマネジャーのメモではないため、利用者の情報として誰が見ても理解できるように記入しなければなりません。
書き方としては、現状の問題を知ったうえで原因を追及、どんなリスクがあるかを考え対策方法などを詳しく記録していきます。
書くポイントとして以下のことがあげられます。
・どこまで一人でできて、どこから一人でできないか
・できるのにやっていないこと、拒否していることはないか
・最終的にどうなりたいか、そのために必要なことは何か
・5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を明確にする
・利用者のニーズ・訴えに対しての問題点やリスク、解決しうる環境などを具体的に明記する
・主観を入れず客観的に記載する
・「娘の希望」ではなく「長女の希望」などと主語を明確にする
・できるだけ略語は使用せず正式名称を使用する(略語を使用する場合は、広く周知されているものを選ぶ)
以上のポイントをふまえて分かりやすいアセスメントシートにまとめていきましょう。
書き方としては、現状の問題を知ったうえで原因を追及、どんなリスクがあるかを考え対策方法などを詳しく記録していきます。
書くポイントとして以下のことがあげられます。
・どこまで一人でできて、どこから一人でできないか
・できるのにやっていないこと、拒否していることはないか
・最終的にどうなりたいか、そのために必要なことは何か
・5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を明確にする
・利用者のニーズ・訴えに対しての問題点やリスク、解決しうる環境などを具体的に明記する
・主観を入れず客観的に記載する
・「娘の希望」ではなく「長女の希望」などと主語を明確にする
・できるだけ略語は使用せず正式名称を使用する(略語を使用する場合は、広く周知されているものを選ぶ)
以上のポイントをふまえて分かりやすいアセスメントシートにまとめていきましょう。
アセスメントシートの5つの様式と選び方
アセスメントシートには5つの様式が存在します。
施設によって使用しているものは異なりますのでご注意下さい。
1つずつどのようなシートなのかを見ていきましょう。
施設によって使用しているものは異なりますのでご注意下さい。
1つずつどのようなシートなのかを見ていきましょう。
インターライ方式
在宅・施設どちらにも使用可能。
在宅と施設を行き来する機会が多い高齢者のアセスメントツールとして定評があります。
精神面・健康問題・ケアの管理・機能面・感覚面・失禁の管理の6領域を包括的に把握できるように工夫されています。
在宅と施設を行き来する機会が多い高齢者のアセスメントツールとして定評があります。
精神面・健康問題・ケアの管理・機能面・感覚面・失禁の管理の6領域を包括的に把握できるように工夫されています。
包括的自立支援プログラム
全国老人保健施設協会、全国老人福祉施設協議会、介護力強化病院連絡協議会の3団体が開発したもの。
要介護認定に用いる認定調査票と連動していることが最大の特徴。
施設用ケアプランであるが、在宅復帰のためのケアプランも作成でき、入居から退去後まで一貫した計画作成が可能。
すでに家族から提供されているケアやサービス提供機関において提供されているケアの現状をチェックするためケアの継続性が確保されやすいです。
要介護認定に用いる認定調査票と連動していることが最大の特徴。
施設用ケアプランであるが、在宅復帰のためのケアプランも作成でき、入居から退去後まで一貫した計画作成が可能。
すでに家族から提供されているケアやサービス提供機関において提供されているケアの現状をチェックするためケアの継続性が確保されやすいです。
ケアマネジメント実践記録様式
課題分析の内容が最も広く細部に及びます。
「本人・家族等の意見・要望」と「アセスメント担当者が判断した問題」を記述するスペースがあり、包括的なニーズ把握に効果的。
また、対象者の正確な状態像が把握できるように自由記述欄を設けている。
利用者の心身の状態だけでなく、介護者の健康状態や介護負担など、家族の介護状
況や住宅環境も詳細にアセスメントするようになっているため長時間を要する。
現在ではモニタリング用紙も開発されており、ケアプランの立てっぱなし、サービスのやり
っぱなしを予防できます。
「本人・家族等の意見・要望」と「アセスメント担当者が判断した問題」を記述するスペースがあり、包括的なニーズ把握に効果的。
また、対象者の正確な状態像が把握できるように自由記述欄を設けている。
利用者の心身の状態だけでなく、介護者の健康状態や介護負担など、家族の介護状
況や住宅環境も詳細にアセスメントするようになっているため長時間を要する。
現在ではモニタリング用紙も開発されており、ケアプランの立てっぱなし、サービスのやり
っぱなしを予防できます。
日本介護福祉士会方式
要介護者の生活状況を把握するために「衣・食・住・体の健康・心の健康・家族関係・社会関係」の7領域から課題分析を行います。
訪問介護の活動実践をベースに開発された様式で、要介護者自身の意思・価値観・生活リズムを重視しています。
訪問介護の活動実践をベースに開発された様式で、要介護者自身の意思・価値観・生活リズムを重視しています。
日本訪問看護振興財団方式
主に在宅で生活している成人・高齢者が中心であるが、施設でも使用できます。
複数回記入できる方式を取っているので今までの経緯を確認できるメリットがある反面、調査項目が細かく、アセスメントに時間を要することも。
ターミナルから在宅医療を受けている人まで幅広い対象者のケアプラン作成が可能。
本人のみならず家族や介護者の状況や家事援助など生活支援から疾病の管理まで、幅広いニーズを把握できます。
複数回記入できる方式を取っているので今までの経緯を確認できるメリットがある反面、調査項目が細かく、アセスメントに時間を要することも。
ターミナルから在宅医療を受けている人まで幅広い対象者のケアプラン作成が可能。
本人のみならず家族や介護者の状況や家事援助など生活支援から疾病の管理まで、幅広いニーズを把握できます。
まとめ
アセスメントシートの情報収集は、解決しなければならない課題と利用者の心身状況を明らかにし、援助方針を導くための役目を持っています。
情報が欠落していると大きな事故や実施指導の指摘に繋がるおそれがあるのでケアマネジャーはアセスメントスキルをしっかり身につけ正確にアセスメントしなければなりません。
知識・スキルを向上させ、適切な介護の提供と利用者の自立生活を実現するケアプラン作成のため、品質の良いアセスメントを目指していきましょう。
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
情報が欠落していると大きな事故や実施指導の指摘に繋がるおそれがあるのでケアマネジャーはアセスメントスキルをしっかり身につけ正確にアセスメントしなければなりません。
知識・スキルを向上させ、適切な介護の提供と利用者の自立生活を実現するケアプラン作成のため、品質の良いアセスメントを目指していきましょう。
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
※掲載情報は公開日あるいは2020年07月27日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.