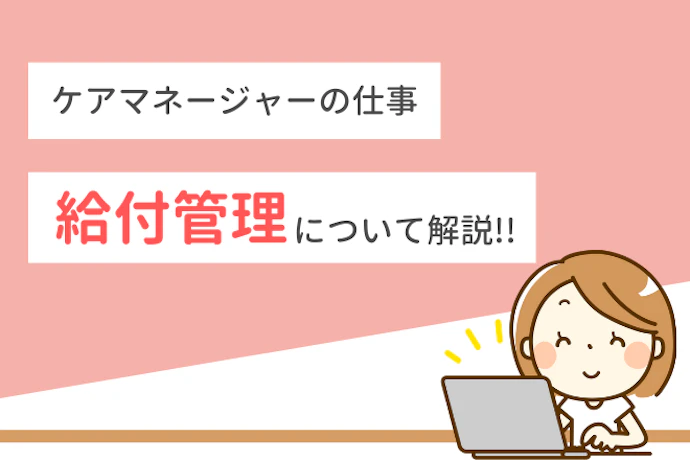介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
居宅ケアマネの仕事、給付管理業務をわかりやすく解説!
#介護
目次
ケアマネージャーの仕事の1つに「給付管理」という業務があります。
毎月の介護給付費(介護報酬)を受給するうえで欠かせない重要な業務です。
本コラムでは、この給付管理について解説していきます。
業務の流れや、注意すべきポイントをわかりやすくお伝えしますのでぜひ参考にしてください。
毎月の介護給付費(介護報酬)を受給するうえで欠かせない重要な業務です。
本コラムでは、この給付管理について解説していきます。
業務の流れや、注意すべきポイントをわかりやすくお伝えしますのでぜひ参考にしてください。
給付管理とは?
給付管理とは利用者の介護費や支援費の支給限度額を管理することで、主に居宅介護支援事業所のケアマネージャーが行う業務です。
(事業所によっては事務員が行う場合もあります。)
・
・
・
といったことを毎月確認します。
ではまず、給付管理の流れから見ていきましょう。
(事業所によっては事務員が行う場合もあります。)
・
計画通りに介護サービスが提供されているか
・
サービス事業所に介護報酬がきちんと支払われているか
・
利用者から介護費(自己負担分)が適正に徴収されているか
といったことを毎月確認します。
ではまず、給付管理の流れから見ていきましょう。
給付管理の流れ
給付管理の全体図です。
ケアマネージャーは給付管理の中心(居宅介護支援事業所)にいます。
要介護者(支援者)が居宅介護支援事業所にサービスを依頼します。
依頼を受けたケアマネージャーは利用者のケアプランを月単位で決定。
ケアマネージャーから各サービス事業者にサービスを依頼します。
サービス事業者はケアプランに基づいて利用者に介護サービスを提供。
ケアマネージャーはその月に提供されたサービス内容を確認。
内容に不備がなく受理されれば、国保連から各事業者に介護給付費が支払われます。
この一連の流れを給付管理といいます。
給付管理に必要な書類
次に、給付管理業務でケアマネージャーが作成しなければならない書類についてご説明していきます。
サービス利用票とサービス利用票別表
まず「サービス利用票」と「サービス利用票別表」の作成が必要です。
サービス利用票には、ひと月あたり利用者にどのようなサービスを提供するかを記入。
サービス利用票別表には、利用者の支給限度額や負担額の概算を記入します。
記載内容を利用者と一緒に確認し、承認をもらいます。
サービス利用票には、ひと月あたり利用者にどのようなサービスを提供するかを記入。
サービス利用票別表には、利用者の支給限度額や負担額の概算を記入します。
記載内容を利用者と一緒に確認し、承認をもらいます。
それぞれ2部作成し、1部は利用者に、1部は控えに
します。サービス提供票とサービス提供票別表
サービス提供票は、提供するサービス内容と各サービス事業者について書かれている書類です。サービス利用票から事業者に必要となる情報を転記したもので、この内容をもとに事業者は介護サービスを提供します。
サービス提供票別表は、サービス提供票の実績内容を数値化したもので、支給限度額の管理を行うための書類です。
ケアマネージャーは
事業者は月の終わりに実績を追記し、ケアマネージャーに戻します。
サービス提供票別表は、サービス提供票の実績内容を数値化したもので、支給限度額の管理を行うための書類です。
ケアマネージャーは
この2点を各サービス事業者に交付
します。事業者は月の終わりに実績を追記し、ケアマネージャーに戻します。
給付管理票
介護給付費を請求するためには、
給付管理票の記入項目はサービス事業者、サービスの種類、給付計画単位数などです。事業者から返送されたサービス提供票・別表と、サービス利用票の控えを照らし合わせて内容を確認し、給付管理票に転載していきます。
必要に応じて居宅介護給付費請求書も作成し、あわせて提出します。
毎月、国保連に給付管理票という書類を提出
しなければなりません。給付管理において最も重要な業務です。給付管理票の記入項目はサービス事業者、サービスの種類、給付計画単位数などです。事業者から返送されたサービス提供票・別表と、サービス利用票の控えを照らし合わせて内容を確認し、給付管理票に転載していきます。
必要に応じて居宅介護給付費請求書も作成し、あわせて提出します。
給付管理業務における注意点
給付管理において特に注意すべきことは、次の3点です。
1|締め切りに間に合わせる
介護給付費の
期限を過ぎると介護報酬の支給が翌月に持ち越しとなり、サービス事業者にも多大な迷惑をかけることになります。
そんなことになれば事業者との関係性も悪化しかねません。
月初は
申請手続き(給付管理票の提出)は翌月10日まで
となっています。期限を過ぎると介護報酬の支給が翌月に持ち越しとなり、サービス事業者にも多大な迷惑をかけることになります。
そんなことになれば事業者との関係性も悪化しかねません。
月初は
前もってスケジュールを確保しスピーディーに
手続きを進められるようにしておきましょう。2|内容に不備がないかチェック
提出書類に不備があった場合には書類が返戻されて書き直しとなります。
こちらも10日を過ぎれば、同様に介護給付費の支給が遅れます。
サービス変更などがある場合には事業者へ詳しい内容を確認したり、提出前のダブルチェックを徹底するなど
こちらも10日を過ぎれば、同様に介護給付費の支給が遅れます。
サービス変更などがある場合には事業者へ詳しい内容を確認したり、提出前のダブルチェックを徹底するなど
ミスや書き漏れが起こらない仕組みを作り
、内容不備で返戻されてしまうことがないようにしましょう。3|利用者の満足度を確認
利用者がケアプランの通りに適切な介護サービスを受けられているか、ご本人やご家族に必ずモニタリングをしましょう。
遠慮して不満や負担をなかなか口にできない利用者もいますので、
また介護職員とも積極的にコミュニケーションをとり、現場の意見を聞いたり、情報収集をすることも重要です。
<関連コラム>
介護におけるモニタリングとは?実践に役立つポイント・注意点・書き方をご紹介!
遠慮して不満や負担をなかなか口にできない利用者もいますので、
話を聞く姿勢、利用者が話しやすい雰囲気づくりが大切
です。また介護職員とも積極的にコミュニケーションをとり、現場の意見を聞いたり、情報収集をすることも重要です。
<関連コラム>
介護におけるモニタリングとは?実践に役立つポイント・注意点・書き方をご紹介!
まとめ
ケアマネージャーが毎月やらなければいけない給付管理業務について解説しました。
給付管理はつい毎月の事務作業になってしまいがちですが、利用者に適切な介護サービスを提供するうえでとても重要な役割を担っています。
書類作成に追われる中でも、常に利用者視点を持つことを意識して業務を行うことが大切です。
給付管理はつい毎月の事務作業になってしまいがちですが、利用者に適切な介護サービスを提供するうえでとても重要な役割を担っています。
書類作成に追われる中でも、常に利用者視点を持つことを意識して業務を行うことが大切です。
ケアマネージャーのお仕事探しは介護ワーカーへ!
「ケアマネとしてより良い条件で働きたい!」
「キャリアアップできる環境で働きたい!」
そんなあなたはぜひ、業界最大手の介護ワーカーをご利用ください。
一般には掲載されていない非公開求人も多数!
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの転職をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★ケアマネの求人を見てみる
「キャリアアップできる環境で働きたい!」
そんなあなたはぜひ、業界最大手の介護ワーカーをご利用ください。
一般には掲載されていない非公開求人も多数!
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの転職をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★ケアマネの求人を見てみる
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月12日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.