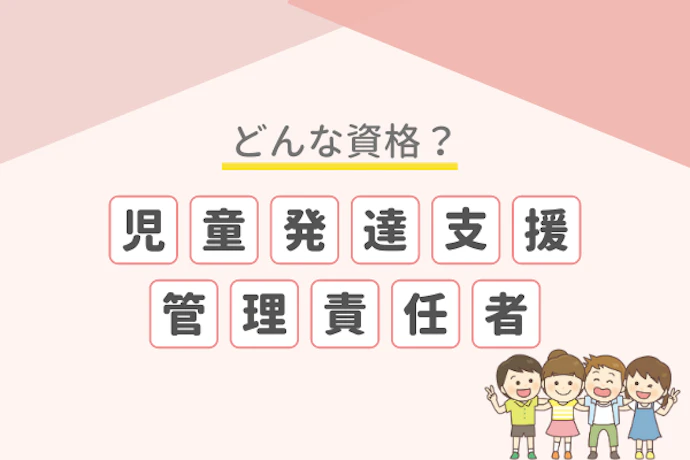介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
児童発達支援管理責任者資格とは?取得要件や研修も詳しく解説!
#介護
目次
障がい児支援施設での仕事に興味ある方のなかには、聞いたことがあるという方もいるのではないでしょうか。
児童発達支援管理責任者とはどのような資格なのか、また仕事内容や資格取得するために必要な要件や研修など詳しく解説していきます。
さっそく見ていきましょう!
児童発達支援管理責任者とは?
児童発達支援管理責任者は「児発管(じはつかん)」「児発(じはつ)」と略称で呼ばれることもあります。
児童発達支援管理責任者の仕事内容
なかでも、個別支援計画書の作成や管理の仕事は児童発達支援管理責任者として重要な仕事です。
個別支援計画書は、作成するにあたってアセスメントやモニタリングをおこない、子ども自身の希望、家族の希望などを聞き、目標や支援方針、支援内容など計画していきます。
利用する子どもや家族のニーズをくみ取り、目標を立てていくことが必要とされるため、これまでの現場で培った経験や知識が必要とされる業務です。
児童発達支援管理責任者の具体的な仕事内容例は以下。
□個別支援計画書の作成
□利用者のアセスメント
□利用者・家族との面接
□利用者・家族へ個別支援計画書の説明と交付
□サービス提供者(職員・従業員)に対する技術的な指導・助言
□支援内容に関連する関係機関との連絡・調整
□個別支援計画書の作成にかかわる会議の運営
□個別支援計画の実施状況をモニタリング
□定期的なモニタリング結果の記録
□個別支援計画書の変更・修正
□自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
□利用者の送迎
など
現場で児童と一緒に過ごし支援をおこなうことは、個別支援計画書に基づいた支援がきちんとおこなわれているのか、また支援内容は適切であるかを確認するモニタリング業務にも繋がります。児童の表情など些細なことも見逃さないよう意識しておくことが大切です。
児童発達支援管理責任者資格を取得するには?
資格取得までの流れとしては以下のようになります。
<資格取得までの流れ>
実務経験の要件を満す
↓
児童発達支援管理責任者基礎研修の受講と修了
↓
OJT
↓
児童発達支援管理責任者実践研修の受講と修了
↓
児童発達支援管理責任者資格の取得
まずは、実務経験の要件が満たせているかを確認してみましょう。
しかしながら、この実務経験の要件が少し複雑になっていて、分かりにくいというのが事実。そこで、実務経験の要件をつぎで分かりやすく解説していきたいと思います。
実務経験の要件を分かりやすく解説!
実務経験の要件は以下3つのいずれかに該当していることです。
A)5年以上の相談支援業務の経験がある
B)8年以上の直接支援業務の経験がある
C)国家資格の有資格者としてそれに係る実務経験が5年以上、相談または直接支援業務の実務経験が3年以上ある
AとBについては、高齢者分野の実務経験も「実務経験年数」に含めることは可能ですが、児童または障害者に対する支援業務に従事した期間が通算3年以上必要です。
児童発達支援管理責任者の実務経験とみなされる業務の範囲は以下の表でご確認ください。
業務の種類 | 業務の範囲 | 必要経験年数 |
(A)相談支援業務 | (a)相談支援業に従事する者 地域生活支援事業 障害児相談支援事業 身体障害者相談支援事業 知的障害者相談支援事業 | 通算5年以上 ※上記経験年数のうち、*印が記載された施設以外での業務経験が通算3年以上必要です。 |
(b)相談機関等において相談支援業務に従事する者 児童相談所 児童家庭支援センター 身体障害者更生相談所 精神障害者社会復帰施設 知的障害者更生相談所 福祉事務所 発達障害者支援センター | ||
(c)施設等において相談支援業務に従事する者 障害児入所施設 乳児院 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設 精神保健福祉センター* 救護施設* 更生施設* 老人福祉施設* 介護老人保健施設* 地域包括支援センター* | ||
(d)就労視線に関する相談支援の業務に従事する者 障害者職業センター 障害者就業・生活支援センター | ||
(e)学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者 幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 高等専門学校 | ||
(f)医療機関において相談支援業務に従事するもので、次のいずれかに該当する者 病院 診療所 | ||
(B)直接支援業務 | (a)施設等において介護業務に従事する者 障害児入所施設 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 認可保育所 幼保連携型認定こども園 児童更生施設 児童家庭支援センター 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設 老人福祉施設* 介護老人保健施設* 病院または診療所の療養病床* | 通算8年以上 ※上記経験年数のうち、*印が記載された施設以外での業務経験が通算3年以上必要です。 |
(b)事業所等において介護業務に従事する者 障害児通所支援事業 児童自立支援生活援助事業 放課後児童健全育成事業 子育て短期支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 小規模住居型児童養育事業 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 病児保育事業 子育て援助活動支援事業 障害福祉サービス事業 老人居宅介護等事業* | ||
(c)医療機関等において介護業務に従事する者 保険医療機関 保険薬局 訪問看護事業所 | ||
(d)障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事するもの 特例子会社* 重度障害者多数雇用事業所における就業支援業務従事者* | ||
(e)学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者 幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 高等専門学校 | ||
(C)有資格者 | (a)次のいずれかに該当するもの (1)社会福祉主事任用資格 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために 必要な知識および技術を習得したものと認められるもの (3)保育士 (4)児童指導員任用資格者 (5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者 | 直接支援業務の経験が通算5年以上 ※上記経験年数のうち、(B)の*印が記載された施設以外での業務経験が通算3年以上必要です。 |
(b)国家資格による従事期間が通算5年以上の者 【国家資格】 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 | (A)+(B)の経験が通算3年以上 ※上記経験年数のうち、*印が記載された施設以外での業務経験が通算3年以上必要です。 |
<< 注意! >>
実務経験の要件に含まれる業務の範囲は、各都道府県で異なる場合があります。
申し込みをする場合は、働く都道府県の「資格要件」を必ず確認してください。
児童発達支援管理責任者の研修(基礎研修・実践研修)について
新しくなった児童発達支援管理責任者の研修は、以下表のように大きく3つに分けられます。
それでは、新しくなった児童発達支援管理責任者研修ついて見ていきましょう。
基礎研修について
〇相談支援従事者初心者研修(講義の一部を受講)
〇サービス管理責任者等研修(研修内容統一)研修講義・演習を受講
それぞれの研修内容について見ていきましょう。
【相談支援従事者初心者研修 講義部分】計11時間
講義 | (1)障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 | 5時間 |
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義 | 3時間 | |
(3)相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 | 3時間 |
講義 | (1)サービス管理責任者・児童発達管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義 | 7.5時間 |
演習 | (2)サービス提供プロセスの管理に関する演習 | 7.5時間 |
OJTについて
児童発達支援管理責任者を取得するためのOJTは、基礎研修修了後に「相談支援業務」または「直接支援業務」に通算2年以上従事することが必要です。
OJT期間2年以上を満たすことで、次の実践研修を受講することが可能になります。
実践研修について
実践研修の研修内容は以下です。
【サービス管理責任者等実践研修(講義・演習)】計14.5時間
講義 | (1)障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |
演習 | (2)サービス提供に関する講義及び演習 | 6.5時間 |
(3)人材育成の手法に関する講義及び演習 | 2.5時間 | |
(4)多職種及び地域連携に関する講義及び演習 | 3.5時間 |
5年ごとの更新研修について
5年ごとの受講
が必要になりました。更新研修での研修内容は以下の通りです。
【サービス管理責任者等更新研修(講義・演習)】計13時間
講義 | (1)障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |
講義・演習 | (2)サービス提供の自己検証に関する演習 | 5時間 |
(3)サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び演習 | 7時間 |
児童発達支援管理責任者はどこで働ける?
児童発達支援管理責任者が活躍できる場は幅広く、さまざまな職場で働くことが可能です。
働ける施設は、大きく分けると下記の2つに分類されます。
◇障がい児通所支援
◇障がい児入所支援
それぞれに分類される施設は以下の通りです。
【障がい児通所支援施設】
●児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業類型)
●医療型児童発達支援
●放課後等デイサービス
●保育所等訪問支援
【障がい児入所支援施設】
●知的障がい児施設
●第一種自閉症児施設
●第二種自閉症児施設
●盲児施設
●ろうあ児施設
●肢体不自由児施設
●肢体不自由児療護施設
●重症心身障がい児施設
上記に挙げたすべての施設事業所は「児童発達支援管理責任者を1名以上配置しなければならない」という配置基準が定められています。
そのため勤務先を探す際は、働きたい施設で求人を検索すると希望している施設を見つけやすくなります。
まとめ
そのため、資格を取得するにはそれなりの実務経験や研修の修了が必要とされます。また、資格取得後も5年ごとに資格更新のための研修を受講することも必要です。
児童発達支援管理責任者資格は、取得までに年数必要とする資格ではありますが、介護職としての経験や知識、介護資格を活かせる仕事といえるでしょう。子どもと関わりながら介護の経験を活かしたい方、今後スキルアップを目指している方におすすめの資格です。
障がい児支援施設への転職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!
介護職での転職をお考えの方へ!
「障がい者支援に関するスキルをつけたい」
などお考えの方はぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護