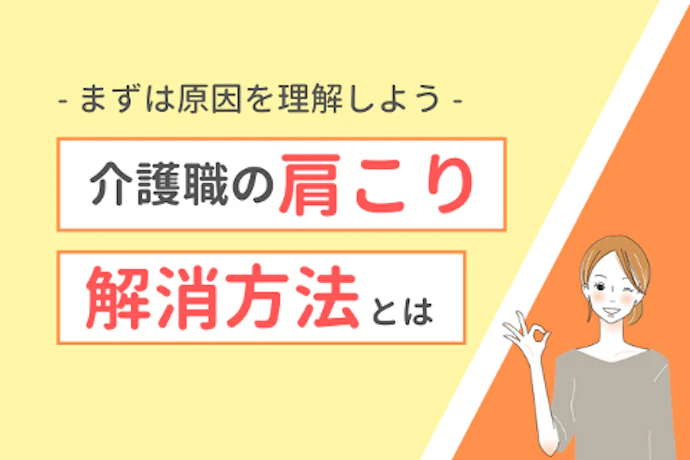介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
介護職に多い肩こりを劇的に解消する5つの方法!
#介護
目次
介護職員にとって、肩こりは腰痛の次に多い悩み。
利用者の介助をする際は腰や肩に負担がかかります。
また案外デスクワークも多いため、猫背など悪い姿勢になりがちです。
肩こりが悪化してしまうと、頭痛を引き起こしたり、痛みで仕事が続けられなくなる可能性もありますので、「たかが肩こり」と放置せず、できるだけ解消するようにしたいものですね。
本コラムでは、肩こり解消に効果的な5つの方法をお伝えしていきます!
<<腰痛にお悩みの方はこちら>>
介護職の腰痛を予防するには?!知っておきたい3つのポイントと対策
利用者の介助をする際は腰や肩に負担がかかります。
また案外デスクワークも多いため、猫背など悪い姿勢になりがちです。
肩こりが悪化してしまうと、頭痛を引き起こしたり、痛みで仕事が続けられなくなる可能性もありますので、「たかが肩こり」と放置せず、できるだけ解消するようにしたいものですね。
本コラムでは、肩こり解消に効果的な5つの方法をお伝えしていきます!
<<腰痛にお悩みの方はこちら>>
介護職の腰痛を予防するには?!知っておきたい3つのポイントと対策
介護職に肩こりが多い原因
肩こりになる原因は色々あり、いくつかの要因が重なって起こる場合もあります。
主な原因には
・運動不足
・血行不良
・身体のゆがみ
・眼精疲労
・ストレス
などが挙げられます。
まずは何といっても運動不足。
筋力が低下し筋肉が緊張していきます。
次に身体のゆがみ。
決まった体勢を続けることでゆがみが生じ、肩こりにつながります。
介護職の場合、「いつも同じ足で踏ん張っている」「腰をかばう動きになる」など、身体のゆがみによって肩こりになっている人も多いのではないかと思います。
さらに眼精疲労からも肩こりは起こります。
仕事でパソコンやタブレットを使用しますし、今や誰もがスマホを持っている時代。小さな文字を凝視することやブルーライトを浴びることで眼を酷使しています。
また意外かもしれませんが、ストレスも肩こりの大きな原因です。
ストレスは精神の緊張をもたらし、自律神経(交感神経と副交感神経のバランス)を乱します。
ストレスを感じているときは交感神経が働きますが、交感神経が優位になると精神も体も緊張状態になり血流が滞ってしまいます。
その結果、十分な酸素や栄養が体に巡らなくなり肩こりにつながるのです。
他にも過重労働や冷え、睡眠不足・・・・肩こりの原因は本当にさまざまです。
しかしこれらは生活習慣を工夫することで改善できる場合もあります。
自身の肩こりの原因を理解することから始めましょう。
主な原因には
・運動不足
・血行不良
・身体のゆがみ
・眼精疲労
・ストレス
などが挙げられます。
まずは何といっても運動不足。
筋力が低下し筋肉が緊張していきます。
筋肉は血液を全身に送るポンプの役割をしているため、筋力が弱まると血の巡りが悪くなり血行不良を引き起こします。
次に身体のゆがみ。
決まった体勢を続けることでゆがみが生じ、肩こりにつながります。
介護職の場合、「いつも同じ足で踏ん張っている」「腰をかばう動きになる」など、身体のゆがみによって肩こりになっている人も多いのではないかと思います。
さらに眼精疲労からも肩こりは起こります。
仕事でパソコンやタブレットを使用しますし、今や誰もがスマホを持っている時代。小さな文字を凝視することやブルーライトを浴びることで眼を酷使しています。
また意外かもしれませんが、ストレスも肩こりの大きな原因です。
ストレスは精神の緊張をもたらし、自律神経(交感神経と副交感神経のバランス)を乱します。
ストレスを感じているときは交感神経が働きますが、交感神経が優位になると精神も体も緊張状態になり血流が滞ってしまいます。
その結果、十分な酸素や栄養が体に巡らなくなり肩こりにつながるのです。
他にも過重労働や冷え、睡眠不足・・・・肩こりの原因は本当にさまざまです。
しかしこれらは生活習慣を工夫することで改善できる場合もあります。
自身の肩こりの原因を理解することから始めましょう。
肩こり解消に効果的な5つのこと
肩こりを解消するために取り組むべきことは大きく2点です。
第一にこりの原因を取り除く(減らす)こと。そしてもう一点は、凝り固まった筋肉を柔軟にすることです。
ここからは肩こり解消に効果的なことを具体的にお伝えしていきます。
日常生活の中で意識して取り入れてみてください。
第一にこりの原因を取り除く(減らす)こと。そしてもう一点は、凝り固まった筋肉を柔軟にすることです。
ここからは肩こり解消に効果的なことを具体的にお伝えしていきます。
日常生活の中で意識して取り入れてみてください。
1.湯船につかる
入浴は血流改善に効果的です。
シャワーで済まさず、できるだけ毎日湯船につかることを心がけましょう。
40°C前後のお湯に10分~15分つかり、身体の芯までしっかり温めてください。
湯船に浸かりながら首や肩を回すなど、首回りや肩甲骨をほぐすようなストレッチを取り入れるのもおすすめです。
シャワーで済まさず、できるだけ毎日湯船につかることを心がけましょう。
40°C前後のお湯に10分~15分つかり、身体の芯までしっかり温めてください。
湯船に浸かりながら首や肩を回すなど、首回りや肩甲骨をほぐすようなストレッチを取り入れるのもおすすめです。
2.姿勢を正す
普段の何気ない習慣が悪い姿勢を作ります。
例えばスマホを見るときの姿勢、化粧をするときに鏡を覗き込む姿勢・・・無意識に猫背や頭が前に突き出たような姿勢になっているのではないでしょうか? 仕事中も、パソコン操作、移乗介助、入浴介助などなど、不良姿勢が続くことで肩こりは悪化します。 仕事に関してはどうしようもないこともありますが、極力正しい姿勢を意識しましょう。長時間同じ姿勢が続いた後には意識して肩甲骨を動かすことを習慣づけ、肩こりを予防していきましょう。
例えばスマホを見るときの姿勢、化粧をするときに鏡を覗き込む姿勢・・・無意識に猫背や頭が前に突き出たような姿勢になっているのではないでしょうか? 仕事中も、パソコン操作、移乗介助、入浴介助などなど、不良姿勢が続くことで肩こりは悪化します。 仕事に関してはどうしようもないこともありますが、極力正しい姿勢を意識しましょう。長時間同じ姿勢が続いた後には意識して肩甲骨を動かすことを習慣づけ、肩こりを予防していきましょう。
3.枕を変える
枕の高さが合っていないと寝ている間に悪い姿勢を形成してしまいよくありません。
枕が低すぎる(枕を使用しない)と、頭が下に下がりすぎて顎が前に突き出るような状態になり、これは猫背の原因となります。
反対に枕が高すぎると、首が前に曲がりすぎて頸椎や胸椎、腰椎にも負担がかかります。
頭から胸までの傾斜は一般的に15~20°C程度が理想とされています。
顎を軽く引けている姿勢がベストで、喉が詰まる感じはないか、呼吸が楽にできるかをチェックしてください。
合わない枕を使用し続けると睡眠の質も下がりますので、できるだけ早く改善しましょう。
枕が低すぎる(枕を使用しない)と、頭が下に下がりすぎて顎が前に突き出るような状態になり、これは猫背の原因となります。
反対に枕が高すぎると、首が前に曲がりすぎて頸椎や胸椎、腰椎にも負担がかかります。
頭から胸までの傾斜は一般的に15~20°C程度が理想とされています。
顎を軽く引けている姿勢がベストで、喉が詰まる感じはないか、呼吸が楽にできるかをチェックしてください。
合わない枕を使用し続けると睡眠の質も下がりますので、できるだけ早く改善しましょう。
4.リラックスする
ストレスは肩こりの原因になると先ほどお伝えしました。積極的にリラックスできる時間を作るようにしましょう。
入浴には抜群のリラックス効果がありますが、入浴剤やアロマオイルを入れて香りを楽しむこともおすすめです。
また十分な睡眠をとることも意識しましょう。睡眠不足は疲労やストレスを引き起こす要因にもなりますし、血行不良やさまざまな不調をきたします。
睡眠・休息をしっかりととり、心身を緩めることがとても大切です。
入浴には抜群のリラックス効果がありますが、入浴剤やアロマオイルを入れて香りを楽しむこともおすすめです。
また十分な睡眠をとることも意識しましょう。睡眠不足は疲労やストレスを引き起こす要因にもなりますし、血行不良やさまざまな不調をきたします。
睡眠・休息をしっかりととり、心身を緩めることがとても大切です。
5.運動・ストレッチ
普段、仕事以外であまり体を動かさない人は、軽い運動やストレッチを取り入れてみてください。肩こりは体を動かさない状態が続くと、どんどん凝り固まっていってしまいます。
無理のない範囲で少しずつ体を動かすようにしましょう。
ストレッチや体操、ウォーキングなどで全身の筋肉を使って関節の可動域を拡げていきます。
毎日少しずつの継続で筋肉がほぐれていくことを実感できるでしょう。
血行不良やむくみの改善、ストレス解消にも効果的です。
次にご紹介するストレッチもぜひ試してみてください。
無理のない範囲で少しずつ体を動かすようにしましょう。
ストレッチや体操、ウォーキングなどで全身の筋肉を使って関節の可動域を拡げていきます。
毎日少しずつの継続で筋肉がほぐれていくことを実感できるでしょう。
血行不良やむくみの改善、ストレス解消にも効果的です。
次にご紹介するストレッチもぜひ試してみてください。
肩こり解消に効果的なストレッチ
肩こりにはいわゆる慢性的な肩周辺のこりに加え、首のこり、背中のこりがあり、どこか一ヶ所のマッサージやストレッチで改善するというものではないでしょう。
骨や筋肉を正しい位置に戻したり、筋膜をはがしたり、複合的なアプローチが必要になります。
まず大前提として、
筋肉を痛めるような激しい動きで鍛えるトレーニングではありません。
筋肉の伸びを感じながら深く呼吸。リラックスして行いましょう。
骨や筋肉を正しい位置に戻したり、筋膜をはがしたり、複合的なアプローチが必要になります。
まず大前提として、
ストレッチは呼吸を止めずにゆっくり行うことが基本
です。筋肉を痛めるような激しい動きで鍛えるトレーニングではありません。
筋肉の伸びを感じながら深く呼吸。リラックスして行いましょう。
肩のこりに
◆
肩こりがある人の多くは、菱形筋というインナーマッスルが使えておらず、肩甲骨の位置がずれて固まってしまっているといいます。
猫背の人は肩甲骨が開き過ぎていたり、パソコン作業などで肩が上がっている人は肩甲骨も上に上がり過ぎている状態です。
肩甲骨、またその周辺の筋肉を「寄せる」「下げる」を意識して、内外・上下に動かすストレッチを行いましょう。
肩甲骨を動かす
肩こりがある人の多くは、菱形筋というインナーマッスルが使えておらず、肩甲骨の位置がずれて固まってしまっているといいます。
猫背の人は肩甲骨が開き過ぎていたり、パソコン作業などで肩が上がっている人は肩甲骨も上に上がり過ぎている状態です。
肩甲骨、またその周辺の筋肉を「寄せる」「下げる」を意識して、内外・上下に動かすストレッチを行いましょう。
首のこりに
◆
パソコンやスマホの使用で凝り固まった首周辺の筋肉をほぐします。
右の首筋を伸ばす場合は左手で頭を軽く持って左側に、左の首筋を伸ばす場合は右手で頭を軽く持って右側に倒していきます。
首を前後・左右に伸ばすストレッチ
パソコンやスマホの使用で凝り固まった首周辺の筋肉をほぐします。
右の首筋を伸ばす場合は左手で頭を軽く持って左側に、左の首筋を伸ばす場合は右手で頭を軽く持って右側に倒していきます。
◆
小胸筋は大胸筋の深層にあるインナーマッスルで、肩甲骨を下に引き下げたり、肋骨を引き上げたりする役割があります。
姿勢が悪くなり首や肩が前に出てしまっている人は、小胸筋が硬くなっている可能性が高いです。
鎖骨下辺りにあるくぼみを押し込んでほぐし、首や肩をしっかり引きましょう。
◆
鎖骨と胸骨から頭蓋骨の両脇に伸びる筋肉です。
首こりの人は、小胸筋と同様に胸鎖乳突筋も凝り固まっていることが多いでしょう。
耳の後ろの出っ張りの下にあるくぼみに指や拳を当ててマッサージしてください。
小胸筋のマッサージ
小胸筋は大胸筋の深層にあるインナーマッスルで、肩甲骨を下に引き下げたり、肋骨を引き上げたりする役割があります。
姿勢が悪くなり首や肩が前に出てしまっている人は、小胸筋が硬くなっている可能性が高いです。
鎖骨下辺りにあるくぼみを押し込んでほぐし、首や肩をしっかり引きましょう。
◆
胸鎖乳突筋のマッサージ
鎖骨と胸骨から頭蓋骨の両脇に伸びる筋肉です。
首こりの人は、小胸筋と同様に胸鎖乳突筋も凝り固まっていることが多いでしょう。
耳の後ろの出っ張りの下にあるくぼみに指や拳を当ててマッサージしてください。
背中のこりに
◆
背中でこりやすい部分は僧帽筋です。
僧帽筋は背中の一番大きな筋肉で、一点のアプローチではなかなかこりはほぐれません。
フォームローラーなどを使った筋膜リリースなど、筋肉全体をほぐすストレッチを取り入れることがおすすめです。
僧帽筋のストレッチ
背中でこりやすい部分は僧帽筋です。
僧帽筋は背中の一番大きな筋肉で、一点のアプローチではなかなかこりはほぐれません。
フォームローラーなどを使った筋膜リリースなど、筋肉全体をほぐすストレッチを取り入れることがおすすめです。
まとめ
介護職の人を悩ませる肩こりを解消するための方法をお伝えしました。
ご紹介したストレッチや生活習慣の改善は、決して無理をせずできる範囲で少しずつ始めましょう。
また持病がある方、痛みやしびれなどがある方は、自己判断のマッサージやストレッチはせず、専門家の指導を受けるようにしてください。
ご紹介したストレッチや生活習慣の改善は、決して無理をせずできる範囲で少しずつ始めましょう。
また持病がある方、痛みやしびれなどがある方は、自己判断のマッサージやストレッチはせず、専門家の指導を受けるようにしてください。
介護のお仕事相談は介護ワーカーへ!!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★介護ワーカーの求人を見てみる
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★介護ワーカーの求人を見てみる
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.