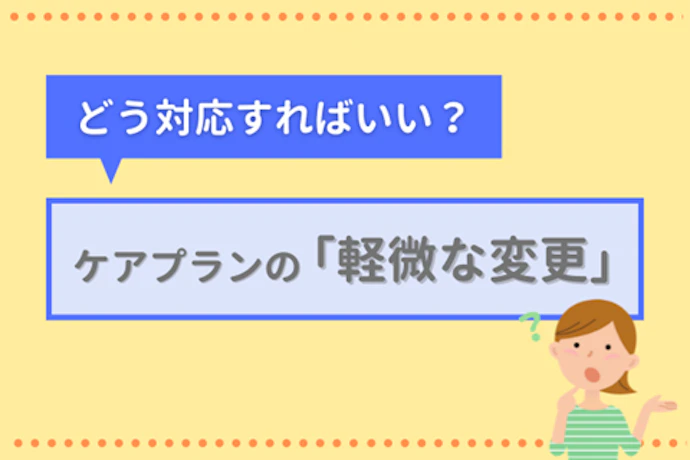介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.10
ケアプランの「軽微な変更」はどう対応すればいい?
#介護
目次
ケアマネージャー(介護支援専門員)の仕事であるケアプランの作成。
利用者のサービスに変更がある場合、再アセスメントからケアプランの交付まで一連の流れを経て、ケアプランを変更します。
しかし「軽微な変更」に該当する内容のものであれば、これらの業務を省略してケアプランの該当内容を変更することが可能です。
ケアマネージャーとして経験があまりない方の場合、軽微な変更に該当するのかどうか、判断に迷ってしまう方は多いはず。そこで、軽微な変更に該当する事例、該当しない事例、また注意点やどのように対応したらよいのかを説明していきたいと思います。
利用者のサービスに変更がある場合、再アセスメントからケアプランの交付まで一連の流れを経て、ケアプランを変更します。
しかし「軽微な変更」に該当する内容のものであれば、これらの業務を省略してケアプランの該当内容を変更することが可能です。
ケアマネージャーとして経験があまりない方の場合、軽微な変更に該当するのかどうか、判断に迷ってしまう方は多いはず。そこで、軽微な変更に該当する事例、該当しない事例、また注意点やどのように対応したらよいのかを説明していきたいと思います。
ケアプランにおける軽微な変更とは?
利用者のサービスに変更がある場合、原則として次の流れで作成し直します。
【再アセスメント】
↓
【ケアプランの原案再作成】
↓
【利用者本人や家族の意向確認】
↓
【サービス担当者会議】
↓
【利用者本人や家族の同意】
↓
【ケアプランの再交付】
↓
【ケアプランの原案再作成】
↓
【利用者本人や家族の意向確認】
↓
【サービス担当者会議】
↓
【利用者本人や家族の同意】
↓
【ケアプランの再交付】
このように、一連の流れを経てケアプランを再作成し変更しなければなりません。
しかし、変更内容が厚生労働省が定める「軽微な変更」の項目に該当するものであれば、再アセスメントやケアプランの再作成、サービス担当者会議、ケアプランの再交付などの業務を省略することができます。
「軽微な変更」として認められているのは、
しかし、変更内容が厚生労働省が定める「軽微な変更」の項目に該当するものであれば、再アセスメントやケアプランの再作成、サービス担当者会議、ケアプランの再交付などの業務を省略することができます。
「軽微な変更」として認められているのは、
厚生労働省の「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている項目のみ
です。ケアプランの「軽微な変更」に該当する項目
実際に「軽微な変更」に該当する内容はどのようなものなのか見ていきましょう。
厚生労働省 老健局振興課の「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている、軽微な変更と認められている項目は以下の9つ。
(1)サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもので、単なる曜日、日付、時間帯の変更のような場合。
(2)サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合
(3)利用者の住所変更
利用者の住所変更の場合
(4)事業所の名称変更
単なる事業所の名所変更の場合
(5)目標期間の延長
ケアプラン上の課題や期間を変更する必要がなく、単に目標期間の延長する場合
(6)福祉用具の変更
福祉用具で同等の用具に変更する際、単位数のみが異なる場合
(7)事業所の変更
目標・サービスの変更を伴わず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更の場合
(8)目標を達成するためのサービス内容の変更
解決すべき課題、目標、サービス種別などが変わらない範囲で、目標達成するためのサービス内容を変更するだけの場合
(9)担当介護支援専門員の変更
契約してる居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更で、新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識がある場合
※参考:厚生労働省 老健局振興課「介護保険最新情報Vol.155」
上記のように、ケアプランの軽微な変更の取り扱いが決められています。
しかし、あくまで例示とされており「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容によって軽微であるか否かが判断されます。
そのため解釈ミスなどを起こさないためにも、どのような状況に当てはまるのかをしっかりと理解しておかなければなりません。
厚生労働省 老健局振興課の「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている、軽微な変更と認められている項目は以下の9つ。
【「軽微な変更」が認められる項目と内容】
(1)サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもので、単なる曜日、日付、時間帯の変更のような場合。
(2)サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合
(3)利用者の住所変更
利用者の住所変更の場合
(4)事業所の名称変更
単なる事業所の名所変更の場合
(5)目標期間の延長
ケアプラン上の課題や期間を変更する必要がなく、単に目標期間の延長する場合
(6)福祉用具の変更
福祉用具で同等の用具に変更する際、単位数のみが異なる場合
(7)事業所の変更
目標・サービスの変更を伴わず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更の場合
(8)目標を達成するためのサービス内容の変更
解決すべき課題、目標、サービス種別などが変わらない範囲で、目標達成するためのサービス内容を変更するだけの場合
(9)担当介護支援専門員の変更
契約してる居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更で、新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識がある場合
※参考:厚生労働省 老健局振興課「介護保険最新情報Vol.155」
上記のように、ケアプランの軽微な変更の取り扱いが決められています。
しかし、あくまで例示とされており「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容によって軽微であるか否かが判断されます。
そのため解釈ミスなどを起こさないためにも、どのような状況に当てはまるのかをしっかりと理解しておかなければなりません。
ケアプランの「軽微な変更」に該当しない事例
「軽微な変更」に該当するかどうかの線引きには注意が必要です。
実際、軽微な変更に該当すると間違って解釈し、サービス担当者会議を開催しなかったところ、じつは該当しない事例であり指摘されるケースは少なくありません。
運営違反とならないようにするためには「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている変更内容の文言を正確に読み取り判断しなければなりません。
そこで、判断ミスが起こりやすい「軽微な変更に該当しない事例」を紹介したいと思います。
実際、軽微な変更に該当すると間違って解釈し、サービス担当者会議を開催しなかったところ、じつは該当しない事例であり指摘されるケースは少なくありません。
運営違反とならないようにするためには「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている変更内容の文言を正確に読み取り判断しなければなりません。
そこで、判断ミスが起こりやすい「軽微な変更に該当しない事例」を紹介したいと思います。
◆「目標期間の延長」での誤った判断 ◆
ケアプランの変更で「目標期間の延長」は、軽微な変更として認められている項目です。
目標期間の延長は、
しかし、ケアプランの更新で何度も同じ短期目標で更新していると、目標設定に問題があると判断されてしまう可能性があります。目標達成ができないプランだと判断された場合、別の目標に設定を変更しなければなりません。目標を変更すれば、サービス担当者会議の開催は必須となるため、軽微な変更に該当しなくなります。
目標期間の延長をする場合は、目標に向けて結果が出ている状況であることが重要なポイントです。そして、もう少し期間を延ばせば短期目標を達成できる状況である場合に該当すると理解しておきましょう。
目標期間の延長は、
ケアプランの課題や目標に変更がなく、サービスの実施期間を延長する場合
を指しています。しかし、ケアプランの更新で何度も同じ短期目標で更新していると、目標設定に問題があると判断されてしまう可能性があります。目標達成ができないプランだと判断された場合、別の目標に設定を変更しなければなりません。目標を変更すれば、サービス担当者会議の開催は必須となるため、軽微な変更に該当しなくなります。
目標期間の延長をする場合は、目標に向けて結果が出ている状況であることが重要なポイントです。そして、もう少し期間を延ばせば短期目標を達成できる状況である場合に該当すると理解しておきましょう。
◆「担当介護支援専門の変更」での誤った判断 ◆
「担当介護支援専門の変更」は、軽微な変更として認められている項目です。
しかし、これは
以前と同じケアプランであっても、異なる事業所のケアマネージャーに担当を変えることは「軽微な変更」として認められません。
また、担当ケアマネージャーやケアプランの内容に変更がなく、事業所のみ変更である場合、サービス担当者会議は必要ないと勘違いしてしまいがちです。しかし、たとえ担当ケアマネージャーもケアプランも同じであっても、事業所が変更する場合は軽微な変更に該当しないということを覚えておきましょう。
※参考:厚生労働省 老健局振興課|介護保険最新情報Vol.155
しかし、これは
同一事業所における場合のみ
と指定があります。以前と同じケアプランであっても、異なる事業所のケアマネージャーに担当を変えることは「軽微な変更」として認められません。
また、担当ケアマネージャーやケアプランの内容に変更がなく、事業所のみ変更である場合、サービス担当者会議は必要ないと勘違いしてしまいがちです。しかし、たとえ担当ケアマネージャーもケアプランも同じであっても、事業所が変更する場合は軽微な変更に該当しないということを覚えておきましょう。
※参考:厚生労働省 老健局振興課|介護保険最新情報Vol.155
ケアプラン「軽微な変更」の対応方法とは
「軽微な変更」に該当すると判断した場合の対応方法について説明していきます。
軽微な変更に当てはまると判断した場合は、ケアプランの該当する箇所を見え消しで変更します。
この際に、変更日時やその理由を明確に分かりやすく記載します。
また、支援経過記録などに「軽微な変更」がどのように行われたのか、また変更した理由など、経緯を詳細に記載しておきます。さらに、利用者や利用者家族にサービス担当者会議を開催しない同意を得ておき、その同意を得た年月日、確認方法についても詳しく記載しておくことが必要です。
その後、サービス事業所など関係各所に変更内容の情報共有をしておきましょう。
「軽微な変更」は、サービス担当者会議の開催が義務付けられていませんが、ケアマネージャーがサービス担当者会議を開催するべきと判断した場合、実施することは可能です。
<ケアプラン>
<支援経過記録など>
軽微な変更に当てはまると判断した場合は、ケアプランの該当する箇所を見え消しで変更します。
この際に、変更日時やその理由を明確に分かりやすく記載します。
また、支援経過記録などに「軽微な変更」がどのように行われたのか、また変更した理由など、経緯を詳細に記載しておきます。さらに、利用者や利用者家族にサービス担当者会議を開催しない同意を得ておき、その同意を得た年月日、確認方法についても詳しく記載しておくことが必要です。
その後、サービス事業所など関係各所に変更内容の情報共有をしておきましょう。
「軽微な変更」は、サービス担当者会議の開催が義務付けられていませんが、ケアマネージャーがサービス担当者会議を開催するべきと判断した場合、実施することは可能です。
<ケアプラン>
・該当箇所を「見え消し」で変更
・変更日時、理由を記載
<支援経過記録など>
・変更の経緯を記載
・利用者、家族の同意を得た年月日の記載
・確認方法の記載
「軽微な変更」での注意点
「軽微な変更」に該当する場合、サービス担当者会議の開催は必須ではありません。
しかし、誤った判断や勘違いによってサービス担当者会議を行わなかった場合、運営基準違反となり「介護報酬の返還、減算」や「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」などの罰則が課せられます。
「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」となった場合には、返還する金額は多額にたるため、事業所の運営ができなくなる可能性もあるため、注意しなければなりません。
ここでは、最もリスクが高い「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」の内容について説明していきたいと思います。
しかし、誤った判断や勘違いによってサービス担当者会議を行わなかった場合、運営基準違反となり「介護報酬の返還、減算」や「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」などの罰則が課せられます。
「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」となった場合には、返還する金額は多額にたるため、事業所の運営ができなくなる可能性もあるため、注意しなければなりません。
ここでは、最もリスクが高い「運営基準減算」「特定事業所加算の全額返還」の内容について説明していきたいと思います。
「運営基準減算による介護報酬返還」のリスク
「軽微な変更」に該当すると勘違いして、サービス担当者会議を開催なかった場合には運営基準減算の罰則が課せられます。
減算となる期間は、該当する状態の始まりから解消された月の前月までです。
減算の単位は、所定単位数の50%に減算されます。また、違反している状態が2カ月以上継続している場合、2カ月目以降は所定単位数を算定しないとなっており、介護報酬の全額を返還することになります。
法人自体が解釈ミスをしている場合は、長期間に渡る多額の報酬返還が発生することもあります。
※参考:厚生労働省|居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について(検討の方向性)
減算となる期間は、該当する状態の始まりから解消された月の前月までです。
減算の単位は、所定単位数の50%に減算されます。また、違反している状態が2カ月以上継続している場合、2カ月目以降は所定単位数を算定しないとなっており、介護報酬の全額を返還することになります。
法人自体が解釈ミスをしている場合は、長期間に渡る多額の報酬返還が発生することもあります。
※参考:厚生労働省|居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について(検討の方向性)
「特定事業所加算の全額返還」のリスク
特定事業所加算にはⅠ~Ⅳまでの4種類があります。
しかし「運営基準減算」になると、Ⅰ~Ⅳすべての加算ができなくなり、全額返還しなければならなくなります。
これは特定事業所加算の算定要件に「運営基準減算」には該当しないという項目が定められているからです。
<特定事業所加算の単位数>
(Ⅰ)月500単位
(Ⅱ)月400単位
(Ⅲ)月300単位
(Ⅳ)月125単位
これらがすべて返還を求められるため、事業所の運営ができなくなってしまうこともあります。
※参考:厚生労働省|居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について(検討の方向性)
しかし「運営基準減算」になると、Ⅰ~Ⅳすべての加算ができなくなり、全額返還しなければならなくなります。
これは特定事業所加算の算定要件に「運営基準減算」には該当しないという項目が定められているからです。
<特定事業所加算の単位数>
(Ⅰ)月500単位
(Ⅱ)月400単位
(Ⅲ)月300単位
(Ⅳ)月125単位
これらがすべて返還を求められるため、事業所の運営ができなくなってしまうこともあります。
※参考:厚生労働省|居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について(検討の方向性)
ケアプラン「軽微な変更」の記入例
ケアプランで「軽微な変更」の際、ケアプランの該当箇所の見え消しや変更日時、理由の記載が必要となります。
また、支援経過記録にも変更の理由など経緯を記載しておかなければなりません。
この支援経過記録にどのように書けばよいのか迷っている方もいるはず。そこで、いくつか記入例をご紹介したいと思います。
軽微な変更の際、支援経過記録に書く経緯の参考にしてみてください。
また、支援経過記録にも変更の理由など経緯を記載しておかなければなりません。
この支援経過記録にどのように書けばよいのか迷っている方もいるはず。そこで、いくつか記入例をご紹介したいと思います。
軽微な変更の際、支援経過記録に書く経緯の参考にしてみてください。
「利用者の住所変更」の記入例
引っ越しをすることになり住所が変更となった。
アセスメントをおこなった結果、家族構成や住環境に変わりなく利用者の身体状況や現在の課題などに変更はないため「ケアプランの軽微な変更」と判断。
〇年○月〇日、利用者宅にて本人及びご家族へ説明をおこない、同意を得たうえで居宅サービス計画書の住所を見え消しして変更した。また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
アセスメントをおこなった結果、家族構成や住環境に変わりなく利用者の身体状況や現在の課題などに変更はないため「ケアプランの軽微な変更」と判断。
〇年○月〇日、利用者宅にて本人及びご家族へ説明をおこない、同意を得たうえで居宅サービス計画書の住所を見え消しして変更した。また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
「目標期間の延長」の記入例
短期目標の修了月である〇月にモニタリングを行ったところ、サービス提供の効果は評価できるが短期目標達成するためには、あと〇カ月同じ内容のサービス提供をしていくことが妥当と判断。利用者の希望をヒアリングしたところ、利用者自身もこれまで通りのサービスを受けたいと希望している。
よって「ケアプランの軽微な変更」とし、〇年○月〇日利用者宅にて本人及びご家族へ説明をおこない、同意を得たうえで居宅サービス計画書の該当部分を見え消しして変更した。
また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
よって「ケアプランの軽微な変更」とし、〇年○月〇日利用者宅にて本人及びご家族へ説明をおこない、同意を得たうえで居宅サービス計画書の該当部分を見え消しして変更した。
また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
「サービス提供の曜日の変更」の記入例
ご家族の都合により、〇年〇月のサービス提供曜日を「〇曜日→〇曜日」に変更。
サービス提供曜日の変更につき、利用者及びご家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認したところ、身体状況や現在の課題等に変更はなく、目標内容も変更の必要性はないと判断した。
よって「ケアプランの軽微な変更(単なるサービス提供曜日の変更)」とし、〇年〇月〇日に本人及びご家族へ説明し、同意を得たうえで該当部分を見え消しし変更した。
また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
軽微な変更は、正しく取り扱わなければ大きなリスクを招いてしまいます。
そのため、支援経過記録には詳しく経緯を記載しておかなければなりません。
記入例はあくまで参考とし、働く事業所の記入ルールに沿って丁寧に書きましょう。また、実際に支援経過記録へ記入する前に、文章に間違いや足りない点はないかなど必ず先輩ケアマネージャーなどに確認をしてもらいましょう。
サービス提供曜日の変更につき、利用者及びご家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認したところ、身体状況や現在の課題等に変更はなく、目標内容も変更の必要性はないと判断した。
よって「ケアプランの軽微な変更(単なるサービス提供曜日の変更)」とし、〇年〇月〇日に本人及びご家族へ説明し、同意を得たうえで該当部分を見え消しし変更した。
また、軽微な変更をしたことを利用者及びご家族、サービス事業所に周知した。
軽微な変更は、正しく取り扱わなければ大きなリスクを招いてしまいます。
そのため、支援経過記録には詳しく経緯を記載しておかなければなりません。
記入例はあくまで参考とし、働く事業所の記入ルールに沿って丁寧に書きましょう。また、実際に支援経過記録へ記入する前に、文章に間違いや足りない点はないかなど必ず先輩ケアマネージャーなどに確認をしてもらいましょう。
まとめ
ケアプランの「軽微な変更」は、業務を大幅に省略できるというメリットがある一方、判断ミスをしてしまったときのリスクが大きいというデメリットがあります。
「軽微な変更」に当てはまるのか判断に迷う場合は、サービス担当者会議を開催するようにしましょう。また、解釈が合っているのか迷う場合は、自己判断せず必ず行政に確認しましょう。
きちんと解釈し判断できるようになるまでは、先輩ケアマネージャーなどに相談したうえで対応していきましょう。
「軽微な変更」に当てはまるのか判断に迷う場合は、サービス担当者会議を開催するようにしましょう。また、解釈が合っているのか迷う場合は、自己判断せず必ず行政に確認しましょう。
きちんと解釈し判断できるようになるまでは、先輩ケアマネージャーなどに相談したうえで対応していきましょう。
介護の転職なら介護ワーカー!
介護の転職なら介護ワーカー!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.