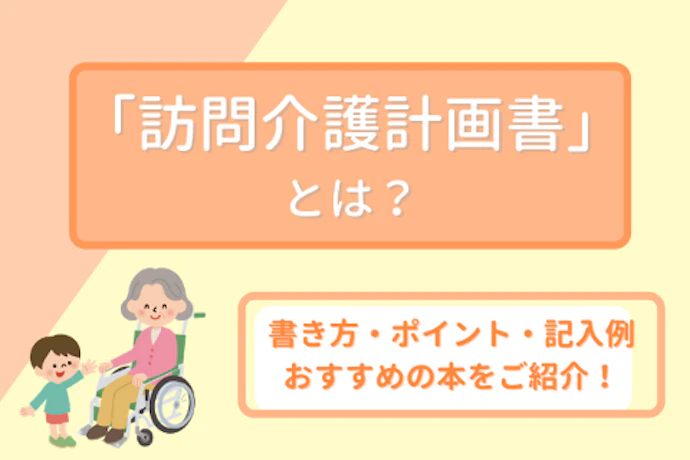介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.14
訪問介護計画書とは?基本の書き方、ポイントをおさえよう!
#介護
目次
サービス提供責任者の仕事の一つである訪問介護計画書の作成。
訪問介護計画書は、訪問介護サービスを提供する際に必ず必要となる書類です。
利用者や家族の希望やどのような内容のサービスを提供していくのかを具体的に記載していきます。
サービス提供責任者を目指している方のために、訪問介護計画書とはどのような書類なのか、そして基本の書き方やポイント、記入例、おすすめの本をご紹介したいと思います。
訪問介護計画書は、訪問介護サービスを提供する際に必ず必要となる書類です。
利用者や家族の希望やどのような内容のサービスを提供していくのかを具体的に記載していきます。
サービス提供責任者を目指している方のために、訪問介護計画書とはどのような書類なのか、そして基本の書き方やポイント、記入例、おすすめの本をご紹介したいと思います。
訪問介護計画書とは
訪問介護計画書は、訪問介護サービスの提供に関する計画書のこと。
訪問介護計画書の作成はサービス提供責任者がおこない「サービス内容」「提供手順」「提供方法」を記載し確定します。
利用者には訪問介護サービスの提供前に、サービスの内容だけでなく提供手順や提供方法について計画書を用いてしっかりと説明し、サービス内容を確認してもらい同意を得ます。
訪問介護計画書は、その際に必要となる書類であるためとても重要な役割を担っています。
◇サービス提供責任者とは?◇
サービス提供責任者とは、身体介護や生活援助をおこなう介護職の業務において、リーダー的役割を担う職種です。サービス提供責任者は「サ責」と略称で呼ばれていることがほとんど。サービス提供責任者の仕事内容は、訪問介護業務、管理業務(ヘルパーの勤務状況管理、勤務調整、指導)、訪問介護計画書などの書類作成など、さまざまな業務をこなします。
リーダー的役割を担う職種であるため、一般的な介護職よりも給与アップが叶うなど待遇が良くなるため、キャリアアップとして目指す方は少なくありません。
◎サービス提供責任者についてもっと詳しく知りたいという方は、以下のコラムもぜひご覧ください。
「サービス提供責任者とは?」
訪問介護計画書の作成はサービス提供責任者がおこない「サービス内容」「提供手順」「提供方法」を記載し確定します。
利用者には訪問介護サービスの提供前に、サービスの内容だけでなく提供手順や提供方法について計画書を用いてしっかりと説明し、サービス内容を確認してもらい同意を得ます。
訪問介護計画書は、その際に必要となる書類であるためとても重要な役割を担っています。
◇サービス提供責任者とは?◇
サービス提供責任者とは、身体介護や生活援助をおこなう介護職の業務において、リーダー的役割を担う職種です。サービス提供責任者は「サ責」と略称で呼ばれていることがほとんど。サービス提供責任者の仕事内容は、訪問介護業務、管理業務(ヘルパーの勤務状況管理、勤務調整、指導)、訪問介護計画書などの書類作成など、さまざまな業務をこなします。
リーダー的役割を担う職種であるため、一般的な介護職よりも給与アップが叶うなど待遇が良くなるため、キャリアアップとして目指す方は少なくありません。
◎サービス提供責任者についてもっと詳しく知りたいという方は、以下のコラムもぜひご覧ください。
「サービス提供責任者とは?」
「訪問介護計画書」作成の流れ
まずは、訪問介護計画書を作成する流れについて見ていきましょう。
訪問介護計画書の作成の流れは、ケアマネージャーが作成したケアプランを確認することから始まります。
ケアプランに基づいて、その利用者に合わせた個別の訪問介護計画を立てていきます。
訪問介護計画書を作成し、利用者と家族に説明し同意を得てからサービス提供がスタートします。
訪問介護計画書はサービス提供を始める前だけではなく、定期的な見直しやサービス提供を続けている途中であっても進捗状況や要望があった際などに計画の見直しをおこまいます。
◎ケアプランについて詳しく知りたい方はこちら
「ケアプランの作成方法とは?作成の流れ・記入例・ポイントもご紹介!」
ケアプランに基づいて、その利用者に合わせた個別の訪問介護計画を立てていきます。
訪問介護計画書を作成し、利用者と家族に説明し同意を得てからサービス提供がスタートします。
訪問介護計画書はサービス提供を始める前だけではなく、定期的な見直しやサービス提供を続けている途中であっても進捗状況や要望があった際などに計画の見直しをおこまいます。
◎ケアプランについて詳しく知りたい方はこちら
「ケアプランの作成方法とは?作成の流れ・記入例・ポイントもご紹介!」
訪問介護計画書の作成手順と書き方
訪問介護計画書の作成手順は以下の3つに分けられます。
(1)利用者状況の把握(アセスメント)
(2)課題(ニーズ)の特定
(3)訪問介護計画書の作成
それぞれどのようなことをするのか、詳しく見ていきましょう。
(1)利用者状況の把握(アセスメント)
(2)課題(ニーズ)の特定
(3)訪問介護計画書の作成
それぞれどのようなことをするのか、詳しく見ていきましょう。
1.| 利用者状況の把握(アセスメント)
訪問介護計画書を作成する前に、利用者の身体状況や生活状況などの情報を把握するため、ケアマネージャーとは別にあらためてアセスメントをおこなう必要があります。
アセスメントを通して、利用者にどのような支援が必要なのかを判断し、具体的な支援方法を導きます。
◎アセスメントのコツを知りたい方はこちらも参考にしてみてください!
「ケアマネ必見!アセスメントのコツ&アセスメントシートの書き方まとめ」
アセスメントを通して、利用者にどのような支援が必要なのかを判断し、具体的な支援方法を導きます。
◎アセスメントのコツを知りたい方はこちらも参考にしてみてください!
「ケアマネ必見!アセスメントのコツ&アセスメントシートの書き方まとめ」
2.|課題(ニーズ)の特定
アセスメントを行いながら、利用者の課題(ニーズ)を特定していきます。
ここでの「ニーズ」は「専門職が客観的な基準に照らし合わせて判断した援助の必要性」を指します。利用者が自覚し意識して求める要求は「利用者の要求」であり、ニーズと同じとは限りません。
「利用者の要求」と「ニーズ」を区別することで、表面に現れているニーズ以外の隠れたニーズを把握することが可能になり、利用者の隠された可能性の発見に繋がります。
利用者の隠された可能性を発見することで、利用者が持っている力を維持・向上させるなど自立支援に向けたサービスをできるようになります。
●「利用者や家族の要求」と「ニーズ」の区別をする
●表面に現れているニーズ以外の「隠れたニーズ」を把握する
●全体の状況を理解し「利用者の隠された可能性」を発見する
ここでの「ニーズ」は「専門職が客観的な基準に照らし合わせて判断した援助の必要性」を指します。利用者が自覚し意識して求める要求は「利用者の要求」であり、ニーズと同じとは限りません。
「利用者の要求」と「ニーズ」を区別することで、表面に現れているニーズ以外の隠れたニーズを把握することが可能になり、利用者の隠された可能性の発見に繋がります。
利用者の隠された可能性を発見することで、利用者が持っている力を維持・向上させるなど自立支援に向けたサービスをできるようになります。
[アセスメントで気を付けておくポイント]
●「利用者や家族の要求」と「ニーズ」の区別をする
●表面に現れているニーズ以外の「隠れたニーズ」を把握する
●全体の状況を理解し「利用者の隠された可能性」を発見する
3.|訪問介護計画書の作成
訪問介護計画書の書き方について見ていきましょう。
ここでは、訪問介護計画書に盛り込むべき事項について解説していきます。
1.)計画書の作成者の氏名、作成年月日
誰が、いつ作成したのかを明確にします。
計画書の作成年月日や氏名が書かれていないと、アセスメントや設定した目標などがいつ時点のものか分からず、評価に影響が出てしまうため一番初めに記入しましょう。
2.)利用者の情報
サービスを提供する利用者の基本的な情報を記載します。
・氏名
・性別
・住所
・生年月日
・要介護認定日
・要介護度 など
3.)日常生活全般の状況
利用者の日常生活全般の状況について、ポイントをおさえながら分かりやすく記載します。
4.)援助目標(長期目標、短期目標)
解決すべき課題、長期目標、短期目標を記載します。
事後の評価に役立つ援助目標とするため、漠然とした目標ではなく具体的に書きます。
たとえば「利用者の状況が〇〇なので、△△することを目指す」のように「行動・生活状態」を観察できるように記載する。
援助目標を記載するのは「ヘルパーが何のために来ているか」ということを利用者に理解してもらうためでもあり、実際に訪問するヘルパー自身が「何のために訪問しているのか」を意識できるようにするためでもあります。
5.)見直しの時期
訪問介護計画書の見直し時期を記載します。
6.)本人および家族の意向・希望
利用者本人の価値観や考え方を踏まえて、面接を通じて「利用者の希望・要望」「家族の希望・要望」を明確に記載します。
「利用者が主人公となって、自分で自分の介護を決めていく」ということが重要です。
●利用者や家族が発した言葉で、重要なことはそのまま記載する。
利用者や家族の言葉をサービス提供責任者の解釈で翻訳して書かずに、そのままの言葉で残しておく。
●利用者と家族の言葉は、区別して記載しておく。
家族間で意向に違いがある場合も少なくないため、意向の違いがある場合は誰がどのような意向なのかなど分かるように書き分けましょう。
7.)サービス区分
「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の区分とサービス準備・記録等、排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、移動・移乗介助、通院介助、整容、掃除、洗濯、調理、買い物などのサービスの種類を記載。
具体的なサービス行為ごとの区分や記載方法については、以下をご覧ください。
※厚生労働省老健局振興課長|平成30年3月30日「「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について」
8.)サービス内容と所要時間
<サービス内容>
サービス区分に応じたサービス内容を記載する。
例)区分:身体介護の「排泄介助」の場合
具体的なサービス内容が以下のどれであるかを記載する。
・トイレ利用
・ポータブルトイレ利用
・おむつ交換
また具体的なサービス内容だけでなく、サービスの提供方法も記載しておく。
サービスの提供方法まで詳しく記載しておくことで、利用者が理解しやすくなるだけでなく「ヘルパーによってサービスの提供方法が異なる」ということを避けることができ、サービスの質を維持していくことが可能になります。
<所要時間>
標準的な時間を目安として、サービスの提供にどのくらいの時間がかかるのかを記載します。「どのようなサービスをどれだけの時間でおこなうのか」を明確にしていくことが大切です。標準よりも時間がかかってしまう場合は、その理由を「留意事項」に記載しておきましょう。また、提供方法方などで注意すべきことなどがあれば、それも留意事項に記載します。
9.)週間予定表
いつどのような内容のサービス提供がおこなわれるかを記載します。
何曜日の何時からどのような内容のサービスを提供するのか、利用者やヘルパーが一目で分かるように記載しましょう。
10.)サービス提供に関する評価
サービスの提供後に、介護訪問計画の内容について精査、評価したことを記載。
評価は、原則として目標期間の終了時点でおこないますが、利用者の状況など必要に応じておこないます。
※この欄は、訪問介護計画書に基づきサービスを提供した後に記載する欄ですので、訪問介護計画書の作成時に利用者へ交付する際は空欄となります。
11.)説明者・説明日
利用者や家族に説明した日および説明した職員を記載します。
12.)利用者、家族への説明と同意
利用者や家族にしっかりと説明し、同意を得ます。同意の確認として必ず署名をもらうこと。
訪問介護計画書は一種のサービス契約書で、利用者とともに作り上げていきます。そのため、訪問介護計画書には「説明日、説明者、利用者同意署名欄」の記載は欠かせません。
※参考:「訪問介護計画作成の手引き」堺市南保健福祉総合センター地域福祉課介護保険係
ここでは、訪問介護計画書に盛り込むべき事項について解説していきます。
1.)計画書の作成者の氏名、作成年月日
誰が、いつ作成したのかを明確にします。
計画書の作成年月日や氏名が書かれていないと、アセスメントや設定した目標などがいつ時点のものか分からず、評価に影響が出てしまうため一番初めに記入しましょう。
2.)利用者の情報
サービスを提供する利用者の基本的な情報を記載します。
・氏名
・性別
・住所
・生年月日
・要介護認定日
・要介護度 など
3.)日常生活全般の状況
利用者の日常生活全般の状況について、ポイントをおさえながら分かりやすく記載します。
4.)援助目標(長期目標、短期目標)
解決すべき課題、長期目標、短期目標を記載します。
事後の評価に役立つ援助目標とするため、漠然とした目標ではなく具体的に書きます。
たとえば「利用者の状況が〇〇なので、△△することを目指す」のように「行動・生活状態」を観察できるように記載する。
援助目標を記載するのは「ヘルパーが何のために来ているか」ということを利用者に理解してもらうためでもあり、実際に訪問するヘルパー自身が「何のために訪問しているのか」を意識できるようにするためでもあります。
5.)見直しの時期
訪問介護計画書の見直し時期を記載します。
6.)本人および家族の意向・希望
利用者本人の価値観や考え方を踏まえて、面接を通じて「利用者の希望・要望」「家族の希望・要望」を明確に記載します。
「利用者が主人公となって、自分で自分の介護を決めていく」ということが重要です。
[書き方のポイント]
●利用者や家族が発した言葉で、重要なことはそのまま記載する。
利用者や家族の言葉をサービス提供責任者の解釈で翻訳して書かずに、そのままの言葉で残しておく。
●利用者と家族の言葉は、区別して記載しておく。
家族間で意向に違いがある場合も少なくないため、意向の違いがある場合は誰がどのような意向なのかなど分かるように書き分けましょう。
7.)サービス区分
「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の区分とサービス準備・記録等、排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、移動・移乗介助、通院介助、整容、掃除、洗濯、調理、買い物などのサービスの種類を記載。
具体的なサービス行為ごとの区分や記載方法については、以下をご覧ください。
※厚生労働省老健局振興課長|平成30年3月30日「「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について」
8.)サービス内容と所要時間
<サービス内容>
サービス区分に応じたサービス内容を記載する。
例)区分:身体介護の「排泄介助」の場合
具体的なサービス内容が以下のどれであるかを記載する。
・トイレ利用
・ポータブルトイレ利用
・おむつ交換
また具体的なサービス内容だけでなく、サービスの提供方法も記載しておく。
サービスの提供方法まで詳しく記載しておくことで、利用者が理解しやすくなるだけでなく「ヘルパーによってサービスの提供方法が異なる」ということを避けることができ、サービスの質を維持していくことが可能になります。
<所要時間>
標準的な時間を目安として、サービスの提供にどのくらいの時間がかかるのかを記載します。「どのようなサービスをどれだけの時間でおこなうのか」を明確にしていくことが大切です。標準よりも時間がかかってしまう場合は、その理由を「留意事項」に記載しておきましょう。また、提供方法方などで注意すべきことなどがあれば、それも留意事項に記載します。
9.)週間予定表
いつどのような内容のサービス提供がおこなわれるかを記載します。
何曜日の何時からどのような内容のサービスを提供するのか、利用者やヘルパーが一目で分かるように記載しましょう。
10.)サービス提供に関する評価
サービスの提供後に、介護訪問計画の内容について精査、評価したことを記載。
評価は、原則として目標期間の終了時点でおこないますが、利用者の状況など必要に応じておこないます。
※この欄は、訪問介護計画書に基づきサービスを提供した後に記載する欄ですので、訪問介護計画書の作成時に利用者へ交付する際は空欄となります。
11.)説明者・説明日
利用者や家族に説明した日および説明した職員を記載します。
12.)利用者、家族への説明と同意
利用者や家族にしっかりと説明し、同意を得ます。同意の確認として必ず署名をもらうこと。
訪問介護計画書は一種のサービス契約書で、利用者とともに作り上げていきます。そのため、訪問介護計画書には「説明日、説明者、利用者同意署名欄」の記載は欠かせません。
※参考:「訪問介護計画作成の手引き」堺市南保健福祉総合センター地域福祉課介護保険係
訪問介護計画書を書くポイントは3つ!
訪問介護計画書を書くポイントについて見ていきましょう。
POINT1「要点が簡潔にまとまっているか」
ヘルパーや利用者、利用者家族など、誰が計画書を読んでも内容が把握できるように書きましょう。読んですぐに理解できるような、分かりやすい文章や表現で記載することが大切です。詳しく丁寧に書いていても文章が長すぎると読みづらくなるため、あまり長くならないように要点を押さえ簡潔に記入しましょう。「いつ・どこで・誰が・なにを・なぜ・どうするか」など、5W1Hを意識して文章をつくるとスッキリまとめられます。
POINT2「利用者に合った内容となっているか」
訪問介護計画は利用者のための計画書です。利用者の身体機能や家庭環境によって援助内容や方法は異なります。
サービス内容やサービス計画が利用者の状態に合った内容となっているかを意識し作成することが大切です。
サービス内容やサービス計画が利用者の状態に合った内容となっているかを意識し作成することが大切です。
POINT3「記載漏れ・誤字脱字に気を付ける」
週間予定表に記載しているサービスがすべて援助内容として記載されているか確認しましょう。援助内容は具体的かつ明確か、また記載に漏れがないかもチェックを忘れずに。
訪問介護計画書が手書きの場合は、誰もが読みやすい字になるよう丁寧に記入していきましょう。さらに手書きだけでなく、パソコンでの入力の場合も誤字脱字には気を付けましょう。
訪問介護計画書が手書きの場合は、誰もが読みやすい字になるよう丁寧に記入していきましょう。さらに手書きだけでなく、パソコンでの入力の場合も誤字脱字には気を付けましょう。
訪問介護計画書の記入例
訪問介護計画書の援助目標にあたる「解決すべき課題」「援助目標」「本人・家族希望」欄に書く記入例をご紹介したいと思います。
●ふらつきがあるが、屋外での移動の際に安全に移動できるようになりたい
●自力で歩行ができるようになりたい
●歩行が不安定で転倒の不安があるが、外出できるようになりたい
●自力で車いすへ移動できるようになりたい
●車いすで散歩にでかけたい
●トイレに間に合わないことがあるが、失敗せずに自力で排せつできるようになりたい
●自力で排泄時の衣服の上げ下げができるようになりたい
●食事中にむせることが多い、安心して食事を摂りたい
●家族で旅行に行けるようになりたい
●言葉がスムーズに出にくいが、自分の思いをしっかりと伝えたい
【長期目標】
●家族で旅行に行く
●自分1人で散歩に行くことができる
●体を動かして筋力を維持し健康を保つ
●介助を受けることなく自力で入浴できる
●自分1人でトイレに行けるようになる
【短期目標】
●リハビリを頑張り、筋力と体力をつける
●近くの公園まで歩いて行くことができる
●定期的な運動をして体の柔軟性を保ち、転倒しない体作りをする
●できる入浴動作を増やす
●自力で排泄後の水洗ができるようになる
【本人の希望】
●歩いて外出がしたい
●自宅のお風呂に入りたい
●1人でトイレにいけるようになりたい
●子どもの手を借りずに生活したい
●以前のように料理をできるようになりたい
【家族の希望】
●怪我無く安全に歩行してほしい
●母らしく楽しんで生活をしてほしい
●できる限り家で介護をしてあげたい
●施設に入所してラクになってもらいたい
●できるだけ本人の希望を優先してあげたい
◇解決すべき課題の記入例◇
●ふらつきがあるが、屋外での移動の際に安全に移動できるようになりたい
●自力で歩行ができるようになりたい
●歩行が不安定で転倒の不安があるが、外出できるようになりたい
●自力で車いすへ移動できるようになりたい
●車いすで散歩にでかけたい
●トイレに間に合わないことがあるが、失敗せずに自力で排せつできるようになりたい
●自力で排泄時の衣服の上げ下げができるようになりたい
●食事中にむせることが多い、安心して食事を摂りたい
●家族で旅行に行けるようになりたい
●言葉がスムーズに出にくいが、自分の思いをしっかりと伝えたい
◇援助目標の記入例◇
【長期目標】
●家族で旅行に行く
●自分1人で散歩に行くことができる
●体を動かして筋力を維持し健康を保つ
●介助を受けることなく自力で入浴できる
●自分1人でトイレに行けるようになる
【短期目標】
●リハビリを頑張り、筋力と体力をつける
●近くの公園まで歩いて行くことができる
●定期的な運動をして体の柔軟性を保ち、転倒しない体作りをする
●できる入浴動作を増やす
●自力で排泄後の水洗ができるようになる
◇本人・家族の希望の記入例◇
【本人の希望】
●歩いて外出がしたい
●自宅のお風呂に入りたい
●1人でトイレにいけるようになりたい
●子どもの手を借りずに生活したい
●以前のように料理をできるようになりたい
【家族の希望】
●怪我無く安全に歩行してほしい
●母らしく楽しんで生活をしてほしい
●できる限り家で介護をしてあげたい
●施設に入所してラクになってもらいたい
●できるだけ本人の希望を優先してあげたい
「訪問介護計画書」のおすすめ本をご紹介!
訪問介護計画書の作成に役立つおすすめの本3冊をご紹介したいと思います。
サービス提供責任者として勉強中の方など、訪問介護計画書作成の詳しい解説が読みたい方はぜひ購入の参考にしてみてください。
著者/編集:大橋佳子、須加美明
出版社 :中央法規
価格 :2100円(税込み)
URL :https://www.chuohoki.co.jp/
著者/編集:佐藤ちよみ
出版社 :日本医療企画
価格 :2200円(税込み)
URL :http://www.jmp.co.jp/index.html
監修/著者:石田英一郎、坂本文典/監修 高辻恵示、佐々木香織、平山智也/著者
出版社 :中央法規
価格 :2420円(税込み)
URL :https://www.chuohoki.co.jp/
サービス提供責任者として勉強中の方など、訪問介護計画書作成の詳しい解説が読みたい方はぜひ購入の参考にしてみてください。
おすすめ1|『訪問介護計画書マニュアル』
著者/編集:大橋佳子、須加美明
出版社 :中央法規
価格 :2100円(税込み)
URL :https://www.chuohoki.co.jp/
おすすめ2|『よくわかり、すぐ使える新訪問介護計画書のつくりかた』
著者/編集:佐藤ちよみ
出版社 :日本医療企画
価格 :2200円(税込み)
URL :http://www.jmp.co.jp/index.html
おすすめ3|『サービス提供責任者のための訪問介護計画作成ガイドブック』
監修/著者:石田英一郎、坂本文典/監修 高辻恵示、佐々木香織、平山智也/著者
出版社 :中央法規
価格 :2420円(税込み)
URL :https://www.chuohoki.co.jp/
まとめ
訪問介護計画書の基本の書き方や記入例などを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?利用者に最適な介護サービスを提供するためには、しっかりとアセスメントをおこないニーズを把握することが重要です。また、誰が見ても分かるように要点をおさえ簡潔に記入することが大切です。
サービス提供責任者として勉強中の方は、ぜひ紹介した本も参考にしてみてください!
◎サービス提供責任者の資格について詳しく知りたい方は以下のコラムも読んでみてください!
「サービス提供責任者とは?」
サービス提供責任者として勉強中の方は、ぜひ紹介した本も参考にしてみてください!
◎サービス提供責任者の資格について詳しく知りたい方は以下のコラムも読んでみてください!
「サービス提供責任者とは?」
介護の転職なら介護ワーカー!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.