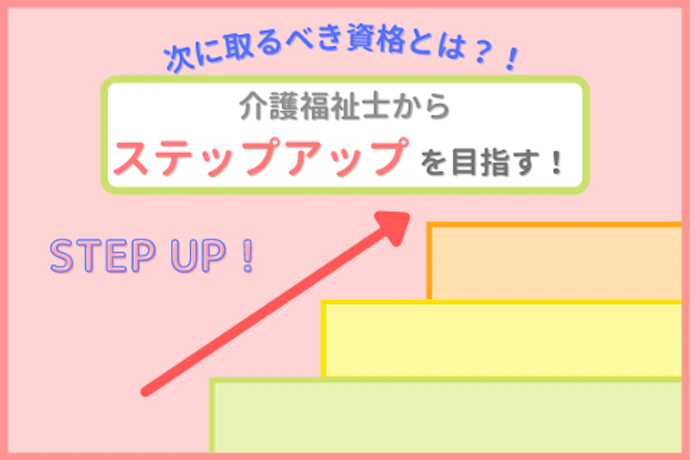介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.14
介護福祉士からステップアップを目指す!次に取るべき資格とは?!
#介護
目次
介護福祉士という国家資格を取得し働いている方で、さらにステップアップしたいと考えている方は少なくないはず。
しかし、自分の中で「介護福祉士としての将来像」や「どんなスキルを習得すべきか」がはっきりしていないと、次にどのような資格を取得すべきなのか分からないですよね。
そこで、介護福祉士におすすめの資格を目的別でまとめてみました。
ステップアップを目指したいけれど、次にどんな資格を取得すればいいか迷子になっている方は、ぜひ参考にしてみてください!
しかし、自分の中で「介護福祉士としての将来像」や「どんなスキルを習得すべきか」がはっきりしていないと、次にどのような資格を取得すべきなのか分からないですよね。
そこで、介護福祉士におすすめの資格を目的別でまとめてみました。
ステップアップを目指したいけれど、次にどんな資格を取得すればいいか迷子になっている方は、ぜひ参考にしてみてください!
介護福祉士から次はどんな資格を取得する?
介護福祉士からステップアップのために資格を取得するといっても「どのようにステップアップしたいのか」で選ぶ資格は変わってきます。
どんな資格を取得すればいいか迷子になっている方は、この「どのようにステップアップしたいのか」を具体的に考えてみてください。
具体的に考えることで、以下のように「何を目的として資格取得を目指すのか」がはっきりし、自分に必要な資格はどれなのかが分かり選びやすくなります。
それでは、上記3つの目的別にどのような資格がおすすめなのかを紹介していきたいと思います。
どんな資格を取得すればいいか迷子になっている方は、この「どのようにステップアップしたいのか」を具体的に考えてみてください。
具体的に考えることで、以下のように「何を目的として資格取得を目指すのか」がはっきりし、自分に必要な資格はどれなのかが分かり選びやすくなります。
◆介護福祉士としてスキルアップをしたい
◆介護福祉士からキャリアアップを狙いたい
◆介護福祉士から他職種に転職をしたい
それでは、上記3つの目的別にどのような資格がおすすめなのかを紹介していきたいと思います。
介護福祉士からのスキルアップにおすすめの資格とは?
介護福祉士からのスキルアップにおすすめの資格とは?
[喀痰吸引等研修]
喀痰吸引等研修は、「喀痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)」を実施できる介護職員を養成するための研修です。
実務者研修の科目に含まれている「医療的ケア」で、喀痰の吸引や経管栄養についての学習、シミュレーターを使用した演習を実施したかと思います。しかし、実務者研修を修了し介護福祉士の国家試験に合格するだけでは「喀痰吸引等」を実施することはできません。
喀痰吸引等研修を修了することで、喀痰の吸引や経管栄養の対応をすることが可能になります。喀痰吸引等研修では、講義と演習の基本講習に加えて実地研修があります。
この両方を修了することで、医師の指示や看護師との連携のもと「喀痰の吸引・経管栄養」をおこなえるようになります。
◎喀痰吸引等研修 について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「喀痰吸引等研修 ってどんな資格?」
実務者研修の科目に含まれている「医療的ケア」で、喀痰の吸引や経管栄養についての学習、シミュレーターを使用した演習を実施したかと思います。しかし、実務者研修を修了し介護福祉士の国家試験に合格するだけでは「喀痰吸引等」を実施することはできません。
喀痰吸引等研修を修了することで、喀痰の吸引や経管栄養の対応をすることが可能になります。喀痰吸引等研修では、講義と演習の基本講習に加えて実地研修があります。
この両方を修了することで、医師の指示や看護師との連携のもと「喀痰の吸引・経管栄養」をおこなえるようになります。
◎喀痰吸引等研修 について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「喀痰吸引等研修 ってどんな資格?」
[医療介護福祉士]
医療介護福祉士とは、一般社団法人日本慢性期医療協会が認定をおこなっている民間資格です。介護福祉士としての実務経験が1年以上あれば受講することが可能で、講義(16単位)+実習(8単位)の全24単位を修了し、認定試験に合格することで取得できます。
「チーム医療のメンバーとして活躍できる介護福祉士を育成すること」がこの資格の目的であるため、講義や実習では身体介護だけでなく、慢性期医療でおこなわれる検査や薬についての知識、救急処置についてなど、介護と医療について深く学びます。
介護だけでなく医療の知識もさらに深めたい方におすすめのスキルアップ資格です。
「チーム医療のメンバーとして活躍できる介護福祉士を育成すること」がこの資格の目的であるため、講義や実習では身体介護だけでなく、慢性期医療でおこなわれる検査や薬についての知識、救急処置についてなど、介護と医療について深く学びます。
介護だけでなく医療の知識もさらに深めたい方におすすめのスキルアップ資格です。
※2022年9月1日現在「医療介護福祉士」資格の講座は開講されておりません。また、今後の開講予定も現在のところ未定となっております。
[認定介護福祉士]
認定介護福祉士は、介護福祉士の上級資格として位置づけられている民間資格です。2015年12月からスタートしたまだ新しい資格となっています。認定介護福祉士を取得することで、専門的な介護実践力や現場リーダークラスへの指導力、サービス管理能力、地域の介護力向上、人材マネジメントなどのスキルを身につけられます。
養成研修のカリキュラムは全600時間とかなり多いですが、幅広い役割を担える資格でありスキルアップだけでなくキャリアアップにも繋がる資格です。
◎認定介護福祉士について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「詳しく解説!認定介護福祉士ってなに?」
養成研修のカリキュラムは全600時間とかなり多いですが、幅広い役割を担える資格でありスキルアップだけでなくキャリアアップにも繋がる資格です。
◎認定介護福祉士について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「詳しく解説!認定介護福祉士ってなに?」
【受講期間】
1年半~2年程度
※期間や日数は実施団体によって異なります。
【受講条件】
<認定介護福祉士養成研修Ⅰ類>
●介護福祉士資格を取得後、5年以上の実務経験があること
●介護職員対象の現任研修の受講歴が100時間以上あること。
●研修実施団体が課すレポート課題または受講試験で一定水準の成績を修めていること(一部免除される場合があります)
<認定介護福祉士養成研修Ⅱ類>
●認定介護福祉士養成研修Ⅰ類を修了していること
●介護職の小チームのリーダーとしての実務経験があること
※小チームとは、ユニットなど5~10名の介護職によるサービス提供チームのこと。
【費用】
会員の場合:30万円前後
非会員の場合:60万円前後
受講費用は全国一律ではなく、実施団体によって異なります。実施団体の会員であるなど、条件を満たすと受講費用が大幅に免除される場合もあります。また、地域によっては補助金制度を利用できることも。
※参考:一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構
1年半~2年程度
※期間や日数は実施団体によって異なります。
【受講条件】
<認定介護福祉士養成研修Ⅰ類>
●介護福祉士資格を取得後、5年以上の実務経験があること
●介護職員対象の現任研修の受講歴が100時間以上あること。
●研修実施団体が課すレポート課題または受講試験で一定水準の成績を修めていること(一部免除される場合があります)
<認定介護福祉士養成研修Ⅱ類>
●認定介護福祉士養成研修Ⅰ類を修了していること
●介護職の小チームのリーダーとしての実務経験があること
※小チームとは、ユニットなど5~10名の介護職によるサービス提供チームのこと。
【費用】
会員の場合:30万円前後
非会員の場合:60万円前後
受講費用は全国一律ではなく、実施団体によって異なります。実施団体の会員であるなど、条件を満たすと受講費用が大幅に免除される場合もあります。また、地域によっては補助金制度を利用できることも。
※参考:一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構
介護福祉士からキャリアアップを狙うならこの資格
キャリアアップを狙っているなら、以下のような資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか?
[認定介護福祉士]
介護福祉士の上位資格として認定されている資格です。介護福祉士よりもさらに多様な利用者や環境に対応することができる知識とスキルを習得することができます。
◎認定介護福祉士について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「詳しく解説!認定介護福祉士ってなに?」
◎認定介護福祉士について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「詳しく解説!認定介護福祉士ってなに?」
【受講期間】
1年半~2年程度
※期間や日数は実施団体によって異なります。
【受講条件】
認定介護福祉士養成研修Ⅰ類・Ⅱ類の条件を満たしている者
※Ⅰ類・Ⅱ類の詳細については「認定介護福祉士認証・認定機構」にてご確認ください。
【費用】
会員の場合:30万円前後
非会員の場合:60万円前後
※受講費用は、実施団体によって異なります。
※参考:一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構
1年半~2年程度
※期間や日数は実施団体によって異なります。
【受講条件】
認定介護福祉士養成研修Ⅰ類・Ⅱ類の条件を満たしている者
※Ⅰ類・Ⅱ類の詳細については「認定介護福祉士認証・認定機構」にてご確認ください。
【費用】
会員の場合:30万円前後
非会員の場合:60万円前後
※受講費用は、実施団体によって異なります。
※参考:一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構
[ケアマネージャー(介護支援専門員)]
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは、さまざまある介護サービスの中から利用者に合ったサービスの選択、提案(ケアプランの作成)などができるようになる資格です。
介護福祉士を取得後、次の目標としてケアマネージャーを目指す方が多い資格でもあります。
◎ケアマネージャー(介護支援専門員)のについて詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「介護支援専門員(ケアマネージャー)ってどんな資格?」
介護福祉士を取得後、次の目標としてケアマネージャーを目指す方が多い資格でもあります。
◎ケアマネージャー(介護支援専門員)のについて詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「介護支援専門員(ケアマネージャー)ってどんな資格?」
【受講期間】
約18日間(前期研修8日間+実習3日間+後期研修7日間)
※実施スケジュール、回数は都道府県によって異なるため、詳細は実施団体にてご確認ください。
【受講条件】
以下(1)(2)のいずれかを満たす人が対象となる。
(1)特定の国家資格を持っている。尚且つ、国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上の従事期間、900日以上の従事日数がある。
(2)生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、相談援助業務に通算5年以上の従事期間、900日以上の従事日数がある。
【費用】
研修費用:6万300円+テキスト代
受験費用:1万3800円+払い込み手数料
※上記の金額は大阪府のものであり、取得にかかる費用は都道府県により異なります。
※参考:大阪府介護支援専門員試験・研修情報
約18日間(前期研修8日間+実習3日間+後期研修7日間)
※実施スケジュール、回数は都道府県によって異なるため、詳細は実施団体にてご確認ください。
【受講条件】
以下(1)(2)のいずれかを満たす人が対象となる。
(1)特定の国家資格を持っている。尚且つ、国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上の従事期間、900日以上の従事日数がある。
(2)生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、相談援助業務に通算5年以上の従事期間、900日以上の従事日数がある。
【費用】
研修費用:6万300円+テキスト代
受験費用:1万3800円+払い込み手数料
※上記の金額は大阪府のものであり、取得にかかる費用は都道府県により異なります。
※参考:大阪府介護支援専門員試験・研修情報
[社会福祉主事(社会福祉主事任用資格)]
社会福祉主事とは、都道府県や市町村の各行政機関で社会福祉に関わる仕事をおこなう職種のこと。保護や援助を必要とする人のために相談・指導・援助の業務をおこないます。
社会福祉主事に任用されるために必要なのが「社会福祉主事任用資格」です。
社会福祉主事任用資格を取得し、地方公務員試験に合格後に福祉事務所に配属されると社会福祉主事として働くことができます。社会福祉主事任用資格を取得するためには、大学や通信教育、指定養成機関、講習会で科目履修や講習会受講などによって取得することが可能です。
◎社会福祉主事について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「社会福祉主事任用資格について~社会福祉主事とは結局違うの?同じなの?~」
社会福祉主事に任用されるために必要なのが「社会福祉主事任用資格」です。
社会福祉主事任用資格を取得し、地方公務員試験に合格後に福祉事務所に配属されると社会福祉主事として働くことができます。社会福祉主事任用資格を取得するためには、大学や通信教育、指定養成機関、講習会で科目履修や講習会受講などによって取得することが可能です。
◎社会福祉主事について詳しく知りたい方はこちらのコラムもチェックしてみて!
「社会福祉主事任用資格について~社会福祉主事とは結局違うの?同じなの?~」
【取得条件】
下記5つのうちいずれかを満たしていること
●大学等で指定科目を3科目以上履修して卒業
●指定の通信教育課程を修了
●指定養成機関を修了
●都道府県等講習会を受講
●社会福祉士、精神保健福祉士の資格を取得
【受講期間】
通信教育課程ルート:1年
養成機関ルート:2年~4年ほど
※詳細については「厚生労働省|社会福祉主事任用資格の取得方法」をご覧ください。
下記5つのうちいずれかを満たしていること
●大学等で指定科目を3科目以上履修して卒業
●指定の通信教育課程を修了
●指定養成機関を修了
●都道府県等講習会を受講
●社会福祉士、精神保健福祉士の資格を取得
【受講期間】
通信教育課程ルート:1年
養成機関ルート:2年~4年ほど
※詳細については「厚生労働省|社会福祉主事任用資格の取得方法」をご覧ください。
介護福祉士から転職を考える方におすすめの資格
介護福祉士の経験を活かせる分野に転職を考えている方におすすめの資格こちら。
[看護師]
看護師は、医師の診療・治療の介助、患者さんの心体のケアなど、医療をサポートする国家資格です。
【取得条件】
受験資格を取得するには、文部科学大臣指定の学校もしくは厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業することが必要です。
以下のうち、いずれかを卒業すること。
●大学(4年制:看護学系学部)
●短大(3年制:看護学科など)
●専門学校(養成所)
【学習期間】
●大学:4年
●短大:3年
●専門学校(養成所):3年、4年
【費用】
大学、短大、専門学校(養成所)のどれに通うかで、学費は大きく異なってきます。
大学の場合:【公立】約250万円【私立】約450万円~700万円
短大学の場合:【公立】約250万円【私立】400万円ほど
専門学校の場合:【公立】約60万円【私立】約250万円~300万円
受験資格を取得するには、文部科学大臣指定の学校もしくは厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業することが必要です。
以下のうち、いずれかを卒業すること。
●大学(4年制:看護学系学部)
●短大(3年制:看護学科など)
●専門学校(養成所)
【学習期間】
●大学:4年
●短大:3年
●専門学校(養成所):3年、4年
【費用】
大学、短大、専門学校(養成所)のどれに通うかで、学費は大きく異なってきます。
大学の場合:【公立】約250万円【私立】約450万円~700万円
短大学の場合:【公立】約250万円【私立】400万円ほど
専門学校の場合:【公立】約60万円【私立】約250万円~300万円
[准看護師]
准看護師は、都道府県知事発行の免許です。
准看護師も看護師と同じように患者さんのケアをおこなうことが仕事ですが、看護師との違いは「医師・歯科医師または看護師の指示を受けて業務をおこなう」ということです。
養成学校に通い2年で取得できるほか、全日制と半日制の通学スタイルがあり選ぶことができるため、働きながら資格取得を目指すことが可能です。
准看護師も看護師と同じように患者さんのケアをおこなうことが仕事ですが、看護師との違いは「医師・歯科医師または看護師の指示を受けて業務をおこなう」ということです。
養成学校に通い2年で取得できるほか、全日制と半日制の通学スタイルがあり選ぶことができるため、働きながら資格取得を目指すことが可能です。
【取得条件】
●中学校を卒業していること
●養成学校にて規定のカリキュラム修了し卒業すること
【学習期間】
2年
【費用】
どの養成学校に通うのか、また全日制なのか半日制なのかによって学費は異なります。下記の学費額は一例です。
学費:約140万円(2年間合計)
※参考:一般社団法人 大阪精神科病院協会 大精協看護専門学校
●中学校を卒業していること
●養成学校にて規定のカリキュラム修了し卒業すること
【学習期間】
2年
【費用】
どの養成学校に通うのか、また全日制なのか半日制なのかによって学費は異なります。下記の学費額は一例です。
学費:約140万円(2年間合計)
※参考:一般社団法人 大阪精神科病院協会 大精協看護専門学校
[理学療法士/作業療法士]
理学療法士と作業療法士は、どちらもリハビリテーションをおこなう国家資格です。
理学療法士は、運動機能回復のスペシャリストとして「立ち上がる・起き上がる・歩く・寝返り」など基本となる体の動作の訓練をおこないます。
作業療法士は、日常生活をスムーズにするための動作に焦点をあて「食事をする・顔や体を洗う・料理・字を書く」など生活するうえで必要となる動作の訓練をおこないます。
理学療法士も作業療法士も病院や介護施設などと関わりの深い職種であるため、介護士からキャリアアップのために取得すし転職する方も多い資格です。
理学療法士は、運動機能回復のスペシャリストとして「立ち上がる・起き上がる・歩く・寝返り」など基本となる体の動作の訓練をおこないます。
作業療法士は、日常生活をスムーズにするための動作に焦点をあて「食事をする・顔や体を洗う・料理・字を書く」など生活するうえで必要となる動作の訓練をおこないます。
理学療法士も作業療法士も病院や介護施設などと関わりの深い職種であるため、介護士からキャリアアップのために取得すし転職する方も多い資格です。
【取得験条件】
●高校を卒業していること
●文部科学大臣に指定されている養成校にて、規定のカリキュラムを修了し卒業すること
【学習期間】
大学、短大、専門学校(3年制・4年制)と、選ぶルートにより異なる。
●大学:4年
●短大:3年
●専門学校:3年~4年
【費用】
学費の金額は、選ぶルートが「大学、短大、専門学校(3年制・4年制)」なのかによって異なります。以下は働きながら資格取得を目指せる「専門学校(夜間部あり)」の学費例です。
<理学療法士>
昼間部(4年制):541万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
夜間部(4年制):418万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
<作業療法士>
昼間部(4年制):541万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
夜間部(4年制):418万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
※参考:大阪医療福祉専門学校
●高校を卒業していること
●文部科学大臣に指定されている養成校にて、規定のカリキュラムを修了し卒業すること
【学習期間】
大学、短大、専門学校(3年制・4年制)と、選ぶルートにより異なる。
●大学:4年
●短大:3年
●専門学校:3年~4年
【費用】
学費の金額は、選ぶルートが「大学、短大、専門学校(3年制・4年制)」なのかによって異なります。以下は働きながら資格取得を目指せる「専門学校(夜間部あり)」の学費例です。
<理学療法士>
昼間部(4年制):541万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
夜間部(4年制):418万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
<作業療法士>
昼間部(4年制):541万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
夜間部(4年制):418万5000円(入学金・授業料・実習費・設備費・教育教材演習費)
※参考:大阪医療福祉専門学校
[社会福祉士]
社会福祉士とは「社会福祉及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務における国家資格です。社会福祉士は、身体上、精神上の障がいがあること、また環境上の理由によって日常生活を送ることが難しくなった方の相談を受け、助言や指導をおこない福祉サービスや医療サービスとの連携や調整などをおこなうことが仕事です。
実際、上記の業務は資格を持っていなくてもおこなうことは可能ですが「社会福祉士」と名乗ることはできません。社会福祉と名乗るには国家資格が必要となります。
◎社会福祉士について詳しく知りたい方は以下のコラムをチェックしてみて!
「 わかりやすく解説!社会福祉士 ってどんな資格?」
実際、上記の業務は資格を持っていなくてもおこなうことは可能ですが「社会福祉士」と名乗ることはできません。社会福祉と名乗るには国家資格が必要となります。
◎社会福祉士について詳しく知りたい方は以下のコラムをチェックしてみて!
「 わかりやすく解説!社会福祉士 ってどんな資格?」
【取得条件】
規定のルートを経て国家試験の受験資格を満すことが必要です。
資格取得のルートは、学歴や実務経験によって12通りに分かれています。自分がどのルートに当てはまるのかをチェックし、必要カリキュラムを修了しなければなりません。
ルートは以下のリンクからチェックしてみてください。
「公益社団法人 社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」」
※参考:公益社団法人 社会福祉振興・試験センター
【受講期間】
短期養成施設等:6カ月以上
一般養成施設等:1年以上
【費用】
「短期養成施設・一般養成施設」で必要カリキュラムを受講する場合の学費は、各養成施設によって異なります。以下の学費は一例ですので、詳細については各養成施設へお問い合わせください。
<短期養成通信課程>
学費:21万7000円(選考料・入学金・授業料・諸費用)
実習費:10万円((実務経験が1年以上ある場合、実習は免除になり実習費は不要))
<一般養成通信課程>
学費:32万1000円(選考料・入学金・授業料・諸費用)
実習費:10万円(実習費(実務経験が1年以上ある場合、実習は免除になり実習費は不要))
※参考:東京福祉専門学校
規定のルートを経て国家試験の受験資格を満すことが必要です。
資格取得のルートは、学歴や実務経験によって12通りに分かれています。自分がどのルートに当てはまるのかをチェックし、必要カリキュラムを修了しなければなりません。
ルートは以下のリンクからチェックしてみてください。
「公益社団法人 社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」」
※参考:公益社団法人 社会福祉振興・試験センター
【受講期間】
短期養成施設等:6カ月以上
一般養成施設等:1年以上
【費用】
「短期養成施設・一般養成施設」で必要カリキュラムを受講する場合の学費は、各養成施設によって異なります。以下の学費は一例ですので、詳細については各養成施設へお問い合わせください。
<短期養成通信課程>
学費:21万7000円(選考料・入学金・授業料・諸費用)
実習費:10万円((実務経験が1年以上ある場合、実習は免除になり実習費は不要))
<一般養成通信課程>
学費:32万1000円(選考料・入学金・授業料・諸費用)
実習費:10万円(実習費(実務経験が1年以上ある場合、実習は免除になり実習費は不要))
※参考:東京福祉専門学校
介護福祉から取得すると「免除」がある資格とは?
今持っている介護福祉士の国家資格をできれば活用し、新たな資格を取得したいと考えている方は少なくないはず。様々ある資格のなかには、介護福祉士資格を取得していることで受験科目の一部が免除されるものもあります。
一部免除のある資格というのが
保育士資格は、介護福祉士資格を保有していると保育士試験の全9科目中3科目「社会福祉」「子ども家庭福祉」「社会的養護」の筆記受験が免除されます。
免除されている理由としては、介護分野と保育分野で重複する基礎内容とっていること、また介護福祉士はこれらの知識が身についているという扱いになっているからです。
子どもと関わりたいと思っているのであれば、保育士の資格取得を目指すのもよいでしょう。介護福祉士の資格を持ちながら保育士の資格を取得することで、一般的な保育施設だけでなく障がい児施設や介護施設に併設されている保育所などでも働くことが可能となります。
介護福祉士の資格保有者で保育に興味がある方は、保育士を取得することで一般的な保育士よりも活躍できる職場が広がるでしょう。
一部免除のある資格というのが
「保育士」資格
です。保育士資格は、介護福祉士資格を保有していると保育士試験の全9科目中3科目「社会福祉」「子ども家庭福祉」「社会的養護」の筆記受験が免除されます。
免除されている理由としては、介護分野と保育分野で重複する基礎内容とっていること、また介護福祉士はこれらの知識が身についているという扱いになっているからです。
子どもと関わりたいと思っているのであれば、保育士の資格取得を目指すのもよいでしょう。介護福祉士の資格を持ちながら保育士の資格を取得することで、一般的な保育施設だけでなく障がい児施設や介護施設に併設されている保育所などでも働くことが可能となります。
介護福祉士の資格保有者で保育に興味がある方は、保育士を取得することで一般的な保育士よりも活躍できる職場が広がるでしょう。
【取得条件】
保育士資格は、ルートにより取得条件が異なります。
●保育系大学、短大、専門学校などを卒業
●大学、短大、専門学校に2年以上の在学+保育士試験の合格
●実務経験2年以上(高卒)+保育士試験の合格
●実務経験5年以上(中卒)+保育士試験の合格
【受講期間】
保育系大学、短大、専門学校の卒業以外は、独学もしくは通信教育などで保育士試験に向けての勉強が必要です。
通信教育:最短6カ月~1年
【費用】
保育士資格取得にかかる費用は、どのルートで取得するかによります。
働きながら資格取得を目指せる通信教育にかかる費用の例は以下です。
5万9700円(教材・指導費・消費税含む)
※参考:生涯学習のユーキャン
保育士資格は、ルートにより取得条件が異なります。
●保育系大学、短大、専門学校などを卒業
●大学、短大、専門学校に2年以上の在学+保育士試験の合格
●実務経験2年以上(高卒)+保育士試験の合格
●実務経験5年以上(中卒)+保育士試験の合格
【受講期間】
保育系大学、短大、専門学校の卒業以外は、独学もしくは通信教育などで保育士試験に向けての勉強が必要です。
通信教育:最短6カ月~1年
【費用】
保育士資格取得にかかる費用は、どのルートで取得するかによります。
働きながら資格取得を目指せる通信教育にかかる費用の例は以下です。
5万9700円(教材・指導費・消費税含む)
※参考:生涯学習のユーキャン
まとめ
介護福祉士から取得できるおすすめの資格について、紹介してきましたが気になる資格は見つかったでしょうか?どのような資格を取得するか迷っている方は、何を目的に資格取得を考えているのか、また資格の取得後にどのように働きたいのかなどを一度考えてみるといいかもしれません。働きながら資格を取得したい方は、夜間部で学べる資格や通信講座がある資格など条件を絞って探してみてくださいね。
介護の転職なら介護ワーカー!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.