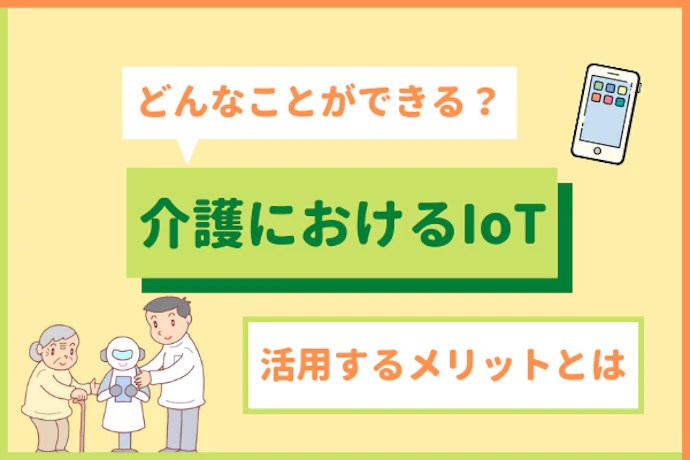介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
介護におけるIoTはどんなことができる?活用するメリットとは
#介護
目次
近年、介護業界でもIoT技術を導入する施設や事業者などが増えてきました。
しかし「IoT」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどのようなものなのか詳しくは分らないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回の記事では、IoTの意味や介護におけるIoTとはどのようなものなのか、また介護でIoTを活用するメリットなども含めて解説したいと思います。ぜひ、参考に読んでみてくださいね。
しかし「IoT」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどのようなものなのか詳しくは分らないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回の記事では、IoTの意味や介護におけるIoTとはどのようなものなのか、また介護でIoTを活用するメリットなども含めて解説したいと思います。ぜひ、参考に読んでみてくださいね。
介護におけるIoTとは?
IoTという言葉を最近よく耳にしますが、
「IoTって何?」
「聞いたことはあるけど、よく分からない」
「介護にIoTって関係あるの?」
といったように、あまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。
まずは「そもそもIoTとはどのようなものなのか」について解説していきたいと思います。
「IoTって何?」
「聞いたことはあるけど、よく分からない」
「介護にIoTって関係あるの?」
といったように、あまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。
まずは「そもそもIoTとはどのようなものなのか」について解説していきたいと思います。
そもそも「IoT」ってナニ?
IoTは「Internet of Things」の頭文字を取り略した言葉です。日本語に直訳すると「モノのインターネット」となります。
IoTは、自動車や家電製品のような従来インターネットに繋がっていない様々な「モノ(物体)」自体に、通信機能を持たせてインターネットに繋げ、相互に情報交換をするという仕組みです。
つまり、モノに通信機器(センサー)を付けてインターネットに接続し、取得した情報をより便利に活用できるようにすることを表します。
これまでインターネットと関係の無かったジャンルの「モノ」と「インターネット」を繋ぐ際にIoTという言葉が使われています。
IoT技術はすでに身近なモノにも活用されているので、自分でも気づかないうちに日常生活で利用している方は少なくないでしょう。たとえば、家電製品であればテレビやエアコン、冷蔵庫、電気、スピーカーなどです。家電製品でIoT技術が活用されているものは「IoT家電」とも呼ばれています。
IoT家電でどのようなことが可能になるのかというと、エアコンであれば「遠隔操作をおこない、帰宅時間に合わせて部屋の温度設定ができる」また、洗濯機であれば「洗濯物の量や天気、これまでの洗濯履歴に基づいて最適量の洗剤や柔軟剤を自動投入する」などです。
IoTは、自動車や家電製品のような従来インターネットに繋がっていない様々な「モノ(物体)」自体に、通信機能を持たせてインターネットに繋げ、相互に情報交換をするという仕組みです。
つまり、モノに通信機器(センサー)を付けてインターネットに接続し、取得した情報をより便利に活用できるようにすることを表します。
これまでインターネットと関係の無かったジャンルの「モノ」と「インターネット」を繋ぐ際にIoTという言葉が使われています。
IoT技術はすでに身近なモノにも活用されているので、自分でも気づかないうちに日常生活で利用している方は少なくないでしょう。たとえば、家電製品であればテレビやエアコン、冷蔵庫、電気、スピーカーなどです。家電製品でIoT技術が活用されているものは「IoT家電」とも呼ばれています。
IoT家電でどのようなことが可能になるのかというと、エアコンであれば「遠隔操作をおこない、帰宅時間に合わせて部屋の温度設定ができる」また、洗濯機であれば「洗濯物の量や天気、これまでの洗濯履歴に基づいて最適量の洗剤や柔軟剤を自動投入する」などです。
介護におけるIoTはどんなことができるのか?
IoTの技術は人々の日常生活を便利にするだけでなく、介護業界でも活用され始めています。
介護におけるIoTは、
●高齢者の健康状態や安全を遠く離れている場所からでも確認できる
●高齢者の状態の異変を察知し素早く通知、さらにロボットで声かけをする
●在庫管理や発注といった業務を自動化
など、高齢者に関わることから介護スタッフの業務の効率化などにつながるものまで、色々なモノに活用されています。
IoT技術の活用は、介護業務の負担軽減だけでなく介護の質の向上に繋がると期待されています。
実際にどのようなIoT機器が導入されているのか、次で紹介していきたいと思います。
介護におけるIoTは、
●高齢者の健康状態や安全を遠く離れている場所からでも確認できる
●高齢者の状態の異変を察知し素早く通知、さらにロボットで声かけをする
●在庫管理や発注といった業務を自動化
など、高齢者に関わることから介護スタッフの業務の効率化などにつながるものまで、色々なモノに活用されています。
IoT技術の活用は、介護業務の負担軽減だけでなく介護の質の向上に繋がると期待されています。
実際にどのようなIoT機器が導入されているのか、次で紹介していきたいと思います。
介護現場に導入されているIoT機器とは
介護の現場で役立つIoT機器の種類はさまざまで、次々と新しい機能を備えて発売されています。そのため、同じ役割のIoT機器でも選ぶメーカーや種類によって備えている機能は異なります。
そこで、介護施設や事業所などで導入されることの多いIoT機器を紹介したいと思います。
介護施設などで導入されることの多いIoT機器は、
■見守りシステム
■コミュニケーションサポートシステム
■事務業務の負担軽減システム
など、上記3つのいずれかを導入していることがほとんどです。
それぞれ、どのようなIoT機器なのか見ていきましょう。
見守り型のIoTシステムは、接触型と非接触型の2種類があります。
接触型の機器は、ベッドに敷いて使うセンサーマットやバイタルセンサーなどです。
非接触型の機器は、ドアや壁、ベッドの下、などに設置するセンサーやカメラ、スマホなどに搭載されています。
見守りセンサーは、高齢者の異常を検知するとすぐにスマートフォンやPCなどに通知をおくります。また通知だけでなく、カメラで高齢者の状態を確認することも可能なため、緊急の場合などすぐに必要な対応をすることが可能になります。
このように多くの場合、見守りセンサーだけではなくスマートフォンやPC、介護ロボットなど複数の機器を連携させていることがほとんどです。
また見守りセンサーは、介護施設以外にも遠方で暮らす高齢者の家族の見守りにも活用されています。
高齢者のコミュニケーションをサポートするシステムを備えているのが介護ロボットと呼ばれるIoT機器です。
介護ロボットは、センサーで高齢者を見守ったり、声かけをしてコミュニケーションを図ったりします。また、レクリエーションのプログラムを搭載している介護ロボットであれば、音楽を流したり、音楽に合わせて身体を動かす遊びをしたり、クイズを出したりとさまざまな機能が備わっています。
介護ロボットにAI(人工知能)を搭載しているものであれば、言葉の学習や相手を認識し表情などを読み取れるものもあります。さらには、介護ロボットにモニターが付いているものであれば、遠方にいるなど直接面会することが難しい家族とモニター越しに対話することも可能です。
事務業務の負担を軽減させるIoTシステムは、
・電子カルテなどの介護記録をタブレット端末などで入力できるもの
・コール履歴を自動で取込み、日常記録と合わせて表示できるもの
・高齢者のヘルスケアに必要なデータを集約できるもの
・消耗品などの備品の在庫管理をおこない発注までしてくれるもの
などがあります。
介護記録などの情報が電子化になることで、手書きで作成するよりも書類作成業務の負担が軽減されるだけでなく、紙よりも利用者情報を共有しやすく、タブレット端末さえあればその場ですぐに情報を確認できるようになります。
また、在庫管理などの業務もIoT機器を導入すれば在庫数もすぐに確認することが可能です。最新のものであれば、一定量を過ぎると知らせてくれるだけでなく自動で発注もしてくれるため、発注ミスによる過剰在庫や欠品を防ぐことが可能です。
そこで、介護施設や事業所などで導入されることの多いIoT機器を紹介したいと思います。
介護施設などで導入されることの多いIoT機器は、
■見守りシステム
■コミュニケーションサポートシステム
■事務業務の負担軽減システム
など、上記3つのいずれかを導入していることがほとんどです。
それぞれ、どのようなIoT機器なのか見ていきましょう。
見守りシステム
見守り型のIoTシステムは、接触型と非接触型の2種類があります。
接触型の機器は、ベッドに敷いて使うセンサーマットやバイタルセンサーなどです。
非接触型の機器は、ドアや壁、ベッドの下、などに設置するセンサーやカメラ、スマホなどに搭載されています。
見守りセンサーは、高齢者の異常を検知するとすぐにスマートフォンやPCなどに通知をおくります。また通知だけでなく、カメラで高齢者の状態を確認することも可能なため、緊急の場合などすぐに必要な対応をすることが可能になります。
このように多くの場合、見守りセンサーだけではなくスマートフォンやPC、介護ロボットなど複数の機器を連携させていることがほとんどです。
また見守りセンサーは、介護施設以外にも遠方で暮らす高齢者の家族の見守りにも活用されています。
コミュニケーションサポートシステム
高齢者のコミュニケーションをサポートするシステムを備えているのが介護ロボットと呼ばれるIoT機器です。
介護ロボットは、センサーで高齢者を見守ったり、声かけをしてコミュニケーションを図ったりします。また、レクリエーションのプログラムを搭載している介護ロボットであれば、音楽を流したり、音楽に合わせて身体を動かす遊びをしたり、クイズを出したりとさまざまな機能が備わっています。
介護ロボットにAI(人工知能)を搭載しているものであれば、言葉の学習や相手を認識し表情などを読み取れるものもあります。さらには、介護ロボットにモニターが付いているものであれば、遠方にいるなど直接面会することが難しい家族とモニター越しに対話することも可能です。
事務業務の負担を軽減させるシステム
事務業務の負担を軽減させるIoTシステムは、
・電子カルテなどの介護記録をタブレット端末などで入力できるもの
・コール履歴を自動で取込み、日常記録と合わせて表示できるもの
・高齢者のヘルスケアに必要なデータを集約できるもの
・消耗品などの備品の在庫管理をおこない発注までしてくれるもの
などがあります。
介護記録などの情報が電子化になることで、手書きで作成するよりも書類作成業務の負担が軽減されるだけでなく、紙よりも利用者情報を共有しやすく、タブレット端末さえあればその場ですぐに情報を確認できるようになります。
また、在庫管理などの業務もIoT機器を導入すれば在庫数もすぐに確認することが可能です。最新のものであれば、一定量を過ぎると知らせてくれるだけでなく自動で発注もしてくれるため、発注ミスによる過剰在庫や欠品を防ぐことが可能です。
介護にIoT導入するメリット
介護現場にIoT機器を導入するメリットは以下の3つ。
メリット①|介護スタッフの業務負担が軽減する
介護現場にIoT機器を導入することで、介護スタッフの業務負担がかなり軽減されます。
どのIoT機器を導入するのかによって、どの業務の負担が軽くなるのかは違ってきますが、介護記録の作成などの事務作業や夜間の見回りなどの負担を軽減することができます。
事務作業などは、介護業務の合間にすることがほとんどですが、人手不足もあり忙しいため残業をして作成している介護職は少なくありません。IoT機器を導入することで、書類作成にあてていた業務時間を大幅に短縮できるようになり、業務時間内に終わらせられるようになります。
どのIoT機器を導入するのかによって、どの業務の負担が軽くなるのかは違ってきますが、介護記録の作成などの事務作業や夜間の見回りなどの負担を軽減することができます。
事務作業などは、介護業務の合間にすることがほとんどですが、人手不足もあり忙しいため残業をして作成している介護職は少なくありません。IoT機器を導入することで、書類作成にあてていた業務時間を大幅に短縮できるようになり、業務時間内に終わらせられるようになります。
メリット②|介護ケアの質を向上できる
IoT機器を導入するすることで介護職1人ひとりが心に余裕ができ、ケアの質の向上を図れます。人手不足のなか多くの業務をこなす介護スタッフは、常に業務に追われ忙しくしています。
そのため、心に余裕をもてず利用者に寄り添った介護をしたいと思いながらも、業務こなすのに必死で利用者のペースに合わせてあげられないこともあります。しかし、IoT機器を導入し業務負担が軽減することで介護職の心にも余裕が生まれ、より利用者に寄り添ったケアを提供できるようになり、結果ケアの質の向上に繋がります。
そのため、心に余裕をもてず利用者に寄り添った介護をしたいと思いながらも、業務こなすのに必死で利用者のペースに合わせてあげられないこともあります。しかし、IoT機器を導入し業務負担が軽減することで介護職の心にも余裕が生まれ、より利用者に寄り添ったケアを提供できるようになり、結果ケアの質の向上に繋がります。
メリット③|緊急時に迅速な対応をおこなえる
IoT機器を導入することによって、利用者の転倒や急病などの異変に素早く気付けるようになり、迅速かつ適切な対応をおこなうことが可能になります。
センサーなどのIoT機器を導入していれば、居室から離れていても異変があればアラームで知らせてくれ、スマートフォンやタブレットなどで様子を確認できます。とくに、センサーなどのIoT機器を導入することで、夜間帯に勤務している介護職が持つ不安感を和らげることができます。
IoT機器を導入するメリットは他にもたくさんありますが、これらのIoT機器の導入が思うほど進んでいないのが現状です。その理由を次で見ていきましょう。
センサーなどのIoT機器を導入していれば、居室から離れていても異変があればアラームで知らせてくれ、スマートフォンやタブレットなどで様子を確認できます。とくに、センサーなどのIoT機器を導入することで、夜間帯に勤務している介護職が持つ不安感を和らげることができます。
IoT機器を導入するメリットは他にもたくさんありますが、これらのIoT機器の導入が思うほど進んでいないのが現状です。その理由を次で見ていきましょう。
介護現場でIoT機器の導入が進まない理由
介護現場への導入が進まない理由はさまざまありますが、なかでも一番の理由は「IoTの導入費用が高い」ということです。
IoT機器を活用するには、インターネット環境があることが必要不可欠。そのため、インターネットの環境が整っていない施設は、まずIoT機器を使える環境を整える必要があります。また、見守りセンサーなどの機器とその情報を受け取るためのパソコンやタブレット端末、スマートフォンなどを揃えなければなりません。
これらの機器を購入し、設備を整えるのには多額の費用が必要になるため、導入したくても導入できない施設が多く、介護現場でIoT機器の普及が進まない理由となっています。
IoT機器を活用するには、インターネット環境があることが必要不可欠。そのため、インターネットの環境が整っていない施設は、まずIoT機器を使える環境を整える必要があります。また、見守りセンサーなどの機器とその情報を受け取るためのパソコンやタブレット端末、スマートフォンなどを揃えなければなりません。
これらの機器を購入し、設備を整えるのには多額の費用が必要になるため、導入したくても導入できない施設が多く、介護現場でIoT機器の普及が進まない理由となっています。
IoT導入には補助金制度を活用しよう!
IoT機器の導入をする際に活用できる補助金制度をご紹介したいと思います。
IoT導入に活用できる補助金制度は以下。
◆ICT導入支援事業
◆介護ロボット導入支援事業
IoT導入に活用できる補助金制度は以下。
◆ICT導入支援事業
◆介護ロボット導入支援事業
【ICT導入支援事業】
介護業務の効率化を図るため、厚生労働省が設けた「ICT導入支援事業」。
この支援事業では、ICT導入に必要となる費用の一部を補助してくれます。
補助の対象となるのは、ネットワーク機器やタブレット端末、スマートフォン、介護ソフト、バックオフィスソフトなどの購入費用です。
<補助上限額>(令和2年度 補正)
事業所規模(職員数)に応じて設定
●1人~10人 100万円
●11~20人 160万円
●21~30人 200万円
●31人~ 260万円
<補助率>
一定の要件を満たす事業所は、3/4を下限に都道府県の裁量により設定。
それ以外の事業所は1/2を下限に都道府県の裁量により設定
<補助対象>
従来の機器・介護ソフトに加え、以下を新たに対象とする。
・wi-fi購入・設置費(通信費は含まない)
・業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト(一気通貫等の要件は満たす必要あり)
ICT導入支援事業について詳しく知りたい方は、以下リンクもしくは各都道府県のホームページよりご確認ください。
「地域医療介護総合確保基金-ICT導入支援事業」
この支援事業では、ICT導入に必要となる費用の一部を補助してくれます。
補助の対象となるのは、ネットワーク機器やタブレット端末、スマートフォン、介護ソフト、バックオフィスソフトなどの購入費用です。
<補助上限額>(令和2年度 補正)
事業所規模(職員数)に応じて設定
●1人~10人 100万円
●11~20人 160万円
●21~30人 200万円
●31人~ 260万円
<補助率>
一定の要件を満たす事業所は、3/4を下限に都道府県の裁量により設定。
それ以外の事業所は1/2を下限に都道府県の裁量により設定
<補助対象>
従来の機器・介護ソフトに加え、以下を新たに対象とする。
・wi-fi購入・設置費(通信費は含まない)
・業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト(一気通貫等の要件は満たす必要あり)
ICT導入支援事業について詳しく知りたい方は、以下リンクもしくは各都道府県のホームページよりご確認ください。
「地域医療介護総合確保基金-ICT導入支援事業」
【介護ロボット導入支援事業】
各都道府県に設置されている「地域医療介護総合確保基金」を活用した、介護施設等に対する介護ロボット導入支援です。
新型コロナウイルス感染症の発生によって、職員体制の縮小や感染症対策などの業務が増加したことにより、職員の負担軽減や業務効率化を図るため補助金額の引き上げなど更なる拡充がおこなわれました。
<補助上限額>(令和2年度 3次補正予算)
■介護ロボット導入補助額(1機器あたり)
・移乗支援(装着型・非装着型):上限100万円
・入浴支援:上限100万円
・上記以外:上限30万円
■見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備(Wi-Fi工事、インカム)
上限750万円(1事業所あたり)
※見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連動させる情報連携のネットワーク構築経費を対象に追加
<補助上限台数>
1事業所あたり:必要台数(制限の撤廃)
<補助率>
一定の要件を満たす事業所は、3/4を下限に都道府県の裁量により設定。
それ以外の事業所は1/2を下限に都道府県の裁量により設定。
介護ロボット導入支援の補助金について、詳しく知りたい方は以下リンクもしくは各都道府県のホームページよりご確認ください。
「地域医療介護総合確保基金-介護ロボット導入支援事業」
※参考:厚生労働省|「介護ロボットの開発・普及の促進」
新型コロナウイルス感染症の発生によって、職員体制の縮小や感染症対策などの業務が増加したことにより、職員の負担軽減や業務効率化を図るため補助金額の引き上げなど更なる拡充がおこなわれました。
<補助上限額>(令和2年度 3次補正予算)
■介護ロボット導入補助額(1機器あたり)
・移乗支援(装着型・非装着型):上限100万円
・入浴支援:上限100万円
・上記以外:上限30万円
■見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備(Wi-Fi工事、インカム)
上限750万円(1事業所あたり)
※見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連動させる情報連携のネットワーク構築経費を対象に追加
<補助上限台数>
1事業所あたり:必要台数(制限の撤廃)
<補助率>
一定の要件を満たす事業所は、3/4を下限に都道府県の裁量により設定。
それ以外の事業所は1/2を下限に都道府県の裁量により設定。
介護ロボット導入支援の補助金について、詳しく知りたい方は以下リンクもしくは各都道府県のホームページよりご確認ください。
「地域医療介護総合確保基金-介護ロボット導入支援事業」
※参考:厚生労働省|「介護ロボットの開発・普及の促進」
まとめ
介護におけるIoT機器の活用は、働く介護職の業務負担を軽減させるだけでなく、利用者である高齢者の健康を守ることにも役立ちます。また、上手くIoT機器を活用することによって、スタッフのストレスを軽減することができ心の余裕を作ることができるため、ケアの質を向上させることができ利用者のQOLの向上にも繋がります。
ICTのことや介護ロボットのことなどについて、もっと詳しく知りたい方は以下のコラムも併せて読んでみてください。
◎「介護現場でICTを活用!どんなメリットがある?」
◎「介護ロボットが注目される理由とは?種類や導入のメリットもご紹介」
ICTのことや介護ロボットのことなどについて、もっと詳しく知りたい方は以下のコラムも併せて読んでみてください。
◎「介護現場でICTを活用!どんなメリットがある?」
◎「介護ロボットが注目される理由とは?種類や導入のメリットもご紹介」
介護の転職なら介護ワーカー
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.