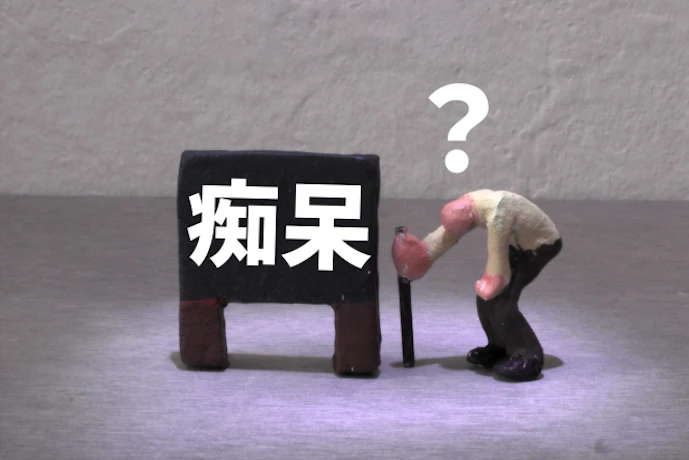介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.01
痴呆症と認知症の違いとは? 名称が変更した経緯を解説
#介護
目次
痴呆症と認知症の違いについて知っていますか?
認知症について知っていても、痴呆症について詳しく知らない方が多いでしょう。
それに、痴呆症について調べようとしても、詳しく解説された資料が見つからないかもしれません。
今回は痴呆症と認知症の違いがわかるように、様々な視点から解説します。
認知症について知っていても、痴呆症について詳しく知らない方が多いでしょう。
それに、痴呆症について調べようとしても、詳しく解説された資料が見つからないかもしれません。
今回は痴呆症と認知症の違いがわかるように、様々な視点から解説します。
痴呆症と認知症の違いとは?
痴呆症は認知症の以前の名称
痴呆症と認知症の違いはありません。
違いをあげるとすると、以前使用されていた名称が痴呆症で、現在使用されている名称が認知症であるということです。
平成16(2004)年に厚生労働省が「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」を開催し、「認知症」を新しい名称として提唱しました。
それ以降、痴呆症や痴呆という名称は使用されなくなりました。
違いをあげるとすると、以前使用されていた名称が痴呆症で、現在使用されている名称が認知症であるということです。
平成16(2004)年に厚生労働省が「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」を開催し、「認知症」を新しい名称として提唱しました。
それ以降、痴呆症や痴呆という名称は使用されなくなりました。
痴呆症が認知症になった理由
痴呆症から認知症へ名称を変更したのは、痴呆症の使用には以下のような様々な問題点があったためです。
国民的な理解を得るための妨げになる
病状を正しく表していない
痴呆症の高齢者は感情やプライドが傷つけられる
何もわからなくなるわけではない
記憶障害は人や病状によって様々である
誤った実態を広めている要因の一つである
怖さや恥ずかしさなどの認識が施策実施の支障になっている
名称が恐怖心や羞恥心を増幅させている
上記の問題点を踏まえ、前述の検討会が開催されました。
● 侮蔑感を感じさせる表現である
国民的な理解を得るための妨げになる
病状を正しく表していない
痴呆症の高齢者は感情やプライドが傷つけられる
● 病状・実態を正確に表していない
何もわからなくなるわけではない
記憶障害は人や病状によって様々である
誤った実態を広めている要因の一つである
● 早期発見や早期診断などの取り組みを妨げる
怖さや恥ずかしさなどの認識が施策実施の支障になっている
名称が恐怖心や羞恥心を増幅させている
上記の問題点を踏まえ、前述の検討会が開催されました。
痴呆症の名称変更の経緯
痴呆症の名称変更には以下のような経緯がありました。
このような流れを受けて、厚生労働省が「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」を、平成16(2004)年に合計4回開催し、認知症という新名称を提唱したのです。
● 厚生労働大臣が名称変更の要望書を痴呆症の研究機関から受け取った
● 日本老年精神医学会の「痴呆名称に関する検討委員会」で検討された
このような流れを受けて、厚生労働省が「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」を、平成16(2004)年に合計4回開催し、認知症という新名称を提唱したのです。
認知症が痴呆症と呼ばれていた時代
厚生労働省が新名称として認知症を提唱する以前は痴呆症と呼ばれてました。ここでは痴呆症と呼ばれていた平成16(2004)年以前についてみていきましょう。
痴呆症の高齢者 は少なかった
以前は痴呆症の高齢者だけではなく高齢者が現在と比べてが少ない状況でした。
平成14(2002)年9月時点で痴呆性老人自立度II以上の方が228万人いました。
認知症が500万人以上、65歳以上高齢者の約7人に1人が認知症とされる現在の半分以下の数です。
なお、痴呆性老人自立度とは、痴呆症によって日常生活に支障があるかを示した指標で、Ⅰから数字が増えるにしたがって状態の悪化を示します。
参照:厚生労働省 「痴呆」に替わる用語に関する検討会
また、平成14(2002)年9月と令和5(2023)年1月の高齢者数と高齢化率も、下表のように大きく異なっています。
平成14(2002)年9月時点で痴呆性老人自立度II以上の方が228万人いました。
認知症が500万人以上、65歳以上高齢者の約7人に1人が認知症とされる現在の半分以下の数です。
なお、痴呆性老人自立度とは、痴呆症によって日常生活に支障があるかを示した指標で、Ⅰから数字が増えるにしたがって状態の悪化を示します。
参照:厚生労働省 「痴呆」に替わる用語に関する検討会
また、平成14(2002)年9月と令和5(2023)年1月の高齢者数と高齢化率も、下表のように大きく異なっています。
| 総人口 | 65歳以上の高齢者人口 | 高齢化率 |
平成14年9月 | 12,738万人 | 2,358万人 | 18.5% |
令和5年1月 | 12,477万人 | 3,621万人 | 29.0% |
社会的入院が社会問題になっていた
以前は高齢者の社会的入院が社会問題になっていました。
社会的入院とは、治療の必要がない患者の長期間の入院です。
日本では自宅での介護が困難であるといった理由で、長期間入院する高齢者が多い状況でした。
不必要な長期間の入院は、医療費の増大やベッド満床による救急患者の受け入れを難しくさせることなどの様々な問題を引き起こしていました。
平成12(2000)年に創設された介護保険制度は、高齢者の社会的入院を解消させる目的もありました。
社会的入院とは、治療の必要がない患者の長期間の入院です。
日本では自宅での介護が困難であるといった理由で、長期間入院する高齢者が多い状況でした。
不必要な長期間の入院は、医療費の増大やベッド満床による救急患者の受け入れを難しくさせることなどの様々な問題を引き起こしていました。
平成12(2000)年に創設された介護保険制度は、高齢者の社会的入院を解消させる目的もありました。
小説『恍惚の人』で痴呆症と呼ばれていた時代がわかる!
痴呆症と呼ばれていた時代は、有吉佐和子の小説『恍惚の人』で描かれています。
『恍惚の人』は、昭和47(1972)年に出版されベストセラーになり、映画化やテレビドラマ化もされました。
痴呆症の高齢者の介護をテーマにした同作品は社会的反響を呼び、当時の高齢者福祉行政に影響を与えたとされています。
作品内では舅を介護する長男の嫁が福祉事務所に相談するが、入所する施設もなく精神病院に入院するしかないと福祉事務所の職員から助言される様子も描かれいます。
介護施設が整備され要介護度が高ければ施設入所ができる現在との違いがわかる作品です。
痴呆症(認知症)の高齢者の詳細な様子がわかるため、授業で映画の視聴をする福祉系学校もあるようです。
『恍惚の人』は、昭和47(1972)年に出版されベストセラーになり、映画化やテレビドラマ化もされました。
痴呆症の高齢者の介護をテーマにした同作品は社会的反響を呼び、当時の高齢者福祉行政に影響を与えたとされています。
作品内では舅を介護する長男の嫁が福祉事務所に相談するが、入所する施設もなく精神病院に入院するしかないと福祉事務所の職員から助言される様子も描かれいます。
介護施設が整備され要介護度が高ければ施設入所ができる現在との違いがわかる作品です。
痴呆症(認知症)の高齢者の詳細な様子がわかるため、授業で映画の視聴をする福祉系学校もあるようです。
名称変更によって認知症への理解は深まったのか?
痴呆症から認知症へ名称変更した理由の一つに、痴呆症という名称が国民的な理解を得るための妨げになっていることがありました。
認知症への名称変更後は国民的な理解が得られるようになったのでしょうか。
ここでは、名称変更後の認知症をめぐる社会の変化について解説します。
認知症への名称変更後は国民的な理解が得られるようになったのでしょうか。
ここでは、名称変更後の認知症をめぐる社会の変化について解説します。
一般の方も認知症の高齢者を見守る時代に
国や自治体の取り組みによって、福祉関係者以外の一般の方も認知症についてかかわるようになりました。
認知症サポーター等養成事業は、平成17年からスタートした地域や職域における認知症理解と認知症支援者養成のため事業です。
主な事業内容は以下のとおりです。
参照:厚生労働省 認知症サポーター等養成事業の実施について
また、東京都練馬区は、高齢者の見守りを目的にした「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」を、民間事業者や団体と締結しています。
民間事業者や団体が地域の高齢者を見守り、必要に応じて地域包括支援センターや警察などと連携することが特徴です。
なお、同協定の見守りは認知症以外の高齢者も対象にしています。
参照:東京都練馬区 練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定
認知症サポーター等養成事業は、平成17年からスタートした地域や職域における認知症理解と認知症支援者養成のため事業です。
主な事業内容は以下のとおりです。
● 認知症サポーター養成事業:地域や職域で認知症の方と家族を支える認知症サポーターを養成する
● ステップアップ講座の実施:認知症サポーター養成事業の講座修了者に認知症の基礎知識と理解を深める ための講義等を実施する
● キャラバン・メイト養成研修事業:認知症サポーター養成講座を企画・立案するキャラバン・メイトを養成する
参照:厚生労働省 認知症サポーター等養成事業の実施について
また、東京都練馬区は、高齢者の見守りを目的にした「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」を、民間事業者や団体と締結しています。
民間事業者や団体が地域の高齢者を見守り、必要に応じて地域包括支援センターや警察などと連携することが特徴です。
なお、同協定の見守りは認知症以外の高齢者も対象にしています。
参照:東京都練馬区 練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定
認知症関連の資格が増えた
認知症への名称変更後は認知症関連の資格が増えました。
創設された認知症関連の資格は以下のとおりです。
民間資格
認知症への理解が深まり、認知症の方への正しい理解・介護をしようとする考えが広まった結果なのかもしれません。
創設された認知症関連の資格は以下のとおりです。
民間資格
● 認知症ケア専門士
● 認知症ライフケアパートナー
● 認知症介助士
● 認知症介護基礎研修
● 認知症介護実践者研修
● 認知症介護実践リーダー
認知症への理解が深まり、認知症の方への正しい理解・介護をしようとする考えが広まった結果なのかもしれません。
痴呆症と同じように名称変更した疾患がある
認知症と同様に名称変更した疾患・障害があります。名称が変更した疾患・障害の変更年と以前の名称は以下のとおりです。
上記の名称変更には以下のような理由がありました。
認知症が名称変更したのとほぼ同じような理由と言えます。
参照:厚生労働省 「痴呆」に替わる用語に関する検討会
● 知的障害:平成10年・精神薄弱
● 統合失調症:平成14年・精神分裂病
上記の名称変更には以下のような理由がありました。
● 実態を正確に表していない
● 人格を否定するニュアンスがある
● 偏見や差別などを助長させる
認知症が名称変更したのとほぼ同じような理由と言えます。
参照:厚生労働省 「痴呆」に替わる用語に関する検討会
痴呆症を理解すれば認知症の理解がさらに深まる!
痴呆症は認知症と同じ病気で認知症の以前の名称です。
痴呆症という名称の使用の継続には多くの問題があったため、厚生労働省の検討会で議論し認知症という新しい名称を提唱しました。
痴呆症と呼ばれていた時代は、痴呆症の理解不足や偏見だけではなく、高齢者の社会的入院といった問題もありました。
痴呆症から認知症への名称変更によって、一般の方や民間事業者などが地域の認知症の高齢者を見守る時代に替わりつつあります。
痴呆症という名称の使用の継続には多くの問題があったため、厚生労働省の検討会で議論し認知症という新しい名称を提唱しました。
痴呆症と呼ばれていた時代は、痴呆症の理解不足や偏見だけではなく、高齢者の社会的入院といった問題もありました。
痴呆症から認知症への名称変更によって、一般の方や民間事業者などが地域の認知症の高齢者を見守る時代に替わりつつあります。
※掲載情報は公開日あるいは2023年03月14日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.