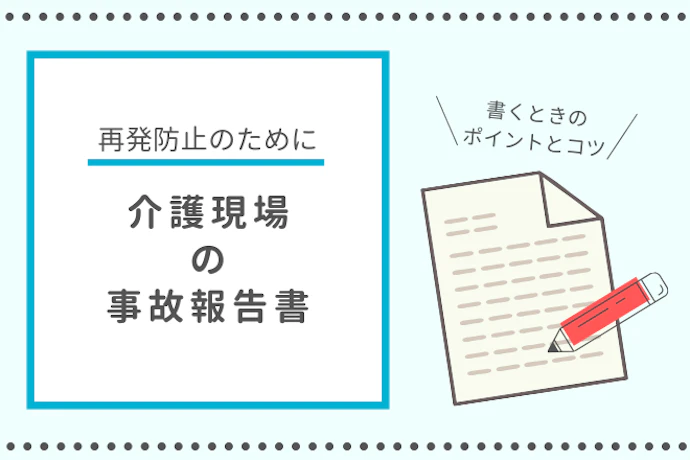介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
介護の事故報告書を書く目的、書き方のポイントを解説!
#介護
目次
ケガや転倒などの事故が発生した場合に書く「事故報告書」。
忙しいなかでこの報告書を書くことを負担に感じる介護職員さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし介護現場における「事故報告書」はとても重要な業務。
本コラムでは、介護の事故報告書に関する
■書く目的
■書く内容
■書き方のポイント
について解説しています。
忙しい介護職員さんの負担をできるだけ減らせるように、早く書き上げられるコツも交えてお伝えします。
忙しいなかでこの報告書を書くことを負担に感じる介護職員さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし介護現場における「事故報告書」はとても重要な業務。
本コラムでは、介護の事故報告書に関する
■書く目的
■書く内容
■書き方のポイント
について解説しています。
忙しい介護職員さんの負担をできるだけ減らせるように、早く書き上げられるコツも交えてお伝えします。
介護の事故報告書とは
介護の事故報告書とは、介護サービス提供時に起こった事故の詳細を報告するための書類です。
どの介護事業所においても、この事故報告書は書かなければなりません。(介護保険法に基づいて報告が必要な事故の基準が定められています。)
それぞれの事業所(あるいは市町村)で報告書のフォーマットや報告フローが定められているのでその方法に従って対応してください。
どの介護事業所においても、この事故報告書は書かなければなりません。(介護保険法に基づいて報告が必要な事故の基準が定められています。)
それぞれの事業所(あるいは市町村)で報告書のフォーマットや報告フローが定められているのでその方法に従って対応してください。
事故報告書を書く目的
事故報告書は行政への報告のためだけに書くものではありません。
書く目的は大きく3つあります。
1.
事故を起こしてしまった場合には、同様の事故の再発防止策を必ず考えなければいけません。
そのためには、事故の詳細を振り返ることができる「事故報告書」がとても重要になります。
報告書にまとめて保管しておくことで、一つの事例だけでなく、蓄積した過去のデータを合わせて問題点を分析し、業務を改善することができます。
事故報告書には単なる事故の報告のためではなく「振り返り改善していく」目的があることを理解しましょう。
2.
職場全体に事例を共有することで、介護サービスの質を向上させます。
また再発防止の観点からも職員全体への共有は不可欠です。
事故の当事者だけでなく職員全員が気を引き締めて業務を行うためでもあります。
一方的な発信ではなく、全体ミーティングなどで事例を共有し、皆で改善策を話し合うなどの時間を設けてもよいかもしれません。
3.
事故の経緯や原因を利用者のご家族へ報告し、理解していただくために記録を残します。
事故に合わせてしまった利用者のご家族の不安感を取り除くために正確な事実を説明できるようにしておかなければいけません。
またトラブルを回避するための情報開示という役割もあります。
事故報告書の作成は、万が一事故が原因で訴訟になった場合などに、事業所や職員を守るためのものでもあるのです。
書く目的は大きく3つあります。
1.
同じような事故を繰り返し起こさないため
事故を起こしてしまった場合には、同様の事故の再発防止策を必ず考えなければいけません。
そのためには、事故の詳細を振り返ることができる「事故報告書」がとても重要になります。
報告書にまとめて保管しておくことで、一つの事例だけでなく、蓄積した過去のデータを合わせて問題点を分析し、業務を改善することができます。
事故報告書には単なる事故の報告のためではなく「振り返り改善していく」目的があることを理解しましょう。
2.
事故の詳細を全体に共有し職員全員で把握するため
職場全体に事例を共有することで、介護サービスの質を向上させます。
また再発防止の観点からも職員全体への共有は不可欠です。
事故の当事者だけでなく職員全員が気を引き締めて業務を行うためでもあります。
一方的な発信ではなく、全体ミーティングなどで事例を共有し、皆で改善策を話し合うなどの時間を設けてもよいかもしれません。
3.
いつでも情報開示できるようにするため
事故の経緯や原因を利用者のご家族へ報告し、理解していただくために記録を残します。
事故に合わせてしまった利用者のご家族の不安感を取り除くために正確な事実を説明できるようにしておかなければいけません。
またトラブルを回避するための情報開示という役割もあります。
事故報告書の作成は、万が一事故が原因で訴訟になった場合などに、事業所や職員を守るためのものでもあるのです。
ヒヤリハットとは
ここでヒヤリハットについても少し触れておきましょう。
事業所によっては「事故報告書」だけでなく「ヒヤリハット報告書」を義務付けている場合があります。
この「ヒヤリハット報告書」、名前の通り「ヒヤリ!」「ハッ!」としたとき、事故にはならなかったものの事故につながる危険性があった場合に報告するというものです。
”経緯や原因を突き止め再発防止に努める”という点は事故報告書と同じです。
現状、事故かヒヤリハットかの区別に明確な基準は設けられておらず、その棲み分けは事業所によって異なります。どういった場合が「事故」になり「ヒヤリハット」になるのかという判断基準が不明瞭な場合には、必ず確認しておきましょう。
事業所によっては「事故報告書」だけでなく「ヒヤリハット報告書」を義務付けている場合があります。
この「ヒヤリハット報告書」、名前の通り「ヒヤリ!」「ハッ!」としたとき、事故にはならなかったものの事故につながる危険性があった場合に報告するというものです。
”経緯や原因を突き止め再発防止に努める”という点は事故報告書と同じです。
現状、事故かヒヤリハットかの区別に明確な基準は設けられておらず、その棲み分けは事業所によって異なります。どういった場合が「事故」になり「ヒヤリハット」になるのかという判断基準が不明瞭な場合には、必ず確認しておきましょう。
事故報告書に書く内容
報告書には、概ね下記のような内容を記載します。
・事故を起こした者(関係者)の名前
・利用者の情報
・事故の発生状況(発生日時・場所・事故の種別・受傷程度)
・事故発生の経緯・原因
・事故発生後の対応・状況
・再発防止対策案
特に重要なのが「
先述したとおり事故報告書の大きな目的は事故の再発防止であるからです。
まずは事故発生時の状況・経緯を客観的に捉えて整理し、原因究明を行います。
そこから、どうしたら事故の再発を防げるかを導き出すという流れで報告書を作成していきます。
事故発生の経緯と原因
」、それに対する「再発防止対策
案」の項目。先述したとおり事故報告書の大きな目的は事故の再発防止であるからです。
再発防止策を考える際は、「事故が起こった原因は何で、どこに問題があったのか」を見極めることが非常に重要
です。まずは事故発生時の状況・経緯を客観的に捉えて整理し、原因究明を行います。
そこから、どうしたら事故の再発を防げるかを導き出すという流れで報告書を作成していきます。
事故報告書作成のポイントと書くときのコツ
事故報告書の内容は、自分だけが理解できても意味がありません。
・正確な情報であること
・全容が把握できること
・誰が読んでも理解できること
・事故発生後すぐに書くこと
が重要なポイントとなります。
そのためにはどんなことを意識して書けばいいのでしょうか。
わかりやすい事故報告書を書くためのコツを紹介していきます。
・正確な情報であること
・全容が把握できること
・誰が読んでも理解できること
・事故発生後すぐに書くこと
が重要なポイントとなります。
そのためにはどんなことを意識して書けばいいのでしょうか。
わかりやすい事故報告書を書くためのコツを紹介していきます。
5W1Hで書く
事故の状況は、
When/いつ
Where/どこで
Who/誰が
What/何を
Why/なぜ
How/どのようにして
を使って説明するといいでしょう。
報告においての基本の型であり、漏れなく情報を伝えられる手段です。
どんな事故がなぜ起こってしまったのかがわかるように書きましょう。
「5W1H」
When/いつ
Where/どこで
Who/誰が
What/何を
Why/なぜ
How/どのようにして
を使って説明するといいでしょう。
報告においての基本の型であり、漏れなく情報を伝えられる手段です。
どんな事故がなぜ起こってしまったのかがわかるように書きましょう。
短文で簡潔に書く
見やすい報告書にするには、要点を整理して簡潔に書くことが欠かせません。
事故の全容を、読み手が苦労せずに理解できる文章になっているか意識してください。
必要な情報を盛り込みつつ、できるだけ短文で書くとよいでしょう。
事故の全容を、読み手が苦労せずに理解できる文章になっているか意識してください。
必要な情報を盛り込みつつ、できるだけ短文で書くとよいでしょう。
事実を客観的に書く
客観的な視点で書くことが大切です。
例えば「事故に対する言い訳」や「利用者さんへの不満」のような私情(主観)を挟む必要はありません。
また些細な内容でも気になる点があれば省略せず文章で残しておきましょう。
起こった事実を起こったとおりに記述し、誰が読んでも客観的に概要を把握できる書き方を心がけてください。
例えば「事故に対する言い訳」や「利用者さんへの不満」のような私情(主観)を挟む必要はありません。
また些細な内容でも気になる点があれば省略せず文章で残しておきましょう。
起こった事実を起こったとおりに記述し、誰が読んでも客観的に概要を把握できる書き方を心がけてください。
専門用語や難解な言葉は使わない
「誰が読んでも理解できる内容にする」というのは、職場内だけの話ではなく外部の人が見てもわかるようにということです。
事故報告書は場合によっては行政や利用者のご家族など第三者に開示する場合もあります。
職員だけに伝わる隠語や略語、専門用語などはなるべく使わずに書くことが望ましいでしょう。
事故報告書は場合によっては行政や利用者のご家族など第三者に開示する場合もあります。
職員だけに伝わる隠語や略語、専門用語などはなるべく使わずに書くことが望ましいでしょう。
早く書き上げるためのコツは?
報告書は事故発生後すぐに書かなければいけません。
時間が経つほど、事故発生時の詳細な記憶が薄れていってしまい正確な情報ではなくなってしまうためです。
再発防止の改善策についても早期検討し、全体に周知する必要があります。
最優先で取りかかるべき重要な業務といえるでしょう。
とはいえ、「通常業務で忙しくて、つい後回しにしてしまった・・・」ということがあるのではないでしょうか?
以下は、少しでも報告書作成の時間を短縮し、負担を減らすための提案です。
・
おそらく事業所ごとに決まった報告書のフォーマットがあるかと思います。
その報告書の項目ごとに、書くべき情報を整理していきましょう。
結論(最も重要なポイント)を示した後、詳細を肉付けしていくというやり方がおすすめです。
このひな型で書くと決めていれば毎回書き方に迷うことはありません。
お手本が欲しいという方は、他の人が書いた事故報告書に習って書くのもよいでしょう。時間短縮につながります。
・
記載内容に書き漏れがないか、チェックリストを作成して最終確認しましょう。
例えば、
時間が経つほど、事故発生時の詳細な記憶が薄れていってしまい正確な情報ではなくなってしまうためです。
再発防止の改善策についても早期検討し、全体に周知する必要があります。
最優先で取りかかるべき重要な業務といえるでしょう。
とはいえ、「通常業務で忙しくて、つい後回しにしてしまった・・・」ということがあるのではないでしょうか?
以下は、少しでも報告書作成の時間を短縮し、負担を減らすための提案です。
・
書く前に要点を整理する
おそらく事業所ごとに決まった報告書のフォーマットがあるかと思います。
その報告書の項目ごとに、書くべき情報を整理していきましょう。
結論(最も重要なポイント)を示した後、詳細を肉付けしていくというやり方がおすすめです。
このひな型で書くと決めていれば毎回書き方に迷うことはありません。
お手本が欲しいという方は、他の人が書いた事故報告書に習って書くのもよいでしょう。時間短縮につながります。
・
チェックリストを作っておく
記載内容に書き漏れがないか、チェックリストを作成して最終確認しましょう。
例えば、
5W1Hが全て明確に書かれているか?
客観的な事実のみで書かれているか?
誤字脱字、略語などの記述はないか
などです。
これを徹底することで、手戻り・修正の時間を減らせます。
事故報告書の作成は重要業務ではありますが、通常業務が疎かになっては本末転倒です。
わかりやすく簡潔に書くことと、時短・効率化も意識して作成しましょう。
これを徹底することで、手戻り・修正の時間を減らせます。
事故報告書の作成は重要業務ではありますが、通常業務が疎かになっては本末転倒です。
わかりやすく簡潔に書くことと、時短・効率化も意識して作成しましょう。
まとめ
■
1.同じような事故を繰り返し起こさないため
2.事故の詳細を全体に共有し職員全員で把握するため
3.いつでも情報開示できるようにするため
■
・正確な情報であること
・全容が把握できること
・誰が読んでも理解できること
・事故発生後すぐに書くこと
■
・5W1Hで書く
・事実を客観的に書く
・専門用語や難解な言葉は使わない
・書く前に要点を整理する
・チェックリストで書き漏れ防止
事故報告書は通常業務で忙しい中でも最優先で取り掛かるべき重要な業務。
作成する際は、ぜひ、上記のポイントを意識して作成してみてください。
事故報告書を書く目的
1.同じような事故を繰り返し起こさないため
2.事故の詳細を全体に共有し職員全員で把握するため
3.いつでも情報開示できるようにするため
■
書くときに意識するポイント
・正確な情報であること
・全容が把握できること
・誰が読んでも理解できること
・事故発生後すぐに書くこと
■
わかりやすい事故報告書を書くためのコツ
・5W1Hで書く
・事実を客観的に書く
・専門用語や難解な言葉は使わない
・書く前に要点を整理する
・チェックリストで書き漏れ防止
事故報告書は通常業務で忙しい中でも最優先で取り掛かるべき重要な業務。
作成する際は、ぜひ、上記のポイントを意識して作成してみてください。
転職のご相談は介護ワーカーへ
「介護職の転職を考えている」
「キャリアアップしたい」
とお考えの方は業界最大手の介護ワーカーにお任せください!
資格取得支援制度がある事業所、資格や能力による評価制度を設けている施設など、全国各地の施設からあなたの今の状況に応じた転職先をご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
<<介護ワーカーに相談する>>
「キャリアアップしたい」
とお考えの方は業界最大手の介護ワーカーにお任せください!
資格取得支援制度がある事業所、資格や能力による評価制度を設けている施設など、全国各地の施設からあなたの今の状況に応じた転職先をご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
<<介護ワーカーに相談する>>
※掲載情報は公開日あるいは2020年06月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.