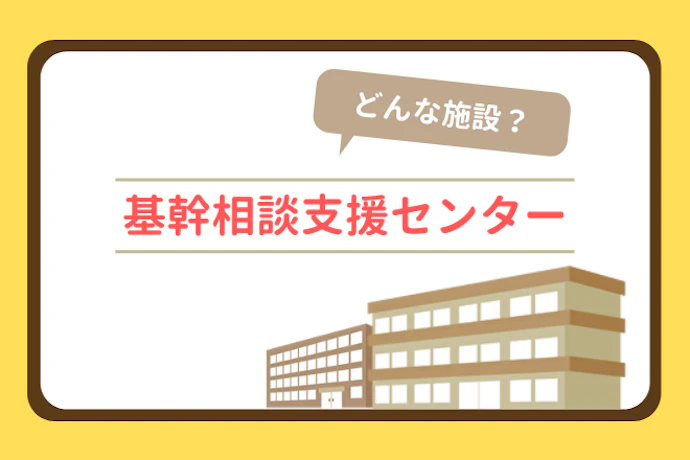介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.10
基幹相談支援センターとはどんな施設?役割や仕事内容をわかりやすく解説!
#介護
目次
「基幹相談支援センター」という施設をご存知でしょうか?
相談支援専門員や社会福祉士の方にはなじみがあるかもしれません。
本コラムでは、障がい者の方々の支援や介護に関わる方向けに、基幹相談支援センターのとはどんな施設なのか、その役割や業務内容について詳しく解説していきます。
相談支援専門員や社会福祉士の方にはなじみがあるかもしれません。
本コラムでは、障がい者の方々の支援や介護に関わる方向けに、基幹相談支援センターのとはどんな施設なのか、その役割や業務内容について詳しく解説していきます。
基幹相談支援センターってどんな施設?
基幹相談支援センターは障がい者支援を行う施設で、全国の市町村に設置されています。
障がいを持った方、またそのご家族のための総合相談窓口として、
障がいを持った方、またそのご家族のための総合相談窓口として、
社会にとけこみ自立した生活を送れるよう
に必要な援助や情報提供を行なっていきます。基幹相談支援センターの役割
地域における障がい者相談支援施設や団体の中核的な役割を担う機関として設置されているのが基幹相談支援センターです。
障害・福祉ニーズは年々多様化・増大化しており、国は様々な困りごとに対応するための自立支援・相談支援の強化に取り組んできました。
その取り組みの1つとして基幹相談支援センターの設立があります。
総合的な相談支援を行う拠点として、平成24年に設立されました。
相談支援事業所や地域包括支援センター、さらには地域の病院や学校などの
障害・福祉ニーズは年々多様化・増大化しており、国は様々な困りごとに対応するための自立支援・相談支援の強化に取り組んできました。
その取り組みの1つとして基幹相談支援センターの設立があります。
総合的な相談支援を行う拠点として、平成24年に設立されました。
相談支援事業所や地域包括支援センター、さらには地域の病院や学校などの
各施設と連携をとりながら、その地域に住む障がい者の方々のサポート
を行なっていきます。基幹相談支援センターはどこにあるの?
基幹相談支援センターは、平成29年度時点で全国の市町村426ヵ所に設置されています。
参照:基幹相談支援センター設置促進のための手引き
運営は市町村、あるいは市町村が委託する社会福祉法人や社会福祉協議会などが行っています。
多くのセンターは他の施設との併設事業となっており、役所や相談支援事業所、居住サポート事業所、虐待防止センターなどと併設されています。
なお、基幹相談支援センターの設置は義務ではなく市町村の任意のため、
センターが障がい者やそのご家族に必要とされているのは確かですが、設置されていない理由としては
・人財の確保が難しい
・予算がとれない
・委託先がない
といった背景があるようです。
参照:基幹相談支援センター設置促進のための手引き
運営は市町村、あるいは市町村が委託する社会福祉法人や社会福祉協議会などが行っています。
多くのセンターは他の施設との併設事業となっており、役所や相談支援事業所、居住サポート事業所、虐待防止センターなどと併設されています。
なお、基幹相談支援センターの設置は義務ではなく市町村の任意のため、
設置している自治体はまだまだ少なく全市区町村の約3割程度
という状況です。センターが障がい者やそのご家族に必要とされているのは確かですが、設置されていない理由としては
・人財の確保が難しい
・予算がとれない
・委託先がない
といった背景があるようです。
基幹相談支援センターの主な仕事内容
では基幹相談支援センターの仕事内容についてご説明していきます。
厚生労働省の資料による基幹相談支援センターの業務イメージは下記の通りです。
厚生労働省の資料による基幹相談支援センターの業務イメージは下記の通りです。
<基幹相談支援センターの主業務>
○ 自ら、障害者等の相談、情報提供、助言
○ 地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援
出典:厚生労働省「障害者自立支援法改正案資料」
とあるように、「相談支援の実施」や「支援体制の強化」が主な業務となります。
さらに細かく見ていきましょう。
さらに細かく見ていきましょう。
◆
障がい者の生活全般における相談支援をします。
さらに、さまざまなニーズに応じて専門的な相談支援を実施します。
◆
地域の相談機関との連携や、相談事業者への専門的な指導助言、人材育成を行います。
◆
施設や病院と連携し、障がい者の生活準備を行います。
夜間の連絡や緊急時の対応が必要な場合にも支援をします。
◆
虐待や権利擁護に関する相談窓口としても機能しています。
家庭や施設で虐待を受けている障がい者の相談支援、ご本人の代わりに各種契約などのサポートを行います。
他にも、施設によっては、
・協議会の運営
・当事者のグループ活動などの支援
・研修会の企画運営
というようなことに取り組んでいるところもあります。
業務内容のひとつに「地域の相談機関の連携強化」がありますが、主に連携が必要となるのは下記の機関です。
総合的・専門的な相談の実施
障がい者の生活全般における相談支援をします。
さらに、さまざまなニーズに応じて専門的な相談支援を実施します。
◆
地域の相談支援体制強化の取組み
地域の相談機関との連携や、相談事業者への専門的な指導助言、人材育成を行います。
◆
地域移行・地域定着の促進の取組み
施設や病院と連携し、障がい者の生活準備を行います。
夜間の連絡や緊急時の対応が必要な場合にも支援をします。
◆
権利擁護・虐待の防止
虐待や権利擁護に関する相談窓口としても機能しています。
家庭や施設で虐待を受けている障がい者の相談支援、ご本人の代わりに各種契約などのサポートを行います。
他にも、施設によっては、
・協議会の運営
・当事者のグループ活動などの支援
・研修会の企画運営
というようなことに取り組んでいるところもあります。
業務内容のひとつに「地域の相談機関の連携強化」がありますが、主に連携が必要となるのは下記の機関です。
<主な業務連携機関>
・障害福祉担当の行政窓口
・障害福祉サービス事業所
・相談支援事業所
・地域包括支援センター
・学校・幼稚園・保育所など
・病院・施設
・生活困窮者自立相談支援機関など
生活に必要なサービスの紹介や生活コーディネートを、病院や施設などの関係各所と連携しながら支援していきます。
当事者にとって相談窓口が基幹相談支援センターのみに簡素化されていることは大きなメリットです。
そのため、
密に情報共有や調整をするための中心的役割を担うことは基幹相談支援センターの重要な務め
となります。また、
相談支援事業者への専門的な指導・助言といった人材育成の役割も期待
されています。基幹相談支援センターで働くには?
基幹相談支援センターの求人はあまり多くはありません。
まず1ヵ所あたりの就業人数が少ないためです。
公益社団法人日本社会福祉士会による「基幹相談支援センター設置促進のための手引き」によれば、
2人が専任の常勤職員、2人が他業務と兼務、プラス非常勤職員が1人というイメージです。
さらに人材不足の場合にも
転職を希望している方は知識・経験を積みながら、常時求人をチェックしておきましょう。
まず1ヵ所あたりの就業人数が少ないためです。
公益社団法人日本社会福祉士会による「基幹相談支援センター設置促進のための手引き」によれば、
センター1カ所あたりの平均職員数は4 .6人
。2人が専任の常勤職員、2人が他業務と兼務、プラス非常勤職員が1人というイメージです。
さらに人材不足の場合にも
新規採用の予算がなかなか取れない
という面があります。職員になるにはそれ相応の経験や知識も必要とされる
ため、基幹相談支援センターへの転職は狭き門といえるでしょう。転職を希望している方は知識・経験を積みながら、常時求人をチェックしておきましょう。
働くための資格要件は?
必須とされている資格はありませんが、以下の資格所有者(経験者)の配置が推奨されています。
主任相談支援専門員
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師
相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師に加えて、平成30年度から新たに創設された主任相談支援専門員が位置づけられました。
その背景としては、人材の養成の急務が挙げられます。
これまでは比較的経験の浅い方も配置されており、十分な相談支援ができていないという実態がありました。
そのため
業界経験が浅い場合、転職のハードルは高くなる可能性があります。
基幹相談支援センターで働きたいとお考えの方は、転職を見据えながら、まずは上記の職種での業務経験を積んでいくことをおすすめします。
その背景としては、人材の養成の急務が挙げられます。
これまでは比較的経験の浅い方も配置されており、十分な相談支援ができていないという実態がありました。
主任相談支援専門員を配置し地域でしっかりと人材を養成することで、センターの機能充実を図る
ねらいがあります。そのため
今後はより一層障がい者の相談支援に関する豊富な経験、知識、技術を持っている人材が求められる
でしょう。業界経験が浅い場合、転職のハードルは高くなる可能性があります。
基幹相談支援センターで働きたいとお考えの方は、転職を見据えながら、まずは上記の職種での業務経験を積んでいくことをおすすめします。
まとめ
障がい者の方々のお困りごとやニーズは一括りにはできず多種多様です。
基幹相談支援センターでは様々な相談に対応できる専門家の配置が望まれており、主任相談支援専門員の需要も高まっています。
新たなフィールドで障がい者の方の支援を行なっていきたいとお考えの、相談支援専門員や社会福祉士の皆さんは、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?
基幹相談支援センターでは様々な相談に対応できる専門家の配置が望まれており、主任相談支援専門員の需要も高まっています。
新たなフィールドで障がい者の方の支援を行なっていきたいとお考えの、相談支援専門員や社会福祉士の皆さんは、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?
介護福祉業界の転職は介護ワーカーにお任せください!
スキルアップできる環境で働きたい!
もう少し給料をあげたい!
キャリアを生かした転職をお考えのあなたは、ぜひ業界最大手の介護ワーカーにご相談ください。
一般の求人には掲載されない非公開求人のご紹介も可能です。
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたの転職を手厚くサポートいたします!
★介護ワーカーへ相談する
もう少し給料をあげたい!
キャリアを生かした転職をお考えのあなたは、ぜひ業界最大手の介護ワーカーにご相談ください。
一般の求人には掲載されない非公開求人のご紹介も可能です。
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたの転職を手厚くサポートいたします!
★介護ワーカーへ相談する
※掲載情報は公開日あるいは2020年07月27日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.