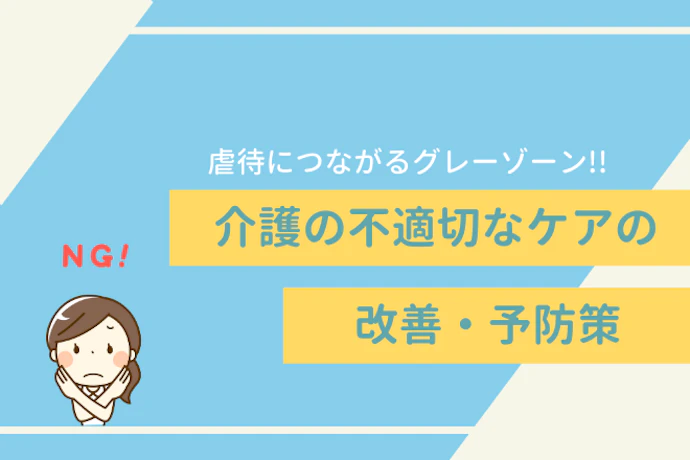介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.10
介護現場で起こる不適切なケアの改善・予防について
#介護
目次
今回は介護現場での「不適切なケア」について書いていきたいと思います。リーダーや教育担当の方に特に知っていただきたい内容となっています。
人手が足りない介護現場では、1人の職員が何人もの利用者の介護を担当しなければなりません。忙しくて素っ気ない対応をしてしまったり、利用者の要望すべてに答えられない場面も多々あるのではないでしょうか。
職員のこのような対応は、意図せずとも時に「不適切なケア」になってしまう場合があります。
本コラムでは、具体的な事例をまじえながら、不適切ケアが起こる背景と改善方法、予防策について考えていきたいと思います。
人手が足りない介護現場では、1人の職員が何人もの利用者の介護を担当しなければなりません。忙しくて素っ気ない対応をしてしまったり、利用者の要望すべてに答えられない場面も多々あるのではないでしょうか。
職員のこのような対応は、意図せずとも時に「不適切なケア」になってしまう場合があります。
本コラムでは、具体的な事例をまじえながら、不適切ケアが起こる背景と改善方法、予防策について考えていきたいと思います。
介護現場における不適切なケアとは?
介護現場における不適切なケアとはいったいどういったケアを指すのでしょうか?
利用者の被害が明らかなものは「虐待」と認識されます。
例えば暴行を加える身体的虐待、暴言や精神的苦痛を与える対応をする心理的虐待、介護や世話の放棄などがあります。
<虐待の種類>
利用者の被害が明らかなものは「虐待」と認識されます。
例えば暴行を加える身体的虐待、暴言や精神的苦痛を与える対応をする心理的虐待、介護や世話の放棄などがあります。
<虐待の種類>
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任 |
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
上記のような
明らかな虐待ではないけれど決して正しい方法でもない、「倫理的に問題のある行為」のことを不適切なケア
と呼んでいます。不適切なケアから虐待までの境界線は曖昧です。
顕在化した虐待の周辺には、表面化していない意図的虐待や、介護者にそのつもりがなくとも結果的に虐待を行ってしまっている非意図的虐待があります。さらにはグレーゾーンと呼ばれる、虐待と判断するかどうか迷うような行為も存在しています。
図のように
不適切なケアは、決して虐待ではないから許される範囲というわけではありません。
これらの行為が放置されることによって虐待にエスカレートしてしまう可能性もあるのです。
不適切なケアは「虐待の芽」ととらえ、該当する行為がある場合にはその時点で改善し対策をとるべきと考えましょう。
顕在化した虐待の周辺には、表面化していない意図的虐待や、介護者にそのつもりがなくとも結果的に虐待を行ってしまっている非意図的虐待があります。さらにはグレーゾーンと呼ばれる、虐待と判断するかどうか迷うような行為も存在しています。
図のように
虐待と不適切なケアには明確な境界線がなく、不適切なケアを底辺として連続しているもの
と捉えることができます。不適切なケアは、決して虐待ではないから許される範囲というわけではありません。
これらの行為が放置されることによって虐待にエスカレートしてしまう可能性もあるのです。
不適切なケアは「虐待の芽」ととらえ、該当する行為がある場合にはその時点で改善し対策をとるべきと考えましょう。
◆不適切なケアの事例
不適切なケアは、その判断基準が難しい部分があります。
同じ行為であっても利用者によってとらえ方が違ったり、状況に応じてやむをえないようなケースもあったりするからです。
例えば、次のような言動は「不適切なケア」に該当すると考えられます。
同じ行為であっても利用者によってとらえ方が違ったり、状況に応じてやむをえないようなケースもあったりするからです。
例えば、次のような言動は「不適切なケア」に該当すると考えられます。
・ご自身で着脱ができる利用者にもかかわらず、時間がかかりすぎるという理由で全介助を行う
・利用者の呼びかけや要望に対して、「ちょっと待って」と長い時間放置する
・「〇〇したらダメ!」などと命令口調で行動を抑制する
・ケアコール(ナースコール)にすぐ対応しない
・なかなか食事を食べようとしない利用者に無理やり食事介助をする
・トイレに行きたいと頻繁に言う利用者に「さっきも行ったよね」と言って対応を後回しにする
人手不足の状況下でのやむを得ない対応であったり、事故防止のためについ強い口調になってしまったという場合もあるかもしれません。
しかしそれは利用者の尊厳を無視した「不適切なケア」となってしまっている可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。
しかしそれは利用者の尊厳を無視した「不適切なケア」となってしまっている可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。
不適切なケアが行われてしまう背景
介護現場で高齢者虐待や不適切なケアが発生する背景には、さまざまな要因があると考えられています。
特に大きな要因として、介護現場の労働環境の悪さや業務負担の大きさ、それにともなう職員のストレスがあります。
特に大きな要因として、介護現場の労働環境の悪さや業務負担の大きさ、それにともなう職員のストレスがあります。
虐待・不適切なケアが起こる要因
◆
・介護理念や組織全体の方針がない、理念を共有するための具体策がない
・責任や役割が不明確、必要な組織がない、又は形骸化している
・情報公開に消極的、家族と連携する姿勢がない
◆
・リーダーの役割が不明確、又は介護単位があいまい又は広すぎる
・情報共有の仕組みや意思決定の仕組みがない
・異なる職種間の連携がない、又は年齢や採用条件による壁がある
◆
・認知症の知識がなく、行動・心理症状(BPSD)への対応がその場しのぎ
・アセスメントやケアプランが実際のケアと連動していない
・ケアに関して学習する機会がなくアセスメントとその活用方法の知識がない
◆
・安易な身体拘束や一斉介護・流れ作業など“非”利用者本位
・職業倫理の薄れ、介護理念が共有されていない
・高齢者虐待防止法、その他必要な法令を知らない
◆
・人手不足や業務の多忙さ、夜勤時の負担が大きい
・負担の多さからくるストレスや職場内の人間関係に問題がある
・見て見ぬふり、安易な身体拘束の容認、連絡の不徹底がある
出典:「高齢者虐待を考える 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止の事例集」認知症介護情報ネットワーク
不適切ケアを予防するには、職員一人ひとりの意識改善が大切です。
しかしそれ以上に、
組織運営
・介護理念や組織全体の方針がない、理念を共有するための具体策がない
・責任や役割が不明確、必要な組織がない、又は形骸化している
・情報公開に消極的、家族と連携する姿勢がない
◆
チームアプローチ
・リーダーの役割が不明確、又は介護単位があいまい又は広すぎる
・情報共有の仕組みや意思決定の仕組みがない
・異なる職種間の連携がない、又は年齢や採用条件による壁がある
◆
ケアの質
・認知症の知識がなく、行動・心理症状(BPSD)への対応がその場しのぎ
・アセスメントやケアプランが実際のケアと連動していない
・ケアに関して学習する機会がなくアセスメントとその活用方法の知識がない
◆
倫理観
・安易な身体拘束や一斉介護・流れ作業など“非”利用者本位
・職業倫理の薄れ、介護理念が共有されていない
・高齢者虐待防止法、その他必要な法令を知らない
◆
ストレス
・人手不足や業務の多忙さ、夜勤時の負担が大きい
・負担の多さからくるストレスや職場内の人間関係に問題がある
・見て見ぬふり、安易な身体拘束の容認、連絡の不徹底がある
出典:「高齢者虐待を考える 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止の事例集」認知症介護情報ネットワーク
不適切ケアを予防するには、職員一人ひとりの意識改善が大切です。
しかしそれ以上に、
不適切ケアの要因となる環境や仕組みそのものの改善に取り組むこ
とが重要なのではないでしょうか。不適切ケアの改善・予防するための4つのポイント
高齢者虐待の防止には、その背景要因を理解し、解消することが何よりも重要です。
不適切なケアが起こった時に、その都度対処したり、職員に「してはいけない」という指導を行うだけでは根本的な解決につながらないでしょう。
では具体的にどのようなリスクマネジメント行えばよいのでしょうか。
次の4つのポイントについてお伝えしていきます。
1.体制・環境の改善
2.業務の量見直し
3.職員のメンタルヘルス対策
4.職員への教育の強化
不適切なケアが起こった時に、その都度対処したり、職員に「してはいけない」という指導を行うだけでは根本的な解決につながらないでしょう。
「そもそもの根源を予測し対処することで不適切なケアの発生を回避する」というリスクマネジメントを行うことが改善・予防につながる
と考えられています。では具体的にどのようなリスクマネジメント行えばよいのでしょうか。
次の4つのポイントについてお伝えしていきます。
1.体制・環境の改善
2.業務の量見直し
3.職員のメンタルヘルス対策
4.職員への教育の強化
ポイント1|体制・環境の改善
不適切なケアの発生は事業所全体の問題と考え、まずは組織の体制や運営面の改善が必要となるでしょう。
まずは事業所が掲げる理念や運営方針を明確に言語化し、それを職員全体で共有することが大切です。
また理念や方針を実現していくために、実際とるべき行動や提供する介護サービスについて具体的な内容にまで落とし込み、指針を示すことが重要です。
さらに職種による責任や役割を明確にすることも必要となります。
責任の所在や指示系統を明確にし、組織図を作成し開示してもよいでしょう。
そして、第三者の目を入れ、開かれた組織にすることで虐待や不適切なケアの横行を防ぎます。
利用者やそのご家族への情報共有もすぐに行える管理体制を整備しましょう。
まずは事業所が掲げる理念や運営方針を明確に言語化し、それを職員全体で共有することが大切です。
また理念や方針を実現していくために、実際とるべき行動や提供する介護サービスについて具体的な内容にまで落とし込み、指針を示すことが重要です。
さらに職種による責任や役割を明確にすることも必要となります。
責任の所在や指示系統を明確にし、組織図を作成し開示してもよいでしょう。
そして、第三者の目を入れ、開かれた組織にすることで虐待や不適切なケアの横行を防ぎます。
利用者やそのご家族への情報共有もすぐに行える管理体制を整備しましょう。
\POINT/
・介護の理念や組織運営の方針を職員に共有する
・実現のための具体的な指針を示す
・責任の所在、指示系統を明確化する
・第三者の目を入れる
ポイント2|業務量の見直し
人手不足の介護業界では、職員一人当たりの業務負荷が大きいため、職員の都合を優先したことから不適切なケアが発生してしまうというケースも少なくありません。
職員のマインドセットを行う前に、しっかりと現場の声を聞き、まずは業務量の見直しを行うべきでしょう。
まずは一人当たりの負荷を軽減できるよう、柔軟な人員配置を検討しましょう。
職員一人で複数人の利用者を同時に見るため、どうしても「利用者の要求を放置してしまう」「慌てて強い口調になってしまう」「動作が雑になってしまう」といった事態が起こります。
これらは職員の問題以前に、そもそもの仕組みに問題があるために起こってしまうと考えられます。
負荷がかかっている役割や業務内容について見直し、改善を図りましょう。増員や効率化できる機会の導入など、無理なく対応できる方法がないか検討します。
ギリギリの人数で回している夜勤に関しては特に配慮を行う必要があるでしょう。
職員のマインドセットを行う前に、しっかりと現場の声を聞き、まずは業務量の見直しを行うべきでしょう。
まずは一人当たりの負荷を軽減できるよう、柔軟な人員配置を検討しましょう。
職員一人で複数人の利用者を同時に見るため、どうしても「利用者の要求を放置してしまう」「慌てて強い口調になってしまう」「動作が雑になってしまう」といった事態が起こります。
これらは職員の問題以前に、そもそもの仕組みに問題があるために起こってしまうと考えられます。
負荷がかかっている役割や業務内容について見直し、改善を図りましょう。増員や効率化できる機会の導入など、無理なく対応できる方法がないか検討します。
ギリギリの人数で回している夜勤に関しては特に配慮を行う必要があるでしょう。
\POINT/
・職員都合による不適切なケアを防ぐための体制づくり
・人員配置や業務量など、負荷がかかっている部分の見直し・改善
ポイント3|職員のメンタルヘルス対策
業務量の負荷、責任の大きさ、人間関係の問題などから、職員は大きなストレスを抱えている可能性があります。
管理者やリーダーの立場にある人は常にスタッフの様子や仕事ぶりを気にかけ関心を持つよう心がけてください。
悩みやストレスを一人で抱え込んでいるスタッフがいないように、日頃のコミュニケーションはもちろん、定期的な面談やミーティングをするなどして、職員の心の状態を把握できる環境を作りましょう。
そして職員間でそれぞれの立場を思いやり、気にかけ、助け合う職場の風土を築いていくことが大切です。
管理者やリーダーの立場にある人は常にスタッフの様子や仕事ぶりを気にかけ関心を持つよう心がけてください。
悩みやストレスを一人で抱え込んでいるスタッフがいないように、日頃のコミュニケーションはもちろん、定期的な面談やミーティングをするなどして、職員の心の状態を把握できる環境を作りましょう。
そして職員間でそれぞれの立場を思いやり、気にかけ、助け合う職場の風土を築いていくことが大切です。
\POINT/
・職員の業務量やストレスを把握
・上司からの積極的なコミュニケーション
・思いやり、助け合う職場の風土作り
ポイント4|職員への教育の強化
不適切なケアや虐待は、それらに関する基本的な知識や技術が不足していることによって発生する可能性も考えられます。
したがって職員全員が適切な介護サービスを提供できるように、倫理観とコンプライアンスを高める教育を強化していく必要があります。
利用者の尊厳を守る「利用者ファースト」の介護を実施することを基本として、実際にいま提供しているケアの内容や方法がそれに基づいたものであるかをチェックしていきましょう。
そして介護の専門知識や技術が不足している職員には教育の場を設けることが必要となります。
一般的な倫理観や法律に関する教育を行うとともに、実践で活かすための具体的なケアの方法についても指導し、介護サービスの質の向上を図ります。
適切なケアを行うためには利用者の心身状態をアセスメント(診断・見立て)するスキルや、さらにそのアセスメントに基づいて、個別の状況に即したケアを検討するスキルが欠かせません。
効率重視・流れ作業のサービスを見直し、個別ケアを重視することも必要でしょう。
したがって職員全員が適切な介護サービスを提供できるように、倫理観とコンプライアンスを高める教育を強化していく必要があります。
利用者の尊厳を守る「利用者ファースト」の介護を実施することを基本として、実際にいま提供しているケアの内容や方法がそれに基づいたものであるかをチェックしていきましょう。
そして介護の専門知識や技術が不足している職員には教育の場を設けることが必要となります。
一般的な倫理観や法律に関する教育を行うとともに、実践で活かすための具体的なケアの方法についても指導し、介護サービスの質の向上を図ります。
適切なケアを行うためには利用者の心身状態をアセスメント(診断・見立て)するスキルや、さらにそのアセスメントに基づいて、個別の状況に即したケアを検討するスキルが欠かせません。
効率重視・流れ作業のサービスを見直し、個別ケアを重視することも必要でしょう。
\POINT/
・倫理観、法律に関する知識の教育を強化
・利用者の尊厳を守るケアが提供できているかを確認
・介護サービスの質の見直し
・ケアの具体的な方法を指導(アセスメント力など)
不適切なケアのチェックリスト
職員への教育・指導時には「不適切なケアのチェックリスト」をぜひ活用しましょう。
具体的にどのような行為が不適切になるのかを職員全員が理解し、チェックできる体制を作ることをおすすめします。
東京都福祉保健財団による「虐待の目 チェックリスト」というものがありますので、参考にしてみてください。
このチェックリストは不適切なケアに対する職員一人ひとりの意識を高めることにも有効ですが、どこに課題があるのかを分析し改善していくべきかを知るための材料にもなります。
チェックして「気をつけましょう」で終わりではなく、ぜひ業務改善に活用していただければと思います。
具体的にどのような行為が不適切になるのかを職員全員が理解し、チェックできる体制を作ることをおすすめします。
東京都福祉保健財団による「虐待の目 チェックリスト」というものがありますので、参考にしてみてください。
このチェックリストは不適切なケアに対する職員一人ひとりの意識を高めることにも有効ですが、どこに課題があるのかを分析し改善していくべきかを知るための材料にもなります。
チェックして「気をつけましょう」で終わりではなく、ぜひ業務改善に活用していただければと思います。
もしも不適切なケアが起きたらどうするか
もしもあなたの職場で高齢者への不適切なケアが行われていた場合には、上司や管理者へ報告し、速やかな対応が求められます。
まずは利用者の心身の状態を把握し、利用者の安全を確保することが第一優先になります。
正確な事実確認を行った上で、利用者への説明と謝罪、必要に応じてご家族へのご説明も行います。
そして管理者の立場にある人は不適切ケアを行ってしまった職員への指導をします。
また管理者の責任についても検討すべきでしょう。
職員にも事例を共有し、同じようなことを繰り返さないように徹底していかなければなりません。
そのためにも、先述した不適切なケアの改善・予防の体制を整えていくことが必要です。
まずは利用者の心身の状態を把握し、利用者の安全を確保することが第一優先になります。
正確な事実確認を行った上で、利用者への説明と謝罪、必要に応じてご家族へのご説明も行います。
そして管理者の立場にある人は不適切ケアを行ってしまった職員への指導をします。
また管理者の責任についても検討すべきでしょう。
職員にも事例を共有し、同じようなことを繰り返さないように徹底していかなければなりません。
そのためにも、先述した不適切なケアの改善・予防の体制を整えていくことが必要です。
まとめ
忙しい中でついやってしまった行為や言ってしまった一言が、利用者の方を傷つける「不適切なケア」となってしまう場合があります。
不適切なケアに見て見ぬふりをすることで虐待にエスカレートする可能性もあります。
職員一人ひとりの意識改革も大切ですが、組織の問題として事業所全体で不適切なケアをなくすためのリスクマネジメントを行なっていくことが重要ではないでしょうか。
また、よりよいケアを提供するためには職員同士、立場を超えて協力しあうことが必要不可欠ではないかと考えます。
ぜひ、職場全体で不適切なケアの改善・予防策に取り組んでみてください。
不適切なケアに見て見ぬふりをすることで虐待にエスカレートする可能性もあります。
職員一人ひとりの意識改革も大切ですが、組織の問題として事業所全体で不適切なケアをなくすためのリスクマネジメントを行なっていくことが重要ではないでしょうか。
また、よりよいケアを提供するためには職員同士、立場を超えて協力しあうことが必要不可欠ではないかと考えます。
ぜひ、職場全体で不適切なケアの改善・予防策に取り組んでみてください。
介護のお仕事探しなら介護ワーカーへ!!
転職をお考えの場合はぜひ業界最大手の介護ワーカーをご利用ください!
あなたのご希望に合わせて、経験豊富な専任のアドバイザーが転職を手厚くサポートいたします!
まずは、お気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談する(無料)
★まずは求人を見てみる
あなたのご希望に合わせて、経験豊富な専任のアドバイザーが転職を手厚くサポートいたします!
まずは、お気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談する(無料)
★まずは求人を見てみる
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.