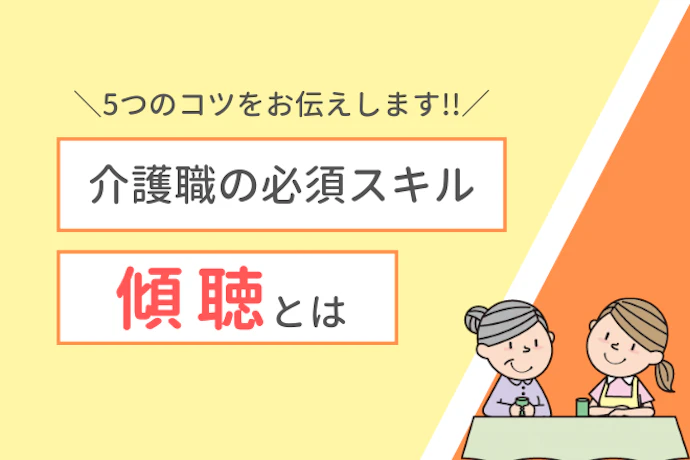介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
介護職員の必須スキル「傾聴」上手に話を聴く5つのコツ
#介護
目次
介護職員が利用者さんとコミュニケーションする際に必要不可欠な傾聴スキル。
「介護の仕事は傾聴が大事」という話はよく耳にしますが、ただ話を聞けばいいということではありません。
本コラムでは傾聴とは一体どういった話の聴き方なのかを解説。
そしてどうすれば利用者さんが心を開いて話してくれるのか、具体的な傾聴のコツをお伝えしていきます。
「介護の仕事は傾聴が大事」という話はよく耳にしますが、ただ話を聞けばいいということではありません。
本コラムでは傾聴とは一体どういった話の聴き方なのかを解説。
そしてどうすれば利用者さんが心を開いて話してくれるのか、具体的な傾聴のコツをお伝えしていきます。
介護職に求められる「傾聴」とは?
「傾聴」とは字の通り、相手の話に耳を傾けじっくりと聴くこと。
今や社会人が持っておくべきビジネススキルのひとつですが、介護職にもこの「傾聴する力」は必要不可欠といえるでしょう。
傾聴では「聴く」という漢字を使っていますが、いわゆる”きく”には3つの違いがあります。
今や社会人が持っておくべきビジネススキルのひとつですが、介護職にもこの「傾聴する力」は必要不可欠といえるでしょう。
傾聴では「聴く」という漢字を使っていますが、いわゆる”きく”には3つの違いがあります。
聞く
聞こえる、音が耳に入ってくる、聞いて何かを知る
訊く
何かを尋ねる、質問する、問いただす
聴く
熱心に聴く、積極的に耳を傾けて聴く
傾聴では、「聞く」でも「訊く」でもなく「聴く」、相手の話を積極的に熱心に聴くことが大切になります。
「相手の話を受け止め、共感し、受容する」それが傾聴です。
単に話を聞き理解するのではなく、話し手の気持ちに寄り添い、尊重することがとても大切ということです。
では、傾聴の基本のステップをお伝えしましょう。
「相手の話を受け止め、共感し、受容する」それが傾聴です。
単に話を聞き理解するのではなく、話し手の気持ちに寄り添い、尊重することがとても大切ということです。
では、傾聴の基本のステップをお伝えしましょう。
ステップ1:まずは相手を受け入れる(受容)
受容とは、話し手自身あるいは話し手の言葉や気持ちを、ありのまま受け止めることです。
批判や否定をすることなく、まずは相手をそのまま受け止めることが傾聴の基本としてとても重要です。
批判や否定をすることなく、まずは相手をそのまま受け止めることが傾聴の基本としてとても重要です。
ステップ2:真摯に話を聴く
話に集中しましょう。
話に関心を持つことは大前提ですが、加えて相手が安心して本音を話せているかどうかを確認しながら、声のトーンや表情にも気を配る必要があります。
決して話を急かしたりせず、リラックスできる環境でじっくり話を聴くことが大切です。
話に関心を持つことは大前提ですが、加えて相手が安心して本音を話せているかどうかを確認しながら、声のトーンや表情にも気を配る必要があります。
決して話を急かしたりせず、リラックスできる環境でじっくり話を聴くことが大切です。
ステップ3:相手の立場に立って理解する
話を聴いたら、話し手の立場になって共感することに努めます。
後ほど詳しくご説明しますが、話を聴きながら「相槌」や「うなずき」を入れたり、話に同調することで、話し手は「自分を理解してくれている」「しっかり聴いてくれている」と感じることができるでしょう。
後ほど詳しくご説明しますが、話を聴きながら「相槌」や「うなずき」を入れたり、話に同調することで、話し手は「自分を理解してくれている」「しっかり聴いてくれている」と感じることができるでしょう。
なぜ介護では傾聴が大切といわれるのか
介護のコミュニケーションにおいて、なぜ傾聴力が大切なのでしょうか。
その理由は、利用者との信頼関係を築くためです。
誰しもが「自分の話を聞いてもらいたい」「理解してもらいたい」「認めてもらいたい」という承認欲求を少なからず持っています。
自分の話を途中で遮って話したり、否定したりするような人と話したいと思う人はあまりいないでしょう。
利用者の方々も同じです。
話をじっくり聞いて受け入れてくれる職員と、反応が薄かったり話を否定するような職員だったら、どちらを信頼し、どちらに介護してもらいたいと思うでしょうか?
介護をするうえでは利用者に信頼され、心を開いてもらうことが第一歩となります。安心して介護を任せてもらうためには、傾聴の力を身につけ利用者とうまくコミュニケーションを取れるようになることがとても大切です。
それは
傾聴は利用者の本音を引き出し、よりよい介護を提供できるようになるための必須スキルなのです。
その理由は、利用者との信頼関係を築くためです。
誰しもが「自分の話を聞いてもらいたい」「理解してもらいたい」「認めてもらいたい」という承認欲求を少なからず持っています。
自分の話を途中で遮って話したり、否定したりするような人と話したいと思う人はあまりいないでしょう。
利用者の方々も同じです。
話をじっくり聞いて受け入れてくれる職員と、反応が薄かったり話を否定するような職員だったら、どちらを信頼し、どちらに介護してもらいたいと思うでしょうか?
介護をするうえでは利用者に信頼され、心を開いてもらうことが第一歩となります。安心して介護を任せてもらうためには、傾聴の力を身につけ利用者とうまくコミュニケーションを取れるようになることがとても大切です。
それは
利用者の尊厳を守り、心身ともに快適に過ごしてもらうためでもありますが、介護者が仕事をスムーズに行うためでもあります。
傾聴は利用者の本音を引き出し、よりよい介護を提供できるようになるための必須スキルなのです。
介護現場での傾聴 5つのコツ
”熱心に相手の声に耳を傾け、積極的に話を聴く”と、言うのは簡単ですが、「熱心に」、「積極的に」とは具体的にどのような姿勢でどんなことに注意して話を聴けばいいのでしょうか?
ここからは傾聴のコツをお伝えしていきます。
話を聴く時に意識するポイントを5つご紹介。ぜひ実践してみてください。
ここからは傾聴のコツをお伝えしていきます。
話を聴く時に意識するポイントを5つご紹介。ぜひ実践してみてください。
ポイント1:否定しない
傾聴の基本は相手の話の内容や感情を否定しないことです。
人それぞれ考え方や価値観が異なるため、話し手が話す内容に同意できない場合も必ず出てくるでしょう。
しかし、同意できないからといって自分の意見や考えを伝えて、相手の話を否定してしまってはいけません。
それは相手の考え方や感情を否定して自分の考えを押し付けていることになります。
話を聞きながら「その考えには賛同できないな・・・」ともし思ったとしても、それを伝えるのではなく、「〇〇さん(話し手)はそう思うんだな」と理解し、相手の意見として肯定することを心がけましょう。
それが次にお伝えする「共感」です。
人それぞれ考え方や価値観が異なるため、話し手が話す内容に同意できない場合も必ず出てくるでしょう。
しかし、同意できないからといって自分の意見や考えを伝えて、相手の話を否定してしまってはいけません。
それは相手の考え方や感情を否定して自分の考えを押し付けていることになります。
話を聞きながら「その考えには賛同できないな・・・」ともし思ったとしても、それを伝えるのではなく、「〇〇さん(話し手)はそう思うんだな」と理解し、相手の意見として肯定することを心がけましょう。
それが次にお伝えする「共感」です。
ポイント2:共感する
話を聴く時は共感の気持ちを持って聴くことが大切です。
話し手の気持ちを感じ取り、感情に共感してください。
そうすると話し手は「この人は自分の気持ちを理解してくれる人だ」と感じて、安心して話してくれるようになるでしょう。
つい聞き手は、話に対して何か気の利いたアドバイスをしようとしたり、勇気づけようとしてしまいがちですが、下手にそのようなことをする必要はありません。
「ただ相手の立場になって気持ちを肯定する」それが何より相手の気持ちの後押しになることもあります。
例えば利用者さんが誰かに腹を立ててあなたに文句を言ってきたとします。
決して「まぁまぁ、そんなに怒ることじゃないですよ」など感情を否定するようなことは言わずに、「それは腹が立っちゃいますよね」と、利用者さんの怒りに共感してあげてください。
「~と言われてムカつく!」と怒っていたら、「~と言われてムカついたんですね」とオウム返しで利用者さんの言ったことをそのまま返すのもよいでしょう。
話し手の気持ちを感じ取り、感情に共感してください。
そうすると話し手は「この人は自分の気持ちを理解してくれる人だ」と感じて、安心して話してくれるようになるでしょう。
つい聞き手は、話に対して何か気の利いたアドバイスをしようとしたり、勇気づけようとしてしまいがちですが、下手にそのようなことをする必要はありません。
「ただ相手の立場になって気持ちを肯定する」それが何より相手の気持ちの後押しになることもあります。
例えば利用者さんが誰かに腹を立ててあなたに文句を言ってきたとします。
決して「まぁまぁ、そんなに怒ることじゃないですよ」など感情を否定するようなことは言わずに、「それは腹が立っちゃいますよね」と、利用者さんの怒りに共感してあげてください。
「~と言われてムカつく!」と怒っていたら、「~と言われてムカついたんですね」とオウム返しで利用者さんの言ったことをそのまま返すのもよいでしょう。
ポイント3:話を途中で遮らず最後まで聴く
話し手の話を最後までしっかりと聴くように努めましょう。
話を遮るように途中で言葉を挟んだり、答えを急かしたり、相手の話を先回りして自分が話し始めたりすることのないように注意してください。
利用者さんの場合は特に話のペースがゆっくりだったり、ときに辻褄の合わないことを話すケースもあると思います。
そんな場合でも話を遮らず気持ちに寄り添って最後まで聴くことで、利用者さんの「話したい」という気持ちを満たすことができるでしょう。
話を遮るように途中で言葉を挟んだり、答えを急かしたり、相手の話を先回りして自分が話し始めたりすることのないように注意してください。
利用者さんの場合は特に話のペースがゆっくりだったり、ときに辻褄の合わないことを話すケースもあると思います。
そんな場合でも話を遮らず気持ちに寄り添って最後まで聴くことで、利用者さんの「話したい」という気持ちを満たすことができるでしょう。
ポイント4:話をまとめる
話が一区切りついたら、その話を一旦まとめて整理してみることをおすすめします。
これはまとまっていない話がダラダラと続いてしまう時にも有効です。
相手が話したいテーマや最も伝えたいことを見極め、簡潔に要約することで、話が先に進みます。
「それってこういうことですよね」と優しく伝えましょう。
「それで○○さんはどう思ったんですか?」などと質問をするのも話を発展させるのに効果的です。
これはまとまっていない話がダラダラと続いてしまう時にも有効です。
相手が話したいテーマや最も伝えたいことを見極め、簡潔に要約することで、話が先に進みます。
「それってこういうことですよね」と優しく伝えましょう。
「それで○○さんはどう思ったんですか?」などと質問をするのも話を発展させるのに効果的です。
ポイント5:非言語コミュニケーションを意識
傾聴では言語以外の「非言語コミュニケーション」もまた重要です。
言語コミュニケーション
会話や文字(文章)、声の大きさやトーンなどによるコミュニケーション
非言語コミュニケーション
表情やジェスチャー、しぐさ、距離感など言葉以外のさまざまな手段を用いたコミュニケーション
コミュニケーションにおいて、言語だけで伝えられる情報はたった7%。相手に与える影響は言語以上に聴覚や視覚が大きいといわれています。(メラビアンの法則)
同じ話をした場合でも、例えばアイコンタクトや表情、しぐさなどが変われば、相手への印象や伝わり方も全く違うものになります。
むすっとしたつまらなさそうな表情よりも、笑顔でリアクションをとりながら話を聴いてもらえる方が、話し手は気持ちよく話ができるでしょう。
話し方や話す内容以上に、表情や仕草などが大きな影響を持つことを理解しましょう。
同じ話をした場合でも、例えばアイコンタクトや表情、しぐさなどが変われば、相手への印象や伝わり方も全く違うものになります。
むすっとしたつまらなさそうな表情よりも、笑顔でリアクションをとりながら話を聴いてもらえる方が、話し手は気持ちよく話ができるでしょう。
話し方や話す内容以上に、表情や仕草などが大きな影響を持つことを理解しましょう。
まとめ
介護職員にとって傾聴は、利用者さんとの信頼関係を築くため、そして安心・安全な介護を行うために欠かせないコミュニケーションスキルです。
傾聴力はすぐに身につく技術ではありませんが、日常的に意識して繰り返し訓練することで少しずつ伸びていくでしょう。
傾聴スキルを身につけて、利用者さんからたくさん話しかけられる介護職員になってください!
<
■コラム「利用者への声かけが苦手な介護職員さんへ!明日からすぐに実践できる声かけマニュアル」
■コラム「詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!?」
傾聴力はすぐに身につく技術ではありませんが、日常的に意識して繰り返し訓練することで少しずつ伸びていくでしょう。
傾聴スキルを身につけて、利用者さんからたくさん話しかけられる介護職員になってください!
<
関連コラムはこちら
>■コラム「利用者への声かけが苦手な介護職員さんへ!明日からすぐに実践できる声かけマニュアル」
■コラム「詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!?」
介護のお仕事探しは介護ワーカー
「介護現場で働きたい」
「キャリアアップできる環境で働きたい!」
そんなあなたはぜひ、業界最大手の介護ワーカーをご利用ください。
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの転職をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★求人を見てみる
「キャリアアップできる環境で働きたい!」
そんなあなたはぜひ、業界最大手の介護ワーカーをご利用ください。
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの転職をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談を!
★アドバイザーに相談してみる(無料)
★求人を見てみる
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.