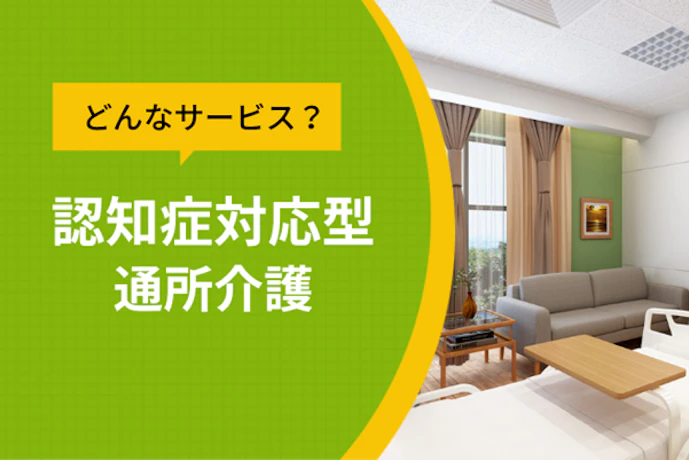介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)とはどんなサービス?特色や仕事内容を解説
#介護
目次
認知症対応型通所介護というものをご存知でしょうか?
その名の通り認知症高齢者の方のためのデイサービスです。
サービスの特徴や通常の通所介護と異なる点、仕事内容などを詳しくご紹介します。
転職をお考えの介護職員さんはぜひ参考にしてください。
その名の通り認知症高齢者の方のためのデイサービスです。
サービスの特徴や通常の通所介護と異なる点、仕事内容などを詳しくご紹介します。
転職をお考えの介護職員さんはぜひ参考にしてください。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)とは
認知症対応型通所介護は、認知症デイサービスともいわれます。
認知症の高齢者に専門的なケアを提供する通称介護サービスです。
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるようサポートします。
認知症の高齢者に専門的なケアを提供する通称介護サービスです。
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるようサポートします。
特色・役割
少人数制の地域密着型サービスである、認知症対応型通所介護。
定員は12名以下とされ、利用者一人ひとりに合わせた認知症ケアを提供することが特徴です。
認知症ケアや機能訓練によって心身機能の維持・回復を促進すること、職員や利用者同士、地域との交流を通して社会参加の場を提供することで、自信を持っていきいきと過ごしてもらうことが目的です。
そして、利用者のご家族の介護負担を軽減することもまた大きな役割といえるでしょう。
定員は12名以下とされ、利用者一人ひとりに合わせた認知症ケアを提供することが特徴です。
認知症ケアや機能訓練によって心身機能の維持・回復を促進すること、職員や利用者同士、地域との交流を通して社会参加の場を提供することで、自信を持っていきいきと過ごしてもらうことが目的です。
そして、利用者のご家族の介護負担を軽減することもまた大きな役割といえるでしょう。
利用対象者
認知症対応型通所介護を利用できる対象者は次の3点をみたす高齢者です。
・事業所が所在する地域の住民であること
・要介護認定(要支援1~要介護5)を受けていること
・認知症と診断されていること
地域密着型サービスであることから、原則として事業所がある市区町村に住んでいる(住民票がある)認知症高齢者に限られています。
・事業所が所在する地域の住民であること
・要介護認定(要支援1~要介護5)を受けていること
・認知症と診断されていること
地域密着型サービスであることから、原則として事業所がある市区町村に住んでいる(住民票がある)認知症高齢者に限られています。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)の種類
認知症対応型通所介護は次の3つのタイプに分かれます。
単独型
・介護福祉施設などに併設されずに単独で運営されている
・利用定員12人以下
併設型
・介護福祉施設などに併設されている事業所
・利用定員は12人以下
共用型
・グループホームや特定施設の居間や食堂などの一部を使って実施され、それらの施設の利用者らと共にサービスが提供される
・地域密着型介護福祉施設などの場合:
各事業所ごとに1日あたり3人以下
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設の場合:
ユニットごとに入居者との合計が12人以下
(※半日しか利用しない者がいる場合、1日の利用人数が3人を超えても可)
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)のサービス内容
認知症対応型通所介護で提唱されるサービスは、
・食事(昼食)
・入浴
・レクリエーション
・機能訓練
・口腔ケア
・自宅までの送迎
などです。
職員が午前中に利用者の自宅まで車で迎えにいき、施設で昼食や入浴をします。
1日の利用時間は日中の4~7時間程度。
機能訓練や口腔ケアをしたり、レクリエーションや職員、利用者同士のお喋りを楽しみ、夕方頃に帰宅するという流れです。
帰りも利用者の自宅まで車で送り届けます。
これらは一般的なデイサービスと大きな違いはありません。
ただ
レクリエーションや機能訓練は認知症の進行を緩和するような内容が中心となり、配置される職員は認知症ケアの資格所有者、認知症介護の経験者を揃えているところが多いでしょう。
・食事(昼食)
・入浴
・レクリエーション
・機能訓練
・口腔ケア
・自宅までの送迎
などです。
職員が午前中に利用者の自宅まで車で迎えにいき、施設で昼食や入浴をします。
1日の利用時間は日中の4~7時間程度。
機能訓練や口腔ケアをしたり、レクリエーションや職員、利用者同士のお喋りを楽しみ、夕方頃に帰宅するという流れです。
帰りも利用者の自宅まで車で送り届けます。
これらは一般的なデイサービスと大きな違いはありません。
ただ
利用者が認知症高齢者に限られていることや、認知症ケアを行うことなど通常のデイサービスと異なる点
です。レクリエーションや機能訓練は認知症の進行を緩和するような内容が中心となり、配置される職員は認知症ケアの資格所有者、認知症介護の経験者を揃えているところが多いでしょう。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)の仕事内容
上記に伴って、認知症対応型通所介護で働く介護職員の仕事内容は、一般的なデイサービスと大きくは違いません。
基本的な介護業務が中心となります。
・自宅-施設間の送迎
・食事介助
・入浴介助
・その他の身体介護(排泄介助や移動介助など)
・レクリエーション
・機能訓練の補助
・記録作成
・施設内の環境整備
などが主な業務内容です。
また送迎時には利用者のご家族と積極的にコミュニケーションをとり、自宅での過ごし方をヒアリングしたり、施設での様子を共有します。
なお、通所介護のため基本的には日勤で、夜勤はありません。
また施設によっては土日が休みの場合もあるでしょう。
<デイサービスの詳しい仕事内容についてはこちら>
◆コラム「デイサービスってどんなサービス?」
基本的な介護業務が中心となります。
・自宅-施設間の送迎
・食事介助
・入浴介助
・その他の身体介護(排泄介助や移動介助など)
・レクリエーション
・機能訓練の補助
・記録作成
・施設内の環境整備
などが主な業務内容です。
また送迎時には利用者のご家族と積極的にコミュニケーションをとり、自宅での過ごし方をヒアリングしたり、施設での様子を共有します。
なお、通所介護のため基本的には日勤で、夜勤はありません。
また施設によっては土日が休みの場合もあるでしょう。
<デイサービスの詳しい仕事内容についてはこちら>
◆コラム「デイサービスってどんなサービス?」
人員基準
認知症対応型通所介護の人員配置基準は以下の通りです。
共用型は異なるため、別途記載しています。
共用型は異なるため、別途記載しています。
<単独型・共用型>
管理者:常勤専従
生活相談員:専従で1人以上
看護師もしくは准看護師、または介護職員:専従で2人以上
機能訓練指導員:1人以上
生活相談員、看護・介護職員のうち、1人以上は常勤であること
<共用型>
従業員:共用される事業所ごとに規定されている人員基準以上の人数を満たすこと。(共用事業所の利用者数+認知症対応型通所介護の利用者数)
管理者:常勤専従
なお、生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員は必須ではありません。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)の職員に必要な資格・経験
認知症対応型通所介護で働くために必要な資格や経験はあるのでしょうか?
職種ごとにみていきましょう。
管理業務を行うために必要な知識を有し、サービス提供に必要な知識や経験があること、とされています。
また、厚生労働大臣が定める研修の
・ 認知症対応型サービス事業管理者研修
・ 認知症介護実践者研修または基礎課程研修
を修了していることが条件になります。
・社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・介護職員基礎研修課程修了者で介護サービス事業所等に介護職員等として2年以上勤務した経験のある者
上記のいずれかの資格要件を満たす者とされています。
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師もしくは准看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
上記いずれかの資格が必要となります。
看護職員は看護師(准看護師)資格が必須です。
介護職員は無資格未経験でも勤務可能ですが、資格や経験があるに越したことはありません。たとえ未経験であっても介護職員初任者研修を修了している方が望ましいでしょう。
また認知症介護に携わった経験や、認知症ケアに関する資格を持っている方は歓迎されるでしょう。
なお、
職種ごとにみていきましょう。
◆管理者
管理業務を行うために必要な知識を有し、サービス提供に必要な知識や経験があること、とされています。
また、厚生労働大臣が定める研修の
・ 認知症対応型サービス事業管理者研修
・ 認知症介護実践者研修または基礎課程研修
を修了していることが条件になります。
◆生活相談員
・社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・介護職員基礎研修課程修了者で介護サービス事業所等に介護職員等として2年以上勤務した経験のある者
上記のいずれかの資格要件を満たす者とされています。
◆機能訓練指導員
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師もしくは准看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
上記いずれかの資格が必要となります。
◆介護職員(看護職員)
看護職員は看護師(准看護師)資格が必須です。
介護職員は無資格未経験でも勤務可能ですが、資格や経験があるに越したことはありません。たとえ未経験であっても介護職員初任者研修を修了している方が望ましいでしょう。
また認知症介護に携わった経験や、認知症ケアに関する資格を持っている方は歓迎されるでしょう。
なお、
通所介護は利用者宅ー施設間の送迎があるため、どの職種であっても普通自動車運転免許が必須とされる傾向にあります
。認知症ケアに関する資格
最後に認知症介護に役立つ資格を紹介します。
認知症に関する専門知識・技術を有する「認知症ケアのプロ」と称される位置づけの資格です。
認知症介護の資格の中でも知名度が高く、転職の際に評価されることもあるでしょう。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症ケア専門士」ってどんな資格?取得のメリット・受験方法についてご紹介
介護現場で役立つ認知症の基礎知識・技術、またそれを実践する際の考え方を学び、認知症の方へ適切なケアを提供できるようになることを目的とした研修です。
認知症に関する経験や知識が浅い職員が認知症介護について学ぶ場合には、まずこの研修を受けるとよいでしょう。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症介護基礎研修ってどんな研修?研修内容や費用など詳しく解説!」
認知症介護のプロフェッショナルを養成するための実践的な研修で、認知症高齢者の介護に関する専門的な知識や技術を習得できます。
国が指定する研修で、認知症加算の対象資格です。
またステップアップ資格になっており、次に紹介する認知症介護実践リーダー研修を受ける場合にも必須の資格です。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症ケアに携わるなら取るべき資格!認知症介護実践者研修ってなに?」
介護現場で5年以上実務経験を積み、かつ認知症実践者研修を修了してから1年以上経っている人が受けることのできる上位資格です。
知識や技術をさらに深めるだけでなく、リーダーとして必要とされるチームマネジメント力を養うことができます。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症介護実践リーダー研修 ってどんな資格?」
◆認知症ケア専門士
認知症に関する専門知識・技術を有する「認知症ケアのプロ」と称される位置づけの資格です。
認知症介護の資格の中でも知名度が高く、転職の際に評価されることもあるでしょう。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症ケア専門士」ってどんな資格?取得のメリット・受験方法についてご紹介
◆認知症介護基礎研修
介護現場で役立つ認知症の基礎知識・技術、またそれを実践する際の考え方を学び、認知症の方へ適切なケアを提供できるようになることを目的とした研修です。
認知症に関する経験や知識が浅い職員が認知症介護について学ぶ場合には、まずこの研修を受けるとよいでしょう。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症介護基礎研修ってどんな研修?研修内容や費用など詳しく解説!」
◆認知症介護実践者研修
認知症介護のプロフェッショナルを養成するための実践的な研修で、認知症高齢者の介護に関する専門的な知識や技術を習得できます。
国が指定する研修で、認知症加算の対象資格です。
またステップアップ資格になっており、次に紹介する認知症介護実践リーダー研修を受ける場合にも必須の資格です。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症ケアに携わるなら取るべき資格!認知症介護実践者研修ってなに?」
◆認知症介護実践リーダー研修
介護現場で5年以上実務経験を積み、かつ認知症実践者研修を修了してから1年以上経っている人が受けることのできる上位資格です。
知識や技術をさらに深めるだけでなく、リーダーとして必要とされるチームマネジメント力を養うことができます。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症介護実践リーダー研修 ってどんな資格?」
まとめ
認知症が対応型通所介護について解説しました。
通常のデイサービスと共通する部分も多いですが、認知症の方を限定としたサービスであるため、利用者への対応方法やコミュニケーションの取り方などに工夫が必要になるでしょう。
認知症高齢者は今後ますます増えていくと予想されます。
そんな中で認知症対応型通所介護はなくてはならないサービスになるでしょう。
認知症ケアに携わりたい方、一人ひとりの方に寄り添った介護がしたい方は、ぜひ転職先として検討されてみてはいかがでしょうか?
通常のデイサービスと共通する部分も多いですが、認知症の方を限定としたサービスであるため、利用者への対応方法やコミュニケーションの取り方などに工夫が必要になるでしょう。
認知症高齢者は今後ますます増えていくと予想されます。
そんな中で認知症対応型通所介護はなくてはならないサービスになるでしょう。
認知症ケアに携わりたい方、一人ひとりの方に寄り添った介護がしたい方は、ぜひ転職先として検討されてみてはいかがでしょうか?
介護の転職は介護ワーカー!
「認知症介護を学びたい」
「小規模の施設で丁寧な介護がしたい」
そんなお仕事探しも介護ワーカーにお任せください!
経験豊富な転職アドバイザーがあなたのご希望をヒアリングの上、ぴったりの求人をご紹介します。
サイトには掲載されていない非公開求人も多数ございます。
ぜひお気軽にご相談ください!
★介護ワーカーに転職相談をする(無料)
★まずは求人を見てみる
「小規模の施設で丁寧な介護がしたい」
そんなお仕事探しも介護ワーカーにお任せください!
経験豊富な転職アドバイザーがあなたのご希望をヒアリングの上、ぴったりの求人をご紹介します。
サイトには掲載されていない非公開求人も多数ございます。
ぜひお気軽にご相談ください!
★介護ワーカーに転職相談をする(無料)
★まずは求人を見てみる
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.