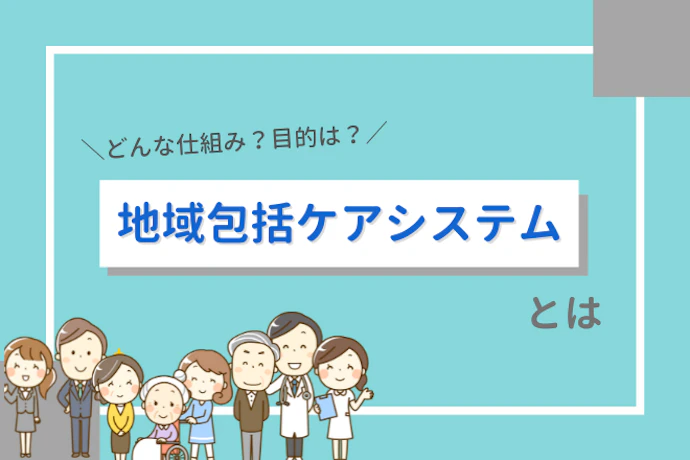介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
地域包括ケアシステムとはどんな制度?目的や構成要素を簡単に解説します
#介護
目次
地域包括ケアシステムについてご存知でしょうか?
高齢者の医療や介護などの支援を地域一体で連携しながら行う仕組みです。
本コラムではこの「地域包括ケアシステム」の仕組みや目的、メリットなどを詳しく解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
高齢者の医療や介護などの支援を地域一体で連携しながら行う仕組みです。
本コラムではこの「地域包括ケアシステム」の仕組みや目的、メリットなどを詳しく解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステムとは、高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで送ることができるよう、地域一体で支援する体制のことです。
地域の範囲は、おおむね30分以内にサービス提供できる日常生活圏域(中学校区域)とされており、その市区町村の地域包括支援センターやケアマネージャーが主体となってコーディネートします。
地域の範囲は、おおむね30分以内にサービス提供できる日常生活圏域(中学校区域)とされており、その市区町村の地域包括支援センターやケアマネージャーが主体となってコーディネートします。
システム構築の目的・背景
地域包括ケアシステムには、高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的があります。
「施設や病院ではなく自分の家で暮らしたい」と願う高齢者はとても多く、そういった意思を尊重しながら十分な支援を行なっていくための仕組みです。
しかしシステム構築の目的はそれだけではありません。
背景には2025年問題、少子高齢化があります。
2025年問題というのは、団塊の世代が75歳(後期高齢者)になる2025年以降に日本が超高齢化社会を迎える問題のことです。
そして皆さんもご存知の通り、日本は少子高齢化が進んでいます。
65歳以上の人口は現在3500万人以上、2042年には約3900万人に達する見込みです。
その後も日本の総人口は減少する一方で、75歳以上の後期高齢者は増加するという時代が続くでしょう。
高齢者が増えれば、その分医療や介護の需要が増加します。
このまま医療や介護の需要が増え続ければ、病院や施設の数、職員が不足して現場が機能しなくなることは目に見えています。
そこで2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築が進められているのです。
「施設や病院ではなく自分の家で暮らしたい」と願う高齢者はとても多く、そういった意思を尊重しながら十分な支援を行なっていくための仕組みです。
しかしシステム構築の目的はそれだけではありません。
背景には2025年問題、少子高齢化があります。
2025年問題というのは、団塊の世代が75歳(後期高齢者)になる2025年以降に日本が超高齢化社会を迎える問題のことです。
そして皆さんもご存知の通り、日本は少子高齢化が進んでいます。
65歳以上の人口は現在3500万人以上、2042年には約3900万人に達する見込みです。
その後も日本の総人口は減少する一方で、75歳以上の後期高齢者は増加するという時代が続くでしょう。
高齢者が増えれば、その分医療や介護の需要が増加します。
このまま医療や介護の需要が増え続ければ、病院や施設の数、職員が不足して現場が機能しなくなることは目に見えています。
そこで2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築が進められているのです。
地域の包括的な支援・サービス提供体制を整えることで、医療・介護を必要とする人々に届けられるようにするというねらい
があります。地域包括ケアシステムの5つの構成要素
地域包括ケアシステムの構成要素は次の5つです。
・医療
・介護
・住まい
・介護予防
・生活支援
これら5つを地域で途切れることなく一体的に提供していきます。
かかりつけ医や地域の連携病院に加えて、急性期病院、回復期リハビリ病院などです。
普段の診察、医療はかかりつけ医や地域の病院に、病気になった際は急性期病院などが対応します。
必要に応じて訪問介護(訪問看護)などの在宅介護サービスや通所介護サービスを提供します。
また小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスによって、臨機応変なサービス提供も可能になります。
常時介護が必要になれば入所施設での介護に切り替えることも可能です。
自宅やサービス付き高齢者向け住宅など、人生の最期まで暮らす場所のことです。
賃貸住宅入居時の保証人を確保するといった手続き関係の支援も含まれます。
介護予防・生活支援は地域包括ケアシステムの土台となります。
自治体による介護予防サービス、ボランティア団体による安否確認・見守り活動などを実施。
また地域交流など社会参加の場や、外出援助や家事援助などの生活支援・自立支援を提供します。
・医療
・介護
・住まい
・介護予防
・生活支援
これら5つを地域で途切れることなく一体的に提供していきます。
◆医療
かかりつけ医や地域の連携病院に加えて、急性期病院、回復期リハビリ病院などです。
普段の診察、医療はかかりつけ医や地域の病院に、病気になった際は急性期病院などが対応します。
◆介護
必要に応じて訪問介護(訪問看護)などの在宅介護サービスや通所介護サービスを提供します。
また小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスによって、臨機応変なサービス提供も可能になります。
常時介護が必要になれば入所施設での介護に切り替えることも可能です。
◆住まい
自宅やサービス付き高齢者向け住宅など、人生の最期まで暮らす場所のことです。
賃貸住宅入居時の保証人を確保するといった手続き関係の支援も含まれます。
◆介護予防・生活支援
介護予防・生活支援は地域包括ケアシステムの土台となります。
自治体による介護予防サービス、ボランティア団体による安否確認・見守り活動などを実施。
また地域交流など社会参加の場や、外出援助や家事援助などの生活支援・自立支援を提供します。
地域包括ケアシステムの捉え方
地域包括ケアシステムはよく植木鉢に例えられています。
この植木鉢の図は、5つの構成要素「医療」「介護」「住まい」「介護予防」「生活支援」をより詳しくしたもので、互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを示しています。
生活の基盤となる住まい・住まい方を植木鉢、生活支援・介護予防を土と捉え、専門サービスの医療・介護・福祉サービスを植物と捉えています。
植木鉢や土などの土台がしっかりしていなければ、そこに植物を植えても育たないということです。
地域包括ケアシステムでは、まず大前提として本人・家族の選択と心構えを土台に、安心して暮らせる住まいとしっかりとした介護予防・生活支援があることが基本的な要素となります。
そのうえで、初めて専門職による医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・福祉が提供されるという姿が、地域包括ケアシステムのあるべき姿と捉えられています。
生活の基盤となる住まい・住まい方を植木鉢、生活支援・介護予防を土と捉え、専門サービスの医療・介護・福祉サービスを植物と捉えています。
植木鉢や土などの土台がしっかりしていなければ、そこに植物を植えても育たないということです。
地域包括ケアシステムでは、まず大前提として本人・家族の選択と心構えを土台に、安心して暮らせる住まいとしっかりとした介護予防・生活支援があることが基本的な要素となります。
そのうえで、初めて専門職による医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・福祉が提供されるという姿が、地域包括ケアシステムのあるべき姿と捉えられています。
地域包括支援センター
ここで地域包括支援センターについても触れておきましょう。
地域包括ケアシステムを構築するうえで欠かせないのが、地域包括支援センターの存在です。
主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士らが配置された介護・医療・福祉・健康などの総合相談窓口で、
①介護予防ケアマネジメント
②総合相談・支援
③権利擁護
④包括的・継続的ケアマネジメント支援
を行います。
運営主体となるのは市町村(もしくは市町村に委託された法人)。
全国に5000カ所以上あり、高齢者の地域での暮らしをサポートする拠点となっています。
<詳しくはこちら>
地域包括支援センターとは?役割や仕事内容、課題などわかりやすく解説します
地域包括ケアシステムを構築するうえで欠かせないのが、地域包括支援センターの存在です。
主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士らが配置された介護・医療・福祉・健康などの総合相談窓口で、
①介護予防ケアマネジメント
②総合相談・支援
③権利擁護
④包括的・継続的ケアマネジメント支援
を行います。
運営主体となるのは市町村(もしくは市町村に委託された法人)。
全国に5000カ所以上あり、高齢者の地域での暮らしをサポートする拠点となっています。
<詳しくはこちら>
地域包括支援センターとは?役割や仕事内容、課題などわかりやすく解説します
地域包括ケアシステムのメリット
ここまでの内容を踏まえて、地域包括ケアシステムのメリットをまとめます。
1.一体的な医療・介護サービスが地域で受けられる
2.要介護者、認知症の高齢者が自宅での暮らしを継続できる
3.高齢者の社会参加の機会が増える
4.家族の負担が軽減される
介護の進行具合や病状、家庭環境によっては、住みなれた地域から離れて暮らさなければならなかったり、施設や病院で余生を過ごさなければなりません。
しかし、地域包括支援システムが機能すれば自宅の暮らしを継続しながら必要な支援を受けられるようになります。
また、介護予防の取り組みによる地域活動への参加や他者との交流が増えることで、高齢者の心の健康を保つことができます。
高齢者がいきいきと活力を持って暮らせるようになれば、その分健康寿命(医療・介護への依存なしで健康的に生活できる期間)を延ばせるかもしれません。
そして高齢者(要介護者)のご家族の負担減少にもつながることが大きなメリットといえるでしょう。
要介護者のご家族にとって在宅介護による介護疲れや介護離職は大きな問題です。
地域包括ケアシステムによってさまざまな専門職が連携しサポートすることで、ご家族の負担をできる限り負担します。
以上が、地域包括ケアシステムの主なメリットです。
1.一体的な医療・介護サービスが地域で受けられる
2.要介護者、認知症の高齢者が自宅での暮らしを継続できる
3.高齢者の社会参加の機会が増える
4.家族の負担が軽減される
介護の進行具合や病状、家庭環境によっては、住みなれた地域から離れて暮らさなければならなかったり、施設や病院で余生を過ごさなければなりません。
しかし、地域包括支援システムが機能すれば自宅の暮らしを継続しながら必要な支援を受けられるようになります。
また、介護予防の取り組みによる地域活動への参加や他者との交流が増えることで、高齢者の心の健康を保つことができます。
高齢者がいきいきと活力を持って暮らせるようになれば、その分健康寿命(医療・介護への依存なしで健康的に生活できる期間)を延ばせるかもしれません。
そして高齢者(要介護者)のご家族の負担減少にもつながることが大きなメリットといえるでしょう。
要介護者のご家族にとって在宅介護による介護疲れや介護離職は大きな問題です。
地域包括ケアシステムによってさまざまな専門職が連携しサポートすることで、ご家族の負担をできる限り負担します。
以上が、地域包括ケアシステムの主なメリットです。
地域包括ケアシステムの主な取り組み
地域包括ケアシステムは自治体が主体となり、民間団体やNPO法人などと連携してその地域に応じた取り組みを行います。
例えば、
・医療と介護の連携を図るための仕組みづくり
・認知症高齢者の支援
・介護予防サービスの推進
・ボランティア団体による交流サロンの運営
・買い物支援、移動支援
・地域ケア会議
などが挙げられますがこれらはほんの一例で、全国各地でさまざまな取り組みが実施されています。
地域包括ケアシステムの取り組みにおいて大切なことは、その地域の実情に合った介護サービスを提供することです。
地域住民の数や高齢者数、医療機関や介護施設の数など、各地域によって介護の実情は異なります。あ
ある地域で成功している事例であっても、他の地域で導入してうまくいくとは限りません。
自治体が主体となり地域の実態に応じた地域包括ケアを行うことで、高齢者やそのご家族らが安心して生活できるようになるのではないでしょうか。
下記ウェブサイトでは全国の市区町村で実施されている地域包括ケアシステム構築の取組事例が紹介されていますので、ぜひ参考になさってください。
地域包括ケアシステムの構築に関する事例集|厚生労働省
例えば、
・医療と介護の連携を図るための仕組みづくり
・認知症高齢者の支援
・介護予防サービスの推進
・ボランティア団体による交流サロンの運営
・買い物支援、移動支援
・地域ケア会議
などが挙げられますがこれらはほんの一例で、全国各地でさまざまな取り組みが実施されています。
地域包括ケアシステムの取り組みにおいて大切なことは、その地域の実情に合った介護サービスを提供することです。
地域住民の数や高齢者数、医療機関や介護施設の数など、各地域によって介護の実情は異なります。あ
ある地域で成功している事例であっても、他の地域で導入してうまくいくとは限りません。
自治体が主体となり地域の実態に応じた地域包括ケアを行うことで、高齢者やそのご家族らが安心して生活できるようになるのではないでしょうか。
下記ウェブサイトでは全国の市区町村で実施されている地域包括ケアシステム構築の取組事例が紹介されていますので、ぜひ参考になさってください。
地域包括ケアシステムの構築に関する事例集|厚生労働省
地域包括ケアシステムの課題
地域包括ケアシステムの本格的な運用開始は2014年の医療介護総合確保推進法が施行されてからとなり、まだまだ歴史の浅い取り組みです。
そのためシステムが完璧に機能しているわけでなく、運用していく中でいくつかの課題が生じています。
主な課題として、次のようなことが挙げられます。
・医療と介護の連携
・地域格差
・浸透率の低さ
・人手不足
ひとつずつ見ていきましょう。
そのためシステムが完璧に機能しているわけでなく、運用していく中でいくつかの課題が生じています。
主な課題として、次のようなことが挙げられます。
・医療と介護の連携
・地域格差
・浸透率の低さ
・人手不足
ひとつずつ見ていきましょう。
医療と介護の連携
地域包括ケアシステムにおいて、医療と介護の連携は必要不可欠です。
しかし、十分に機能しているとは言い難く、特に深夜や早朝の対応が不十分な傾向にあります。
どの時間帯であっても介護職員と医師、看護師らが速やかに連携し高齢者の急な変化に対応できる仕組みづくりが求められています。
しかし、十分に機能しているとは言い難く、特に深夜や早朝の対応が不十分な傾向にあります。
どの時間帯であっても介護職員と医師、看護師らが速やかに連携し高齢者の急な変化に対応できる仕組みづくりが求められています。
地域格差
先にも述べたように、地域の財政や高齢者人口、医療・介護従事者の充足率などの実情は地域ごとに異なっています。
そのため成功している取り組みを行ったとしても、それがすべての地域で機能するわけではないのです。
どの地域にも効果的な施策というものはなく、独自の体制を構築しなければなりません。
地域の自治体が主体となって、地域の特性に応じた取り組みを行っていくことが必要です。
そのため成功している取り組みを行ったとしても、それがすべての地域で機能するわけではないのです。
どの地域にも効果的な施策というものはなく、独自の体制を構築しなければなりません。
地域の自治体が主体となって、地域の特性に応じた取り組みを行っていくことが必要です。
浸透率の低さ
地域包括ケアシステムそのものの認知度を向上することも課題のひとつとなっています。
高齢者やそのご家族への周知はもちろん、医療機関や介護事業所、その他の法人、地域住民らの理解も必要になります。
システムの目的、それぞれの役割を明確にしたうえで、地域全体への啓発活動や協力依頼を行って行かなければなりません。
高齢者やそのご家族への周知はもちろん、医療機関や介護事業所、その他の法人、地域住民らの理解も必要になります。
システムの目的、それぞれの役割を明確にしたうえで、地域全体への啓発活動や協力依頼を行って行かなければなりません。
人手不足
過疎化が進む地域では特に、高齢者の数に対して医療・介護従事者が不足しています。
マンパワー不足では地域包括ケアシステムは機能しません。
人手を確保することが急務となっています。
マンパワー不足では地域包括ケアシステムは機能しません。
人手を確保することが急務となっています。
地域包括ケアシステムで大切な4つの「助」
では最後に地域包括ケアシステムを推進するうえで大切といわれている4つの「助」についてお伝えします。
地域包括ケアシステムによって高齢者一人ひとりのニーズに応える支援を行うためには、「自助」「共助」「互助」「公助」という4つの助を連携させていくことが大切です。
それぞれについて解説します。
地域包括ケアシステムによって高齢者一人ひとりのニーズに応える支援を行うためには、「自助」「共助」「互助」「公助」という4つの助を連携させていくことが大切です。
それぞれについて解説します。
自助
自助は自分で自分を助けることです。高齢者自身が介護予防に取り組み、自身のケアを行うことをいいます。
例えば、健康維持のための検診を受けたり、積極的に他者との交流を図ることなどが挙げられます。
できる限り住み慣れた地域で生活を続けるための、自発的な課題解決力「自助」が必要です。
例えば、健康維持のための検診を受けたり、積極的に他者との交流を図ることなどが挙げられます。
できる限り住み慣れた地域で生活を続けるための、自発的な課題解決力「自助」が必要です。
互助
互助は家族や近隣住民、友人らとの支え合いです。
親しい間柄の人や知り合いが相互に助け合い、問題を解決します。
互助は人と人との自発的な支え合いとされており、ボランティア活動や地域の活動、住民同士の助け合いなどが該当します。
親しい間柄の人や知り合いが相互に助け合い、問題を解決します。
互助は人と人との自発的な支え合いとされており、ボランティア活動や地域の活動、住民同士の助け合いなどが該当します。
共助
共助は介護保険や医療保険サービスなど制度化されている相互扶助を指します。
医療、年金、介護保険、社会保険などの制度・サービスを、リスクを共有する仲間(被保険者)らと相互に負担し合いながら利用するというものです。
医療、年金、介護保険、社会保険などの制度・サービスを、リスクを共有する仲間(被保険者)らと相互に負担し合いながら利用するというものです。
公助
公助は生活困難者を救済するための行政サービスです。
自助・互助・共助では対応出来ない問題を抱えている人に対して、生活保障を行います。
公助は税金で賄われており、高齢者福祉事業、生活困窮者への生活保護、人権擁護、虐待対策などが該当します。
これら4つの「助」は連携しあうことが大切なのですが、基盤となるのは「自助」です。
自分自身を大切にし、ケアをするという心構えや行動が何よりも大切になります。
しかし自助だけでは限界があります。
介護が必要となった時などには周りのサポートが必要不可欠。互助の出番となります。
ただし、支える側の負担が大きくなりすぎた場合には、互助は成り立たなくなってしまいます。
互助でのサポートが難しくなった場合には共助を利用しましょう。
共助は制度化されており、権利として利用できる支援です。互助の負担を共助で補います。
そして自助・互助・共助では賄えなくなった問題には、公助のサポートで対応します。
この4つの「助」は先ほどお伝えした植木鉢の考え方にも通じます。
このように地域包括ケアシステムでは4つの助を連携していくことが大切です。
そのためには
自助・互助・共助では対応出来ない問題を抱えている人に対して、生活保障を行います。
公助は税金で賄われており、高齢者福祉事業、生活困窮者への生活保護、人権擁護、虐待対策などが該当します。
これら4つの「助」は連携しあうことが大切なのですが、基盤となるのは「自助」です。
自分自身を大切にし、ケアをするという心構えや行動が何よりも大切になります。
しかし自助だけでは限界があります。
介護が必要となった時などには周りのサポートが必要不可欠。互助の出番となります。
ただし、支える側の負担が大きくなりすぎた場合には、互助は成り立たなくなってしまいます。
互助でのサポートが難しくなった場合には共助を利用しましょう。
共助は制度化されており、権利として利用できる支援です。互助の負担を共助で補います。
そして自助・互助・共助では賄えなくなった問題には、公助のサポートで対応します。
この4つの「助」は先ほどお伝えした植木鉢の考え方にも通じます。
このように地域包括ケアシステムでは4つの助を連携していくことが大切です。
そのためには
高齢者自身、ご家族、地域住民、自治体・ボランティア、関係機関が、地域包括ケアシステムの仕組みやそれぞれの役割を理解したうえで、一体となって取り組む
ことが重要となります。まとめ
地域包括ケアシステムについて解説しました。
高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしく暮らすためのサポートシステムです。
システム自体はまだ完璧なものではなく課題もありますが、2025年に向けて全国の地域での構築が進められています。
今後の超高齢化社会の日本において、地域包括ケアシステムは必要不可欠なものとなるでしょう。
高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしく暮らすためのサポートシステムです。
システム自体はまだ完璧なものではなく課題もありますが、2025年に向けて全国の地域での構築が進められています。
今後の超高齢化社会の日本において、地域包括ケアシステムは必要不可欠なものとなるでしょう。
介護のお仕事は介護ワーカー!
「地域密着型サービスで介護の仕事がしたい」
「地域包括支援センターの求人ってないの?」
そんな転職をご希望のあなたは、ぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください!
★介護ワーカーに相談してみる(無料)
★まずは求人を見てみる
「地域包括支援センターの求人ってないの?」
そんな転職をご希望のあなたは、ぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください!
★介護ワーカーに相談してみる(無料)
★まずは求人を見てみる
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.