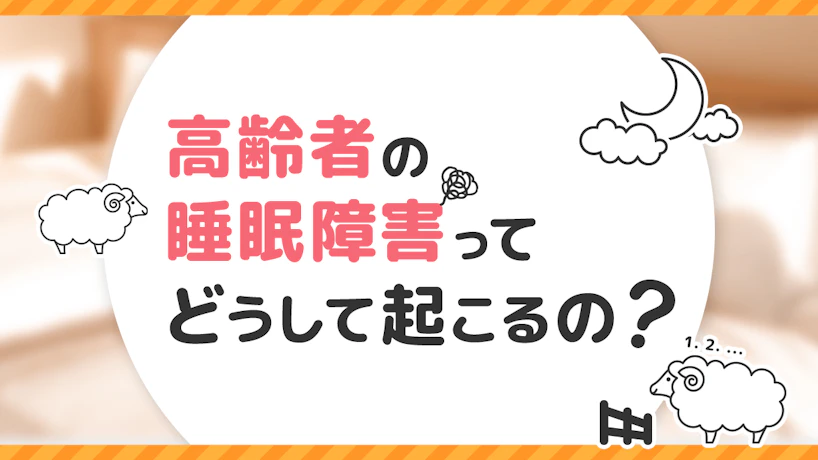介護コラム
公開日:2023.10.12
更新日:2023.11.09
高齢者の睡眠障害ってどうして起こるの?
#介護
眠れない時、あなたは何をしますか?
昔は、よく羊を数えるのがいいと言われましたね。「羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹…」数えたことのある人も多いことでしょう。でもこの方法、実は、ほとんど眠れないですよね。
眠ろうとすればするほど、目がさえていくこともしばしばあります。
自律神経を整える方法を書いた本やCDが人気の現代。ゆったりと心で日常を過ごし、朝までぐっすりと眠りたい。そう願うのは、高齢者ばかりではありません。現在、日本人の5人に1人が何らかの睡眠障害に悩まされていると言われています。
眠ろうとすればするほど、目がさえていくこともしばしばあります。
自律神経を整える方法を書いた本やCDが人気の現代。ゆったりと心で日常を過ごし、朝までぐっすりと眠りたい。そう願うのは、高齢者ばかりではありません。現在、日本人の5人に1人が何らかの睡眠障害に悩まされていると言われています。
睡眠障害の中でも多いのは不眠症
睡眠障害には、いくつかのタイプがあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群や過眠症は、ずいぶん認知が広まってきました。そんな睡眠障害の中でも、1番一般的で悩みが多いのがいわゆる不眠症でしょう。不眠症にも、いくつかのタイプがあります。
1つ目は、眠りにつくのが難しいタイプです。2つめは、眠りについても途中で目が覚めてしまうタイプです。これにはさらに、夜中に目が覚める中途覚醒と、予定より早く目が覚めてしまう早朝覚醒とがあります。それから、ある程度睡眠時間はあるのに、眠りが浅く熟睡感が得られない症状です。
1つ目は、眠りにつくのが難しいタイプです。2つめは、眠りについても途中で目が覚めてしまうタイプです。これにはさらに、夜中に目が覚める中途覚醒と、予定より早く目が覚めてしまう早朝覚醒とがあります。それから、ある程度睡眠時間はあるのに、眠りが浅く熟睡感が得られない症状です。
高齢者が朝早いのは睡眠障害?
昔から、「年寄りは朝が早い」などという言い方があります。実際、高齢になると、朝早く目が覚めてしまう方は多いです。これも早朝覚醒の1つでしょうか。
もちろん中には、そういう方もいらっしゃいます。しかし、実は、これは睡眠障害ではない場合が非常に多いのです。
体が必要とする睡眠の量は、年齢によって違います。昔から、「寝る子は育つ」と言われてきました。成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるからです。成長期にはそれだけの睡眠量が必要なのです。よく高校生ぐらいの健康な男の子は、眠っても、眠っても、寝足りないといいますね。
加齢に伴って、必要とする睡眠の量は減っていきます。体自体が必要とする量が減るだけでなく、若いころに比べると、どうしても日中の運動量も減ります。同じ時間に床につく習慣があれば、自然に目が覚める時間はだんだんと早くなっていきます。ですから、「年寄りは朝が早い」のです。
こういった体のメカニズムを、昔の人は、経験によって知っていたのですね。ですから、高齢者が早朝に目が覚めてしまうのは、睡眠障害でない場合が多いのです。もし、早く起きたくないならば、逆に少し夜更かしをすればいいということになります。
もちろん中には、そういう方もいらっしゃいます。しかし、実は、これは睡眠障害ではない場合が非常に多いのです。
体が必要とする睡眠の量は、年齢によって違います。昔から、「寝る子は育つ」と言われてきました。成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるからです。成長期にはそれだけの睡眠量が必要なのです。よく高校生ぐらいの健康な男の子は、眠っても、眠っても、寝足りないといいますね。
加齢に伴って、必要とする睡眠の量は減っていきます。体自体が必要とする量が減るだけでなく、若いころに比べると、どうしても日中の運動量も減ります。同じ時間に床につく習慣があれば、自然に目が覚める時間はだんだんと早くなっていきます。ですから、「年寄りは朝が早い」のです。
こういった体のメカニズムを、昔の人は、経験によって知っていたのですね。ですから、高齢者が早朝に目が覚めてしまうのは、睡眠障害でない場合が多いのです。もし、早く起きたくないならば、逆に少し夜更かしをすればいいということになります。
加齢以外の睡眠障害の原因は?
その他にも、高齢者の睡眠障害の原因となるものがいくつかあります。
1つは、身体的な問題です。例えば、夜間頻尿があります。また、関節痛などの体の痛みも、大きな原因になります。
次に、心の問題です。悩みや不安、緊張は睡眠の大きな妨げになります。また、前述のような身体的な要因は、心にも大きく影響を与え、不安や悲しみを増大させます。
また、生活面からの要因も見逃せません。アルコールやニコチン、カフェインは不眠を増幅させます。若いころよりも、影響が強く出ることが、多くあります。特に「寝酒」は、実は眠りの質を大きく低下させるので、不眠を悪くする恐れが強いものです。高齢者には、薬の副作用も見逃せません。
1つは、身体的な問題です。例えば、夜間頻尿があります。また、関節痛などの体の痛みも、大きな原因になります。
次に、心の問題です。悩みや不安、緊張は睡眠の大きな妨げになります。また、前述のような身体的な要因は、心にも大きく影響を与え、不安や悲しみを増大させます。
また、生活面からの要因も見逃せません。アルコールやニコチン、カフェインは不眠を増幅させます。若いころよりも、影響が強く出ることが、多くあります。特に「寝酒」は、実は眠りの質を大きく低下させるので、不眠を悪くする恐れが強いものです。高齢者には、薬の副作用も見逃せません。
睡眠障害にはどのように対応すれば?
眠りは、生命維持に大きな役割を果たしています。よく眠れない生活を続けていると、体、もしくは精神に重篤な影響を与える恐れがあります。苦しみながらも、そのままにしておくことは、絶対によいことではありません。
また、睡眠障害には、本当の疾病が隠れていることもあります。例えば、うつ病などは眠れないことが初期症状としてあらわれる場合も多いものです。
ですから、高齢者の方に睡眠障害がみられた場合は、ひどくなる前に医師に相談することが大切です。昔は、怖い印象もあった睡眠薬ですが、現在は、色々な種類が出ており、寝つきがよくなるもの、夜中に目が覚めないようにするものなど、効き目が、細やかになってきています。症状によって、種類や量をコントロールすることが可能です。
もちろんお薬ですから、副作用もあります。お薬手帳を使っての、日常の薬との飲み合わせの確認も必要です。必ず、医師や薬剤師の管理下で使用しましょう。
ただし、お薬での睡眠の改善は一時的なもので、根本的な解決にはなりません。睡眠障害は、治療とともに、生活習慣の見直しが大変重要になってきます。
日中日の光を浴びる、適度な運動をする、あまり早い時間に床につかないなど、生活を少し改善すると、睡眠も改善される場合があります。
また、睡眠障害には、本当の疾病が隠れていることもあります。例えば、うつ病などは眠れないことが初期症状としてあらわれる場合も多いものです。
ですから、高齢者の方に睡眠障害がみられた場合は、ひどくなる前に医師に相談することが大切です。昔は、怖い印象もあった睡眠薬ですが、現在は、色々な種類が出ており、寝つきがよくなるもの、夜中に目が覚めないようにするものなど、効き目が、細やかになってきています。症状によって、種類や量をコントロールすることが可能です。
もちろんお薬ですから、副作用もあります。お薬手帳を使っての、日常の薬との飲み合わせの確認も必要です。必ず、医師や薬剤師の管理下で使用しましょう。
ただし、お薬での睡眠の改善は一時的なもので、根本的な解決にはなりません。睡眠障害は、治療とともに、生活習慣の見直しが大変重要になってきます。
日中日の光を浴びる、適度な運動をする、あまり早い時間に床につかないなど、生活を少し改善すると、睡眠も改善される場合があります。
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.