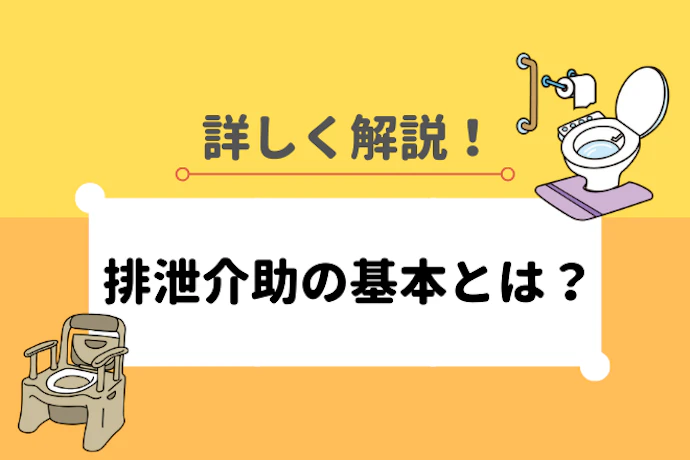介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
詳しく解説!排泄介助の基本とは?
#介護
目次
介護の仕事の中で一番重要な介助とも言われる「排泄介助」。
排泄のお手伝いをするだけではなく、皮膚や排泄物の状態を確認することでその方の体調を把握するための大切な役割も持っています。
また、陰部や臀部などが清潔に保たれずにいると、健康にも悪影響を及ぼすことも。
そこで排泄介助の重要性について詳しくまとめましたので実際に介助をするときにぜひお役立てください。
はじめに、排泄介助について説明していきます。
排泄のお手伝いをするだけではなく、皮膚や排泄物の状態を確認することでその方の体調を把握するための大切な役割も持っています。
また、陰部や臀部などが清潔に保たれずにいると、健康にも悪影響を及ぼすことも。
そこで排泄介助の重要性について詳しくまとめましたので実際に介助をするときにぜひお役立てください。
はじめに、排泄介助について説明していきます。
排泄介助とは?
自分自身で排泄の行為や動作ができない方、もしくは排泄の機能に障害がある方を介助することをいいます。
排泄を介助することで要介護者を清潔に保つだけではなく感染症予防にもなるため、介護においてとても重要なケアの1つです。
自立した日常生活には排泄のコントロールが大事ですが、もし排泄障害を起こしてしまうと
社会活動への参加意欲が低下したり、自らの存在価値を否定したりするようになってしまいます。
そうならないためにも、日頃から排泄支援をおこないコントロールをすることで、よりよい日常生活を営むことができます。
排泄介助と言ってもトイレに連れ行くことだけではなく、他にも介助の種類があります。
では、その種類について1つずつ見ていきましょう。
排泄を介助することで要介護者を清潔に保つだけではなく感染症予防にもなるため、介護においてとても重要なケアの1つです。
自立した日常生活には排泄のコントロールが大事ですが、もし排泄障害を起こしてしまうと
社会活動への参加意欲が低下したり、自らの存在価値を否定したりするようになってしまいます。
そうならないためにも、日頃から排泄支援をおこないコントロールをすることで、よりよい日常生活を営むことができます。
排泄介助と言ってもトイレに連れ行くことだけではなく、他にも介助の種類があります。
では、その種類について1つずつ見ていきましょう。
排泄介助の種類とは?
トイレ介助
名の通り、利用者がトイレに行くまでを介助することをいいます。
基本的に歩行や立位が自立している方、安定して座れる方がメインに使用します。
排泄介助だけでなく歩行するときの足の運び、皮膚の状態などのこまかい確認をする機会となります。
歩行介助に関してはこちらでご紹介しています。
■「安心・安全に歩行介助をおこなうために!」
基本的に歩行や立位が自立している方、安定して座れる方がメインに使用します。
排泄介助だけでなく歩行するときの足の運び、皮膚の状態などのこまかい確認をする機会となります。
歩行介助に関してはこちらでご紹介しています。
■「安心・安全に歩行介助をおこなうために!」
ポータブルトイレ介助
ポータブルトイレは本体と便座、排泄物用のバケツ、ふたが一体となっています。
持ち運びができ寝室などの部屋に置けるので、トイレまでの移動が困難な方の介助に使われます。
日中は普通のトイレを使い、夜間だけポータブルトイレを使用するという方法もあります。
持ち運びができ寝室などの部屋に置けるので、トイレまでの移動が困難な方の介助に使われます。
日中は普通のトイレを使い、夜間だけポータブルトイレを使用するという方法もあります。
オムツ介助
尿意、便意がない方に向いていて、そのまま中に排泄できます。
素材には紙タイプと布タイプがあり、介助者に交換してもらうテープタイプと自力で履けるパンツタイプがあります。
インナーとして吸水パッド、アウターでオムツやパンツを組み合わせて使います。
素材には紙タイプと布タイプがあり、介助者に交換してもらうテープタイプと自力で履けるパンツタイプがあります。
インナーとして吸水パッド、アウターでオムツやパンツを組み合わせて使います。
便器、尿器を使用する介助
寝た状態で尿や便を受けることができる容器で、尿器は男性用と女性用に分かれています。
尿意や便意はあるが、ベッドから起き上がれない方に向いているものです。
それぞれ使用したら洗浄し消毒液があれば消毒しておくといいでしょう。
排泄介助には4つの種類があることが分かりました。
その4つの介助には共通の注意点があります。それを理解しておくことで介助者と利用者の信頼関係を築くこともできます。
では、どんなことに注意したらいいのか見ていきましょう。
尿意や便意はあるが、ベッドから起き上がれない方に向いているものです。
それぞれ使用したら洗浄し消毒液があれば消毒しておくといいでしょう。
排泄介助には4つの種類があることが分かりました。
その4つの介助には共通の注意点があります。それを理解しておくことで介助者と利用者の信頼関係を築くこともできます。
では、どんなことに注意したらいいのか見ていきましょう。
排泄介助で注意することは?
排泄介助の注意点について1つずつ説明していきます。
利用者の自尊心を傷つけない
他人に自分の下の世話をしてもらうことは誰でも嫌なもので、快く受け取る人はあまりいないでしょう。
また、羞恥心や情けない気持ち、介助をされることに罪悪感を感じて心を閉ざしてしまう方もなかにはいます。
たとえ排泄に失敗したとしても責めたり、嫌な顔をしてはなりません。
逆に成功したときは一緒に喜んだり、安心できるよう手や肩に触れるなどのスキンシップをはかることでできるだけ自尊心を傷付けないよう心がけましょう。
また、羞恥心や情けない気持ち、介助をされることに罪悪感を感じて心を閉ざしてしまう方もなかにはいます。
たとえ排泄に失敗したとしても責めたり、嫌な顔をしてはなりません。
逆に成功したときは一緒に喜んだり、安心できるよう手や肩に触れるなどのスキンシップをはかることでできるだけ自尊心を傷付けないよう心がけましょう。
できるところは自分でやってもらう
例えば、トイレまで自力で行ける方に対して過剰に手を貸すことで、今まで自分でできていたこともやらなくなってしまいます。
そして残っている体の機能がどんどん減ってしまい、より介助が必要になり介助者の仕事も増えることになりかねません。
もし、介助をするのであれば、利用者ができるところはやってもらい、本当にできない部分のみ介助者が手伝うようにしましょう。
そして残っている体の機能がどんどん減ってしまい、より介助が必要になり介助者の仕事も増えることになりかねません。
もし、介助をするのであれば、利用者ができるところはやってもらい、本当にできない部分のみ介助者が手伝うようにしましょう。
利用者を急かさない
腹圧が弱まっていることが原因で、トイレに座ってもなかなか排尿や排便ができないこともあります。
そんなときは、決して「早くして」などと急かすような言葉や態度をしてはいけません。
プレッシャーによりさらに時間がかかったり、トイレに行くこと自体を拒否するようになってしまいます。
そのため、出るまで待ってあげるか、必要であればお腹のマッサージなどをしてあげましょう。常に出にくい場合はかかりつけの医者や施設の看護師に相談するのもいいでしょう。
そんなときは、決して「早くして」などと急かすような言葉や態度をしてはいけません。
プレッシャーによりさらに時間がかかったり、トイレに行くこと自体を拒否するようになってしまいます。
そのため、出るまで待ってあげるか、必要であればお腹のマッサージなどをしてあげましょう。常に出にくい場合はかかりつけの医者や施設の看護師に相談するのもいいでしょう。
こまめに水分補給をしてもらう
トイレに行く回数が増えることに億劫になってしまったり、トイレの失敗に恐れを感じて水分補給をしない方が多くいます。
もし、水分補給を減らしてしまえば脱水症状を引き起こしたり便秘になりやすいなど体に異常をきたすことも。
水分を摂取しなければ起こるリスクをしっかりと説明し、こまめな水分補給をうながしましょう。
以上の注意点をふまえたうえで、次に排泄介助のコツやポイントについて介助方法別に詳しく解説していきます。
もし、水分補給を減らしてしまえば脱水症状を引き起こしたり便秘になりやすいなど体に異常をきたすことも。
水分を摂取しなければ起こるリスクをしっかりと説明し、こまめな水分補給をうながしましょう。
以上の注意点をふまえたうえで、次に排泄介助のコツやポイントについて介助方法別に詳しく解説していきます。
排泄介助のコツやポイントは?
トイレ介助
1. 排泄のタイミングをみて、トイレへの声掛けをします。
立ち上がる際のふらつきに注意しましょう。
また、トイレまでの導線に障害物がないか、歩行の様子などを観察しながら安全に移動できるように見守ります。
2. トイレに到着後、自分でできることは自分でしてもらい、できないことだけお手伝いします。羞恥心に気遣い、手早く対応するようにしましょう。
できれば、ズボンを下げたときに皮膚の状態も確認しておきます。
3.便座に座った際、床に足がしっかりつき、安定しているか確認します。
排泄中は、ドアを少しだけ開けいつでも中を確認できるようにしておき、終わるまで外で待ちます。
介助者の存在を気にせず排泄できるよう、物音を立てないよう配慮しましょう。
座りが不安定な方、転倒リスクがある場合は便器の横で見守ります。
4. 排泄後は声をかけてもらうか、呼び出しボタンで知らせてもらいましょう。
トイレットペーパーをちぎったり、拭くことができない場合は、介助します。
このとき、排泄物を観察して健康状態を把握しましょう。
5. トイレで力むと、血圧が上がってしまうことがあるので特に高血圧の症状がある人は、めまいなどが起きていないか確認してください。
6. ズボンを上げるなど、自分でできることは自分で、できないことのみを介助します。
急に立ち上がるとふらつくことがあるので、ゆっくり立ち上がってもらいます。
7.元いた場所に戻るまでしっかり見守りをします。
到着後、体調の変化がないか確認しましょう。
上手く排泄できたことを一緒に喜んだり、足腰の状態が良さそうなことを伝えると自信がつくので、前向きになれるような言葉をかけてあげることが大切です。
立ち上がる際のふらつきに注意しましょう。
また、トイレまでの導線に障害物がないか、歩行の様子などを観察しながら安全に移動できるように見守ります。
2. トイレに到着後、自分でできることは自分でしてもらい、できないことだけお手伝いします。羞恥心に気遣い、手早く対応するようにしましょう。
できれば、ズボンを下げたときに皮膚の状態も確認しておきます。
3.便座に座った際、床に足がしっかりつき、安定しているか確認します。
排泄中は、ドアを少しだけ開けいつでも中を確認できるようにしておき、終わるまで外で待ちます。
介助者の存在を気にせず排泄できるよう、物音を立てないよう配慮しましょう。
座りが不安定な方、転倒リスクがある場合は便器の横で見守ります。
4. 排泄後は声をかけてもらうか、呼び出しボタンで知らせてもらいましょう。
トイレットペーパーをちぎったり、拭くことができない場合は、介助します。
このとき、排泄物を観察して健康状態を把握しましょう。
5. トイレで力むと、血圧が上がってしまうことがあるので特に高血圧の症状がある人は、めまいなどが起きていないか確認してください。
6. ズボンを上げるなど、自分でできることは自分で、できないことのみを介助します。
急に立ち上がるとふらつくことがあるので、ゆっくり立ち上がってもらいます。
7.元いた場所に戻るまでしっかり見守りをします。
到着後、体調の変化がないか確認しましょう。
上手く排泄できたことを一緒に喜んだり、足腰の状態が良さそうなことを伝えると自信がつくので、前向きになれるような言葉をかけてあげることが大切です。
ポータブルトイレ介助
ポータブルトイレを使用する際も、自分できるところはお任せし、できないことのみを介助しましょう。
1. トイレの声掛けをしたのち、手助けしながらゆっくりと体を起こします。
体調の確認をしてからポータブルトイレまで移動してもらいます。
2.トイレのフタを開け、ズボンを下ろして転倒に注意しながら便座に座ってもらいます。
このとき下腹部にタオルをかけるなどしてプライバシーの配慮をしましょう。
3.床に足がしっかりつき安定しているかどうかを確認します。
排泄が終わるまで近くで待機し、終わったら声をかけて知らせてもらいましょう。
自力でトイレットペーパーをちぎったり、拭いたりできない場合は、手早く介助します。
4.トイレで力を入れると、血圧が上がってしまうことがあるので特に高血圧の症状がある人は、めまいなどが起きていないか確認してください。
5. ズボンを上げるなど自分でできることはやってもらい、できないことだけを手伝います。
6. 近くに手洗い場がないときはアルコールなどで手指消毒をしてからベッドに戻ってもらいます。戻ってからも体調の変化がないか確認をしてください。
7. 介助者は排泄物を確認して健康状態を把握します。その後、中のバケツをトイレまで持って行き排泄物を流します。
残った汚れをトイレットペーパーなどで拭き取って流し、バケツを洗います。
室内でポータブルトイレを使用すると臭いが気になるので、できるだけ早く処理しトイレ洗浄液を使用するといいでしょう。
1. トイレの声掛けをしたのち、手助けしながらゆっくりと体を起こします。
体調の確認をしてからポータブルトイレまで移動してもらいます。
2.トイレのフタを開け、ズボンを下ろして転倒に注意しながら便座に座ってもらいます。
このとき下腹部にタオルをかけるなどしてプライバシーの配慮をしましょう。
3.床に足がしっかりつき安定しているかどうかを確認します。
排泄が終わるまで近くで待機し、終わったら声をかけて知らせてもらいましょう。
自力でトイレットペーパーをちぎったり、拭いたりできない場合は、手早く介助します。
4.トイレで力を入れると、血圧が上がってしまうことがあるので特に高血圧の症状がある人は、めまいなどが起きていないか確認してください。
5. ズボンを上げるなど自分でできることはやってもらい、できないことだけを手伝います。
6. 近くに手洗い場がないときはアルコールなどで手指消毒をしてからベッドに戻ってもらいます。戻ってからも体調の変化がないか確認をしてください。
7. 介助者は排泄物を確認して健康状態を把握します。その後、中のバケツをトイレまで持って行き排泄物を流します。
残った汚れをトイレットペーパーなどで拭き取って流し、バケツを洗います。
室内でポータブルトイレを使用すると臭いが気になるので、できるだけ早く処理しトイレ洗浄液を使用するといいでしょう。
オムツ介助
1.オムツ交換することを利用者に伝えておきましょう。
介助者が腰を痛めないようベッドの高さを調節します。
2.体位交換しやすいように利用者さんに腕を組んでもらいます。
新しいオムツとパッドを広げて準備をしておきましょう。
3.声をかけながらズボンを脱がし、汚れたオムツのテープを外します。
動作の前には必ず声をかけましょう 。
4.陰洗ボトルや清拭用タオルで陰部を清潔にします。
新しいオムツを古いオムツの横にセットし利用者を横向きにしてからお尻を清潔にします。
このときお尻に褥瘡などできていないか皮膚の状態観察もしておきましょう。
塗り薬などの保湿が必要な場合は清潔にしてから塗布します。
5.その後汚れたパッドとオムツを丸め込みます。
汚れがオムツまで浸透せずにパッドのみで済んだ場合は、パッドのみ交換しましょう。
6.新しいオムツを丸めこんだ古いオムツの下に半分ほど入れ込みます。
利用者の体を反対向きに体位交換し、入れ込んだ古いオムツを取り出しましょう。
お尻の下に入れておいた新しいオムツを引き出し形を整えます。
7.利用者を仰向けにし、おむつを整えテープを止めます。
脱いでいたズボンを元に戻し、シワができないように伸ばします。
シワがあると褥瘡(じょくそう)の原因にもなりますので注意しましょう。
8.布団をかけて元の状態に戻し、体調に変化がないかを確認します。
オムツやパッドは新聞紙などに包んで捨てましょう。
介助者が腰を痛めないようベッドの高さを調節します。
2.体位交換しやすいように利用者さんに腕を組んでもらいます。
新しいオムツとパッドを広げて準備をしておきましょう。
3.声をかけながらズボンを脱がし、汚れたオムツのテープを外します。
動作の前には必ず声をかけましょう 。
4.陰洗ボトルや清拭用タオルで陰部を清潔にします。
新しいオムツを古いオムツの横にセットし利用者を横向きにしてからお尻を清潔にします。
このときお尻に褥瘡などできていないか皮膚の状態観察もしておきましょう。
塗り薬などの保湿が必要な場合は清潔にしてから塗布します。
5.その後汚れたパッドとオムツを丸め込みます。
汚れがオムツまで浸透せずにパッドのみで済んだ場合は、パッドのみ交換しましょう。
6.新しいオムツを丸めこんだ古いオムツの下に半分ほど入れ込みます。
利用者の体を反対向きに体位交換し、入れ込んだ古いオムツを取り出しましょう。
お尻の下に入れておいた新しいオムツを引き出し形を整えます。
7.利用者を仰向けにし、おむつを整えテープを止めます。
脱いでいたズボンを元に戻し、シワができないように伸ばします。
シワがあると褥瘡(じょくそう)の原因にもなりますので注意しましょう。
8.布団をかけて元の状態に戻し、体調に変化がないかを確認します。
オムツやパッドは新聞紙などに包んで捨てましょう。
尿器を使用する介助
尿器はガラスやプラスチックなど、様々な素材があります。
利用者の好みや介助者にとって使いやすいものを選びましょう。
1. 男性は仰向けか横向きに寝た状態で、女性は仰向けの状態で、尿器の受け口を陰部にあてて使用します。
女性はお尻のほうにトイレットペーパーやタオルを敷いておくとシーツなどを汚さないで済むでしょう。
2. ズボンを下ろす、尿器をあてるなど、できることは自力でやってもらいましょう。
介助者が尿器をおさえる場合は、下腹部にタオルをかけプライバシーを守ります。
3. 排尿が終わるまで横で見守ります。
終わったのち陰部を清潔にし、衣服を整えます。
4.溜まった 尿をトイレに流し、尿器を洗います。
このとき尿の色や状態も確認しておきましょう。
消毒液があれば消毒しておきます。
利用者の好みや介助者にとって使いやすいものを選びましょう。
1. 男性は仰向けか横向きに寝た状態で、女性は仰向けの状態で、尿器の受け口を陰部にあてて使用します。
女性はお尻のほうにトイレットペーパーやタオルを敷いておくとシーツなどを汚さないで済むでしょう。
2. ズボンを下ろす、尿器をあてるなど、できることは自力でやってもらいましょう。
介助者が尿器をおさえる場合は、下腹部にタオルをかけプライバシーを守ります。
3. 排尿が終わるまで横で見守ります。
終わったのち陰部を清潔にし、衣服を整えます。
4.溜まった 尿をトイレに流し、尿器を洗います。
このとき尿の色や状態も確認しておきましょう。
消毒液があれば消毒しておきます。
便器を使用する手順
1. 汚れ軽減と、飛びはね防止のため、事前に便器の中にトイレットペーパーを敷いておくといいでしょう。
利用者が仰向けに寝た状態で便器をお尻の下に入れます。
ゴム製便器の場合は、このときに空気を入れてふくらませます。
3. リクライニング機能があれば、上体を起こして腹圧がかかるようにセッティングしましょう。ない場合は、背中に枕やクッションを挟むと上体が起きます。
4. 介助者が便器をおさえる場合は、下腹部にタオルをかけプライバシーを守ります。
5. 排尿が終わるまで横で見守ります。
終わったのち陰部を清潔にし、衣服を整えます。
6. 排泄物をトイレに流しに行き、便器を洗います。
このとき排泄物を観察し、健康状態を把握しておきましょう。
消毒液があれば消毒しておきます。
利用者が仰向けに寝た状態で便器をお尻の下に入れます。
ゴム製便器の場合は、このときに空気を入れてふくらませます。
3. リクライニング機能があれば、上体を起こして腹圧がかかるようにセッティングしましょう。ない場合は、背中に枕やクッションを挟むと上体が起きます。
4. 介助者が便器をおさえる場合は、下腹部にタオルをかけプライバシーを守ります。
5. 排尿が終わるまで横で見守ります。
終わったのち陰部を清潔にし、衣服を整えます。
6. 排泄物をトイレに流しに行き、便器を洗います。
このとき排泄物を観察し、健康状態を把握しておきましょう。
消毒液があれば消毒しておきます。
まとめ
排泄介助について解説してきましたがご理解いただけたでしょうか?
介助の手順を知ったうえでさらに利用者の排泄パターンを掴んでおくとタイミングが分かり、介助自体がしやすくなります。
また、利用者1人ひとりの状況に合わせて排泄方法を考えることで、「夜は安心して眠れるようになった」「昼は介助なしでトイレにいけるようになった」など、利用者の生活の質も変化します。
「排泄」は生理現象であり毎日の習慣です。介助するときは決して急かしたり、過剰に介助することはせず、本人に残っている能力をしっかりと見極めた上で、本当に必要な介助だけを提供してあげるよう心がけていきましょう。
介助の手順を知ったうえでさらに利用者の排泄パターンを掴んでおくとタイミングが分かり、介助自体がしやすくなります。
また、利用者1人ひとりの状況に合わせて排泄方法を考えることで、「夜は安心して眠れるようになった」「昼は介助なしでトイレにいけるようになった」など、利用者の生活の質も変化します。
「排泄」は生理現象であり毎日の習慣です。介助するときは決して急かしたり、過剰に介助することはせず、本人に残っている能力をしっかりと見極めた上で、本当に必要な介助だけを提供してあげるよう心がけていきましょう。
介護の転職なら介護ワーカー!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーがあなたの介護職デビューをサポートいたします!
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
※掲載情報は公開日あるいは2021年06月17日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.