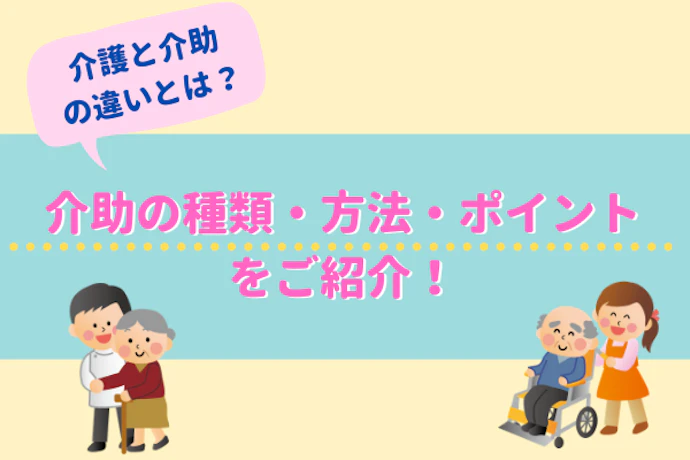介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
介護と介助は何が違う?介助の種類・方法・ポイントをご紹介!
#介護
目次
「介護」と「介助」・・・
どちらも介護業界で使われている言葉ですよね。しかし、何が違うのかまでは分からないという方は多いはず。そこで、介護と介助の違いについて解説したいと思います。
また、介助の種類や方法、押さえておきたいポイントについてもご紹介していきます。
介護の仕事を始めたばかりの方で、これから本格的な介助の作業をおこなう方や介助をやり始めた方は、ぜひ参考にしてみてください。
どちらも介護業界で使われている言葉ですよね。しかし、何が違うのかまでは分からないという方は多いはず。そこで、介護と介助の違いについて解説したいと思います。
また、介助の種類や方法、押さえておきたいポイントについてもご紹介していきます。
介護の仕事を始めたばかりの方で、これから本格的な介助の作業をおこなう方や介助をやり始めた方は、ぜひ参考にしてみてください。
「介護」と「介助」の違いについて
介護業界で働き始めたばかりの方はとくに「介護と介助の違いがあんまり分からない」という方は少なくないはず。
これから介護業界で働くのであれば、2つの違いについては知っておきたいところ。
そこで、介護と介助の違いについて説明したいと思います。
「介護」とは、一人で日常生活を送ることが困難な方に対して、生きていくために必要な日常生活全般の支援や心のサポート、自立を目指す行動すべてを指します。介護でおこなわれる支援は、身体的介助のほか生活援助や社会的援助などです。
具体的な内容は以下のようになります。
・身体的介助:利用者の身体に直接触れておこなう介助のこと。
・生活援助:家事支援(料理、洗濯、掃除、買い物など)、外出支援など、利用者の意思を尊重してその生活を支えること。
・社会的援助:介護保険を使って介護サービスや介護用品を利用すること。
「介助」とは、利用者の日常生活における行動や動作のなかで、自分ではできないことをサポートすることを指します。例えば「入浴、食事、排泄、移動、衣服の着脱など」といった生活の基本的なものです。介助は、介護を実現するために必要不可欠な手段であるといえます。
これから介護業界で働くのであれば、2つの違いについては知っておきたいところ。
そこで、介護と介助の違いについて説明したいと思います。
「介護」とは、一人で日常生活を送ることが困難な方に対して、生きていくために必要な日常生活全般の支援や心のサポート、自立を目指す行動すべてを指します。介護でおこなわれる支援は、身体的介助のほか生活援助や社会的援助などです。
具体的な内容は以下のようになります。
・身体的介助:利用者の身体に直接触れておこなう介助のこと。
・生活援助:家事支援(料理、洗濯、掃除、買い物など)、外出支援など、利用者の意思を尊重してその生活を支えること。
・社会的援助:介護保険を使って介護サービスや介護用品を利用すること。
「介助」とは、利用者の日常生活における行動や動作のなかで、自分ではできないことをサポートすることを指します。例えば「入浴、食事、排泄、移動、衣服の着脱など」といった生活の基本的なものです。介助は、介護を実現するために必要不可欠な手段であるといえます。
「介護士」と「介助士」の違いとは?
介護と介助の違いについて調べていると「介助士」という言葉を目にしたはず。
「介護士」と「介助士」にどのような違いがあるのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、介護士と介助士の違いについて見ていきましょう。
介護士とは、介護職に関わる仕事をしている方を指します。
仕事内容としては、高齢者や障害者の自宅への訪問、もしくは老人ホームやデイサービスなどの介護施設にて、入浴介助や食事介助、排泄介助、レクリエーションなどのサービスをおこないます。
介助士とは、サービス介助士と呼ばれ高齢者や障害者をサポートするうえで活用できる資格です。
サービス介助士の仕事は、高齢者や障がい者が安心して公共施設などを利用できるようにサポートすること。しかし、介護士とは違いサービス介助士の資格は「介助ができる」「介助に関する知識がある」ということの証明であるため、介護士がおこなう介助(食事や入浴など)をすることはできません。
介助士は介護士と混同されやすいですが、仕事内容や役割は大きく異なります。
「介護士」と「介助士」にどのような違いがあるのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、介護士と介助士の違いについて見ていきましょう。
<介護士>
介護士とは、介護職に関わる仕事をしている方を指します。
仕事内容としては、高齢者や障害者の自宅への訪問、もしくは老人ホームやデイサービスなどの介護施設にて、入浴介助や食事介助、排泄介助、レクリエーションなどのサービスをおこないます。
<介助士>
介助士とは、サービス介助士と呼ばれ高齢者や障害者をサポートするうえで活用できる資格です。
サービス介助士の仕事は、高齢者や障がい者が安心して公共施設などを利用できるようにサポートすること。しかし、介護士とは違いサービス介助士の資格は「介助ができる」「介助に関する知識がある」ということの証明であるため、介護士がおこなう介助(食事や入浴など)をすることはできません。
介助士は介護士と混同されやすいですが、仕事内容や役割は大きく異なります。
介護職員がおこなう介助の種類とは?介助方法・ポイントも分かりやすくご紹介!
前述したように、介護職員がおこなう介助には様々な種類があります。
なかでも、介護施設などでおこなわれている主な介助は「移乗介助」「食事介助」「歩行介助」「排泄介助」「入浴介助」の5種類です。
これから本格的に介助の仕事をおこなう方のために、介助の方法や押さえておきたいポイントを分かりやすくご紹介したいと思います。
なかでも、介護施設などでおこなわれている主な介助は「移乗介助」「食事介助」「歩行介助」「排泄介助」「入浴介助」の5種類です。
これから本格的に介助の仕事をおこなう方のために、介助の方法や押さえておきたいポイントを分かりやすくご紹介したいと思います。
『移乗介助』の方法とポイント
移乗介助といっても、介助方法はその状況により変化します。たとえば、ベッドから車いすや車いすからベッド、床からの移動など、パターンはたくさんあります。
さっそく、基本となる「ベッドから車いすへの移乗」の方法とポイントについて見ていきましょう。
【移乗介助(ベッドから車いす)の方法】
移乗介助(ベッドから車いす)の方法は以下です。
1.)挨拶
2.)利用者さんの体を小さくまとめる
3.)ベッドの脇まで水平移動させる
4.)利用者さんの体の向きを変える
5.)テコの原理を活用して上体を起き上がらせる
6.)ベッドの高さを調整する
7.)車いすの角度を調整する
8.)足の角度を調整する
9.)今から車いすに移動することを伝える
10.)掛け声とともに車いすに移乗する
11.)お尻の位置を整える
12.)移乗が終わった事を伝える
移乗介助のポイントは下記5点です。
◎上体を起こす際、持ち上げるのではなくテコの原理と遠心力を利用して回し起こす。
◎ベッドは車椅子よりもやや高くなるように調整する。
◎車椅子の角度はベッドに対して45度にする。
◎利用者さんの足をやや斜めにする。
◎前かがみの姿勢を上手く利用して体重移乗させる。
その他の移乗介助やより詳しい移乗介助の方法について知りたい方は、下記コラムをぜひご覧ください。
〇ベテラン訪問介護士が教える移乗介助マニュアル【動画付き】
〇移乗介助はもう恐くない! ベテラン介護職員が教える移乗介助のポイント
さっそく、基本となる「ベッドから車いすへの移乗」の方法とポイントについて見ていきましょう。
【移乗介助(ベッドから車いす)の方法】
移乗介助(ベッドから車いす)の方法は以下です。
1.)挨拶
2.)利用者さんの体を小さくまとめる
3.)ベッドの脇まで水平移動させる
4.)利用者さんの体の向きを変える
5.)テコの原理を活用して上体を起き上がらせる
6.)ベッドの高さを調整する
7.)車いすの角度を調整する
8.)足の角度を調整する
9.)今から車いすに移動することを伝える
10.)掛け声とともに車いすに移乗する
11.)お尻の位置を整える
12.)移乗が終わった事を伝える
【移乗介助(ベッドから車いす)のポイント】
移乗介助のポイントは下記5点です。
◎上体を起こす際、持ち上げるのではなくテコの原理と遠心力を利用して回し起こす。
◎ベッドは車椅子よりもやや高くなるように調整する。
◎車椅子の角度はベッドに対して45度にする。
◎利用者さんの足をやや斜めにする。
◎前かがみの姿勢を上手く利用して体重移乗させる。
その他の移乗介助やより詳しい移乗介助の方法について知りたい方は、下記コラムをぜひご覧ください。
〇ベテラン訪問介護士が教える移乗介助マニュアル【動画付き】
〇移乗介助はもう恐くない! ベテラン介護職員が教える移乗介助のポイント
『食事介助』の方法とポイント
食事介助のおもな方法とポイントについて見ていきましょう。
【食事介助の方法】
食事介助の方法は以下です。
<準備>
1.)今の体調をチェックする
2.)食事前に排泄をすませてもらう
3.)落ち着いて食事できる環境作りをおこなう
4.)口腔ケア・口腔体操をする
5.)手洗い(介助を受ける方も介助する方も両方)
6.)食事前の声かけ(献立の説明など)
7.)誤嚥を予防のため姿勢を整える
<食事介助>
1.)介助者は同じ目線で介助ができるように座る
2.)口の中を湿らせるため、食事の前に水分を摂ってもらう
3.)食事を提供する(一口ずつ)
4.)食事の摂取量を確認する
5.)口周り・手などを拭く
6.)口腔内のチェック・ケアをする
7.)食事内容や残った食事の量、かかった時間などの詳細を記録する
食事介助のポイントは以下5点です。
◎介助者が座る位置は介助される方の正面ではなくサイドに座る。
◎水分補給は食事前後だけではなく、食事中もこまめに補給してもらう。
◎一口の提供量は、介助用スプーンに軽く一杯くらいを目安とする。
◎スプーンは口の手前に入れ、口を閉じたタイミングでスプーンを抜く。
◎食事の時間は30分を目安にする。(かといって急かすのは禁物)
より詳しい食事介助について知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
〇食事介助のポイントと注意点-安心・美味しい・楽しい食事を-
【食事介助の方法】
食事介助の方法は以下です。
<準備>
1.)今の体調をチェックする
2.)食事前に排泄をすませてもらう
3.)落ち着いて食事できる環境作りをおこなう
4.)口腔ケア・口腔体操をする
5.)手洗い(介助を受ける方も介助する方も両方)
6.)食事前の声かけ(献立の説明など)
7.)誤嚥を予防のため姿勢を整える
<食事介助>
1.)介助者は同じ目線で介助ができるように座る
2.)口の中を湿らせるため、食事の前に水分を摂ってもらう
3.)食事を提供する(一口ずつ)
4.)食事の摂取量を確認する
5.)口周り・手などを拭く
6.)口腔内のチェック・ケアをする
7.)食事内容や残った食事の量、かかった時間などの詳細を記録する
【食事介助のポイント】
食事介助のポイントは以下5点です。
◎介助者が座る位置は介助される方の正面ではなくサイドに座る。
◎水分補給は食事前後だけではなく、食事中もこまめに補給してもらう。
◎一口の提供量は、介助用スプーンに軽く一杯くらいを目安とする。
◎スプーンは口の手前に入れ、口を閉じたタイミングでスプーンを抜く。
◎食事の時間は30分を目安にする。(かといって急かすのは禁物)
より詳しい食事介助について知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
〇食事介助のポイントと注意点-安心・美味しい・楽しい食事を-
『歩行介助』の方法とポイント
歩行介助には「見守り歩行」「寄り添い歩行」「手引き歩行」3つの種類があります。
それぞれの歩行介助の方法とポイントは以下です。
【歩行介助の方法】
歩行介助の方法は以下です。
■見守り歩行
杖などを使用しながらほとんど自力歩行できる方におこなう介助です。
1.)利用者が不安定になりやすい杖の反対側や麻痺を患っている側に立つ
2.)基本的には斜め後ろから見守る
3.)バランスを崩しそうになったら、すぐに支えられる距離を保つ
4.)階段を上るときは介助者は利用者の斜め後ろ、下りるときは斜め前に立つ(麻痺がある場合は麻痺している側に立って支える)
■寄り添い歩行
利用者に寄り添いながら歩行の介助をします。
1.)介助者は利用者の利き手とは逆側に立つ(麻痺のある利用者は、麻痺している側に立つこと)
2.)利用者の利き手が右手の場合、介助者の右手を利用者の右脇に入れ、左手は利用者の手に添える
3.)利用者のペース・歩幅に合わせて歩行する
■手引き歩行
利用者と向かい合って両手をとりながら歩行していく介助方法です。
1.)利用者と向かい合う
2.)利用者の両手が上になるよう下側から手をとる
3.)手だけでなく肘からしっかりと支える
4.)利用者の様子を確認しながら少しずつ歩行する
歩行介助のポイントを補助器具なしとありで分けてまとめてみました。
<補助器具なしの場合>
◎無理にリードせず、利用者の歩行ペースに合わせる。
◎足の運び、歩幅、リズムあわせて声掛けしながら一緒に動く。
◎歩行時の動きの特徴を把握し、ベストなポジションで介助する。
◎階段の上り下りでは、必ず片手で手すりを持ってもらう。(杖を使わない場合)
◎麻痺がある方の場合は、必ず麻痺がある側に立つ。
<補助器具ありの場合>
◎歩行器(タイヤなし)では、脇の下に軽く手を添えておく。
◎歩行器(タイヤあり)では、後方への転倒に備えて後ろから腰や両脇を支える。
より詳しく歩行介助について知りたい方は、下記のコラムもご覧ください。
〇安心・安全に歩行介助をおこなうために! ポイントと注意点をご紹介
それぞれの歩行介助の方法とポイントは以下です。
【歩行介助の方法】
歩行介助の方法は以下です。
■見守り歩行
杖などを使用しながらほとんど自力歩行できる方におこなう介助です。
1.)利用者が不安定になりやすい杖の反対側や麻痺を患っている側に立つ
2.)基本的には斜め後ろから見守る
3.)バランスを崩しそうになったら、すぐに支えられる距離を保つ
4.)階段を上るときは介助者は利用者の斜め後ろ、下りるときは斜め前に立つ(麻痺がある場合は麻痺している側に立って支える)
■寄り添い歩行
利用者に寄り添いながら歩行の介助をします。
1.)介助者は利用者の利き手とは逆側に立つ(麻痺のある利用者は、麻痺している側に立つこと)
2.)利用者の利き手が右手の場合、介助者の右手を利用者の右脇に入れ、左手は利用者の手に添える
3.)利用者のペース・歩幅に合わせて歩行する
■手引き歩行
利用者と向かい合って両手をとりながら歩行していく介助方法です。
1.)利用者と向かい合う
2.)利用者の両手が上になるよう下側から手をとる
3.)手だけでなく肘からしっかりと支える
4.)利用者の様子を確認しながら少しずつ歩行する
【歩行介助のポイント】
歩行介助のポイントを補助器具なしとありで分けてまとめてみました。
<補助器具なしの場合>
◎無理にリードせず、利用者の歩行ペースに合わせる。
◎足の運び、歩幅、リズムあわせて声掛けしながら一緒に動く。
◎歩行時の動きの特徴を把握し、ベストなポジションで介助する。
◎階段の上り下りでは、必ず片手で手すりを持ってもらう。(杖を使わない場合)
◎麻痺がある方の場合は、必ず麻痺がある側に立つ。
<補助器具ありの場合>
◎歩行器(タイヤなし)では、脇の下に軽く手を添えておく。
◎歩行器(タイヤあり)では、後方への転倒に備えて後ろから腰や両脇を支える。
より詳しく歩行介助について知りたい方は、下記のコラムもご覧ください。
〇安心・安全に歩行介助をおこなうために! ポイントと注意点をご紹介
『排泄介助』の方法とポイント
排泄介助といっても、利用者自身が歩いてトイレに行く場合の介助や基本的にベッドで過ごしている方の介助などさまざま。
排泄介助の種類は、下記4つに分けられます。
・トイレ介助
・ポータブルトイレ介助
・オムツ介助
・便器、尿器を使用する介助
それでは、排泄介助の基本となる「トイレ介助」の方法とポイントについて見ていきましょう。
【排泄介助(トイレ介助)の方法】
排泄介助(トイレ介助)の方法は以下です。
1.)排泄のタイミングをみて、トイレへの声掛けをする
2.)トイレに到着後、便座に座った際に床に足がしっかり着き安定しているかを確認する
3.)自分でできることは自分でしてもらい、できないことだけお手伝いする
4.)排泄後は声をかけてもらうか、呼び出しボタンで知らせてもらう
5.)トイレで力むと、血圧が上がってしまうことがあるため、めまいなどが起きていないか確認する(高血圧の症状がある方はとくに注意する)
6.)ズボンを上げるなど、自分できないことのみを介助する
7.)元いた場所に戻るまでしっかり見守る
移排泄介助のポイントは下記6点です。
◎できるところは自分でやってもらう。
◎排泄前後の立ち上がる際のふらつきに注意する。
◎羞恥心に気遣い、手早く対応する。
◎排泄中の待機は介助者の存在を気にせず排泄できるよう、物音を立てないよう配慮する。
◎排泄物を観察して健康状態を把握する。
◎排泄後の体調に変化が無いかを確認する。
より詳しく知りたい方、その他の排泄介助について知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
〇詳しく解説!排泄介助の基本とは?
排泄介助の種類は、下記4つに分けられます。
・トイレ介助
・ポータブルトイレ介助
・オムツ介助
・便器、尿器を使用する介助
それでは、排泄介助の基本となる「トイレ介助」の方法とポイントについて見ていきましょう。
【排泄介助(トイレ介助)の方法】
排泄介助(トイレ介助)の方法は以下です。
1.)排泄のタイミングをみて、トイレへの声掛けをする
2.)トイレに到着後、便座に座った際に床に足がしっかり着き安定しているかを確認する
3.)自分でできることは自分でしてもらい、できないことだけお手伝いする
4.)排泄後は声をかけてもらうか、呼び出しボタンで知らせてもらう
5.)トイレで力むと、血圧が上がってしまうことがあるため、めまいなどが起きていないか確認する(高血圧の症状がある方はとくに注意する)
6.)ズボンを上げるなど、自分できないことのみを介助する
7.)元いた場所に戻るまでしっかり見守る
【排泄介助(トイレ介助)のポイント】
移排泄介助のポイントは下記6点です。
◎できるところは自分でやってもらう。
◎排泄前後の立ち上がる際のふらつきに注意する。
◎羞恥心に気遣い、手早く対応する。
◎排泄中の待機は介助者の存在を気にせず排泄できるよう、物音を立てないよう配慮する。
◎排泄物を観察して健康状態を把握する。
◎排泄後の体調に変化が無いかを確認する。
より詳しく知りたい方、その他の排泄介助について知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
〇詳しく解説!排泄介助の基本とは?
『入浴介助』の方法とポイント
入浴介助は、浴室内でおこなうため危険も多く、介助者にとっては体力・注意力が必要な介助といえます。
さっそく、入浴介助の方法とポイントについて見ていきましょう。
【入浴介助の方法】
入浴介助の方法は以下です。
1.)入浴前に声かけをする(お風呂の日であることを伝えておく)
2.)洋服を脱いでもらいます
3.)滑らないよう足元に注意しながら、シャワーチェアーに腰かけてもらいます
4.)ある程度体を温めたら、頭から洗います
5.)体はボディタオルやスポンジでやさしく洗う
洗う順番:顔→首→手→足→背中→お尻→陰部
6.)汗をかきやすい部分に洗い残しがないか確認する(脇、乳房の下、肘や膝の内側など)
7.)あくまでも「できないところだけをお手伝い」する
<浴槽の出入り方法>
1.)シャワーチェアーを浴槽に横つけて、シャワーチェアーのひじ掛けを上げます(ひじ掛けがないものもある)
2.)利用者が後ろに倒れないように肩を支えながら、足を「浴槽側の足→外側の足」の順に浴槽に入れてもらいます
3.)利用者の両足が浴槽の底についたのを確認後、手すりがあればつかまって立ってもらう
4.)介助者は片足だけ浴槽に入ったうえで、利用者が後ろに倒れないよう横から支えながら、ゆっくりと座ってもらう
5.)利用者の背中が浴槽の壁につくまで支える(湯舟に浸かるまでは手すりは話さないように伝える)
※お湯に浸かる時間は5分程度(のぼせを防止するため)
6.)足を伸ばしている状態であれば曲げてもらう
7.)手すりにつかまってもらい、入る時と同様に介助者が横から重心を支えながらゆっくり立ってもらう(急に立ち上がるとふらつき転倒おそれがあるので注意が必要)
8.)入るときに使用したシャワーチェアーに座ってもらい、外側の足から順番に浴槽から出してもらう
9.)上がり湯をかけてから浴室から出る(手すりを持ってもらい、体を支えながらゆっくり歩く)
<入浴後>
1.)血圧の変動でふらついてしまうこともあるため、タオルをひいた椅子に座って身体を拭き、着替えてもらう
2.)皮膚科で処方されている軟膏や保湿剤があれば、入浴後の皮膚がきれいになったタイミングで塗る
入浴介助のポイントは下記6点です。
◎滑る危険があるため必ずゆっくり動作してもらう。
◎絶対に目を離さないこと。
◎立ち上がる、座るの動作をしたら気分を聞く。
◎全身を確認する。(皮膚の腫れ、発疹、傷、出血などの異常がないか)
◎湯舟に浸かる時間は5分程度にとどめる。
◎気分が悪くなりやすい空腹時や食事直後の入浴は避ける。
さっそく、入浴介助の方法とポイントについて見ていきましょう。
【入浴介助の方法】
入浴介助の方法は以下です。
1.)入浴前に声かけをする(お風呂の日であることを伝えておく)
2.)洋服を脱いでもらいます
3.)滑らないよう足元に注意しながら、シャワーチェアーに腰かけてもらいます
4.)ある程度体を温めたら、頭から洗います
5.)体はボディタオルやスポンジでやさしく洗う
洗う順番:顔→首→手→足→背中→お尻→陰部
6.)汗をかきやすい部分に洗い残しがないか確認する(脇、乳房の下、肘や膝の内側など)
7.)あくまでも「できないところだけをお手伝い」する
<浴槽の出入り方法>
1.)シャワーチェアーを浴槽に横つけて、シャワーチェアーのひじ掛けを上げます(ひじ掛けがないものもある)
2.)利用者が後ろに倒れないように肩を支えながら、足を「浴槽側の足→外側の足」の順に浴槽に入れてもらいます
3.)利用者の両足が浴槽の底についたのを確認後、手すりがあればつかまって立ってもらう
4.)介助者は片足だけ浴槽に入ったうえで、利用者が後ろに倒れないよう横から支えながら、ゆっくりと座ってもらう
5.)利用者の背中が浴槽の壁につくまで支える(湯舟に浸かるまでは手すりは話さないように伝える)
※お湯に浸かる時間は5分程度(のぼせを防止するため)
6.)足を伸ばしている状態であれば曲げてもらう
7.)手すりにつかまってもらい、入る時と同様に介助者が横から重心を支えながらゆっくり立ってもらう(急に立ち上がるとふらつき転倒おそれがあるので注意が必要)
8.)入るときに使用したシャワーチェアーに座ってもらい、外側の足から順番に浴槽から出してもらう
9.)上がり湯をかけてから浴室から出る(手すりを持ってもらい、体を支えながらゆっくり歩く)
<入浴後>
1.)血圧の変動でふらついてしまうこともあるため、タオルをひいた椅子に座って身体を拭き、着替えてもらう
2.)皮膚科で処方されている軟膏や保湿剤があれば、入浴後の皮膚がきれいになったタイミングで塗る
【入浴介助のポイント】
入浴介助のポイントは下記6点です。
◎滑る危険があるため必ずゆっくり動作してもらう。
◎絶対に目を離さないこと。
◎立ち上がる、座るの動作をしたら気分を聞く。
◎全身を確認する。(皮膚の腫れ、発疹、傷、出血などの異常がないか)
◎湯舟に浸かる時間は5分程度にとどめる。
◎気分が悪くなりやすい空腹時や食事直後の入浴は避ける。
さいごに
介助は、介護を実現するうえで必要不可欠な手立てです。
利用者が、その人らしい日常生活を送るためには適切な介助をおこなうことが重要となります。これから本格的に介助をおこなう初心者の方は、上記で紹介した基本的な介助方法とポイントをしっかりと押さえて、実践に役立ててみてください。
介助には危険が伴うため、初めのうちは必ず先輩に指導してもらいながら介助をおこなってくださいね。
利用者が、その人らしい日常生活を送るためには適切な介助をおこなうことが重要となります。これから本格的に介助をおこなう初心者の方は、上記で紹介した基本的な介助方法とポイントをしっかりと押さえて、実践に役立ててみてください。
介助には危険が伴うため、初めのうちは必ず先輩に指導してもらいながら介助をおこなってくださいね。
※掲載情報は公開日あるいは2021年06月17日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.