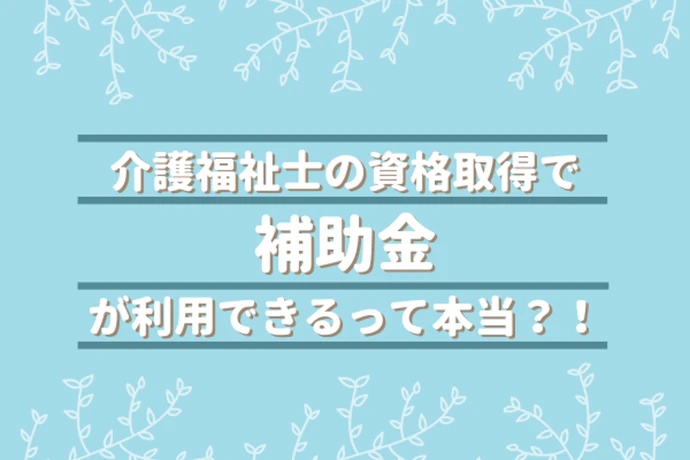介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
介護福祉士の資格取得で“補助金”が利用できるって本当?!
#介護
目次
介護福祉士の資格取得に、国や自治体から補助金や給付金を利用できることを知っていますか?
介護職が不足していると言われている今、介護業界での人材確保やキャリアアップの促進を図るため、介護の資格取得を支援する取り組みが国や自治体で積極的におこなわれています。介護に関わる資格のなかでも、国家資格である「介護福祉士」はキャリアアップを考えるのであれば、目指すべき資格といえます。そこで、これから介護福祉士の取得を考えている方のために、資格取得の際に利用できる補助金や給付金についてご紹介したいと思います。
介護職が不足していると言われている今、介護業界での人材確保やキャリアアップの促進を図るため、介護の資格取得を支援する取り組みが国や自治体で積極的におこなわれています。介護に関わる資格のなかでも、国家資格である「介護福祉士」はキャリアアップを考えるのであれば、目指すべき資格といえます。そこで、これから介護福祉士の取得を考えている方のために、資格取得の際に利用できる補助金や給付金についてご紹介したいと思います。
「介護福祉士」の取得にかかる費用はどれくらい?
介護福祉士の取得を考えたとき、まず気になるのは費用のことではないでしょうか?
国家資格である介護福祉士の資格取得には、どのくらいの費用が必要なのか分からない方も少なくないはず。まずは、取得にかかる費用について見ていきましょう。
介護福祉士の資格取得にかかる費用は、取得するルートによって異なります。
介護福祉士の取得を目指せるのは、以下4つのルートです。
・養成施設ルート
・実務経験ルート
・福祉系高校ルート
・経済連携協定(EPA)ルート
資格取得にかかる費用は、国家試験の受験費用である1万5300円のほか、どのルートを選択するのかによって大きく違ってきます。
これから介護職として働くことを考えている方や、キャリアアップのために取得を考えている方は、養成施設ルートもしくは実務経験ルートで介護福祉士資格を目指すことがほとんどです。そこで、養成施設ルートと実務経験ルートでかかる費用を見ていきましょう。
国家資格である介護福祉士の資格取得には、どのくらいの費用が必要なのか分からない方も少なくないはず。まずは、取得にかかる費用について見ていきましょう。
介護福祉士の資格取得にかかる費用は、取得するルートによって異なります。
介護福祉士の取得を目指せるのは、以下4つのルートです。
・養成施設ルート
・実務経験ルート
・福祉系高校ルート
・経済連携協定(EPA)ルート
資格取得にかかる費用は、国家試験の受験費用である1万5300円のほか、どのルートを選択するのかによって大きく違ってきます。
これから介護職として働くことを考えている方や、キャリアアップのために取得を考えている方は、養成施設ルートもしくは実務経験ルートで介護福祉士資格を目指すことがほとんどです。そこで、養成施設ルートと実務経験ルートでかかる費用を見ていきましょう。
養成施設ルートでかかる費用について
養成施設ルートでは「介護福祉士養成施設(専門学校等)」「福祉系大学等」「社会福祉養成施設等」「保育士養成施設等」の4つにさらにルートが分かれます。
そのため、資格取得までにかかる費用は、専門学校や大学など通う学校によっても大きく異なります。養成施設ルートで必要になる費用は、学費+国家試験受験費用(1万5300円)です。
必要となる学費の平均金額は以下となっています。
そのため、資格取得までにかかる費用は、専門学校や大学など通う学校によっても大きく異なります。養成施設ルートで必要になる費用は、学費+国家試験受験費用(1万5300円)です。
必要となる学費の平均金額は以下となっています。
・養成施設(専門学校):約80万~200万円
・4年制大学:約400万円前後
・短期大学:約200万円前後
・4年制大学:約400万円前後
・短期大学:約200万円前後
実務経験ルートでかかる費用について
実務経験ルートでは、実務者研修を受講するまでに取得している資格によってかかる費用が異なります。実務経験ルートで必要になる費用は、実務者研修の受講料+国家試験受験費用(1万5300円)です。
持っている資格によってかかる受講料の平均額は以下です。
持っている資格によってかかる受講料の平均額は以下です。
・無資格:13~20万円ほど
・介護職員基礎研修修:3~5万円ほど
・介護職員初任者研修、ホームヘルパー2級:9~18万円ほど
・ホームヘルパー1級:7万円前後
・介護職員基礎研修修:3~5万円ほど
・介護職員初任者研修、ホームヘルパー2級:9~18万円ほど
・ホームヘルパー1級:7万円前後
実務者研修の受講までに取得している資格によっては、受講料だけでなく受講科目も免除されます。そのため、短期間で受講を修了することが可能です。
介護福祉士の資格取得にかかる費用をなるべく抑えたいと考えている方は、実務経験ルートから介護福祉士を目指すと取得にかかる費用は養成施設ルートより少なく済みます。
しかし、実務経験ルートでも無資格で取得を目指すと多い場合は約20万円の費用が必要です。金額を見て、資格の取得を諦めようかと考えた方もいるのではないでしょうか?
そんな方は次を見てみてください。
介護福祉士の資格取得にかかる費用をなるべく抑えたいと考えている方は、実務経験ルートから介護福祉士を目指すと取得にかかる費用は養成施設ルートより少なく済みます。
しかし、実務経験ルートでも無資格で取得を目指すと多い場合は約20万円の費用が必要です。金額を見て、資格の取得を諦めようかと考えた方もいるのではないでしょうか?
そんな方は次を見てみてください。
介護福祉士の資格取得で利用できる補助金・給付金制度とは?
介護福祉士の資格取得を目指す場合、最もお得に資格を取得できるのが実務経験ルートです。それでも無資格の場合、実務者研修を受講するスクールによっては20万円近くの費用が必要となってしまいます。
介護福祉士の資格取得を考えていた方も取得にかかる費用を見ると、
「受講費用が高いから取得を諦めようかな」
「思っていたより高額で取得を迷ってしまう」
「今の給料で生活がギリギリなのに払えないかも・・・」
と思う方は少なくないはず。
そんな方におすすめしたいのが、介護資格を取得するために利用できる“補助金・給付金制度”を活用することです!
介護福祉士の資格を取得するために利用できる補助金・給付金の制度は大きく分けて2つ。
「教育訓練給付制度(教育訓練給付金)」と「求職者支援制度(職業訓練受講給付金)」です。
【教育訓練給付制度(教育訓練給付金)とは】
教育訓練給付制度とは、雇用保険の失業等給付の一つで、所定の要件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講・修了した場合、
教育訓練給付制度は「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分かれており、教育訓練給付金の支給額はそれぞれ受講する教育訓練によって異なります。
※教育訓練給付制度についての詳細は、厚生労働省のホームページよりご確認ください。
【求職者支援制度(職業訓練受講給付金)とは】
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。一定の要件を満たすことで
求職者支援制度は、「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を
それぞれの訓練で受給できる給付額や給付条件などについて見ていきましょう。
※職業訓練受講給付金についての詳細は、厚生労働省の「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」にてご確認ください。
介護福祉士の資格取得を考えていた方も取得にかかる費用を見ると、
「受講費用が高いから取得を諦めようかな」
「思っていたより高額で取得を迷ってしまう」
「今の給料で生活がギリギリなのに払えないかも・・・」
と思う方は少なくないはず。
そんな方におすすめしたいのが、介護資格を取得するために利用できる“補助金・給付金制度”を活用することです!
介護福祉士の資格を取得するために利用できる補助金・給付金の制度は大きく分けて2つ。
「教育訓練給付制度(教育訓練給付金)」と「求職者支援制度(職業訓練受講給付金)」です。
【教育訓練給付制度(教育訓練給付金)とは】
教育訓練給付制度とは、雇用保険の失業等給付の一つで、所定の要件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講・修了した場合、
教育訓練施設に支払った費用の一部が支給される制度
です。教育訓練給付制度は「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分かれており、教育訓練給付金の支給額はそれぞれ受講する教育訓練によって異なります。
※教育訓練給付制度についての詳細は、厚生労働省のホームページよりご確認ください。
【求職者支援制度(職業訓練受講給付金)とは】
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。一定の要件を満たすことで
訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給できます。
求職者支援制度は、「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を
無料(テキスト代などは自己負担)で受講することが可能
です。それぞれの訓練で受給できる給付額や給付条件などについて見ていきましょう。
※職業訓練受講給付金についての詳細は、厚生労働省の「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」にてご確認ください。
『一般教育訓練の教育訓練給付金』について
一般教育訓練給付金とは、働く人が持っている能力を発見し、その能力をより一層高めることへの取組みや長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練受講のために支払った費用の一部を支給するものです。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
【支給対象者】
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は以下の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
受講開始日において被保険者ではなく、被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)から1年以内であり、支給要件期間が3年以上であること。
【支給額】
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練の受講で支払った費用の20%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は10万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
一般教育訓練給付金の支給申請をする場合は、需給資格の有無や受講希望の一般教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は以下の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
受講開始日において被保険者ではなく、被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)から1年以内であり、支給要件期間が3年以上であること。
【支給額】
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練の受講で支払った費用の20%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は10万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
【注意点】
一般教育訓練給付金の支給申請をする場合は、需給資格の有無や受講希望の一般教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
『特定一般教育訓練の教育訓練給付金』について
特定一般教育訓給付金とは、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に役立つ教育訓練を受けた場合に、教育訓練受講のために支払った費用の一部を支給するものです。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
【支給対象者】
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)
のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
特定一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
【支給額】
特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練の受講で支払った費用の40%が支給されます。ただし、給付金の支給上限額は20万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
特定一般教育訓練給付金の支給申請をする場合は、需給資格の有無や受講希望の特定一般教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
また、特定一般教育訓練給付金を受給するには、受講開始日の1カ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、早めの手続きが必要です。
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)
のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
特定一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
【支給額】
特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練の受講で支払った費用の40%が支給されます。ただし、給付金の支給上限額は20万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
【注意点】
特定一般教育訓練給付金の支給申請をする場合は、需給資格の有無や受講希望の特定一般教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
また、特定一般教育訓練給付金を受給するには、受講開始日の1カ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、早めの手続きが必要です。
『専門実践教育訓練の教育訓練給付金』について
専門実践教育訓練給付金とは、働く本人の意思・判断による中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練受講のために支払った費用の一部を支給するものです。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講、修了した場合にハローワークから支給されます。
【支給対象者】
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)
のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
特定一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
【支給額】
専門実践教育訓練給付金の支給は、専門実践教育訓練を“受講している間”と“修了した場合”にハローワークから支給されます。
[専門実践教育訓練の受講中]
教育訓練の受講で支払った費用の50%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は120万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
[専門実践教育訓練の修了後]
資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練の受講で支払った費用の70%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は168万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
※上記の上限金額は、訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額です。
訓練期間が1年や2年の場合は上限額も異なり、上記上限額の1/3(訓練期間1年)、2/3(訓練期間2年)となります。
専門実践教育訓練給付金の支給申請をする場合は、受給資格の有無や受講希望の専門実践教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
また、専門実践教育訓練給付を受給するには、受講開始日の1カ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、早めの手続きが必要です。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)
のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の被保険者で支給要件期間が3年以上ある方
特定一般教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者であって支給要件期間が3年以上あること。
(2)雇用保険の被保険者ではなく資格喪失日から1年以内かつ3年以上の支給要件期間がある方
【支給額】
専門実践教育訓練給付金の支給は、専門実践教育訓練を“受講している間”と“修了した場合”にハローワークから支給されます。
[専門実践教育訓練の受講中]
教育訓練の受講で支払った費用の50%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は120万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
[専門実践教育訓練の修了後]
資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練の受講で支払った費用の70%が支給されます。
ただし、給付金の支給上限額は168万円とし、4千円未満の場合は教育訓練給付金は支給されません。
※上記の上限金額は、訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額です。
訓練期間が1年や2年の場合は上限額も異なり、上記上限額の1/3(訓練期間1年)、2/3(訓練期間2年)となります。
【注意点】
専門実践教育訓練給付金の支給申請をする場合は、受給資格の有無や受講希望の専門実践教育訓練講座が給付制度の対象となっているかなど、条件を満たしているか事前にハローワークに問い合わせて確認しておきましょう。
また、専門実践教育訓練給付を受給するには、受講開始日の1カ月前までに「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、早めの手続きが必要です。
『職業訓練受講給付金(求職者支援訓練・公共職業訓練)』について
職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示によって職業訓練を受講し、一定要件を満たすことで訓練期間中の生活を支援するために支給されるものです。
【支給要件】
職業訓練受講給付金の支給要件は、以下7つの項目すべてを満たす方が対象となります。
(1)本人の収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月 25 万円以下
(3)世帯全体の金融資産が 300 万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)
(6)同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
【支給額】
職業訓練受講給付金は「職業訓練受講手当」と「通所手当」が支給されます。
それぞれの支給額は以下です。
・職業訓練受講手当:10万円(月額)
・通所手当:職業訓練実施施設までの交通費(上限額あり)
※最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所方法・経路による交通費額となります。
支援の対象となる方でも、必ず職業訓練受講給付金を受給できるというわけではありません。また、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否したりすると、給付金が不支給となります。さらには、これを繰り返すと訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。
職業訓練受講給付金の支給要件は、以下7つの項目すべてを満たす方が対象となります。
(1)本人の収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月 25 万円以下
(3)世帯全体の金融資産が 300 万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)
(6)同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
【支給額】
職業訓練受講給付金は「職業訓練受講手当」と「通所手当」が支給されます。
それぞれの支給額は以下です。
・職業訓練受講手当:10万円(月額)
・通所手当:職業訓練実施施設までの交通費(上限額あり)
※最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所方法・経路による交通費額となります。
【注意点】
支援の対象となる方でも、必ず職業訓練受講給付金を受給できるというわけではありません。また、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否したりすると、給付金が不支給となります。さらには、これを繰り返すと訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。
介護福祉士の資格取得で利用できる「貸付金制度」について
上記給付金の対象とならない方や働きながら資格取得を目指したい方は、貸付金制度の利用がおすすめです。介護福祉士の資格取得で利用できる貸付制度をご紹介したいと思います。
『介護福祉士修学資金貸付制度』について
介護福祉士修学資金貸付制度とは、介護福祉士養成施設に在学している方、またはこれから在学しようと考えている方に対して、介護福祉士の資格取得をサポートするための制度です。
【対象者】
修学資金の対象は、介護福祉士養成施設(養成校を含む)に在学中、またはこれから在学する方で介護福祉士の資格取得を目指す方です。
【貸付金額】
修学資金の貸付金額は以下です。
在学期間中:月5万円(授業料、教材費、交通費、介護福祉士試験受験手数料などの費用)
入学準備金:20万円
就職準備金:20万円
国家試験受験対策費用:年4万円
生活費加算:加算あり
【介護福祉士修学資金の利用条件】
介護福祉士修学資金の利用条件は、以下の通り。
・介護福祉士養成施設に在学している方。
・下記(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、養成施設卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就く予定の方
(2)貸付を受けようとする都道府県内の養成施設の学生であって、卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就く予定の方
(3)養成施設での修学のために転居をした方で、転居する前年度の住民登録を貸付を受けようとする都道府県にしていて、かつ、卒業後は転居前の都道府県内(貸付を受けようとする都道府県内)において介護の仕事に就く予定の方
養成施設の卒業日から1年以内に介護福祉士の資格を取得し登録をすること。
そして、介護福祉士の資格取得後、その都道府県内で5年間介護の業務に従事することで貸付金の返還が全額免除されます。
修学資金の対象は、介護福祉士養成施設(養成校を含む)に在学中、またはこれから在学する方で介護福祉士の資格取得を目指す方です。
【貸付金額】
修学資金の貸付金額は以下です。
在学期間中:月5万円(授業料、教材費、交通費、介護福祉士試験受験手数料などの費用)
入学準備金:20万円
就職準備金:20万円
国家試験受験対策費用:年4万円
生活費加算:加算あり
【介護福祉士修学資金の利用条件】
介護福祉士修学資金の利用条件は、以下の通り。
・介護福祉士養成施設に在学している方。
・下記(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、養成施設卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就く予定の方
(2)貸付を受けようとする都道府県内の養成施設の学生であって、卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就く予定の方
(3)養成施設での修学のために転居をした方で、転居する前年度の住民登録を貸付を受けようとする都道府県にしていて、かつ、卒業後は転居前の都道府県内(貸付を受けようとする都道府県内)において介護の仕事に就く予定の方
【貸付金返還の免除について】
養成施設の卒業日から1年以内に介護福祉士の資格を取得し登録をすること。
そして、介護福祉士の資格取得後、その都道府県内で5年間介護の業務に従事することで貸付金の返還が全額免除されます。
※貸付の実施の有無や利用条件など詳細については、各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせ、またはホームページにてご確認ください。
『介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度』について
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度とは、介護業務の実務経験が3年以上ある方を対象とした介護福祉士の資格取得をサポートするための制度です。
【対象者】
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の対象者は、3年の実務経験があり実務者研修を受講し介護福祉士の資格取得を目指す方が対象です。
【貸付金額】
介護福祉士実務者研修受講資金の貸付金額は、最大20万円(実務者研修の受講費用、参考図書などの費用)です。
【介護福祉士実務者研修受講資金の利用条件】
介護福祉士実務者研修受講資金の利用条件は以下の通りです。
・実務者研修施設に在学している方
・下記(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、卒業後に当該都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
(2)貸付を受けようとする都道府県内の実務者研修施設の学生であって、卒業後に当該施設が所在する都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
(3)実務者研修施設の学生となる前年度に貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、実務者研修施設での修学のため転居をしたものであって、卒業後に転居前の都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
養成施設の卒業日から1年以内に介護福祉士の資格を取得し登録をすること。
そして、介護福祉士の資格取得後、その都道府県内で2年間介護の業務に従事することで貸付金の返還が全額免除されます。
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の対象者は、3年の実務経験があり実務者研修を受講し介護福祉士の資格取得を目指す方が対象です。
【貸付金額】
介護福祉士実務者研修受講資金の貸付金額は、最大20万円(実務者研修の受講費用、参考図書などの費用)です。
【介護福祉士実務者研修受講資金の利用条件】
介護福祉士実務者研修受講資金の利用条件は以下の通りです。
・実務者研修施設に在学している方
・下記(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、卒業後に当該都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
(2)貸付を受けようとする都道府県内の実務者研修施設の学生であって、卒業後に当該施設が所在する都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
(3)実務者研修施設の学生となる前年度に貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、実務者研修施設での修学のため転居をしたものであって、卒業後に転居前の都道府県内において介護の業務に従事しようとする方
【貸付金返還の免除について】
養成施設の卒業日から1年以内に介護福祉士の資格を取得し登録をすること。
そして、介護福祉士の資格取得後、その都道府県内で2年間介護の業務に従事することで貸付金の返還が全額免除されます。
※貸付の実施の有無や利用条件など詳細については、各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせ、またはホームページにてご確認ください。
さいごに
介護福祉士の資格取得は、国や自治体の支援によって普通に取得するよりも費用を抑えて取得することが可能です。
上記で紹介した制度は、仕事を辞めて取得を目指すのか、仕事をしながら取得を目指すのかによって、利用できる補助金制度は異なってきます。まずは、自分が住んでいる自治体でどの制度が実施されているのか、また利用条件や給付額などを調べてみてください。
上手く制度を利用し、お得に資格を取得してキャリアアップを目指してみてはいかかでしょうか。
上記で紹介した制度は、仕事を辞めて取得を目指すのか、仕事をしながら取得を目指すのかによって、利用できる補助金制度は異なってきます。まずは、自分が住んでいる自治体でどの制度が実施されているのか、また利用条件や給付額などを調べてみてください。
上手く制度を利用し、お得に資格を取得してキャリアアップを目指してみてはいかかでしょうか。
介護職での転職をお考えの方へ!
「資格を取って介護職に転職したい」
「介護職のスキルをつけたい」
などお考えの方は、ぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
★アドバイザーに相談する(無料)
「介護職のスキルをつけたい」
などお考えの方は、ぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
★アドバイザーに相談する(無料)
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月11日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.