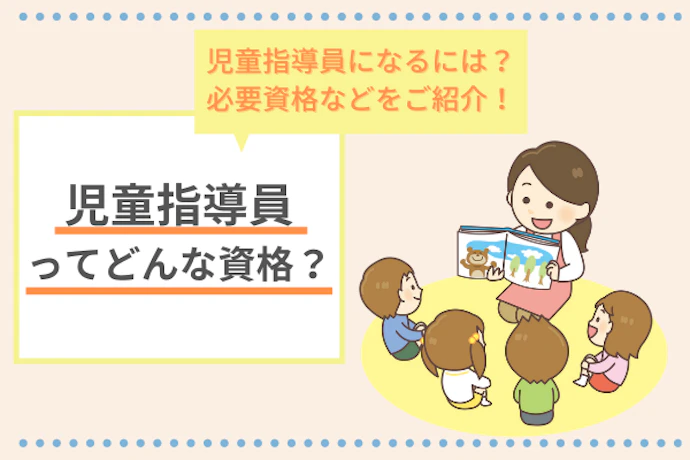介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
児童指導員ってどんな資格?!取得方法や仕事内容について紹介!
#介護
福祉の仕事である「児童指導員」とはどんな仕事なのでしょうか?
児童指導員という職業に興味がある方のために、資格の取得方法から仕事内容までご紹介したいと思います。
児童指導員という職業に興味がある方のために、資格の取得方法から仕事内容までご紹介したいと思います。
児童指導員とは?
児童指導員とは、児童福祉施設で暮らす子どもたちや発達障がいなどの障がいを抱える子どもたちの生活全般のサポート、また自立した生活に向けた訓練などを実施する職業です。
児童福祉施設で暮らす子どもたちの親に代わり、生活環境の整備や生活指導、子供たち相談に乗るなど、健全に成長できるようにサポートしていきます。
児童福祉施設で暮らす子どもたちの親に代わり、生活環境の整備や生活指導、子供たち相談に乗るなど、健全に成長できるようにサポートしていきます。
児童指導員の仕事内容とは?
児童指導員の仕事は、子どもたちの生活全般のサポートをおこなうことです。
しかし、生活のサポートといってもどのような仕事内容なのか分かりにくいですよね。そこで、一般的におこなう児童指導員の仕事内容を紹介したいと思います。
一般的な児童指導員の仕事内容は以下です。
しかし、生活のサポートといってもどのような仕事内容なのか分かりにくいですよね。そこで、一般的におこなう児童指導員の仕事内容を紹介したいと思います。
一般的な児童指導員の仕事内容は以下です。
〇子どもたちに対する生活指導計画の作成や会議の運営
〇子どもへのしつけなど生活指導
〇障がいを抱える子どもたちの療育
〇ケースワーク
〇児童相談所や学校との連絡
〇子どもの引き取りなどに関する保護者との面談
〇内部の連絡や調整
〇周囲との調整
など
〇子どもへのしつけなど生活指導
〇障がいを抱える子どもたちの療育
〇ケースワーク
〇児童相談所や学校との連絡
〇子どもの引き取りなどに関する保護者との面談
〇内部の連絡や調整
〇周囲との調整
など
児童指導員は、0〜18歳までの施設で暮らす子どもたちの保護者に代わって、生活全般の指導をおこないます。
例えば、子どもたちに起床や食事、入浴、就寝の時間を指導し、健全な生活リズムを身につけさせること、また基本的な挨拶や礼儀、食事の作法などのしつけや勉強のフォローなどです。指導といっても、一般家庭と同じように子どもたちと遊んだり食事をしたり、生活をしながら見守っていきます。
生活指導以外の業務は、生活指導計画の作成や日々の活動記録などのデスクワークや関係施設(学校や児童相談所など)との連絡業務、子どもの保護者との面談など。また施設によっては、食事の配膳や後片付け、施設の掃除や洗濯といった家事業務をおこなう場合もあります。生活指導以外の業務のなかでも、子ども引き取りに関わる保護者との面談は、子どもの将来がかかっているためとても重要な仕事です。
さらに、児童指導員の仕事内容は勤務する施設で異なります。
たとえば、障がい児入所施設の場合であれば、子どもたちの食事や入浴、排せつなどの介護業務、通所型施設の場合であれば、子どもたちの送迎業務など働く施設によって仕事内容は多岐に渡ります。
「時には厳しく、時には優しく包み込み、見守りながら子どもたちの生活を支え、子どもたちが巣立ったあと自立した社会生活を送れるように、保護者に代わって育てていくこと」が児童指導員に求められる役割であるといえます。
児童指導員が働ける職場とは?
児童指導員が働いている職場といえば、児童養護施設を思い浮かべる方は多いはず。
しかし、児童指導員として活躍できる職場は養護施設以外にもたくさんあります。そこで、児童指導員が働けるおもな職場をご紹介したいと思います。
児童指導員が活躍している職場は以下です。
・児童養護施設
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・福祉型児童発達支援センター
・医療型児童発達支援センター
・児童家庭支援センター
・情緒障害児短期治療施設
・乳児院
児童指導員は、働く施設によってかかわる子どもが抱えている問題などが異なってきます。そのため、仕事内容もそれぞれの施設によって求められる専門性が違ってきます。転職前に、子供たちとどのようにかかわりたいのかを考えて働く施設の種類を決めるとよいでしょう。
しかし、児童指導員として活躍できる職場は養護施設以外にもたくさんあります。そこで、児童指導員が働けるおもな職場をご紹介したいと思います。
児童指導員が活躍している職場は以下です。
・児童養護施設
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・福祉型児童発達支援センター
・医療型児童発達支援センター
・児童家庭支援センター
・情緒障害児短期治療施設
・乳児院
児童指導員は、働く施設によってかかわる子どもが抱えている問題などが異なってきます。そのため、仕事内容もそれぞれの施設によって求められる専門性が違ってきます。転職前に、子供たちとどのようにかかわりたいのかを考えて働く施設の種類を決めるとよいでしょう。
児童指導員に資格は必要?
児童指導員は、何か資格を取得しなければ働けない職業ではありません。
しかし、児童指導員として働くには「児童指導員任用資格」を得る必要があります。この資格は国家資格や民間資格などのように勉強し受験に合格して得られる資格とは異なり、資格要件に該当していれば無試験で「任用資格」を取得することが可能です。
では「どのように任用資格を取得すればいいのか?」について、次でご紹介していきます。
しかし、児童指導員として働くには「児童指導員任用資格」を得る必要があります。この資格は国家資格や民間資格などのように勉強し受験に合格して得られる資格とは異なり、資格要件に該当していれば無試験で「任用資格」を取得することが可能です。
では「どのように任用資格を取得すればいいのか?」について、次でご紹介していきます。
児童指導員任用資格の取得方法
児童指導員任用資格の取得方法について見ていきましょう。
児童指導員任用資格の資格要件は、大学や大学院の学部を卒業していることや所定の資格を取得していること、または実務経験を問われるなど全部で10項目あります。
以下は児童指導員任用資格の資格要件です。下記のいずれかに該当することで児童指導員として働くことが可能となります。
児童指導員任用資格の資格要件は、大学や大学院の学部を卒業していることや所定の資格を取得していること、または実務経験を問われるなど全部で10項目あります。
以下は児童指導員任用資格の資格要件です。下記のいずれかに該当することで児童指導員として働くことが可能となります。
■都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
■社会福祉士の資格を有する者
■精神保健福祉士の資格を有する者
■学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
■学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
■教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
■三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
■社会福祉士の資格を有する者
■精神保健福祉士の資格を有する者
■学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
■学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
■学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
■教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
■三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
引用:厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条」
上記要件のいずれかを満たしていれば、公立の施設の場合は公務員試験、私立の施設の場合は各施設の採用試験を受け合格することで、児童指導員として働くことができます。
資格要件にある、養成施設や大学、資格、教員免許などが無くても、実務経験ルートで児童指導員を目指すことができるため、他業種から転職する方は多くいます。
とくに、障がい児入所施設などでは介護業務が含まれることもあるため、介護職で得たスキルを活かして児童指導員に転職し活躍している方は少なくありません。
上記要件のいずれかを満たしていれば、公立の施設の場合は公務員試験、私立の施設の場合は各施設の採用試験を受け合格することで、児童指導員として働くことができます。
資格要件にある、養成施設や大学、資格、教員免許などが無くても、実務経験ルートで児童指導員を目指すことができるため、他業種から転職する方は多くいます。
とくに、障がい児入所施設などでは介護業務が含まれることもあるため、介護職で得たスキルを活かして児童指導員に転職し活躍している方は少なくありません。
児童指導員の給与っていくら?
児童指導員の仕事に転職するとなると気になるのが給与額ではないでしょうか?
そこで、児童指導員の給与額について弊社独自に調査してみました。さっそく見ていきましょう。
児童指導員の平均年収額は、正社員で約300万円。月給に換算すると平均月給額は約20万円(基本給+各種手当)です。賞与は年2回、約3カ月分という施設が一般的。
パートやアルバイトの時給額は900円~1200円ほどが多い傾向にあり、働く地域によって給与にも差がありました。
また児童指導員の給与額は、働く施設の運営が公立なのか私立なのか、また施設のサービス種類によっても給与額は大きく異なってきます。児童指導員に転職し稼ぎたいと思っている方は、任用資格を取得したあと公務員試験を受け、公務員として公立の施設で働くことをおすすめします。
そこで、児童指導員の給与額について弊社独自に調査してみました。さっそく見ていきましょう。
児童指導員の平均年収額は、正社員で約300万円。月給に換算すると平均月給額は約20万円(基本給+各種手当)です。賞与は年2回、約3カ月分という施設が一般的。
パートやアルバイトの時給額は900円~1200円ほどが多い傾向にあり、働く地域によって給与にも差がありました。
また児童指導員の給与額は、働く施設の運営が公立なのか私立なのか、また施設のサービス種類によっても給与額は大きく異なってきます。児童指導員に転職し稼ぎたいと思っている方は、任用資格を取得したあと公務員試験を受け、公務員として公立の施設で働くことをおすすめします。
さいごに
児童指導員として働くには任用資格が必要ですが、2~3年の実務経験が認められれば任用資格を取得することが可能です。介護職のスキルを活かすのであれば、障がいを抱える子どもたちがいる施設を選ぶのもよいかもしれません。
児童指導員は、さまざまな家庭環境や問題を抱える子供たちに寄り添いサポートしていく仕事です。そのため「子供が好き」という気持ちが最も必要となります。0歳から18歳までの子どもたちと触れ合い、健やかに育つようサポートしていく児童指導員は、優しく時には厳しく母親のように愛情を注げる方に向いている仕事といえます。
児童指導員は、さまざまな家庭環境や問題を抱える子供たちに寄り添いサポートしていく仕事です。そのため「子供が好き」という気持ちが最も必要となります。0歳から18歳までの子どもたちと触れ合い、健やかに育つようサポートしていく児童指導員は、優しく時には厳しく母親のように愛情を注げる方に向いている仕事といえます。
介護職で転職をお考えの方へ!
「資格を取って児童指導員に転職したい」
「介護職のスキルを活かしたい」
などお考えの方はぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
★アドバイザーに相談する(無料)
「介護職のスキルを活かしたい」
などお考えの方はぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
★アドバイザーに相談する(無料)
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月11日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.