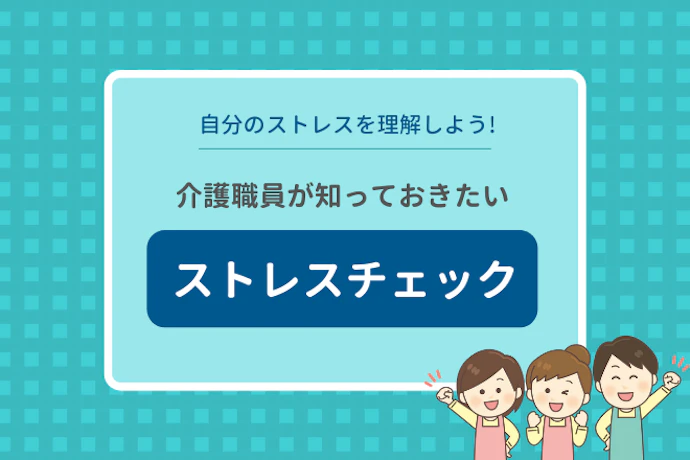介護コラム
公開日:2023.11.15
更新日:2023.11.15
介護職員が知っておきたい!ストレスチェックで悪化を回避!
#介護
目次
それは自分では気付いていないストレスが少しずつ積み重なっているのが原因かもしれません。
介護職はストレスの多い仕事といわれています。
気付かぬ内に悪化して、心身に悪影響を受けている介護従事者もいるでしょう。
そんな中で「ストレスチェック」を実施するなど、職員のメンタルヘルスケアに力を入れている事業所もあります。
本コラムでは、ストレスチェックについて解説しています。
もしあなたの職場で実施されていない場合でも、個人でストレス度合いをチェックして把握することは可能です。
自身の状態を把握し、積み重なったストレスをしっかり解消していきましょう。
<介護職のストレス原因・対処法についてはこちら>
コラム「介護職のストレスの原因とは?「もう限界!」になる前の対処法」
介護職のストレスチェックとは?
ストレスに関する質問シートに労働者が回答し、各自のストレス度合いや心の状態を調べます。
50人以上の労働者がいる事業所では年に一回ストレスチェックを実施する必要があり、50人未満の事業所は現状では努力義務とされています。
この労働者50人以上には、正社員だけでなくパートタイマーも含まれます。
また介護業界に限ったものではなく、全ての産業が対象です。
ストレスチェックの対象者
下記の基準に該当する労働者が対象となっています。
・無期雇用契約の労働者、またはこれまでの契約期間が1年以上あり、今後1年以上の雇用が見込まれる労働者であること
・1週間の労働時間数が、職場(同種の業務に従事する労働者)の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
ストレスチェックを行う目的
ストレスチェックを行うことで、次のような効果が期待できます。
労働者
・自身の心身状態を把握できる
・ストレスを対処するきっかけになる
・高ストレスの場合、専門家の指導を受けられる
・労働環境が改善される可能性がある
事業者
・労働者のメンタルヘルス不調を未然に予防できる
・問題点を把握でき、状況を改善できる
・改善によって労働者のパフォーマンス向上が期待できる
仕事での不安や悩み、ストレスで精神障害を患う、またそれによって自殺に追い込まれる労働者は年間で1万人近くいるといわれています。
このような労働の実態を背景に、2015年、ストレスチェックは義務付けられました。
ストレスの要因となるものを排除していくことで、労働者のメンタルヘルス不調や自殺を一次予防します。
ストレスチェックの内容と手順
ストレスチェックの流れ
ストレスチェック行う際は、まず事業者が実施に向けて準備を整えます。
労働者は用意された質問に回答し、結果を待つだけです。
対象者一人ひとりに紙(もしくはオンライン)の質問票が配布されますので、各自回答を記入していきます。
ストレスチェックの回答自体はそれほど時間のかかるものではありません。
記入を終えたら、医師(実施者)やその補助者らが質問票を回収します。
ここでのポイントは、第三者や人事権を持つ職員が、ストレスチェックの回答を閲覧してはいけないということです。
ストレスチェックの実施者は医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士と決められており、会社の人事担当者などが実施するものではありません。
集めた回答を医師などの実施者が確認してストレス度を判定。
後日、回答者本人に結果が通知されます。
高ストレス判定だった人は、本人の希望によって医師による面接指導を受けたり、就業上の措置を受けたりすることが可能
です。また
事業者は、ストレスチェックの集計・分析結果をもとに職場環境の改善に努めなければなりません
。これがストレスチェックの大まかな流れです。
ストレスチェックシートのアンケート項目
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
厚生労働省が推奨している「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用している事業所が多いでしょう。
今回は、厚生労働省の推奨している調査票より「職業性ストレス簡易調査票 23項目(※職業性ストレス簡易調査票 57項目より抜粋したもの)」の内容をご紹介します。
職業性ストレス簡易調査票 23項目 | ||||
A.あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 | そうだ | まあ そうだ | やや ちがう | ちがう |
1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 時間内に仕事が処理しきれない | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 一生懸命働かなければならない | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる | 1 | 2 | 3 | 4 |
B.最近 1 か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 | ほとんど なかった | ときどき あった | しばしば あった | ほとんど いつもあった |
7. ひどく疲れた | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. へとへとだ | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. だるい | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 気がはりつめている | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. 不安だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. 落着かない | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. ゆううつだ | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. 何をするのも面倒だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. 気分が晴れない | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. 食欲がない | 1 | 2 | 3 | 4 |
29. よく眠れない | 1 | 2 | 3 | 4 |
C.あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか? | 非常に | 多少 | かなり | 全くない |
1. 上司 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか? | 非常に | 多少 | かなり | 全くない |
4. 上司 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか? | 非常に | 多少 | かなり | 全くない |
7. 上司 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
高ストレスの判定基準
調査結果は次のような形で、回答者本人に通知されます。
職業性ストレス簡易調査票(57項目)の回答を合計点数で判断する場合、
・Bの合計点数が77点以上(最高点は116点)であること
・領域AとCの合算の合計点数が76点以上(最高点は104点)であり、かつ領域Bの合計点数が63点以上であること
上記のいずれかに該当すれば高ストレスの判定になります。
その他にも素点換算表を使う方法というものもあります。
詳しい判定方法は下記をご参照ください。
◆数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法|厚生労働省
職場でのストレスチェックがない場合は無料のセルフ診断を!
介護職の場合、腰痛などの体調不良や疲れによるちょっとしたミスなどが積み重なり、大きなミスに繋がってしまうことも。
そんな場合でも、セルフチェックで自分のストレス度を知っておけば、ミスを事前に防げるかもしれません。
また、自分自身の心の問題も発見できるため、大きな病気になる前の予防策が見つかるでしょう。
そのため職場でストレスチェック制度が導入されていない場合でも、ぜひセルフチェックで自身のストレスを把握しておくことをおすすめします。
より安全、快適に働くために自分のストレスとしっかり向き合って対処していくことが大切です。
無料でストレスのセルフチェックができるオンラインサービスもあるので利用されてみてはいかがでしょうか。
今回は簡単な質問に答えるだけでストレスレベルが把握できる厚生労働省のサイトをご紹介します。
◆5分でできる職場のストレスチェック|厚生労働省
ストレスチェック制度を導入したい事業者さんへ
労働者50人以下の事業所は努力義務のため、実施していない所も多いでしょう。
実施するには体制整備や事前準備にコストがかかるため、懸念される事業者様も多いのではないかと思います。
しかしながら、介護職は体力だけでなく精神的な負荷も大きな仕事であるためメンタルヘルスケアが不可欠です。
大切な職員の心の健康を守るために、ストレスチェックには重要な役割があるといえるでしょう。
ストレスチェック制度を導入する際に参考にできる厚生労働省のマニュアルがあります。
◆ストレスチェック制度導入ガイド|厚生労働省
◆ストレスチェック制度導入マニュアル|厚生労働省
また、労働者が50人未満の事業所がストレスチェック制度を導入する際に利用できる助成金もあります。
助成対象と助成金額は以下です。
助成対象 | 助成金額 |
ストレスチェックの実施 | ストレスチェックに係る医師による活動 |
1従業員につき500円を上限に実費を支給 | 1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費を支給(上限3回) |
◆ストレスチェック実施促進のための助成金|独立行政法人 労働者健康安全機構
なお、ストレスチェック制度は、労働者の個人情報を保護し、不正利用されないことが大前提です。
個人情報には守秘義務が課されますので、プライバシーの保護にはくれぐれも気をつけて実施することが求められます。
そうすることで労働者も安心して受けられ、よい結果につなげることができるでしょう。
まとめ
ストレスを放置しておくと、心身に不調をきたすだけでなく、仕事での事故などにもつながりかねません。
セルフチェックなどで自身のストレスを理解し、早めに解消していきましょう。
介護の転職なら介護ワーカー!
専任のアドバイザーが親身になってあなたのよりよい転職をサポートいたします!
★アドバイザーに相談する(無料)
★介護ワーカーの求人を見てみる
#介護