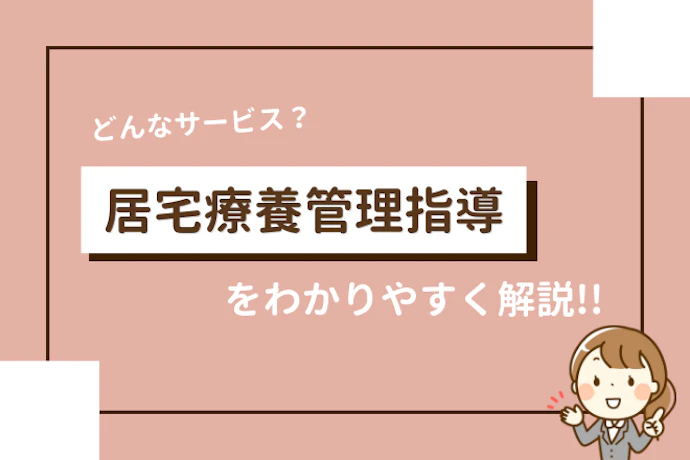介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
居宅療養管理指導とはどんなサービス?算定要件や訪問診療との違いまでわかりやすく解説!
#介護
目次
居宅療養管理指導というサービスがあります。
通院することが難しい要介護者の暮らしをサポートするためのもので、居宅介護支援事業所で働くケアマネージャーには関わりのあるサービスのひとつです。
本コラムでは、居宅療養管理指導とはどのようなサービスなのかを解説していきます。
基本的な内容をわかりやすくお伝えしていきますので、「どんなサービスか知りたい」という介護職員の方や「今さら聞けない!」というケアマネージャーの方は、ぜひ参考にしてください。
通院することが難しい要介護者の暮らしをサポートするためのもので、居宅介護支援事業所で働くケアマネージャーには関わりのあるサービスのひとつです。
本コラムでは、居宅療養管理指導とはどのようなサービスなのかを解説していきます。
基本的な内容をわかりやすくお伝えしていきますので、「どんなサービスか知りたい」という介護職員の方や「今さら聞けない!」というケアマネージャーの方は、ぜひ参考にしてください。
居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護者の居宅に医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。
具体的には、
・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への居宅サービス計画(ケアプラン)作成などに必要な情報提供
・利用者やそのご家族に対して居宅介護サービスを利用する上での留意点や介護方法などの指導・助言
を行うことです。
独居や夫婦2人暮らしなど、家族によるサポートがなかなか受けられない高齢者に役立つサービスです。
利用者の心身状態や生活環境などを把握したうえで療養生活の質を向上させる
ことを目的としており、高齢者が要介護状態になった場合でも、できる限り自宅で自立した日常生活を営むことができるように支援します。具体的には、
・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への居宅サービス計画(ケアプラン)作成などに必要な情報提供
・利用者やそのご家族に対して居宅介護サービスを利用する上での留意点や介護方法などの指導・助言
を行うことです。
独居や夫婦2人暮らしなど、家族によるサポートがなかなか受けられない高齢者に役立つサービスです。
サービスの利用対象者
居宅療養管理指導を利用できるのは、要介護1以上の認定を受けた高齢者です。
要支援1、2の人は居宅療養管理指導の対象外にはなりますが、ほぼ同じ内容の「介護予防居宅療養管理指導」というサービスが適用されます。
また、特定疾病によって要介護認定を受けた40歳~64歳の人も居宅療養管理指導の利用対象となります。
要支援1、2の人は居宅療養管理指導の対象外にはなりますが、ほぼ同じ内容の「介護予防居宅療養管理指導」というサービスが適用されます。
また、特定疾病によって要介護認定を受けた40歳~64歳の人も居宅療養管理指導の利用対象となります。
居宅療養管理指導を提供する事業者とは
居宅療養管理指導を提供しているのはどのような事業者なのでしょうか。
運営基準や人員基準をみていきましょう。
運営基準や人員基準をみていきましょう。
運営基準
居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局です。
さらに事業の運営に必要な広さを有していること、必要な設備及び備品等を備えていることが条件となります。
さらに事業の運営に必要な広さを有していること、必要な設備及び備品等を備えていることが条件となります。
人員基準
居宅療養管理指導事業所における人員基準は下記のように定められています。
◆病院・診療所
・医師または歯科医師
・薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士
(提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数)
◆薬局
・薬剤師
◆病院・診療所
・医師または歯科医師
・薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士
(提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数)
◆薬局
・薬剤師
職種ごとの管理指導内容
居宅療養管理指導のサービス内容は、サービスを提供する側の職種によって異なります。
先述の通り、管理指導を行える職種は
・医師、歯科医師
・薬剤師
・歯科衛生士
・管理栄養士
です。それぞれ見ていきましょう。
先述の通り、管理指導を行える職種は
・医師、歯科医師
・薬剤師
・歯科衛生士
・管理栄養士
です。それぞれ見ていきましょう。
医師・歯科医師
医師や歯科医師は、利用者の居宅にて計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理を実施します。
具体的には、利用者やそのご家族への居宅サービスを利用する上での注意点や介護方法などに関する指導・助言です。
また居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの作成などに必要な情報提供を行います。
なお、訪問診療または往診を行った日に限り有効です。
具体的には、利用者やそのご家族への居宅サービスを利用する上での注意点や介護方法などに関する指導・助言です。
また居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの作成などに必要な情報提供を行います。
なお、訪問診療または往診を行った日に限り有効です。
薬剤師
薬剤師は、医師または歯科医師の指示に基づいて薬学的な管理、指導を行います。
薬学的な管理とは、例えば処方薬の管理方法や服薬指導、副作用の説明といったことです。
また居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの作成に必要な情報を提供します。
薬学的な管理とは、例えば処方薬の管理方法や服薬指導、副作用の説明といったことです。
また居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの作成に必要な情報を提供します。
歯科衛生士
歯科衛生士は、利用者の口腔内や入れ歯の清掃、口腔ケアを行います。
また摂食・嚥下機能の維持・回復を目的とした指導や、歯の磨き方や義歯の手入れ方法などのアドバイスを行います。
これらは必ず訪問歯科診療を行った歯科医師の指示、およびその歯科医師が作成した訪問指導計画に基づいて実施されます。
また摂食・嚥下機能の維持・回復を目的とした指導や、歯の磨き方や義歯の手入れ方法などのアドバイスを行います。
これらは必ず訪問歯科診療を行った歯科医師の指示、およびその歯科医師が作成した訪問指導計画に基づいて実施されます。
管理栄養士
管理栄養士は、医師の指示に基づいて栄養管理に係る情報提供や指導・助言を行います。
具体的には、利用者の状況に合わせた食事内容や調理方法を考えて、本人やご家族に指導するといったことです。
食べる姿勢や食事介助の方法なども指導します。
1回の訪問につき30分以上行うこととされています。
具体的には、利用者の状況に合わせた食事内容や調理方法を考えて、本人やご家族に指導するといったことです。
食べる姿勢や食事介助の方法なども指導します。
1回の訪問につき30分以上行うこととされています。
居宅療養管理指導費の算定要件
居宅療養管理指導を行なった場合には指導費として算定することが可能です。
介護保険適用となり、要介護者は1~3割負担で利用できます。
算定できる介護報酬は下記の通りです。
サービスを提供する職種、また利用者の居宅状況によって報酬金額は異なります。
介護保険適用となり、要介護者は1~3割負担で利用できます。
算定できる介護報酬は下記の通りです。
サービスを提供する職種、また利用者の居宅状況によって報酬金額は異なります。
居宅療養管理指導費の介護報酬 | ||||
職種 | 単一建物居住者 1人 | 単一建物居住者 2~9人 | 単一建物居住者 10人以上 | 利用限度 |
医師(Ⅰ) | 514単位 | 486単位 | 445単位 | 月2回 |
医師(Ⅱ) | 298単位 | 286単位 | 259単位 | 月2回 |
歯科医師 | 516単位 | 486単位 | 440単位 | 月2回 |
薬剤師 (医療機関) | 565単位 | 416単位 | 379単位 | 月2回 |
薬剤師 (薬局) | 517単位 | 378単位 | 341単位 | 月4回 |
管理栄養士 | 544単位 | 486単位 | 443単位 | 月2回 |
管理栄養士 (当該事業所以外) | 524単位 | 466単位 | 423単位 | 月2回 |
歯科衛生士 | 361単位 | 325単位 | 294単位 | 月4回 |
(2021年時点)
医師に関しては居宅療養管理指導費(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、これは「在宅時医学総合管理料(在医総菅)」および「特定施設入居時医学総合管理料」(※)を算定しているかどうかの違いになります。
算定していれば(II)、算定いなければ(I)に該当します。
※「在宅時医学総合管理料(在医総菅)」および「特定施設入居時医学総合管理料」とは
在宅患者への総合的な医学管理を評価する診療報酬です。
通院が困難な患者に対し、本人の同意を得て計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を行う場合に月1回算定できるというものです。
医師に関しては居宅療養管理指導費(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、これは「在宅時医学総合管理料(在医総菅)」および「特定施設入居時医学総合管理料」(※)を算定しているかどうかの違いになります。
算定していれば(II)、算定いなければ(I)に該当します。
※「在宅時医学総合管理料(在医総菅)」および「特定施設入居時医学総合管理料」とは
在宅患者への総合的な医学管理を評価する診療報酬です。
通院が困難な患者に対し、本人の同意を得て計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を行う場合に月1回算定できるというものです。
居宅療養管理指導と訪問診療・往診の違い
ここまで読まれて「医師らによる居宅訪問は、訪問診療や往診と何が違うの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
訪問診療や往診との大きな違いは、居宅療養管理指導では医療行為が行われないという点です。
訪問診療や往診では症状に応じて医療処置や投薬治療が施されますが、
訪問診療や往診との大きな違いは、居宅療養管理指導では医療行為が行われないという点です。
訪問診療や往診では症状に応じて医療処置や投薬治療が施されますが、
居宅療養管理指導の場合はあくまで「療養上の管理」であり、健康のためのアドバイスや服薬の指導などを行うことが目的
となっています。居宅療養管理指導サービスの利用の流れ
最後に、居宅療養管理指導を提供するまでの流れについてです。
大まかな流れは次の通りです。
大まかな流れは次の通りです。
利用者が担当のケアマネージャーや主治医に相談
↓
ケアマネージャーが利用者の心身状況などを把握
↓
ケアマネージャーが事業所を探し、必要な職種を手配
↓
利用者へ契約内容の確認・同意を得る
↓
サービス開始
という流れでサービス提供がスタートします。
ケアマネージャーは利用者の状況を理解し、どのような管理指導が必要か、また本当に必要かどうかを判断します。居宅療養管理指導の事業所や主治医らと連携をとりながら進めます。
準備が整ったらサービス開始となりますが、事前に利用者の承諾を必ず得なければなりません。
なお、利用者が必ずしもケアマネージャーに相談するとは限りません。
主治医に相談した場合は主治医の判断・指示に基づいてサービスが提供されることもあります。
その場合は、事後にケアマネージャーに報告があり、それを受けてケアプランの作成を行うような形となります。
ケアマネージャーは利用者の状況を理解し、どのような管理指導が必要か、また本当に必要かどうかを判断します。居宅療養管理指導の事業所や主治医らと連携をとりながら進めます。
準備が整ったらサービス開始となりますが、事前に利用者の承諾を必ず得なければなりません。
なお、利用者が必ずしもケアマネージャーに相談するとは限りません。
主治医に相談した場合は主治医の判断・指示に基づいてサービスが提供されることもあります。
その場合は、事後にケアマネージャーに報告があり、それを受けてケアプランの作成を行うような形となります。
まとめ
居宅療養管理指導について解説しました。
チームケアの一つである居宅療養管理指導の利用者は年々増えており、今後、在宅介護や地域包括ケアを拡充していく上で欠かせないサービスとなるでしょう。
適正な居宅療養管理指導を実施するためには、ケアマネージャーと医師らとの連携がとても重要になります。相互の情報提供を密に行いながらサービスを提供していくことがとても大切です。
<関連コラム>
◆地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとはどんな制度?目的や構成要素を簡単に解説します
◆ケアプランセンター
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)とは?役割や仕事内容を解説
◆ケアプラン
ケアプランの作成方法とは?作成の流れ・記入例・ポイントもご紹介!
◆サービス担当者会議
サービス担当者会議とは?会議の目的や進め方、主催者のやるべきことを解説
チームケアの一つである居宅療養管理指導の利用者は年々増えており、今後、在宅介護や地域包括ケアを拡充していく上で欠かせないサービスとなるでしょう。
適正な居宅療養管理指導を実施するためには、ケアマネージャーと医師らとの連携がとても重要になります。相互の情報提供を密に行いながらサービスを提供していくことがとても大切です。
<関連コラム>
◆地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとはどんな制度?目的や構成要素を簡単に解説します
◆ケアプランセンター
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)とは?役割や仕事内容を解説
◆ケアプラン
ケアプランの作成方法とは?作成の流れ・記入例・ポイントもご紹介!
◆サービス担当者会議
サービス担当者会議とは?会議の目的や進め方、主催者のやるべきことを解説
ケアマネージャーのお仕事も介護ワーカーへ!
「地域密着型サービスでケアマネの仕事がしたい」
「居宅ケアマネの求人ってないの?」
など、転職をお考えのあなたは、ケアマネージャーの求人も豊富な介護ワーカーへお問合せください!
他にはない非公開の求人も多数!
地域の情報に精通したアドバイザーがあなたのお仕事探しをお手伝いします。
ぜひお気軽にご相談ください。
★介護ワーカーに相談してみる(無料)
「居宅ケアマネの求人ってないの?」
など、転職をお考えのあなたは、ケアマネージャーの求人も豊富な介護ワーカーへお問合せください!
他にはない非公開の求人も多数!
地域の情報に精通したアドバイザーがあなたのお仕事探しをお手伝いします。
ぜひお気軽にご相談ください。
★介護ワーカーに相談してみる(無料)
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.