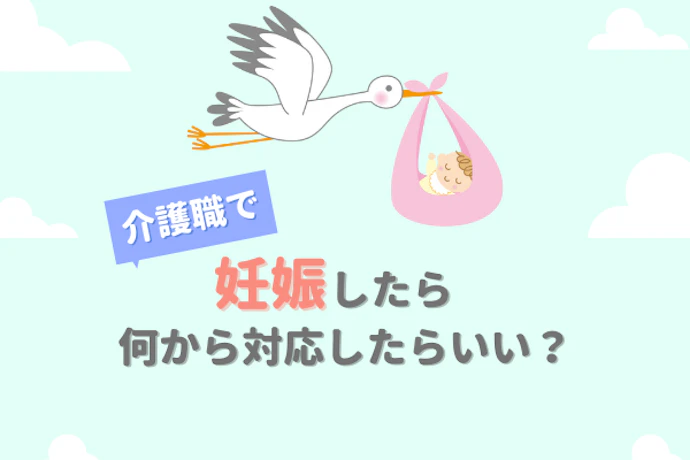介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.13
介護職が妊娠したら何から対応するべき?その方法や注意点をご紹介!
#介護
目次
介護職で妊娠が分かった方のなかには、今後の仕事のことで不安になっている方もいるのではないでしょうか?
「仕事場にはいつ報告したらいいの?」
「そもそも妊娠して介護職って続けられるの?」
など、色々と考えてしまいますよね。
そこで、介護職の妊娠報告のタイミングや妊娠後の働き方、そして注意してほしい点について紹介していきたいと思います。
「仕事場にはいつ報告したらいいの?」
「そもそも妊娠して介護職って続けられるの?」
など、色々と考えてしまいますよね。
そこで、介護職の妊娠報告のタイミングや妊娠後の働き方、そして注意してほしい点について紹介していきたいと思います。
介護職の妊娠報告はいつするべき?
妊娠をした場合、勤め先の上司や一緒に働いている同僚など周囲にいつ報告するべきなのか迷いますよね。一般的には、安定期に入ってから報告する方が多いですが、身体を動かす介護職の場合は報告した方が良いタイミングが少し異なります。
介護職の妊娠報告をするタイミングと報告相手や順番について確認しておきましょう。
介護職の方は、妊娠したことが分かったらなるべく早く職場に妊娠報告をしましょう。
報告する具体的なタイミングとしては、産婦人科を受診し「妊娠」が確定したあとです。
前述したように、一般的には職場などへの報告は「安定期に入ってから報告する」という方が多いと思います。
しかし、介護職の場合は身体を動かす業務が多く、身体への負担も大きい仕事ですので、妊娠後はできる業務とできない業務がでてきます。
そのため、業務内容を見直してもらう必要があるので、人員確保やシフト調整など職場側が対応する時間を確保するうえでも、病院で妊娠確定の診断を受けたら早めに職場へ報告しましょう。
職場での妊娠報告は、報告する相手の順番に気を付けましょう。
報告する相手と順番は以下。
1)上司への報告
2)同僚への報告
3)利用者さんやその家族への報告
まず、最初の報告は直属の上司に口頭で報告しましょう。
仲のいい同僚などに先に話したくなると思いますが、上司が他のスタッフなどから聞くのを避けるためにも、直接報告するまでは話さないのが無難です。
上司に報告・相談する内容は以下
●妊娠週数と出産予定日
●現在の体調
●検診や体調不良で休む可能性があること
●産休や育休の取得予定について
●同僚・利用者さんなどへ報告するタイミング
といった項目です。
また妊娠報告の際に、今後の仕事内容や勤務時間帯など希望することがあれば伝えておきましょう。仕事内容に関しては、妊娠中の方それぞれに体調なども異なるため、どの程度の仕事ができるのか上司にとっては判断がしにくい部分です。
そのため、できる仕事内容や勤務時間帯などの働き方についての希望はしっかりと伝え、無理のない範囲で仕事ができるように、働く環境を整えておくことが大切です。
仕事内容に関してはなかなか言いにくい部分もあると思いますが、妊娠したことを報告するだけでは仕事内容まで上司が配慮してくれるとは限りません。
ですので、自分の体調を第一に考え、希望があればはっきりと伝えましょう。
介護職の妊娠報告をするタイミングと報告相手や順番について確認しておきましょう。
■妊娠報告をするタイミング
介護職の方は、妊娠したことが分かったらなるべく早く職場に妊娠報告をしましょう。
報告する具体的なタイミングとしては、産婦人科を受診し「妊娠」が確定したあとです。
前述したように、一般的には職場などへの報告は「安定期に入ってから報告する」という方が多いと思います。
しかし、介護職の場合は身体を動かす業務が多く、身体への負担も大きい仕事ですので、妊娠後はできる業務とできない業務がでてきます。
そのため、業務内容を見直してもらう必要があるので、人員確保やシフト調整など職場側が対応する時間を確保するうえでも、病院で妊娠確定の診断を受けたら早めに職場へ報告しましょう。
■妊娠報告する相手と順番に気を付けて!
職場での妊娠報告は、報告する相手の順番に気を付けましょう。
報告する相手と順番は以下。
1)上司への報告
2)同僚への報告
3)利用者さんやその家族への報告
まず、最初の報告は直属の上司に口頭で報告しましょう。
仲のいい同僚などに先に話したくなると思いますが、上司が他のスタッフなどから聞くのを避けるためにも、直接報告するまでは話さないのが無難です。
上司に報告・相談する内容は以下
●妊娠週数と出産予定日
●現在の体調
●検診や体調不良で休む可能性があること
●産休や育休の取得予定について
●同僚・利用者さんなどへ報告するタイミング
といった項目です。
また妊娠報告の際に、今後の仕事内容や勤務時間帯など希望することがあれば伝えておきましょう。仕事内容に関しては、妊娠中の方それぞれに体調なども異なるため、どの程度の仕事ができるのか上司にとっては判断がしにくい部分です。
そのため、できる仕事内容や勤務時間帯などの働き方についての希望はしっかりと伝え、無理のない範囲で仕事ができるように、働く環境を整えておくことが大切です。
仕事内容に関してはなかなか言いにくい部分もあると思いますが、妊娠したことを報告するだけでは仕事内容まで上司が配慮してくれるとは限りません。
ですので、自分の体調を第一に考え、希望があればはっきりと伝えましょう。
妊娠後は介護職の仕事をいつまで続けられる?
介護職の仕事は身体に負担が大きい作業も多く、妊娠後に介護職の仕事を続けられるのかと心配している方もいるのではないでしょうか。
実際、妊娠後も介護職として働いている方はたくさんいます。
ただし、身体介助など身体に負担のかかる介護業務はできなくなるので、上司と相談しながら仕事内容を決めていく場合がほとんどです。
では、妊娠後はいつまで仕事ができるのか、また妊娠時期別でできる仕事内容について紹介していきたいと思います。
実際、妊娠後も介護職として働いている方はたくさんいます。
ただし、身体介助など身体に負担のかかる介護業務はできなくなるので、上司と相談しながら仕事内容を決めていく場合がほとんどです。
では、妊娠後はいつまで仕事ができるのか、また妊娠時期別でできる仕事内容について紹介していきたいと思います。
妊娠したらいつまで介護現場で働ける?
基本的には、妊娠中の経過が順調であれば
この時期まで働くことができたら、産前休業を申請し取得することが可能です。
産前休業は出産予定日の6週間前からであれば休業開始日を自分で決めることができるため、出産ギリギリまで働くこともできます。
しかし出産後はすぐに復職という訳にはいきません。
出産後は、産後休業というものがあり出産翌日から8週間は休業する必要があります。
産後休業は、法律で取得することを定められているため、原則就業することはできません。
例外として「産後6週間を過ぎて本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業可能」となっています。
出産予定日の6週間前、多胎妊娠であれば14週間前まで働くことができれば、産休・育休を取得でき出産手当金や育児休業給付金をもらうことができます。(※勤務年数や健康保険への加入などの条件を満たしていることが必要)
妊娠中は体調の変化も多く、つわりで思うように動けない場合や自宅で安静にするよう医師から言われることもあり、仕事を休まなければならないことも出てくるはず。
そんな時は、何よりも自分の身体とお腹にいる赤ちゃんのことを考え、体調が優れない時は無理をしないようにすることが大切です。
◎産休・育休についてもっと詳しく知りたいかたはこちらを参考にご覧ください。
「子育てをしながら働き続けたい あなたも取れる!産休&育休」
「出産予定日の6週間前まで」
双子など多胎妊娠の場合は「出産予定日の14週間前まで」働けます。この時期まで働くことができたら、産前休業を申請し取得することが可能です。
産前休業は出産予定日の6週間前からであれば休業開始日を自分で決めることができるため、出産ギリギリまで働くこともできます。
しかし出産後はすぐに復職という訳にはいきません。
出産後は、産後休業というものがあり出産翌日から8週間は休業する必要があります。
産後休業は、法律で取得することを定められているため、原則就業することはできません。
例外として「産後6週間を過ぎて本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業可能」となっています。
出産予定日の6週間前、多胎妊娠であれば14週間前まで働くことができれば、産休・育休を取得でき出産手当金や育児休業給付金をもらうことができます。(※勤務年数や健康保険への加入などの条件を満たしていることが必要)
妊娠中は体調の変化も多く、つわりで思うように動けない場合や自宅で安静にするよう医師から言われることもあり、仕事を休まなければならないことも出てくるはず。
そんな時は、何よりも自分の身体とお腹にいる赤ちゃんのことを考え、体調が優れない時は無理をしないようにすることが大切です。
◎産休・育休についてもっと詳しく知りたいかたはこちらを参考にご覧ください。
「子育てをしながら働き続けたい あなたも取れる!産休&育休」
妊娠中を通して避けておくべき業務
まず妊娠中を通して避けた方が良い業務は「移乗介助・入浴介助・排せつ介助」など、介護職員の身体への負担が大きい作業や転倒の危険がある業務です。
利用者の身体を支えなければならない身体介護は、身体への負担も転倒の危険もあるため、お腹がまだ目立っていなくても避けておく方が良いでしょう。
また、入浴介助などで浴室にいることも転倒の危険や足元から身体が冷えてしまうこともあるため、担当になっている場合は外してもらうようにしましょう。
その他に避けた方が良いのは「夜勤」です。
生活リズムが崩れてしまう夜勤は、妊娠中の身体に大きな負担がかかります。また、夜勤は職員数が少ないため身体介護など負担の大きい業務をしなければならない場面もでてくるため、避けた方がよいでしょう。
妊娠報告の際、施設側から負担の大きい作業や夜勤を免除してくれる場合もありますが、自分から相談するか希望として伝えないと業務内容を見直してくれない場合もあります。
妊娠報告の際は、事前に避けた方が良い業務などを確認しておき、上司から業務内容等についての話がないようであれば、その場で今後の業務について相談しておきましょう。
利用者の身体を支えなければならない身体介護は、身体への負担も転倒の危険もあるため、お腹がまだ目立っていなくても避けておく方が良いでしょう。
また、入浴介助などで浴室にいることも転倒の危険や足元から身体が冷えてしまうこともあるため、担当になっている場合は外してもらうようにしましょう。
その他に避けた方が良いのは「夜勤」です。
生活リズムが崩れてしまう夜勤は、妊娠中の身体に大きな負担がかかります。また、夜勤は職員数が少ないため身体介護など負担の大きい業務をしなければならない場面もでてくるため、避けた方がよいでしょう。
妊娠報告の際、施設側から負担の大きい作業や夜勤を免除してくれる場合もありますが、自分から相談するか希望として伝えないと業務内容を見直してくれない場合もあります。
妊娠報告の際は、事前に避けた方が良い業務などを確認しておき、上司から業務内容等についての話がないようであれば、その場で今後の業務について相談しておきましょう。
妊娠初期にできる仕事内容
妊娠初期は、妊娠4週~15週(妊娠2ヶ月~4ヶ月)の時期のことを言います。
この時期は、見た目にはほとんど変化はありませんが「つわり」の症状がでるなど、体調の変化を感じる方が多いときです。
つわりの症状は人によってさまざまで、匂いに敏感になる方も多くなかには食事をとることもできない方やお茶などの飲み物でさえも吐いてしまうほど症状がキツイ場合もあります。
妊娠初期にできる仕事内容は
この時期は、見た目にはほとんど変化はありませんが「つわり」の症状がでるなど、体調の変化を感じる方が多いときです。
つわりの症状は人によってさまざまで、匂いに敏感になる方も多くなかには食事をとることもできない方やお茶などの飲み物でさえも吐いてしまうほど症状がキツイ場合もあります。
妊娠初期にできる仕事内容は
●着脱介助
●入浴介助(誘導のみ)
●排泄介助(身体的負担の無い方の介助)
●おむつ交換
●シーツ交換
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成
●普段の生活の見守り など
●入浴介助(誘導のみ)
●排泄介助(身体的負担の無い方の介助)
●おむつ交換
●シーツ交換
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成
●普段の生活の見守り など
妊娠後の体調はその人によってさまざまですので、上記項目が必ずできる業務とは限りません。とくに妊娠初期の場合、匂いでつわりの症状がでることも多いため、排せつ介助やおむつ交換、食事介助なども人によってはできない場合もあります。自分の体調の変化によって、業務内容を都度見直してもらいましょう。
妊娠中期にできる仕事内容
妊娠中期は16週~27週(妊娠5ヶ月~7ヶ月)の時期のことを言います。
比較的に妊娠が安定する「安定期」と呼ばれる時期に入ります。この時期は、つわりも治まってくることが多く、体調も安定してきます。お腹も大きくなってきて胎動を感じられるなど、ほっと一息つける時期です。
妊娠中期にできる仕事内容は
比較的に妊娠が安定する「安定期」と呼ばれる時期に入ります。この時期は、つわりも治まってくることが多く、体調も安定してきます。お腹も大きくなってきて胎動を感じられるなど、ほっと一息つける時期です。
妊娠中期にできる仕事内容は
●着脱介助
●入浴介助(誘導を担当)
●排泄介助(誘導を担当)
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成など事務業務
●普段の生活の見守り など
●入浴介助(誘導を担当)
●排泄介助(誘導を担当)
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成など事務業務
●普段の生活の見守り など
妊娠中期の体調はその人によってさまざまですので、上記項目が必ずできる業務とは限りません。妊娠中期はお腹も大きくなってくるため、前屈姿勢になる業務などは避けるようにしましょう。自分の体調の変化によって、業務内容をその都度見直してもらいましょう。
妊娠後期にできる仕事内容
妊娠後期は28週~40週(妊娠8ヶ月~10ヶ月)の時期のことを言います。
妊娠後期になると、お腹はさらに大きくなり張りを感じることも増えてくる時期です。
胃が押し上げられることによってムカムカするなどの症状がでてきたり、足がむくみやすくなったりします。妊娠後期はお腹が大きくなり、自分の足元が見えづらくなるためとくに階段などの段差には注意が必要です。
妊娠後期にできる仕事内容は
妊娠後期になると、お腹はさらに大きくなり張りを感じることも増えてくる時期です。
胃が押し上げられることによってムカムカするなどの症状がでてきたり、足がむくみやすくなったりします。妊娠後期はお腹が大きくなり、自分の足元が見えづらくなるためとくに階段などの段差には注意が必要です。
妊娠後期にできる仕事内容は
●着脱介助
●排泄介助(誘導を担当)
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成など事務業務
●普段の生活の見守り など
●排泄介助(誘導を担当)
●食事介助、口腔ケア
●車いすでの移動介助
●転倒リスクの少ない歩行介助
●掃除、洗濯
●レクリエーションの企画、進行
●業務日誌、介護記録の作成など事務業務
●普段の生活の見守り など
妊娠後期の体調もその人によってさまざまですので、上記項目が必ずできる業務とは限りません。とくに妊娠後期は、歩いたり動き回ったりするとお腹が張りやすくなるので、無理をしないようにしましょう。
お腹も大きくなり自分自身の足元も見えづらい状態になるので、椅子に座ってできる事務作業などをメインに体調に合わせて業務内容を調整してもらいましょう。
妊娠中の介護職が気を付けておくこと
妊娠中も介護職として働こうと考えている方の場合、出産予定日の6週間前まで働いて産休を取得しようと考えている方は多いはず。
そこで、妊娠中の介護職が気を付けておくべきことについてまとめてみました。
妊娠中の介護職が気を付けておくべきことは以下の3つです。
それぞれ、どのような点に気を付けたらよいのか見ていきましょう。
妊娠中の介護職は「周りの理解と協力を得る」ということがとても重要です。
妊娠中は、体調不良や検診などで休むことが増えてしまうだけでなく、身体に負担のかかる業務は他のスタッフと交代することになります。介護現場の多くは、スタッフの数に余裕があるわけではないため、おのずと他のスタッフに負担がかかってしまいます。
そのため、妊娠中も介護職として働くには周りの理解と協力が必要不可欠です。
妊娠中だからと怠慢にならないよう「他のスタッフが理解し協力してくれている」ということを忘れず、その時期にできる作業は率先しておこなうこと、また感謝の言葉を伝えましょう。
妊娠中は、妊婦が過度のストレスを溜めてしまうと母体だけでなく胎児にも影響があると言われています。
ストレスによる主な影響は以下です。
・妊娠高血圧症候群のリスクが高くなる
・切迫流産、切迫早産のリスクが高くなる
・赤ちゃんが低体重児になるリスクが高くなる
・赤ちゃんが情緒不安定になるリスクが高くなる など
人は過度なストレスを感じると血管を収縮させる作用があるため、妊婦が常にストレスフルの状態になっていると、へその緒で繋がっている胎児に十分な酸素や栄養が届かず、早産や低体重児になる確率が高くなってしまいます。
また、慢性的なストレスを感じていると「コルチゾール」と呼ばれる副腎皮質ホルモンが多く分泌され胎児に届き、神経系の発達に影響を与えてしまいます。
慢性的にストレスを溜めないようにするなめにも、自分に合ったストレス解消法を見つけて、こまめにストレス発散しておくことが大切です。
介護職の仕事は、前屈姿勢やしゃがんだりする体制を取る業務が多いため、妊婦には負担が大きくなります。
妊娠初期の間は、お腹もそれほど目立たないため前屈姿勢やしゃがんだりすることができるかもしれません。しかし、妊娠中期以降はお腹も出てくるため、お腹を圧迫しないように気を付けましょう。とくに慌ててしゃがむとお腹を強く圧迫してしまうため、お腹が目立ってきたら慌ててしゃがまないように意識しておきましょう。
そこで、妊娠中の介護職が気を付けておくべきことについてまとめてみました。
妊娠中の介護職が気を付けておくべきことは以下の3つです。
●周りの理解と協力を得ること
●ストレスをためないようにする
●お腹を圧迫しないように気を付ける
それぞれ、どのような点に気を付けたらよいのか見ていきましょう。
●周りの理解と協力を得ること
妊娠中の介護職は「周りの理解と協力を得る」ということがとても重要です。
妊娠中は、体調不良や検診などで休むことが増えてしまうだけでなく、身体に負担のかかる業務は他のスタッフと交代することになります。介護現場の多くは、スタッフの数に余裕があるわけではないため、おのずと他のスタッフに負担がかかってしまいます。
そのため、妊娠中も介護職として働くには周りの理解と協力が必要不可欠です。
妊娠中だからと怠慢にならないよう「他のスタッフが理解し協力してくれている」ということを忘れず、その時期にできる作業は率先しておこなうこと、また感謝の言葉を伝えましょう。
●ストレスをためないようにする
妊娠中は、妊婦が過度のストレスを溜めてしまうと母体だけでなく胎児にも影響があると言われています。
ストレスによる主な影響は以下です。
・妊娠高血圧症候群のリスクが高くなる
・切迫流産、切迫早産のリスクが高くなる
・赤ちゃんが低体重児になるリスクが高くなる
・赤ちゃんが情緒不安定になるリスクが高くなる など
人は過度なストレスを感じると血管を収縮させる作用があるため、妊婦が常にストレスフルの状態になっていると、へその緒で繋がっている胎児に十分な酸素や栄養が届かず、早産や低体重児になる確率が高くなってしまいます。
また、慢性的なストレスを感じていると「コルチゾール」と呼ばれる副腎皮質ホルモンが多く分泌され胎児に届き、神経系の発達に影響を与えてしまいます。
慢性的にストレスを溜めないようにするなめにも、自分に合ったストレス解消法を見つけて、こまめにストレス発散しておくことが大切です。
●お腹を圧迫しないように気を付ける
介護職の仕事は、前屈姿勢やしゃがんだりする体制を取る業務が多いため、妊婦には負担が大きくなります。
妊娠初期の間は、お腹もそれほど目立たないため前屈姿勢やしゃがんだりすることができるかもしれません。しかし、妊娠中期以降はお腹も出てくるため、お腹を圧迫しないように気を付けましょう。とくに慌ててしゃがむとお腹を強く圧迫してしまうため、お腹が目立ってきたら慌ててしゃがまないように意識しておきましょう。
まとめ
介護職で妊娠が分かった方は、なるべく早く直属の上司に報告と今後の業務などについて相談しましょう。
基本的には妊娠していても介護職を続けることはできますが、できる内容は制限されてしまいます。また、妊婦の体調の変化は個人によって異なるため、体調をみながら業務内容を調整してもらうことが必要です。
介護の仕事は体力的にも精神的にも身体に負担のかかる業務が多いため、お腹の赤ちゃんのためにも無理は禁物です。自分自身の身体とお腹の赤ちゃんの健康を最優先にし、仕事を続けることが難しい場合は休職や退職することも考えてみてくださいね。
基本的には妊娠していても介護職を続けることはできますが、できる内容は制限されてしまいます。また、妊婦の体調の変化は個人によって異なるため、体調をみながら業務内容を調整してもらうことが必要です。
介護の仕事は体力的にも精神的にも身体に負担のかかる業務が多いため、お腹の赤ちゃんのためにも無理は禁物です。自分自身の身体とお腹の赤ちゃんの健康を最優先にし、仕事を続けることが難しい場合は休職や退職することも考えてみてくださいね。
介護の転職なら介護ワーカー!
職場選びや面接に不安な方はぜひ介護ワーカーまでご相談ください。
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
求人のご提案、履歴書添削、面接同行まで・・・
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたのお仕事探しを手厚くサポートいたします!
他にはない非公開の求人も!お気軽にご相談ください。
<<アドバイザーに相談してみる(無料)>>
<<とりあえず求人を見てみる>>
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.