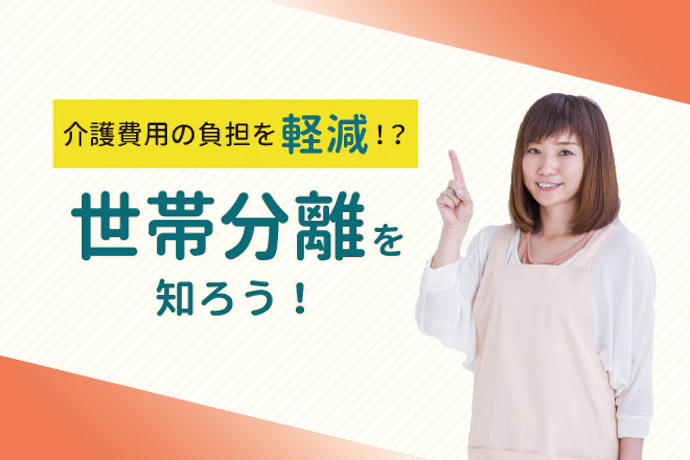介護コラム
公開日:2023.10.11
更新日:2023.10.24
介護費用の負担を軽減する世帯分離について
#介護
目次
ご家族の介護をしている人にとって、介護保険のサービスは日ごろの介護の負担を軽減したり、自分の時間が持てたりと、必要不可欠なサービスと言えるかもしれません。しかし、サービスを利用すればするほど、介護費用がかさみ、家計を圧迫するかもしれません。「世帯分離」をうまく利用すれば、介護費用負担が軽減し、生活にゆとりができるかもしれません。今回は「世帯分離」について説明し、メリット・デメリットも紹介します。
世帯分離とは
世帯分離とは親子の縁を切るという意味ではなく、住民票に登録されている一つの世帯を2つ以上に分けるということです。言い換えると同じ住所に二人以上の世帯主が存在することになります。つまり、同じ住居に住んでいるが、別々の生計を営んでいる2つ以上の家族のことのことです。
世帯分離のメリット
世帯分離をすれば、介護費用負担が軽減するいくつかのメリットがあります。
介護保険サービス自己負担額の軽減
介護保険サービスを利用する場合、サービス費用の1~3割を自己で負担する必要があります。一か月の負担額上限は「高額介護サービス費制度」で決められており、限度額を超えた分は申請することによって払い戻されます。世帯分離をすることによって、世帯の総所得が減ると、介護保険の自己負担の上限額も下がります。
後期高齢者医療保険料が軽減する
75歳以上の全ての人が支払う後期高齢者医療保険料は、所得によって支払う保険料の内訳が変わってきます。世帯分離をすることで、世帯の総所得が減り、結果として後期高齢者医療保険は軽減されます。
施設入所の食費・居住費が軽減する
「特定入所介護サービス費」という制度があり、世帯の所得によって決まる高額介護サービス費の1~3段階に該当すれば、施設入所における食費・居住費が軽減されます。例えば、1段階の人と1~3段階に該当しない人の1年間の負担額を比較するとおよそ40万円くらい、自己負担額が変わってきます。
国民健康保険料の負担額が軽減できる場合がある
国民健康保険料は前年の所得額で決定されるので、世帯分離によって世帯の所得が減れば、減額制度が適応されて負担額が軽減される場合もあります。
デメリット
「世帯分離」はよいことばかりではなく、世帯分離をすることで逆に損をしてしまう場合もあります。
74歳以下なら国民健康保険負担額が逆に増える場合がある
国民健康保険は世帯主に支払い義務があるため、世帯分離をすればそれぞれの世帯主に支払い義務が生じます。全体でみれば負担額が増えてしまう場合があります。
高額療養費の世帯合算ができない
介護サービスを利用している人が2人以上いれば、利用料を合算させて払い戻しを請求することができます。しかし、世帯分離で世帯が分かれれば、それぞれの世帯のサービス料を合算させて支払うことはできません。
会社の健康保険を利用した方がよい場合もある
同一世帯で会社で働いている人がいれば、扶養に入ることで国民健康保険料は払わなくてもよいので、その分の国民健康保険料は浮かすことができます。
実はシンプルな世帯分離手続き
世帯分離と聞くとなんだか難しそうな感じがしますが、地域の役所で簡単に申請をすることができます。まず世帯主か世帯員もしくは委任状を持った代理人が役所に世帯分離届を提出します。その際に、異動届・本人確認書類・印鑑・分離される方全員の国民健康保険被保険者証を持っていきます。届け出をし、受理がされれば、手続きは終了です。
世帯分離が完了すれば、必国民健康保険証の発行が必要な場合があります。世帯分離前は世帯員だった人が新たに世帯主になった場合には保険証が必要となりますのでご注意ください。
もし世帯分離することに戸惑いをもっていたら、世帯分離届を提出する前にメリット・デメリットをもう一度確認するようにして、どちらが自分たちの生活に合っているかを考慮してから提出してください。もし、それでも不安であれが、役所の窓口に前もって問い合わせるようにしてください。
世帯分離が完了すれば、必国民健康保険証の発行が必要な場合があります。世帯分離前は世帯員だった人が新たに世帯主になった場合には保険証が必要となりますのでご注意ください。
もし世帯分離することに戸惑いをもっていたら、世帯分離届を提出する前にメリット・デメリットをもう一度確認するようにして、どちらが自分たちの生活に合っているかを考慮してから提出してください。もし、それでも不安であれが、役所の窓口に前もって問い合わせるようにしてください。
世帯分離を検討してみよう
世帯分離は、介護負担量を軽減する意味でも有用な制度であると思います。しかし、メリットばかりでなく、世帯分離をすることで逆に損をしてしまうこともあります。メリットとデメリットを考慮して選択するようにしてください。
※掲載情報は公開日あるいは2020年06月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.