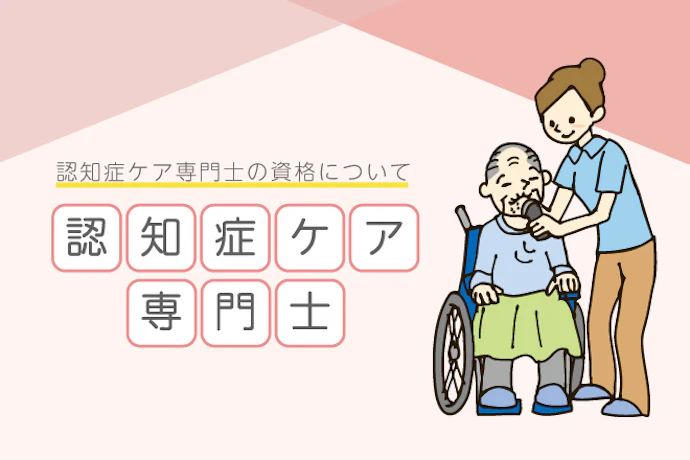介護コラム
公開日:2023.10.11
更新日:2023.11.10
「認知症ケア専門士」ってどんな資格?取得のメリット・受験方法についてご紹介
#介護
目次
認知症ケア専門士とは?
■認知症ケア専門士が活躍できる職場って?
■認知症ケア専門士の資格を取得するメリットって?
1.資格の知名度が高いから評価されやすい!
2.根拠のある知識をもとに認知症ケアが行える!
デメリットは介護報酬の加算対象ではないこと!?
■認知症ケア専門士の受験資格や受験方法、合格率は?
認知症ケア専門士認定試験の受験資格
認知症ケア専門士認定試験の受験方法
まずは「受験の手引き」の申込みを!
第1次試験と第2次試験ごとに受験申込みが必要!
認知症ケア専門士認定試験の概要
第1次試験の概要
第1次試験は分けて受験できる
第2次試験の概要
論述試験のポイント
面接試験のポイント
第2次試験合格の5要件
認知症ケア専門士認定試験に合格したら、登録申請が必要!
認知症ケア専門士認定試験の合格率
■ 認知症ケア専門士認定試験の勉強法は?
公式の「認知症ケア標準テキスト」で勉強する
問題集で問題数をこなしていく
受験対策講座を受講する
すきま時間にアプリで勉強する
■認知症ケア専門士の資格は、更新が必要!
認知症ケア専門士の資格更新費は10,000円
学会などへの参加費は約3000円から10000円/回
30単位に満たない場合は、更新の保留が可能!
■まとめ
介護職の転職をするなら介護ワーカー!
認知症ケア専門士とは?
認知症ケアに対する優れた学識と高度な技術、および倫理観を備えた専門技術士を養成し、日本における認知症ケア技術の向上ならびに保険・福祉に貢献する
ことを目的としています。認知症に関する様々な専門知識と技術を要する「
認知症ケアのプロ
」と称される位置づけとして設定された資格です。■認知症ケア専門士が活躍できる職場って?
また、医療現場でもスタッフへ認知症ケアに関する知識や技術を伝えることができるため、看護師や医師などすでに医療系の資格を持ち活躍している方も、多く認知症ケア専門士の資格を取得しています。(日本認知症ケア学会認定 認知症ケア専門士公式サイトより)
をもとに弊社独自に作成。
なお、内閣府発表の「平成29年版高齢社会白書」によると、将来推計では65歳以上の認知症高齢者数が2060年に850万人になり、2015年の517万人の1.6倍にまで増加すると予想されています。
認知症ケア専門士は民間資格ですが、このように社会が高齢化・認知症高齢者の増加へと進むなか、介護・医療・福祉の分野において必要不可欠とされており、注目度は非常に高くなっています。
■認知症ケア専門士の資格を取得するメリットって?
1.資格の知名度が高いから評価されやすい!
また、認知症の高齢者を支えるご家族からの質問や相談に対して、的確なアドバイスやプロフェッショナルな対応ができるようになるため、職場での評価も高くなりやすい傾向にあります。
このようなことから認知症ケアを行う仕事に対してやりがいをより感じることができるでしょう。
<<介護職の求人を探す>>
2.根拠のある知識をもとに認知症ケアが行える!
また、更新が必要な資格であるため、単位の取得に必要な学会などへ参加することで常に医学的な裏づけをもつ“最先端の技術や理論をもとに認知症ケアにあたること”ができます。
デメリットは介護報酬の加算対象ではないこと!?
認知症ケア専門士は多くの施設で重宝され権威性のある資格ではあるものの、残念ながら現状では介護報酬の加算の対象にはなっていません。
認知症に関する加算には
・認知症加算
・認知症ケア加算
・認知症専門ケア加算
などがありますが、いずれも認知症介護指導者研修や認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修など「国や自治体が行っている認知症介護指導者研修の修了者」の配置が算定要件となっており、民間資格の認知症ケア専門士は知名度は高いながらも算定要件には含まれていません。
もし事業所の介護報酬加算を取ることも資格取得の目的に含まれるならば、認知症介護指導者研修からステップアップして資格を取得していくことをおすすめします。
<詳しくはこちら>
コラム「認知症ケアに携わるなら取るべき資格!認知症介護実践者研修ってなに?」
■認知症ケア専門士の受験資格や受験方法、合格率は?
認知症ケア専門士認定試験の受験資格
認知症ケア専門士認定試験の受験方法
まずは「受験の手引き」の申込みを!
「受験の手引き」は電話かFAX、もしくはインターネットから申込みができ、料金は1部1,000円(税込)です。
手引きに記載の通り必要書類を揃えて送付し、受験料の払込みをして申込完了となります。
第1次試験と第2次試験ごとに受験申込みが必要!
第1次試験の申込期間は3月から4月頃で、受験料は3,000円×受験分野数(4分野まとめて受ける場合は合計12,000円)となります。
また、第2次試験の申込期間は8月から9月頃で、受験料は8,000円となります。
認知症ケア専門士認定試験の概要
第1次試験の概要
また、4分野すべてに合格することが第1次試験の合格ということになります。
出題分野 | 問題数 |
認知症ケアの基礎 | 50問 |
認知症ケアの実際1:総論 | 50問 |
認知症ケアの実際2:各論 | 50問 |
認知症ケアにおける社会資源 | 50問 |
合計 | 200問 |
第1次試験は分けて受験できる
各分野の合格有効期限は5年間なので、働きながら1度に4分野を勉強するは大変…という方も「今回は2分野を受けて、来年は残りの2分野を受けよう」と計画を立てながら資格取得を目指せます。
第2次試験の概要
※事前に設けられた提出期間内に、第2次試験受験申請書類と一緒に郵送する
面 接:6人1グループとなって、ディスカッションとスピーチ(約20分)
論述試験のポイント
「自分ならどんな対処をするか」の根拠と理由を明確に記す
自分なりの意見を大切にする
面接試験のポイント
自分なりの言葉で意見を言う
「人として」や「専門職として」の考えを伝える
周囲の話も聞く、仲間が話しやすい環境を作る
6人1グループで行うので「もしもここが職場だったらどう振る舞うか?」という人との関係も踏まえつつ答えていくことが大切です!
第2次試験合格の5要件
適切なアセスメントの視点を有しているか
認知症を理解しているか
適切な介護計画を立てられるか
制度および社会資源を理解しているか
認知症の人の倫理的課題を理解しているか
認知症ケア専門士認定試験に合格したら、登録申請が必要!
認知症ケア専門士認定試験の合格率
第8回(2012年)から第13回(2017年)の合格結果を踏まえてまとめた以下のグラフから分かるように、認知症ケア専門誌認定試験の合格率は約48%から60%となっており、比較的難易度は高めといえます。
認知症ケア専門士は民間資格ではありますが、難易度・専門性が高いため、しっかりと勉強をして知識をつける必要があります。
■ 認知症ケア専門士認定試験の勉強法は?
公式の「認知症ケア標準テキスト」で勉強する
また、認知症ケア標準テキストには医療・看護・介護・福祉の内容がバランスよく網羅されているため、身につけられる知識が増え、試験勉強で学んだことをそのまま職場で活かすことできます。
問題集で問題数をこなしていく
また、実際の試験では、試験終了後に解答用紙とともに問題用紙も回収されてしまうため、なかなか過去の問題を探すことは困難です。
しかし、過去の受験者の情報などをもとにして作られた問題集はいくつか発売されています。
「認知症ケア標準テキスト」で勉強し、問題集で繰り返し問題を解くことで、より実践に近い対策勉強となり問題にも慣れることができます。
様々な問題集がありますが、問題ごとに分かりやすい解説がついているものを選ぶのがおすすめです。
受験対策講座を受講する
この講座は毎年5月から6月頃に2日間にわたって、全国2か所(横浜・京都など)で開催されており、「認知症ケア標準テキスト」をもとに分野ごとの重要ポイントを講義形式で学べます。
また、本番形式の模擬試験も受けることができ、模擬試験終了後には講師による問題の解説も行われるため、2日間で効率的に試験勉強をすることができます。
参加費は15,000円ですが、講座内で使用する「認知症ケア標準テキスト」の費用や交通費・宿泊費は含まれていないため、そのほかの勉強法より費用はかかってしまいます。
すきま時間にアプリで勉強する
アプリのほとんどは有料ですが、公式テキストや問題集を購入するより安く、なによりも空いた時間にどこでも勉強できるため、忙しくてなかなか勉強時間を作れない方にもおすすめです。
■認知症ケア専門士の資格は、更新が必要!
論文の投稿や発表、学会・講演などへ参加するごとに2から8単位を取得でき、5年以内に30単位以上を取得することで更新が可能です。
万が一、更新申請を忘れてしまった場合は、認知症ケア専門士認定試験の受験からやり直しとなってしまうため注意が必要です!
認知症ケア専門士の資格更新費は10,000円
学会などへの参加費は約3000円から10000円/回
開催地によっては交通費も必要になりますので、参加する項目を事前に確認しておくことが大切です。
30単位に満たない場合は、更新の保留が可能!
保留申請をした場合、次の更新は4年間で30 単位を取得する必要があるため、計画的に単位取得をして5年ごとに更新できるようにするとよいでしょう。
<更新について詳しく知りたい方はこちら>
「認知症ケア専門士の更新忘れてない?更新方法・必要単位数などまとめて解説!」
■まとめ
勉強量も多く、試験期間も約5ヶ月と長いため労力がかかりますが、その分得られる知識やすぐに活かせるスキルも多い資格です。
また、認知症ケア専門士の資格取得者の需要は今後ますます高まる可能性が高いため、医療や介護、福祉の分野でより活躍したいと考えている方はぜひ資格取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
介護職の転職をするなら介護ワーカー!
まずは、お気軽にご相談下さい。
<<アドバイザーに相談する>>
#介護