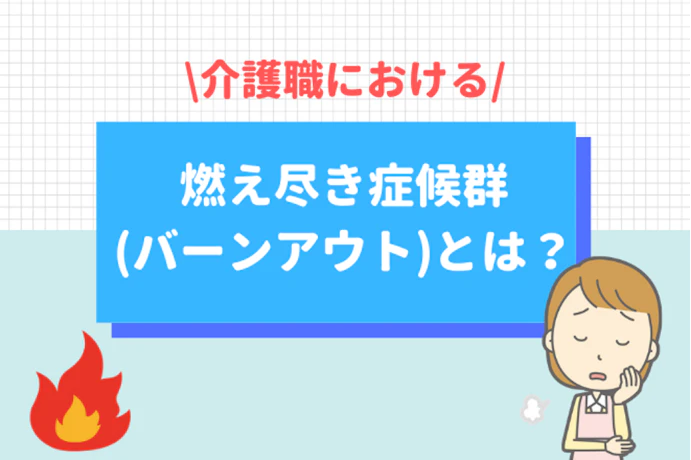介護コラム
公開日:2023.10.20
更新日:2023.11.10
チェック表あり!介護職における燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?
#介護
目次
介護職で働く方には知っておいてもらいたい「燃え尽き症候群(バーンアウト)」。
これは人を相手にする仕事をしている人に多い症状です。
本コラムでは「燃え尽き症候群」の
■意味
■症状
■なりやすい人
■対策方法
について解説していきます。
介護職に就かれている方は、知っておくことで未然に症状を防ぐことができるかもしれません。ぜひお役立てください。
はじめに、燃え尽き症候群とはなにかということから解説していきます。
これは人を相手にする仕事をしている人に多い症状です。
本コラムでは「燃え尽き症候群」の
■意味
■症状
■なりやすい人
■対策方法
について解説していきます。
介護職に就かれている方は、知っておくことで未然に症状を防ぐことができるかもしれません。ぜひお役立てください。
はじめに、燃え尽き症候群とはなにかということから解説していきます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?
燃え尽き症候群は別名「バーンアウト」と呼ばれており、熱心に仕事に打ち込んでいた人がまるで火が燃え尽きてしまったかのように意欲を失ってしまう状態のことを指します。
人を相手とする職種、なかでも介護や医療の現場において多く見られるようです。
なぜ介護や医療の現場に多いのかというところですが、仕事の成果が目に見えない場合が多く、利用者や患者に求められるままに努力をし続けて精力を使い果たしてしまうからです。
そのため、理想を追い求めて努力を続けても適正な評価が得られず、気付かないうちに精神的・身体的に負担がかかってしまい燃え尽き症候群になっているということになります。
このように利用者や患者への過剰な気遣いなどによって慢性的にストレスを抱えると燃え尽き症候群になりやすく、状況によって離職してしまう場合もあります。
そのため、予防や改善方法が課題となっています。
次に、燃え尽き症候群になるとどのような症状が出るのかを見ていきましょう。
人を相手とする職種、なかでも介護や医療の現場において多く見られるようです。
なぜ介護や医療の現場に多いのかというところですが、仕事の成果が目に見えない場合が多く、利用者や患者に求められるままに努力をし続けて精力を使い果たしてしまうからです。
そのため、理想を追い求めて努力を続けても適正な評価が得られず、気付かないうちに精神的・身体的に負担がかかってしまい燃え尽き症候群になっているということになります。
このように利用者や患者への過剰な気遣いなどによって慢性的にストレスを抱えると燃え尽き症候群になりやすく、状況によって離職してしまう場合もあります。
そのため、予防や改善方法が課題となっています。
次に、燃え尽き症候群になるとどのような症状が出るのかを見ていきましょう。
燃え尽き症候群:どんな症状がでる?
燃え尽き症候群になると、心や体が疲れきっている状態が続くため、仕事だけでなく日常生活にまで影響を及ぼしてしまいます。
主な症状と具体的な兆候は以下となります。
これは、仕事を通して情緒的に力を出し尽くし消耗してしまった状態のことを表します。
利用者と接する時に気を遣ったり、信頼関係を築こうと誠実で思いやりのある対応をすることで多くのエネルギーを消費します。
そのなかでも「感情」に使うエネルギーが消耗されることにより生じる症状です。
情緒的消耗感で「感情」に使うエネルギーが枯渇した状態になると、それ以上のエネルギー消費を防ぐため、防衛反応として「脱人格化」が現れます。
他人と関わることに疲れを感じてしまい、相手を気遣う気持ちがなくなるため人と距離をおく行動に出るのです。
情緒的消耗と脱人格化が合わさることによって最終的に仕事へのやりがいを感じられなくなります。
さらには仕事に対する自信を失ってしまい、自分の利用者に対するケアに納得できなくなります。それによって達成感を得られず、ケアの質が下がっていき離職に繋がっていきます。
燃え尽き症候群に繋がる具体的な兆候に関しては以下の例があげられます。
・好きだったことに無関心になる
・夜眠れなくなったり朝起きれなくなったりする
・こだわりがなくなる
・急に遅刻や欠勤が増える
・仕事が雑になる
・感情や意欲がなくなりコミュニケーションをとりづらくなる
・アルコールの量が増える
・体に不調が出る
それではこの燃え尽き症候群に関してどんな人がなりやすいのでしょうか。
皆さんもチェックしてみてください。
主な症状と具体的な兆候は以下となります。
【情緒的消耗感】
これは、仕事を通して情緒的に力を出し尽くし消耗してしまった状態のことを表します。
利用者と接する時に気を遣ったり、信頼関係を築こうと誠実で思いやりのある対応をすることで多くのエネルギーを消費します。
そのなかでも「感情」に使うエネルギーが消耗されることにより生じる症状です。
【脱人格化】
情緒的消耗感で「感情」に使うエネルギーが枯渇した状態になると、それ以上のエネルギー消費を防ぐため、防衛反応として「脱人格化」が現れます。
他人と関わることに疲れを感じてしまい、相手を気遣う気持ちがなくなるため人と距離をおく行動に出るのです。
【個人的達成感の低下】
情緒的消耗と脱人格化が合わさることによって最終的に仕事へのやりがいを感じられなくなります。
さらには仕事に対する自信を失ってしまい、自分の利用者に対するケアに納得できなくなります。それによって達成感を得られず、ケアの質が下がっていき離職に繋がっていきます。
燃え尽き症候群に繋がる具体的な兆候に関しては以下の例があげられます。
・好きだったことに無関心になる
・夜眠れなくなったり朝起きれなくなったりする
・こだわりがなくなる
・急に遅刻や欠勤が増える
・仕事が雑になる
・感情や意欲がなくなりコミュニケーションをとりづらくなる
・アルコールの量が増える
・体に不調が出る
それではこの燃え尽き症候群に関してどんな人がなりやすいのでしょうか。
皆さんもチェックしてみてください。
燃え尽き症候群:どんな人がなりやすい?
え尽き症候群は、「個人的要因」と「環境的要因」の二つが関係することで引き起こす可能性があると考えられています。
どのようなものなのか1つずつ解説していきます。
【個人要因】
これは主に個人の性格や考え方に関係するものです。
ひたむきに仕事と向かい合い過ぎてしまう、相手のために頑張り続けてしまうなど、一所懸命になる人ほど燃え尽き症候群になりやすくなります。
また、年齢が若かったり仕事経験が少ない人ほど仕事に対する理想が高く、現実とのギャップを強く感じてしまうのです。
【環境要因】
これは主に周囲や職場環境に関係することです。
長時間労働が続き身体的に負荷がかかることや、給与が見合っていないと感じることで仕事にやりがいを見出せなくなり発症するケースもあります。
さらには、業務外でもいつ呼び出しが入るか分からない、すぐに対応できるように常に仕事のことを考えているなど、仕事と個人(プライベート)の境界線がないことが体にも心にも影響を与えます。
ただし、2つの要因が関係したときだけでなく、「個人要因」と「環境要因」のどちらか一方だけでも燃え尽き症候群の原因となる可能性があることも頭に入れておきましょう。
バーンアウトを引き起こしているかという症状の度合いをチェックするものとしてチェック表が存在します。
もし気になる点があれば一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
どのようなものなのか1つずつ解説していきます。
【個人要因】
これは主に個人の性格や考え方に関係するものです。
ひたむきに仕事と向かい合い過ぎてしまう、相手のために頑張り続けてしまうなど、一所懸命になる人ほど燃え尽き症候群になりやすくなります。
また、年齢が若かったり仕事経験が少ない人ほど仕事に対する理想が高く、現実とのギャップを強く感じてしまうのです。
【環境要因】
これは主に周囲や職場環境に関係することです。
長時間労働が続き身体的に負荷がかかることや、給与が見合っていないと感じることで仕事にやりがいを見出せなくなり発症するケースもあります。
さらには、業務外でもいつ呼び出しが入るか分からない、すぐに対応できるように常に仕事のことを考えているなど、仕事と個人(プライベート)の境界線がないことが体にも心にも影響を与えます。
ただし、2つの要因が関係したときだけでなく、「個人要因」と「環境要因」のどちらか一方だけでも燃え尽き症候群の原因となる可能性があることも頭に入れておきましょう。
バーンアウトを引き起こしているかという症状の度合いをチェックするものとしてチェック表が存在します。
もし気になる点があれば一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
燃え尽き症候群チェック表 |
こんな仕事もうやめたいと思うことがある(情) |
われを忘れるほど仕事に熱中することがある(個) |
細々と気配りをすることが面倒に感じることがある(脱) |
この仕事は私の性分に合っていると思うことがある(個) |
同僚や顧客の顔を見るのも嫌になることがある(脱) |
自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある(脱) |
1日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある(情) |
出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある(情) |
仕事を終えて、今日は気持ちの良い日だったと思うことがある(個) |
同僚や患者と何も話したくなくなるようなことがある(脱) |
仕事の結果はどうでもよいと思うことがある(脱) |
仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある(情) |
今の仕事に心から喜びを感じることがある(個) |
今の仕事は私にとってあまり意味がないと思うことがある(脱) |
仕事が楽しくて、知らないうちに時間が過ぎることがある(個) |
体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある(情) |
われながら、仕事を上手くやり終えたと思うことがある(個) |
情は【情緒的消耗感】
脱は【脱人格化】
個は【個人的達成感の低下】 を表しています。引用:サービス業従事者における日本版バーンアウト尺度の因子的,構成概念妥当性
これはあくまでも目安となります。
当てはまると絶対に燃え尽き症候群と決定するわけではないのでご注意ください。
ここから、燃え尽き症候群に関しての対策方法について見ていきましょう。
脱は【脱人格化】
個は【個人的達成感の低下】 を表しています。引用:サービス業従事者における日本版バーンアウト尺度の因子的,構成概念妥当性
これはあくまでも目安となります。
当てはまると絶対に燃え尽き症候群と決定するわけではないのでご注意ください。
ここから、燃え尽き症候群に関しての対策方法について見ていきましょう。
燃え尽き症候群:対策方法とは?
自分の心に余裕がないまま仕事をこなしていくことにより、日常生活にも支障が出てしまうので、心の余裕を作ることが大切になります。
そのためにも自分の生活や仕事にメリハリをつけて着地点をはっきりさせておきましょう。
対策方法に関しては以下のことを参考にしてみてください。
・冷静で客観的な態度を持つ
・職場の内外に相談できる相手を持つ
・大きな目標の他に短期間で達成できる小さな目標を設ける
・仕事だけに幸福を求めない
・十分な休養をとる
・自分の中で限界を設定し、仕事から離れる時間を作る
・食事をバランスよくきちんと摂取する
この対策はあくまでも参考にすぎないため、自分に最も合う方法を試して見つけることが一番の解決策となるでしょう 。
そのためにも自分の生活や仕事にメリハリをつけて着地点をはっきりさせておきましょう。
対策方法に関しては以下のことを参考にしてみてください。
・冷静で客観的な態度を持つ
・職場の内外に相談できる相手を持つ
・大きな目標の他に短期間で達成できる小さな目標を設ける
・仕事だけに幸福を求めない
・十分な休養をとる
・自分の中で限界を設定し、仕事から離れる時間を作る
・食事をバランスよくきちんと摂取する
この対策はあくまでも参考にすぎないため、自分に最も合う方法を試して見つけることが一番の解決策となるでしょう 。
燃え尽き症候群:さいごに
介護職における燃え尽き症候群について解説してきましたがご理解いただけたでしょうか?
症状の予防や対策には自分自身の取り組みだけでなく、職場や周囲の協力も必要となることが分かりました。
熱心に仕事をするのは大変素晴らしいことですが、燃え尽き症候群が酷くなると何らかの病気にも繋がりやすくなります。
そのため、より長く働くためにも働き方を考えたり自分の体に目を向けることが大切でしょう。
たとえ燃え尽き症候群になったとしても、「自分の性格に問題がある」などと自らを責めることは避け、問題を一人で抱え込まないように心がけましょう。
症状の予防や対策には自分自身の取り組みだけでなく、職場や周囲の協力も必要となることが分かりました。
熱心に仕事をするのは大変素晴らしいことですが、燃え尽き症候群が酷くなると何らかの病気にも繋がりやすくなります。
そのため、より長く働くためにも働き方を考えたり自分の体に目を向けることが大切でしょう。
たとえ燃え尽き症候群になったとしても、「自分の性格に問題がある」などと自らを責めることは避け、問題を一人で抱え込まないように心がけましょう。
介護のお仕事を探すなら介護ワーカー!
「介護の転職をしたい!」「自分に合う職場を見つけたい!」など転職をお考えの方はぜひ介護ワーカーへお問合せください!
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください。
<<介護ワーカーを見る>>
経験豊富な専任のアドバイザーが親身になってお仕事探しをお手伝いします。
他にはない非公開の求人もたくさんございます。
お気軽にご相談ください。
<<介護ワーカーを見る>>
※掲載情報は公開日あるいは2021年06月17日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。
#介護
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.